採用・労務・経理に関するお役立ち情報
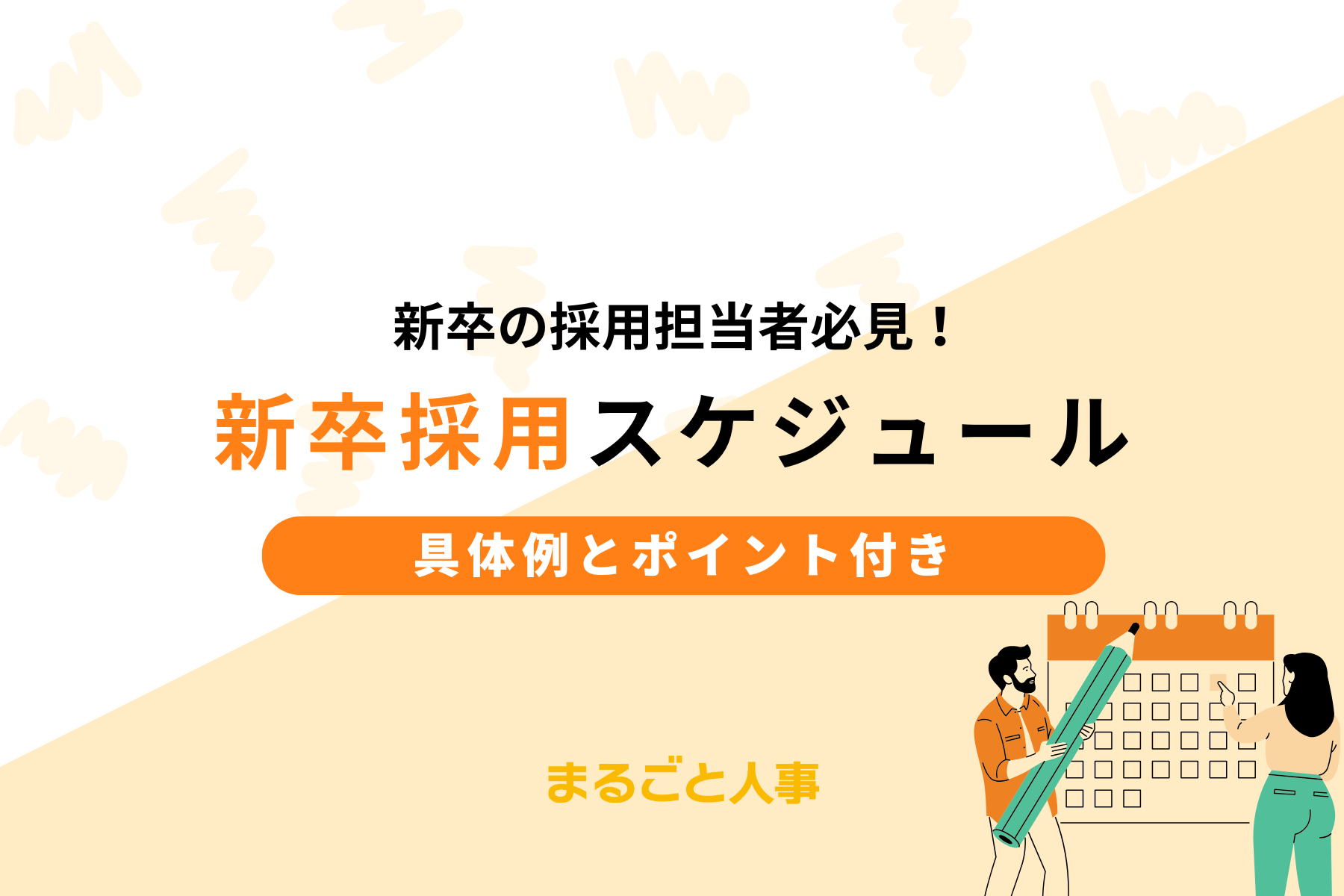
新卒採用を成功させるために重要なのは、戦略設計と社内リソース・採用体制です。
新卒採用スケジュールは年によって変動するため、効率的な採用活動を行うには、学生や競合他社の動向を踏まえ、最適なスケジュールの策定が求められます。
本記事では、27年並びに28年卒業予定の学生を対象とした新卒採用のスケジュールと学生の動向について詳しく解説します。
今後、新卒採用をご検討されているご担当者様は、ぜひご参考ください。
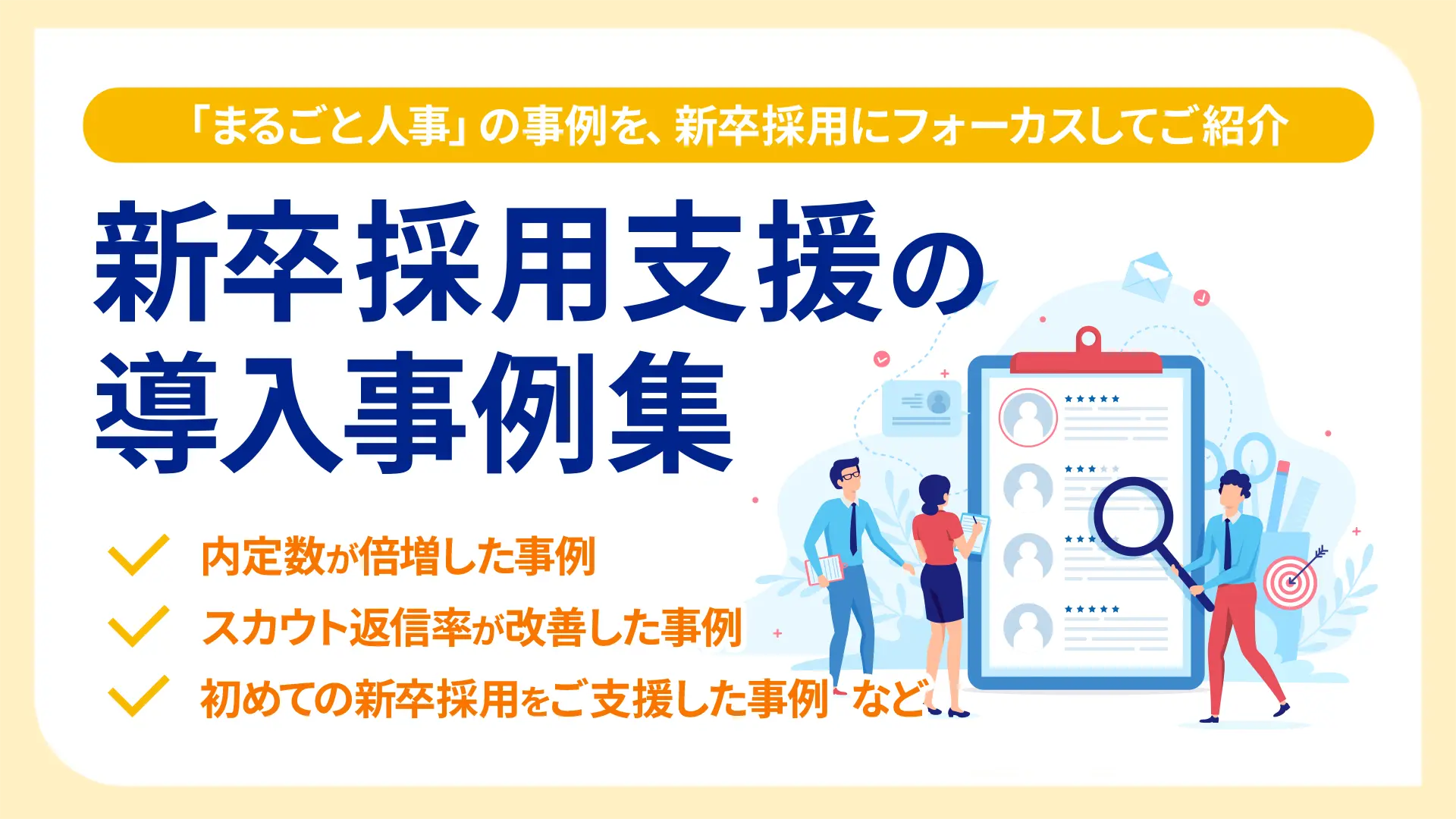
まるごと人事で
新卒採用をご支援した導入事例集
まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!
目次
新卒採用のスケジュール

近年、新卒採用は学生の就職活動の早期化や企業の内定出しの早期化により、年々変化しています。
では、近年の新卒採用スケジュールにはどのような傾向が見られるのでしょうか。
新卒採用の情報解禁日と採用活動の進め方
一般的に、新卒採用の情報解禁日は大学3年生の3月1日とされています。この日以降、企業は自社の採用情報を公開し、学生とのコミュニケーションを開始します。
採用活動は、まず母集団形成から始まり、インターンシップ、選考、内定へと進みます。各プロセスには適切な時期が存在するため、企業はこれを考慮して採用スケジュールを策定する必要があります。
新卒採用の主要なイベントと時期
新卒採用における主要なイベントとその時期は、一般的に「就活ルール」に基づいて設定されています。就活ルールでは、以下の3つの解禁日が定められています。
- 広報解禁日:大学3年生の3月1日
- 選考解禁日:大学4年生の6月1日
- 内定解禁日:大学4年生の10月1日
これらの解禁日を目安として、各イベントは以下のような時期に実施されます。
- 広報解禁日以降:採用情報公開、プレエントリー開始、会社説明会実施、エントリーシート受付
- 選考解禁日以降:本選考(筆記試験、面接など)
- 内定解禁日以降:内定通知、内定者フォロー
ただし、これらの就活ルールは政府による企業への要請であり、法的な拘束力や罰則はありません。そのため、ルールを厳格に遵守するよりも、早期に採用活動を開始する企業が多いのが実情です。
新卒採用の終了時期
新卒採用の終了時期は、原則として翌年4月入社予定の内定者を確保した時点となります。多くの企業では、12月までに内定出しを完了させる傾向があります。
しかし、採用活動はこれで終わりではありません。内定出し後の内定者フォローは、重要な役割を担います。企業は、内定者との継続的なコミュニケーションを通じて、入社意欲の維持・向上を図る必要があります。
2027年新卒採用スタート時期も早期化となるか

経団連が就活ルールを廃止した現在、政府主導で広報解禁日が定められていますが、法的拘束力がないため、早期に採用活動を開始する企業が多いのが実情です。学情の調査では、2026年卒の卒業前々年度内々定率が過去最高を記録しており、2027年卒も早期化が予想されます。
背景には、新卒人口の減少とインターンシップ制度の改正があります。少子高齢化による新卒人口の減少に加え、「新卒採用の2021年問題」で指摘された22歳人口の減少も深刻です。マイナビの調査では、2024年卒の採用充足率が過去最低であり、企業は早期に人材確保に動いています。

また、インターンシップ定義の改正により、企業はインターンシップ情報を採用活動に活用できるようになり、早期内定獲得者の割合が増加しています。2027年卒の採用スケジュール例として、早期化に対応した場合と政府主導のスケジュールに沿った場合が考えられます。
新卒採用の早期化傾向
新卒採用の早期化傾向は、年々顕著になっています。従来、新卒採用は大学3年生の3月に情報が解禁されていましたが、現在では多くの企業が大学2年生の段階から採用活動を開始しています。
具体的には、大学2年生向けのインターンシップの実施や、SNSを活用した早期の情報発信などが行われています。
早期化が進む理由
なぜ新卒採用の早期化が進んでいるのでしょうか。その主な理由は、優秀な学生の獲得競争にあります。
多くの企業は、できるだけ早い段階から学生とのコミュニケーションを開始し、自社への興味・関心を高めたいと考えています。また、長期インターンシップなどを通じて、学生の能力や適性を見極めたいという思惑もあります。早期化によって、他社に先んじて優秀な学生を確保できると期待されているのです。
早期化が進む理由
早期化に対する学生の意識は二分化していると言えます。
一部の学生は、早い段階から就職活動に取り組むことで、有利に進められると考えています。実際、早期にインターンシップに参加したり、企業との接点を持ったりすることで、就職活動をスムーズに進める学生もいます。
しかし、多くの学生にとって、早期化はプレッシャーとなっているのも事実です。大学生活を充実させたい、あるいはじっくりと進路を考えたいという学生にとって、早期化は必ずしも歓迎されていません。企業側は、学生の意向を十分に汲み取りながら、柔軟に対応していく必要があるでしょう。
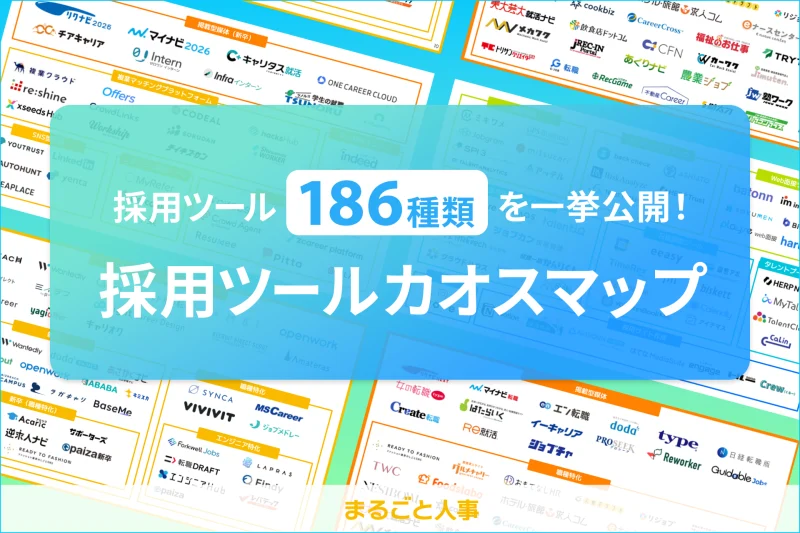
採用ツール210種類を一挙公開!
採用ツールカオスマップ
2025年の採用市場に対応!210種類の最新採用ツールをカテゴリ別に一括整理・比較
2027年卒の採用スケジュールの例
今回は、就職活動開始時期の早期化に対応した場合と、政府主導の就職活動スケジュールに沿った場合の一例を示します。
下記は、27年の学生をターゲットとした、採用開始時期の早いスケジュールの一例です。
28卒の場合は1年スライドさせてください。
早期選考パターン
政府主導スケジュール
参考:「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」内閣官房内
かつて経団連が決定していた就活スケジュールですが、現在、その決定権は政府に移っています。経団連がこの業務から外れた理由としては、「実態と乖離していた」ことが挙げられます。そもそも経団連が定めたスケジュールは、同団体に加盟している企業が遵守すべきものでしたが、その対象企業が限定的であった上、加盟企業であっても発表されたスケジュールを遵守しないケースが散見されたのです。
現在の政府主導の就活スケジュールにおいても、それに沿わない企業が多いのが実情です。
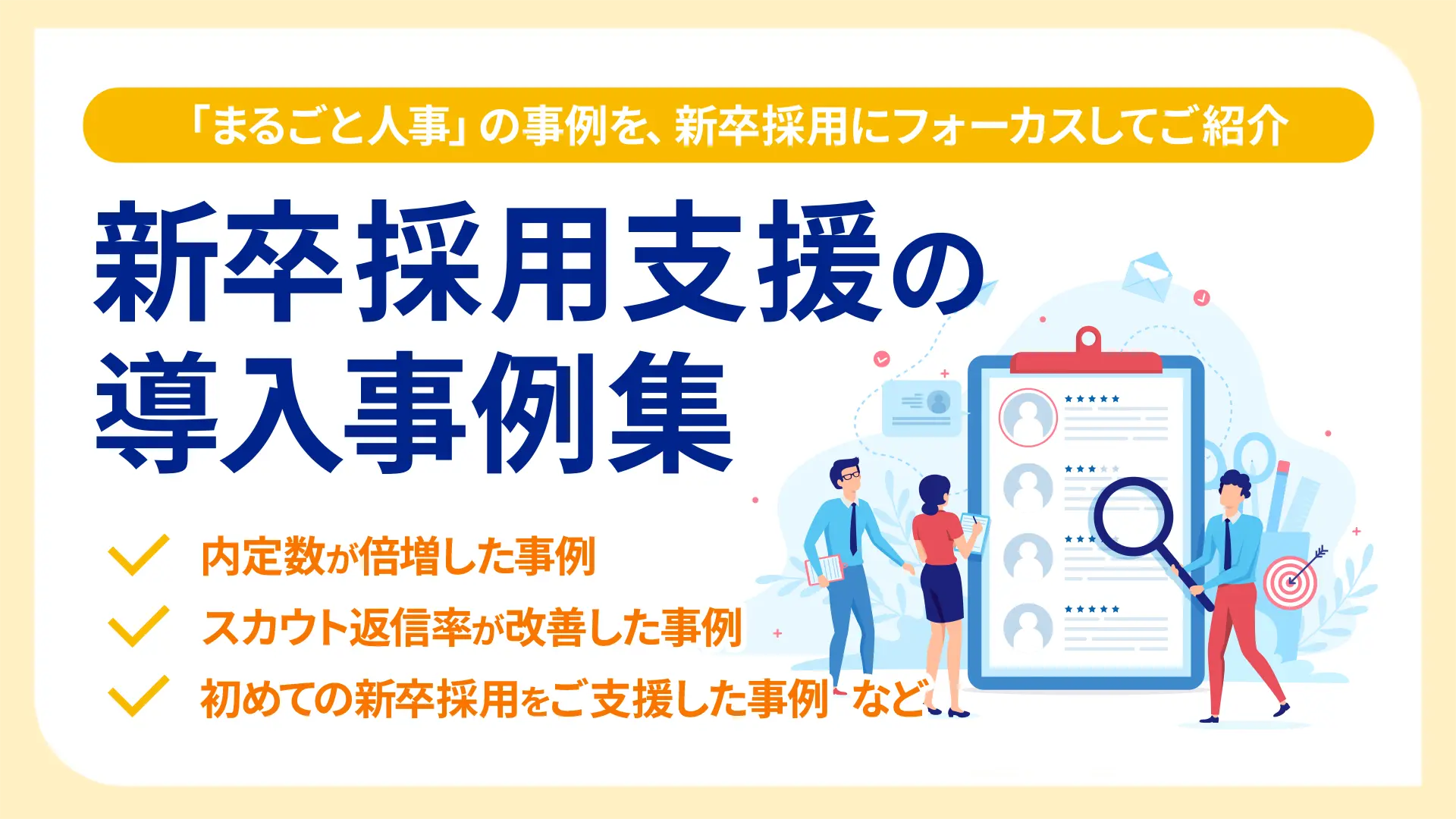
まるごと人事で
新卒採用をご支援した導入事例集
まるごと人事で新卒採用をご支援した企業の、導入前の課題や導入後の効果がまとめてご覧いただけます!
新卒採用の各ステップと開始時期

新卒採用における各ステップと、その適切な開始時期について詳しく見ていきましょう。本稿では、母集団形成、インターンシップ、選考プロセスのそれぞれに関して、いつ頃から着手すべきかを解説します。
母集団形成
母集団形成は、新卒採用における最初の重要なステップであり、可能な限り早期に着手することが望ましいと言えます。多くの企業では、大学3年生の5月頃から8月頃にかけて母集団形成を開始する傾向が見られます。
この時期は、学生の就職に対する意識が徐々に高まり始める時期と重なるため、効果的な母集団形成が期待できます。具体的には、以下の取り組みを通じて学生との接点を構築していきます。
- 自社の採用ウェブサイトを開設する
- ソーシャルメディアを活用して情報発信する
- 合同企業説明会に参加する
インターンシップの実施タイミング
インターンシップは、学生に自社の業務内容や企業文化を理解してもらうための非常に良い機会です。多くの企業では、大学3年生の6月から8月にかけてインターンシップを実施する傾向があります。この時期は、学生の夏休み期間と重なるため、比較的参加しやすいという利点があります。
一方で、採用活動の早期化に伴い、春休み期間(2月から3月)にインターンシップを実施する企業も増加しています。自社の採用戦略を踏まえ、最適な実施時期を選択することが重要です。
選考プロセスと内定出しの実施タイミング
選考プロセスは、エントリーシートの受付に始まり、面接、筆記試験、最終面接を経て内定に至ります。多くの企業では、大学3年生の6月から10月頃にエントリーシートの提出を受け付け、8月から11月頃に面接・選考を実施する傾向があります。
内定出しは、10月から12月頃が一般的です。ただし、近年では選考の早期化が進んでおり、9月中に内定を出す企業も少なくありません。自社の採用ニーズと学生の動向を注視しながら、適切な選考スケジュールを策定することが求められます。
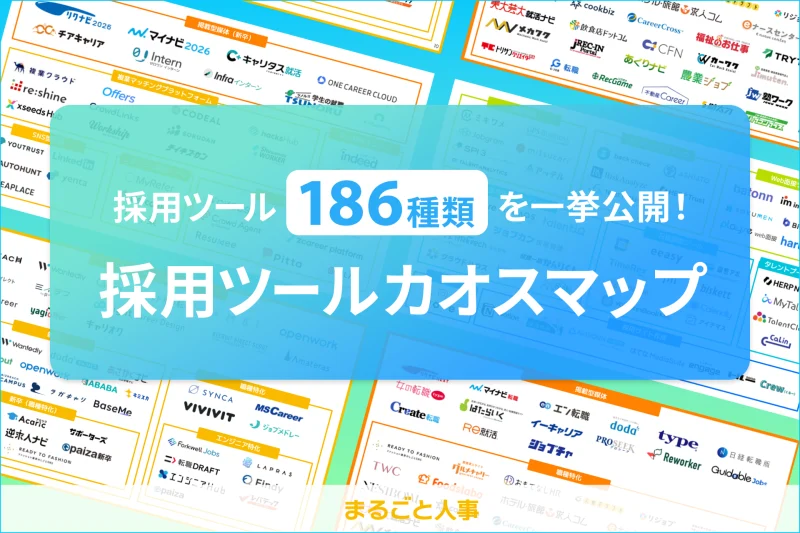
採用ツール210種類を一挙公開!
採用ツールカオスマップ
2025年の採用市場に対応!210種類の最新採用ツールをカテゴリ別に一括整理・比較
新卒採用スケジュールを設定するポイント

新卒採用のスケジュールを検討する際には、様々な要素を考慮することが大切です。ここでは、スケジュールを設定する上で、特に押さえておきたいポイントについて解説いたします。
1.自社の採用ニーズに合わせた目標人数の設定
新卒採用のスケジュールを設定するにあたり、まず自社の採用ニーズを明確にしておく必要があります。
具体的には、どのような人材を、どの程度の人数を採用したいのかを設定しましょう。明確な採用目標を設定することで、それに合わせた適切なスケジュールを組むことが可能になります。
例えば、大量採用が必要な場合は、早期からの母集団形成が不可欠です。一方、少数採用を目指す場合は、選考に時間をかけられるよう、スケジュールに余裕を持たせることが重要となります。
2.新卒採用市場の現状を把握
最新の有効求人倍率や前年度の内々定率などを確認することで、新卒採用市場の現状を正確に把握し、自社の採用計画に反映させることが大切です。
また、自社業界全体の選考進捗状況も把握しておくことで、採用活動の遅れを防ぐための対策を講じやすくなります。
3.広報・ブランディング活動の前倒し
就職活動開始時期の早期化に伴い、広報・ブランディング活動も前倒しで実施しましょう。
オウンドメディアを通じて社員インタビューや福利厚生制度などの情報を発信し、早い段階から学生への魅力付けを図ることが重要です。
また、令和の学生に選ばれるためには、ワークライフバランスの実現や、リモートワーク、フレックスタイム制といった柔軟な働き方が可能な点を積極的に訴求すると良いでしょう。
4.採用競合他社の動向と差別化
自社の採用スケジュールを設定する際は、競合他社の動向を把握しておくことも重要なポイントです。
特に、同業界における人気企業の採用スケジュールは、学生の就職活動に大きな影響を与えるため、注視する必要があります。競合他社の動向を分析した上で、自社の強みを最大限に活かせる採用スケジュールを設定しましょう。
例えば、競合他社よりも早期にインターンシップを実施することで、学生との接点を増やし、自社への関心を高めることができます。また、選考時期を意図的にずらすことで、他社との選考期間の重複を避け、優秀な学生のエントリー機会を創出することも可能です。
5.ターゲットの就活スケジュールとの整合性
新卒採用のスケジュールは、ターゲットとする学生層の就職活動スケジュールとの整合性を図ることが重要です。
例えば、理系学生を対象とする場合、研究室への配属時期を考慮に入れる必要があります。また、外国人留学生を採用する際には、ビザ取得のスケジュールにも配慮が求められます。
学生の就職活動スケジュールを十分に理解し、それに合わせて自社の採用スケジュールを調整することで、より効果的な採用活動を展開できるでしょう。
6.社内リソースと採用体制を整える
新卒採用のスケジュールを設定する際は、社内のリソースと採用体制も慎重に考慮する必要があります。
採用活動には、人的資源、時間、予算をはじめとする多岐にわたるリソースが不可欠です。自社の現状を十分に踏まえ、無理のない範囲で実行可能な採用スケジュールを設定しましょう。
また、採用担当者の育成や、円滑な社内協力体制の構築にも時間を確保することがポイントです。作成した採用スケジュールに合わせて、社内のリソースをできるだけ活かせるような体制を整えていくと良いでしょう。
効果的な新卒採用スケジュールの立て方

効果的な新卒採用スケジュールを立てるためのポイントを、4つに絞って解説いたします。
母集団形成から内定出しまでのプロセスを最適化
効果的な新卒採用スケジュールを設定するには、母集団形成から内定出しに至る一連のプロセスを最適化することが重要となります。
まず、母集団形成の時期と方法を戦略的に設定しましょう。
自社の認知度向上を図り、優秀な学生に興味を持ってもらうためには、早期からの情報発信が有効です。
また、選考プロセスにおいては、学生の特性を多角的に見極められるよう、複数の選考方法を組み合わせることが望ましいでしょう。
内定出しのタイミングは、学生の就職活動状況を注視しつつ、柔軟に調整していくことが大切です。
戦略的にインターンシップを活用
インターンシップは、学生と企業が相互理解を深める上で非常に有益な機会です。戦略的にインターンシップを活用することで、より効果的な新卒採用が実現可能となります。
まず、インターンシップの目的を明確にすることが大事です。早期に優秀な学生を発掘することを主眼とするのか、あるいは自社の魅力を効果的に伝えることを重視するのか、目的に応じて適切なプログラムを設計する必要があります。
また、インターンシップの参加者に対しては、選考プロセスにおいて一定の優遇措置を設けることも有効な手段の一つです。インターンシップを通じて学生と深い関係性を構築することは、その後の採用活動を円滑に進める上で大きな利点となるでしょう。
選考プロセスの設計と信頼関係を構築するコミュニケーション
選考プロセスは、学生の能力や適性を見極める上で極めて重要な機会です。効果的な選考プロセスを設計するためには、自社が求める人物像を明確にし、それに合致した選考基準を設定することが不可欠となります。
また、選考プロセスを通じて、学生とのコミュニケーションを強化することも重要な側面です。面接においては、学生の話に真摯に耳を傾け、丁寧なフィードバックを心がけましょう。筆記試験の結果についても、学生に対して適切に説明することが求められます。このような丁寧なコミュニケーションを通じて学生との信頼関係を構築していくことが、効果的な新卒採用へと繋がります。
内定者フォローと入社意欲の維持・向上
内定出し後の内定者フォローは、その後の採用活動において重要な役割を担います。内定者との継続的なコミュニケーションを通じて、入社意欲の維持・向上を図ることが非常に大事です。具体的には、定期的な情報提供や、社内イベントへの積極的な招待などが効果的でしょう。
また、内定者同士の交流機会を設けることで、内定者コミュニティの形成を促進することも有効です。こうした取り組みを通じて、内定者の入社前の不安を軽減し、入社への期待感を醸成していくことが求められます。
内定者フォローは、新卒採用スケジュールの最終段階に位置づけられますが、入社後の早期離職防止や定着にも大きな影響を与えます。充実した内定者フォローを実施することで、新入社員のスムーズな立ち上がりと早期戦力化に繋げることが期待されます。
まとめ

新卒採用は、卒業見込みの学生を対象に、多くの企業が同時期に実施するものです。学生の多くは、一定のスケジュールに沿って活動する傾向がありますので、例年の流れを参考に、無理のない範囲で採用スケジュールを検討していくのが良いでしょう。現在、人材採用は売り手市場であり、競争は厳しい状況ですが、これは将来有望な若い方々と出会える貴重な機会でもあります。自社の魅力を丁寧に伝えつつ、求める人物像を明確にし、共に未来を築いていけるような若い力を迎えられることを期待しています。
採用に関してご不明な点やお困りごとがございましたら、アウトソーシング・相談先の候補として「まるごと人事」を検討してみてください。
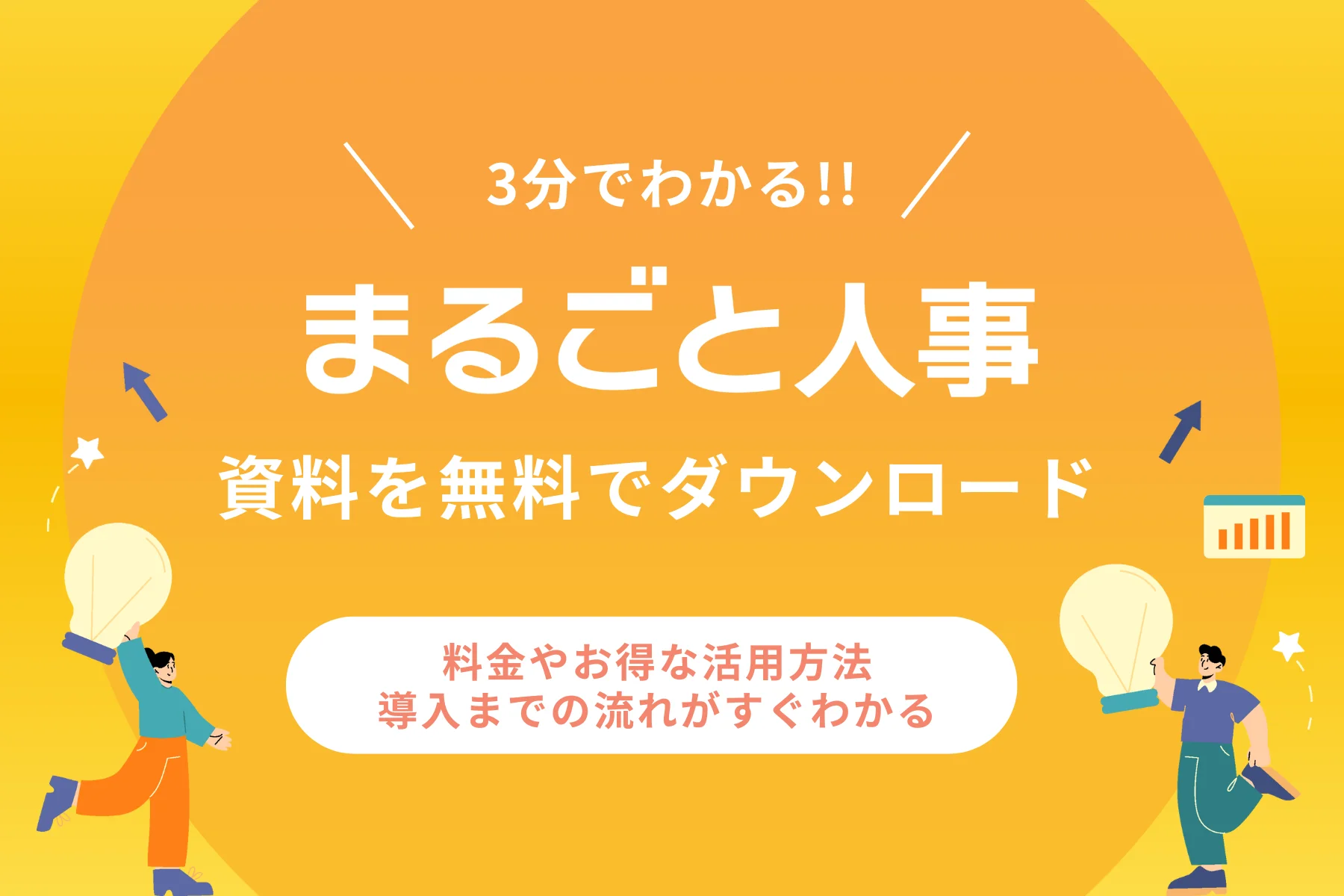
「まるごと人事」の資料を
無料でダウンロード
リピート率95%!!料金やお得な活用方法、企業の声や事例、導入までの流れを無料でご紹介!
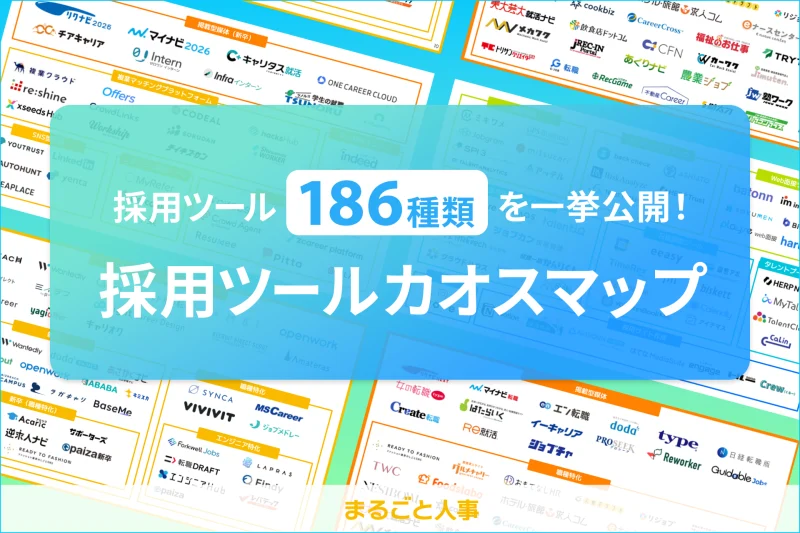
採用ツール210種類を一挙公開!
採用ツールカオスマップ
2025年の採用市場に対応!210種類の最新採用ツールをカテゴリ別に一括整理・比較
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
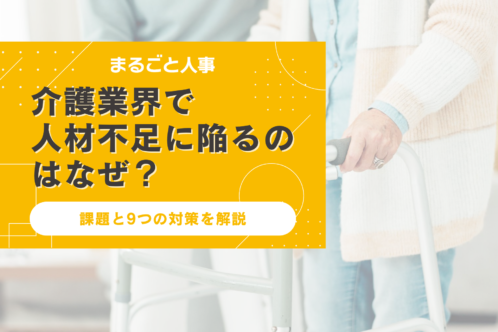
介護業界で人材不足に陥るのはなぜ?課題とデータから見た9つの対策を解説
- 採用企画
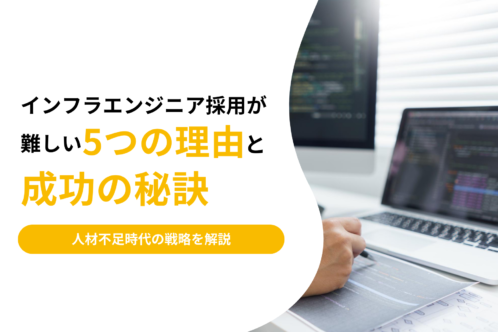
インフラエンジニア採用が難しい5つの理由と成功の秘訣|人材不足時代の戦略を解説
- 採用企画
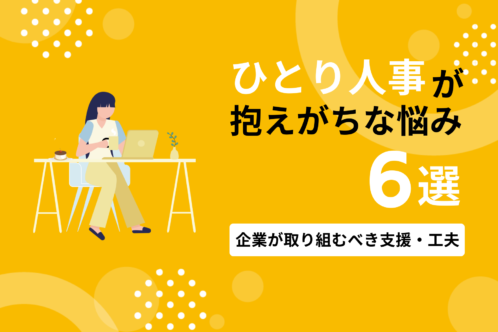
ひとり人事が抱えがちな悩み6選|企業が取り組むべき支援・工夫
- 採用企画
- 採用オペレーション
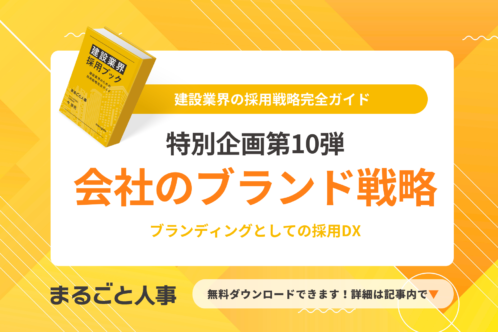
最終回 採用から始まるブランド戦略【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】
- 採用企画
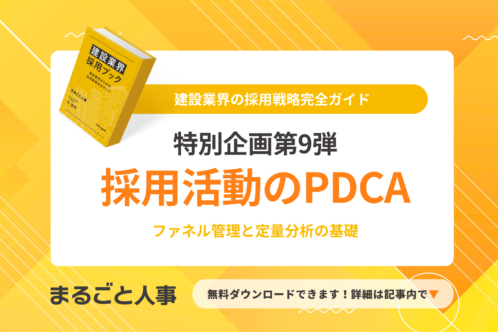
第9回 データで可視化する採用活動のPDCA【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】
- 採用企画
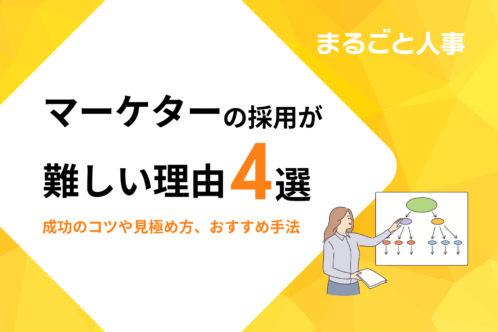
マーケターの採用が難しい理由4選|成功のコツや人材の見極め方、おすすめ手法
- 採用企画











