採用・労務・経理に関するお役立ち情報

転職市場における採用活動は、求人数の増加や人材ニーズの多様化によって難易度が高まっています。中でも利用者規模が大きいリクナビNEXTは、多くの企業にとって欠かせない採用チャネルです。
しかし、媒体特性や料金体系の変化を正しく理解しなければ効果的な活用はできません。特に2025年4月以降はIndeed PLUSとの連携によりクリック課金型へ移行し、従来の運用スタイルが大きく変わりました。
本記事では、リクナビNEXTの特徴や掲載料金の仕組みを整理し、他媒体との違いやメリット・デメリットを比較しながら、採用成功につなげるための実践的な活用ポイントを解説します。

中途採用の募集文作成と確認に便利!
募集文ライティングのチェックリスト
募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き
目次
リクナビNEXTの特徴

リクナビNEXTは登録者数や求人掲載数で国内最大級の規模を誇り、採用手段として幅広く活用されています。ここでは、会員数や職種カバレッジ、企業規模別の利用実態に分けて特徴を整理します。
会員数・利用者数の規模感(1,000万人以上の登録者)
リクナビNEXTの登録者数は2020年に1,000万人を突破し、その後も増加を続けています。2020年12月末には約1,043万人、2022年2月末には約1,148万人に達しました。
日本の労働人口約6,830万人のうち約6人に1人が登録している計算となり、転職者の約8割が利用する転職サイトと位置付けられています。新規会員も毎月10万人以上増えており、月間利用者数は100万人を超える規模に達しました。
求職者層が安定的に流入し続ける環境が整っているため、採用活動における母集団形成力は非常に高い水準にあるといえます。
幅広い職種・業界に対応する求人数
リクナビNEXTに掲載される求人件数は年々増加傾向にあり、2025年9月時点で約108.1万件が確認されています。営業・事務・管理・企画・マーケティング・サービス・販売、Web・ゲーム・クリエイティブ・専門職・ITエンジニアなど、412種類の職種分類で検索可能です。
さらに、IT・通信・メーカー・商社・不動産・建設・金融・保険など多彩な業種に対応しており、未経験者歓迎の求人も多数存在します。
求人数の推移
- 2025年9月:約108.1万件
- 2025年4月:約104万件
- 2024年6月:約13.4万件
- 2023年10月:約10.1万件
- 2022年5月:約6.1万件
中小企業から大企業まで利用可能な媒体
リクナビNEXTは大企業だけでなく中小企業からの利用も非常に多い点が特徴です。従業員数50名以下の企業が約5割、100名以下では6割超を占めています。
2023年10月時点の掲載実績では、従業員数10名以下の求人が3,239件、11~100名が29,442件にのぼり、全体の約3割が100名以下の企業でした。求人は企業規模を問わず条件に一致する求職者の画面に表示される仕組みとなっているため、知名度の低い企業でも対象人材へ効果的に情報を届けられます。
業種別では不動産・建築・メーカー・小売・IT・通信など幅広く利用されており、採用ターゲットに応じた効果的な露出を実現できます。大手企業との競合環境においても十分な存在感を発揮できる媒体です。
リクナビNEXTの掲載料金と課金方式の変化
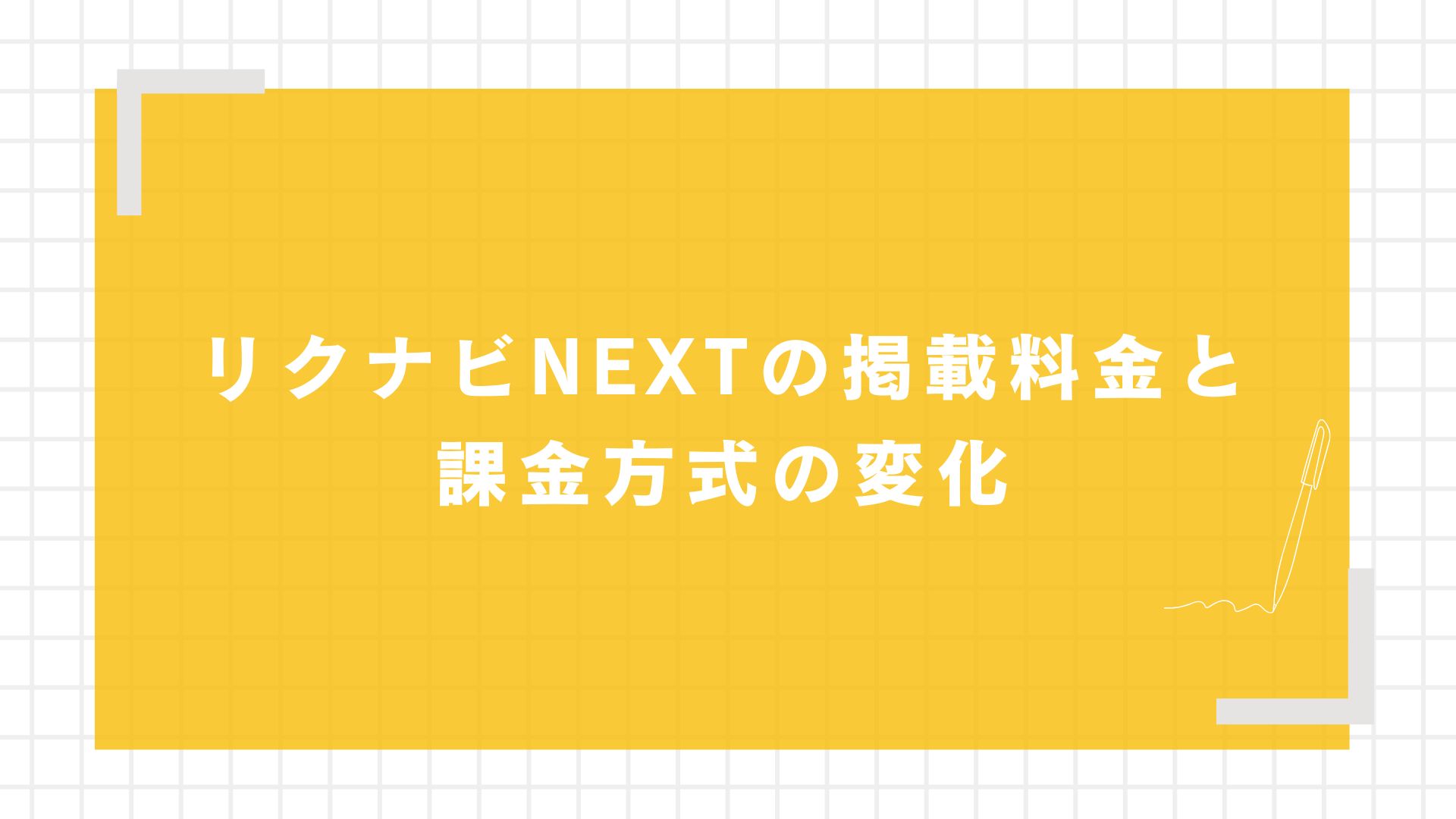
求人広告の料金体系は、採用計画や予算設計に直結する重要なポイントです。従来の掲載課金型の仕組みから、Indeed PLUSとの連携によるクリック課金型への移行までを整理し、企業に及ぼす影響を確認します。
従来の掲載課金型と費用感
リクナビNEXTでは長らく掲載課金型を採用しており、勤務地エリア、原稿サイズ、掲載期間、オプションの有無によって料金が変動していました。原稿サイズはN1からN5まで5段階が設定され、情報量や表示順位に差が出る仕組みで、N3が最も利用されるプランでした。
掲載期間は2週間または4週間から選択可能で、長期掲載の方が1日あたりの単価は割安になります。採用人数にかかわらず料金は固定で、大量採用を計画する企業にとっては採用単価を抑えやすい方式でした。
| プラン | 2週間掲載 | 4週間掲載 |
|---|---|---|
| 全国企画 | N1:18万円〜N5:144万円 | N1L:20万円〜N5L:180万円 |
| エリアA(関西・東海・北関東) | N1:13万円〜N5:115万円 | N1L:17万円〜N5L:153万円 |
| エリアB(北海道・東北・北陸甲信越・中国四国・九州沖縄) | N1:12万円〜N5:110万円 | N1L:15万円〜N5L:135万円 |
Indeed PLUSとの連携とクリック課金型への移行
2024年1月からIndeed PLUSとの連携が始まり、2025年3月末で従来の掲載課金型は終了し、以降はIndeed PLUS経由の掲載に一本化されました。料金体系はクリック課金型に変更され、求人が閲覧されるたびに費用が発生します。
AIが自動で最適な求人媒体を選び、リクナビNEXT以外にもタウンワークやはたらいくなど複数サイトへ同時掲載される仕組みです。応募経路が多様化する一方、従来のDMやスカウトといったオプション機能は利用できなくなりました。
新料金体系が企業に与える影響
クリック課金型の導入により、企業は予算上限を設定して費用をコントロールできるようになりました。最低3,000円から運用可能で、クリック単価はAIが最適化し、実績値として400〜800円程度で推移しています。
予算上限に達すると掲載が自動で停止し、再設定すれば再開される仕組みです。一方、AIによる自動配信のため差別化施策は制限され、原稿改善の重要性が高まりました。
企業への主な影響
- 予算管理が柔軟になり少額から利用開始可能
- 他社との差別化は原稿内容に依存
- オプション機能が利用できずアプローチ手段が減少
- 「Airワーク採用管理」などの連携ツールで応募者を一元管理可能
新料金体系は効率的な運用を実現する一方で、採用戦略における自由度は低下しています。

中途採用の募集文作成と確認に便利!
募集文ライティングのチェックリスト
募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き
リクナビNEXTの強み
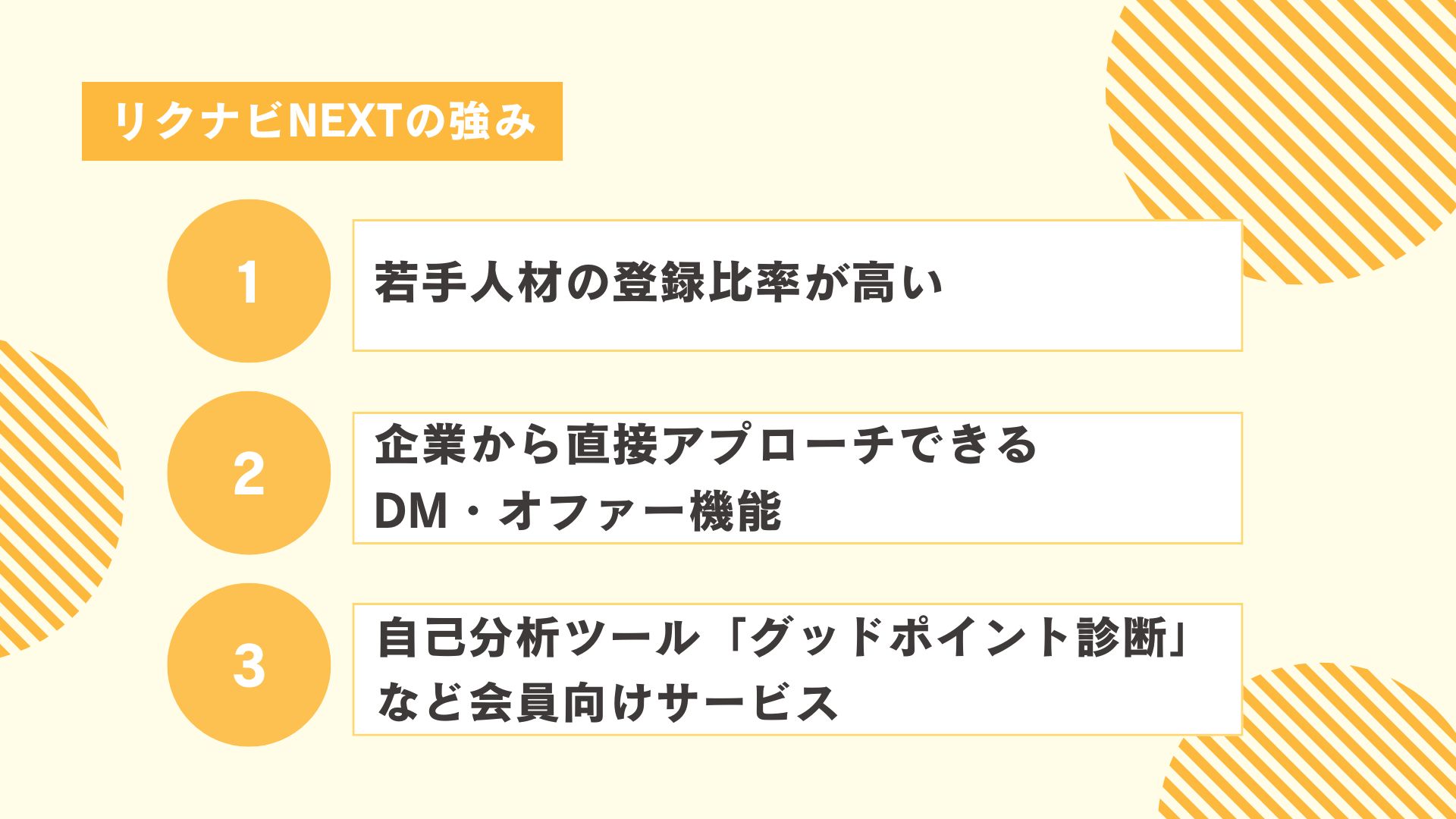
リクナビNEXTは登録者数や求人件数だけでなく、利用者層の特徴や企業が利用できる機能面でも優位性を持っています。以下では若手人材の登録状況、企業からの直接アプローチ機能、会員向けサービスを中心に強みをみていきましょう。
若手人材の登録比率が高い(35歳以下が約7割)
リクナビNEXTにおける新規登録会員の年齢分布は若手層が中心で、全体の約7割を35歳以下が占めています。
- 24歳以下:7%
- 25〜29歳:16%
- 30〜34歳:22%
- 35歳以下合計:約50%〜70%
20代〜30代前半の登録比率が高いため、若手採用を重視する企業にとって有力な採用チャネルといえます。20代応募者が多いという口コミも寄せられており、経験よりもポテンシャルを重視した募集や第二新卒採用を進めたい場合に効果的です。
企業から直接アプローチできるDM・オファー機能
リクナビNEXTは応募を待つだけでなく、企業から能動的に求職者へ働きかけられる仕組みが整っています。代表的な機能は、以下のとおりです。
- らくらくオファー(無料):AIが候補者を自動抽出して定型文を送信
- 求人告知メール(有料):ターゲット層に求人情報を案内
- ターゲットDM(有料):自由に文面を作成して送信可能
- スピードアプローチ(無料):求人閲覧者へ自動で応募を促すメッセージを送信
- こだわりアプローチ(無料):匿名レジュメから個別に誘致メッセージを送信
リクルートの調査では、企業からのアプローチを受けた求職者の約3人に2人が応募へ進んでおり、応募数や採用率を高める実効性の高い手段になっています。
自己分析ツール「グッドポイント診断」など会員向けサービス
会員向けサービスも多彩で、転職活動の効率を大きく高めています。特に注目されるのが「グッドポイント診断」で、18種類の性格特性の中から5つの強みを抽出し、組み合わせは8,568通りに及びます。診断結果は履歴書や自己PR作成に活用でき、応募時に添付することも可能です。実際に利用者の8割以上が診断を利用しています。
その他の機能としては、以下が挙げられます。
- 希望条件に基づく新着求人通知
- 職務経歴書の自動作成機能
- 類似求人のレコメンド
- 面接日程リマインド
- 気になるリスト
- スマホアプリによる情報同期と通知機能
上記によって求職者は効率的に活動を進められ、企業側にとっては応募率や選考参加率の向上につながります。
リクナビNEXTの掲載を検討する企業が知るべきメリット4選
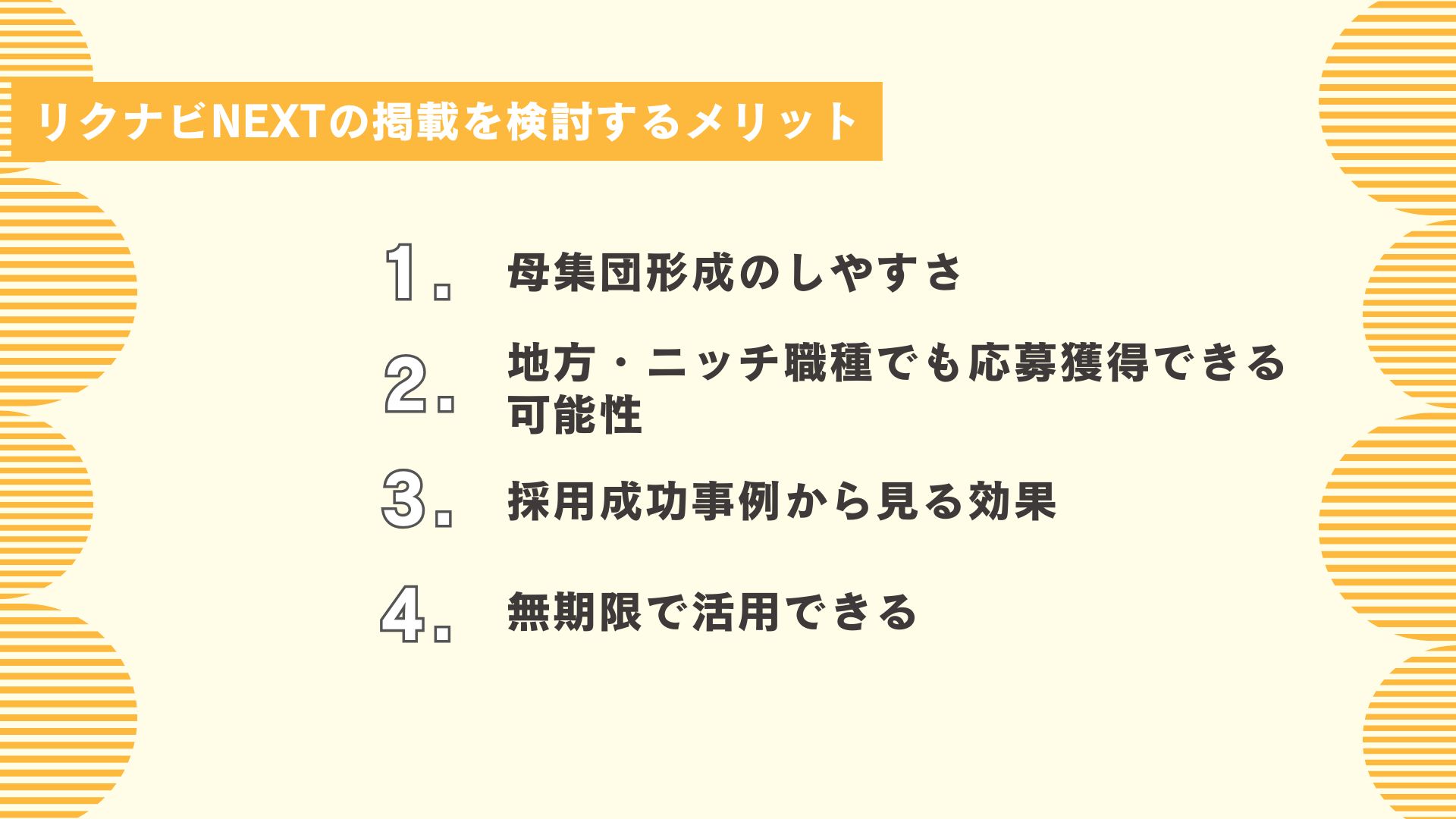
リクナビNEXTは国内最大級の登録者数と求人数を背景に、多様な採用シーンで効果を発揮します。ここでは4つの視点から、リクナビNEXTの長期的な利用可能性について整理しました。
豊富な登録者数による母集団形成のしやすさ
リクナビNEXTの利用者は転職希望者全体の約8割を占めるとされており、国内最大級の母集団を形成しています。応募率も他の転職サイトを上回り、幅広い職種や雇用形態で人材を集めやすい点が特徴です。
大量採用を目指すケースや複数職種で同時に募集を行う場合にも強みを発揮します。特に転職活動を始めたばかりの意欲の高い層へ確実にリーチできるため、採用成功率を高めやすい仕組みが整っています。
地方・ニッチ職種でも応募獲得できる可能性
リクナビNEXTは412の職種分類と多彩な業種を網羅しており、都市部だけでなく地方求人やニッチ職種でも応募を集めやすい点が強みです。利用者の声では「地方でも求人が見つかった」「ニッチ職種で20件の応募を獲得できた」といった事例が確認されています。
さらに、従業員数10名以下や100名以下といった中小規模の企業も多く利用しているため、知名度の低い企業であっても適切な条件設定により対象人材の目に触れる機会を得られます。
採用成功事例から見る効果
リクナビNEXTを活用した企業からは、応募数の多さや候補者の質に対する評価が多く寄せられています。例えば、施工管理スタッフを募集した従業員75名の企業では他媒体で採用できなかった状況から応募が一気に増え、選考がスムーズに進行しました。
従業員102名の企業では企画営業職募集において応募数や男女比のバランスが良好で、年間回数券の継続利用を決定しています。さらに、従業員34名の企業では即戦力エンジニア採用に成功し、30代リーダークラスの人材獲得につながりました。
無期限で活用できる
リクナビNEXTは利用期間に制限がなく、求職者が自分のペースで活動できる点もメリットです。転職エージェントでは3〜6か月のサポート期間が一般的ですが、リクナビNEXTでは登録後に長期的な利用が可能になります。
求職者は「すぐ転職をしたいわけではないが情報収集は続けたい」といったスタンスでも登録しやすいため、潜在層へのリーチにも有効です。企業側にとっては採用計画に合わせて柔軟に活動でき、短期採用から長期的な母集団形成まで幅広い採用戦略に対応できます。

中途採用の募集文作成と確認に便利!
募集文ライティングのチェックリスト
募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き
リクナビNEXT利用時のデメリット3選
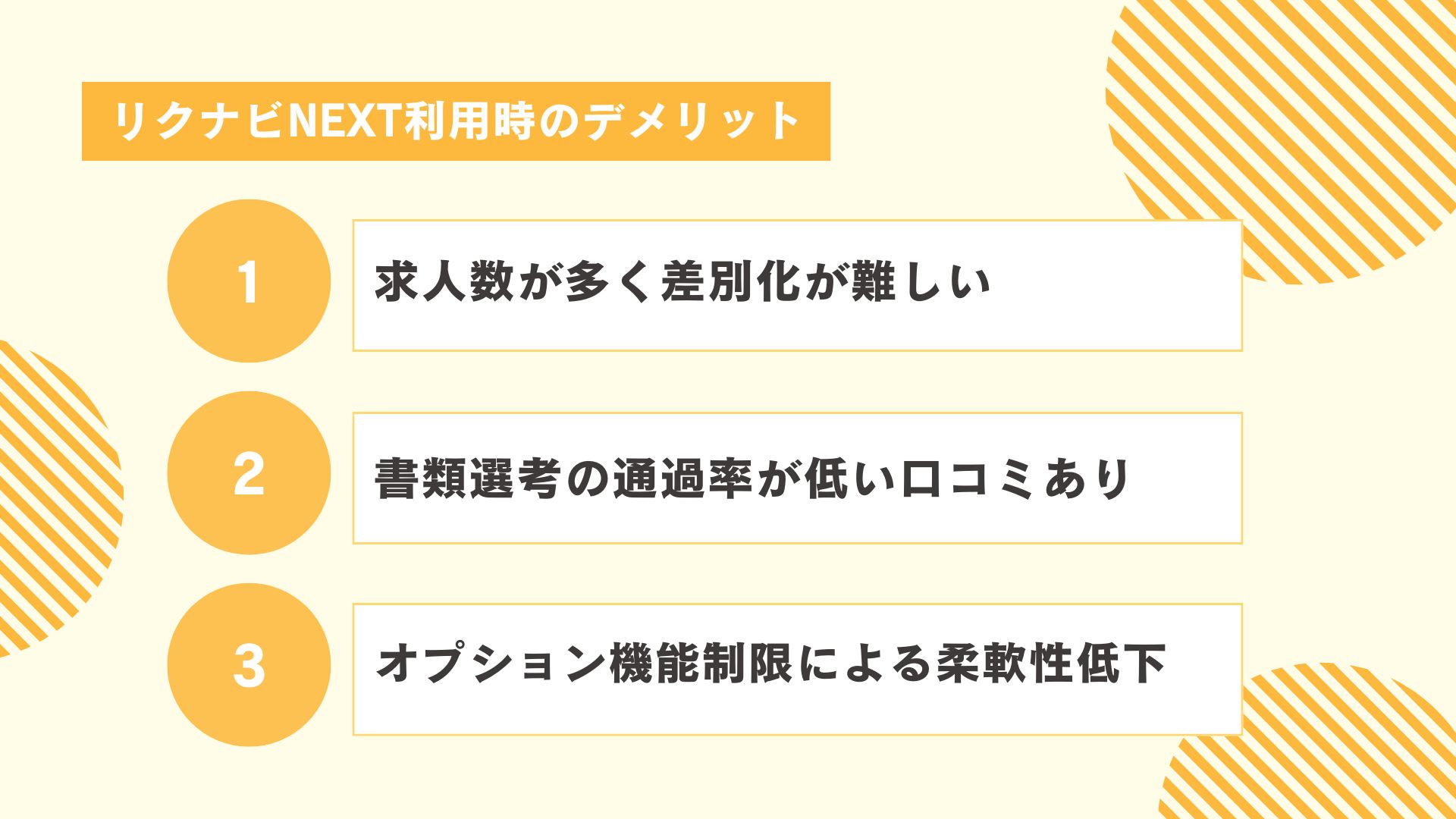
リクナビNEXTは大規模な母集団形成が可能な一方で、利用にあたっては注意すべき点も存在します。ここでは3つの視点から、リクナビNEXT利用時のデメリットについて解説します。
求人数が多く差別化が難しい
リクナビNEXTは国内最大級の求人件数を持つ反面、情報量が多すぎることで求職者にとって絞り込みが大変になるという声があります。
例えば「求人が多すぎて選びにくい」「質の低い求人が混ざっている」という口コミが散見され、求人の玉石混交化が課題とされています。掲載料金を支払えば規模を問わず求人を載せられるため、ブラック企業が含まれるとの指摘も一部で見られました。
さらに、Indeed PLUSとの連携によってAIが求人を自動配信する仕組みになった結果、特定企業が目立つ工夫が難しくなり、従来以上に原稿内容での差別化が不可欠となっています。
書類選考の通過率が低いとの口コミがある
転職エージェントと異なり、リクナビNEXTは企業に直接応募するスタイルのため、キャリアアドバイザーによる添削や面接対策などの支援を受けられません。結果、書類選考を通過しづらいという意見も目立ちます。
実際に「準備不足のまま応募すると落ちやすい」「応募してもなかなか通らない」といった口コミが寄せられていました。さらに、求人内容に誇張があるケースも指摘されており、特に給与水準が高すぎる案件やワークライフバランスを過度に強調することには注意が必要です。
オプション機能制限により柔軟性が低下する
Indeed PLUSへの完全移行によって、リクナビNEXTに従来用意されていたスカウトやDMといったオプション機能が使えなくなりました。AIが求人を自動的に最適な媒体へ配信する仕組みのため、企業側が意図的にターゲットを絞り込み、柔軟に戦略を組む余地が減少しています。
さらに、掲載しても必ずリクナビNEXTに表示されるわけではなく、掲載のコントロール権が弱まっている点もデメリットです。結果として、他社との差別化は原稿内容や改善サイクルに依存する割合が大きくなり、従来よりも運用の工夫が不可欠となっています。
リクナビNEXTと他の転職サイトとの違い
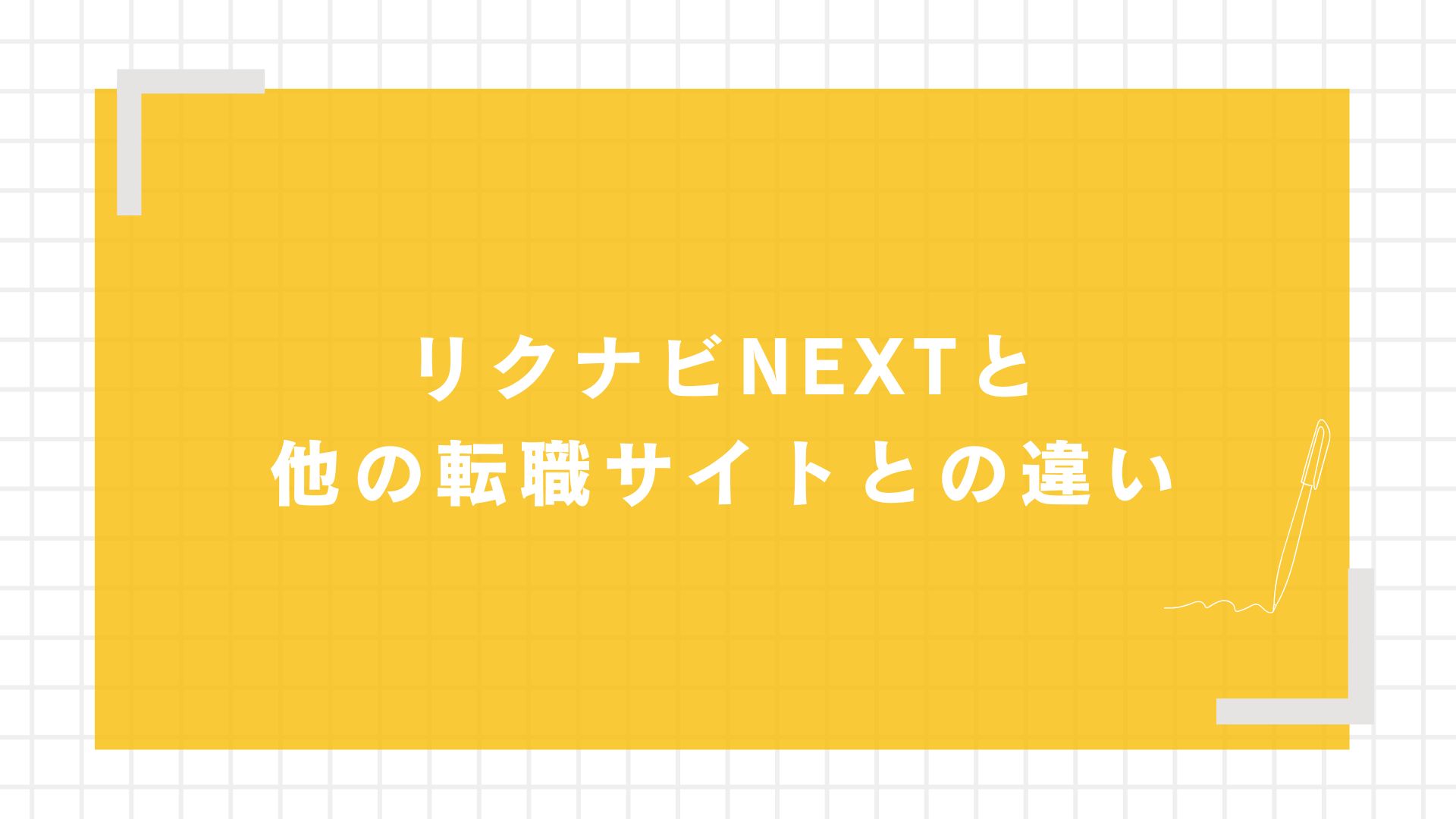
転職活動の主要サービスは多数存在しますが、提供形態や利用者層はそれぞれ異なります。リクルートエージェントやリクルートダイレクトスカウトといった同グループのサービス、さらにマイナビ転職やビズリーチといった競合サービスと比較すると立ち位置が明確に分かれます。
リクルートエージェントやダイレクトスカウトとの比較
リクナビNEXTは求人を検索して応募する「求人サイト」であり、キャリアアドバイザーによる個別支援は提供されません。対してリクルートエージェントは、担当アドバイザーが求人紹介や書類添削、面接対策まで伴走する「転職エージェント型サービス」であり、サポート期間は通常3〜6か月に設定されています。
また、リクルートダイレクトスカウトは登録者のプロフィールを見た企業やヘッドハンターからスカウトが届く仕組みを持ち、年収800万円以上の非公開求人が中心です。求人数と利用者規模で幅広さを誇るのがリクナビNEXT、短期での転職成功や専門サポートを重視する場合はリクルートエージェント、ハイクラス層へのアプローチを目的とするならリクルートダイレクトスカウトが適しています。
マイナビやビズリーチと比較した強み
他社サービスと比べた場合、リクナビNEXTの最大の強みは会員数と求人数の規模にあります。
マイナビ転職は2023年時点で会員数約756万人、dodaは2022年末で約750万人ですが、リクナビNEXTは約1,148万人を超えており大きな差を示していました。ビズリーチは約200万人の会員を擁しますが、対象はハイクラス層に限定されます。
一方でリクナビNEXTは幅広い年齢層や職種に対応し、地方や未経験歓迎の求人も豊富です。さらに、スマートフォンアプリの評価が高く「利用者数No.1」「ストア評価No.1」を獲得しており、利便性の面でも優位に立っています。

中途採用の募集文作成と確認に便利!
募集文ライティングのチェックリスト
募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き
求人掲載を成功させるためのポイント3選
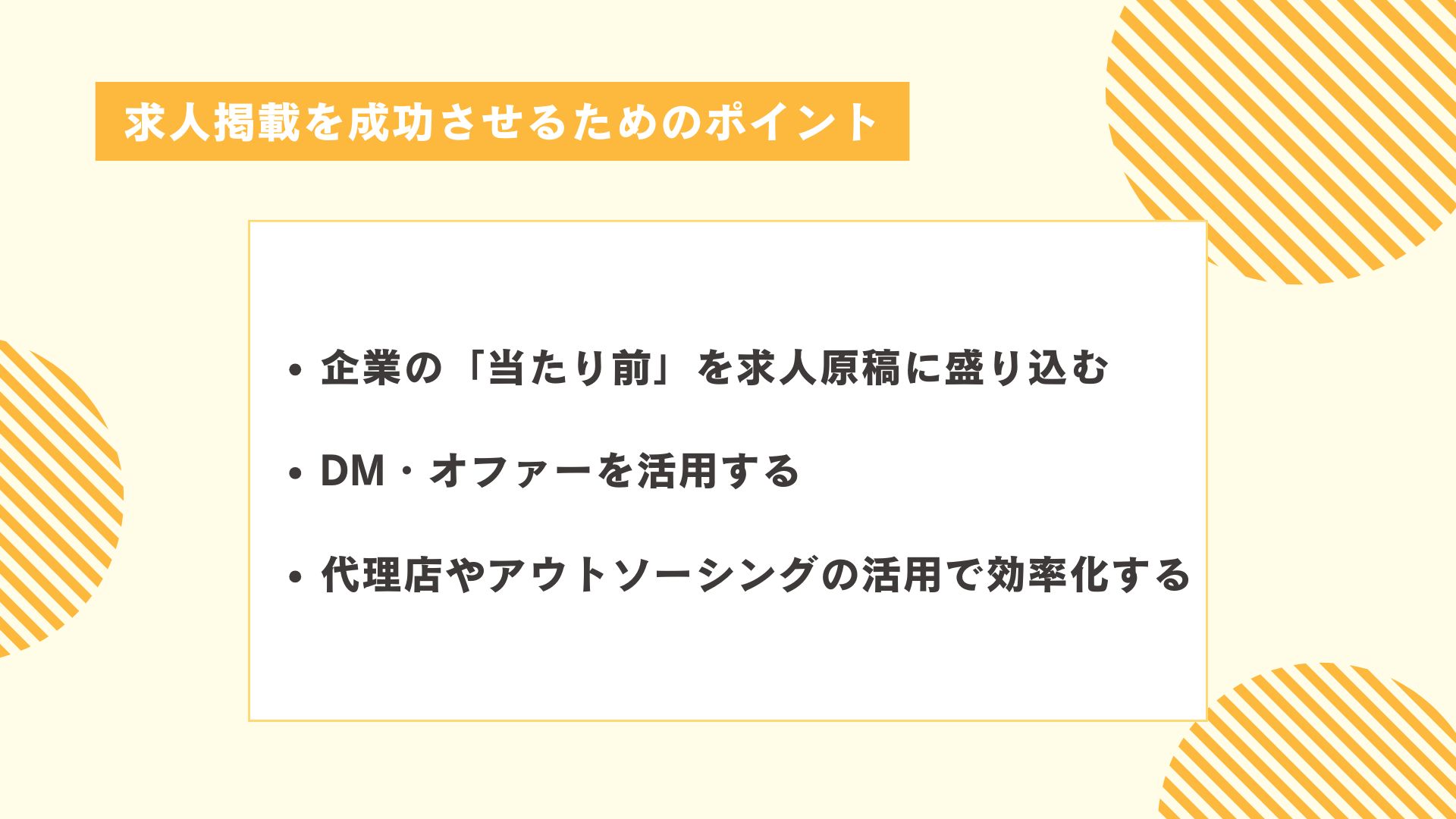
リクナビNEXTを有効に活用するためには、原稿内容の工夫やアプローチ手段の活用、代理店との連携が重要です。ここでは、採用成果を最大化するための3つの具体的なポイントを解説します。
企業の「当たり前」を求人原稿に盛り込む
求人原稿では給与や条件だけでなく、働く現場で日常的に感じられる魅力を伝えることが差別化の鍵になります。女性社員の働き方を紹介する写真やメッセージの掲載、第二新卒向けに「向いている人・向いていない人」を明記する方法などが効果的です。
Indeed PLUSへの移行後はオプション機能の制約があり、原稿改善の重要度は一層高まっています。タイトルや仕事内容の表現を継続的に見直し、応募者の反応をもとに最適化を重ねることで応募率の向上が期待できます。
DM・オファーを活用する
リクナビNEXTのアプローチ機能は単なる「送信手段」ではなく、応募率を高めるための戦略的ツールとして活用できます。例えば、AIが抽出した候補者に自動送信される「らくらくオファー」は母集団拡大に有効ですが、一方で即戦力を狙う場合は「ターゲットDM」でオリジナル文面を作り込み、候補者の経歴やスキルに合わせた具体的な魅力を伝える方が効果的です。
さらに、自社求人を閲覧した人材へ即座に反応できる「スピードアプローチ」を組み合わせると、熱量の高い応募を取り込みやすくなります。実際のデータでも、スカウトを受けた候補者の約3人に2人が応募に進み、閲覧者へ面接確約スカウトを送れば応募数は平均1.2倍に伸びています。
代理店やアウトソーシングの活用で効率化する
求人広告代理店や採用アウトソーシングを利用することで、採用計画から原稿作成、掲載後の分析までを一括でサポートしてもらえます。代理店は取材を通じて魅力的な求人原稿を作成し、掲載結果を分析して改善提案を行うため、中小企業に不足しがちなノウハウを補完します。
特にIndeed認定パートナー代理店に依頼すれば、クリック課金型運用や媒体最適化にも対応可能です。外部リソースを取り入れることで、費用対効果を高めつつ効率的に採用活動を進められます。
まとめ
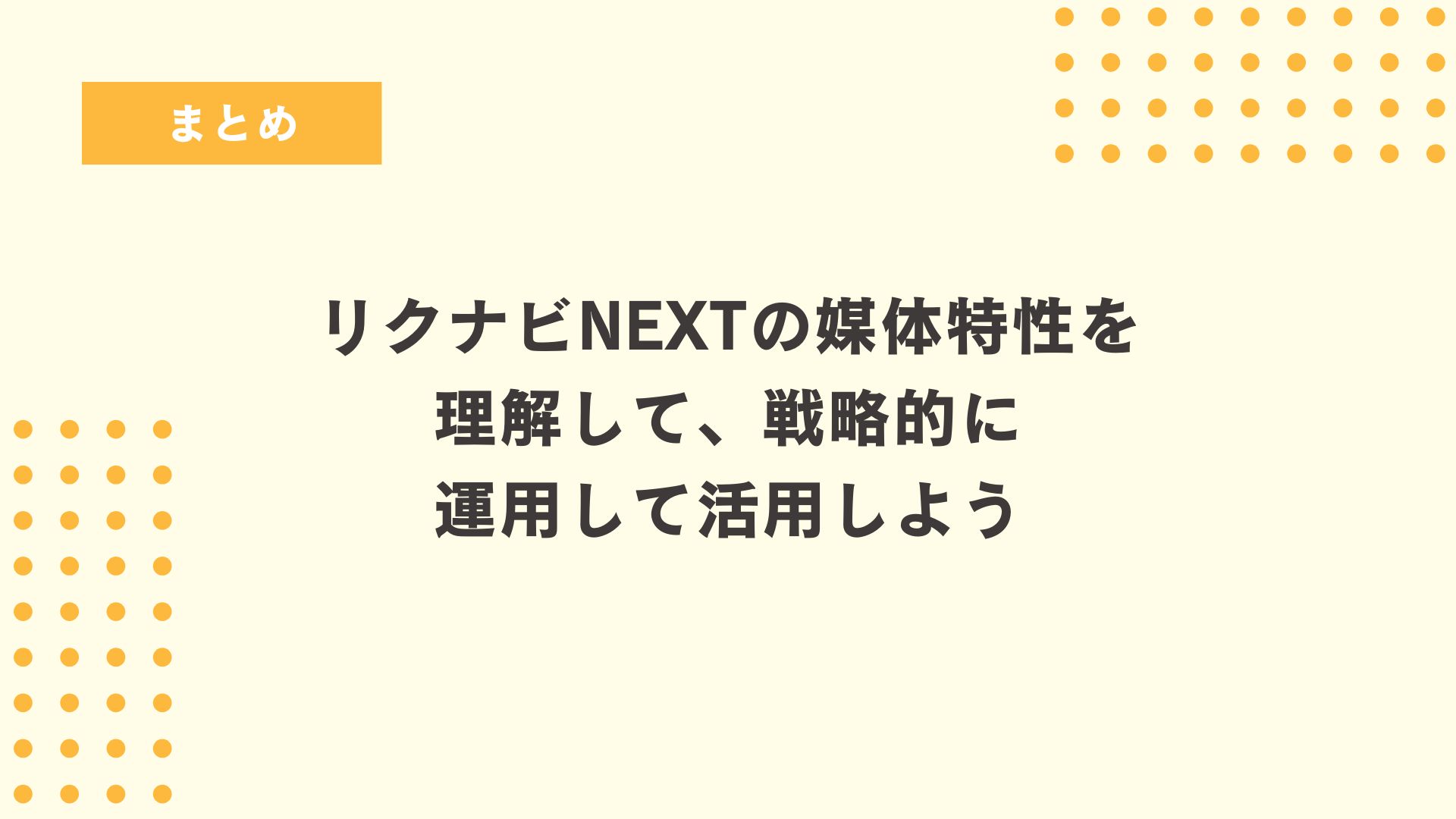
本記事では、リクナビNEXTの特徴や掲載料金の変化、利用時のメリット・デメリット、そして成功のための活用ポイントを整理しました。採用活動は媒体特性を理解し、戦略的に運用することが欠かせませんが、現場のリソース不足やノウハウの限界から成果につながらないケースも少なくありません。
採用に関する課題を解決する有効な手段が、外部の専門支援を取り入れることです。まるごと人事は、560社以上の支援実績と契約継続率95%以上を誇る月額制の採用チームで、設計から運用・改善まで一貫して伴走します。最短1か月から柔軟に導入できるので、採用体制の強化を検討する企業はぜひご相談ください。

中途採用の募集文作成と確認に便利!
募集文ライティングのチェックリスト
募集文作成に活用できるリストを無料で配布中!公開前に確認すべきチェックリスト付き
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事

【業界別】採用サイトのキャッチコピー事例50選|作り方のコツも紹介
- 採用媒体・チャネル
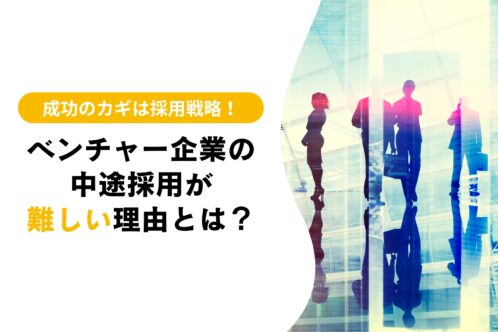
ベンチャー企業の中途採用が難しい理由とは?成功のカギは採用戦略!
- 採用企画
- 採用媒体・チャネル
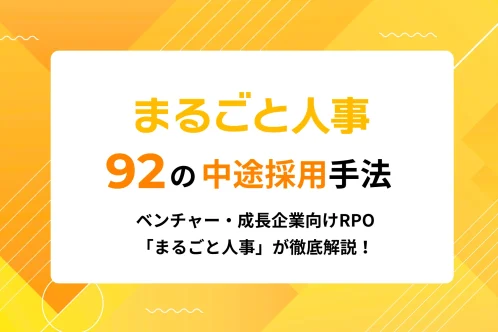
【中途採用の施策大全】92個の中途採用の施策まとめ
- 採用企画
- 採用媒体・チャネル
- 採用オペレーション
- 採用代行
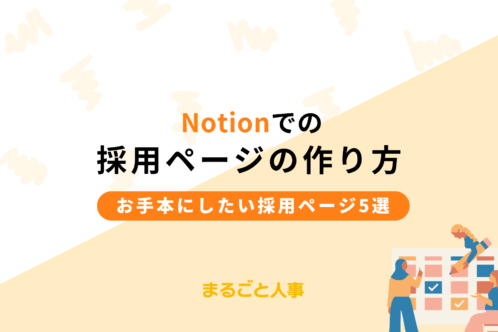
Notionでの採用ページの作り方|お手本にしたい採用ページ5選
- 採用媒体・チャネル
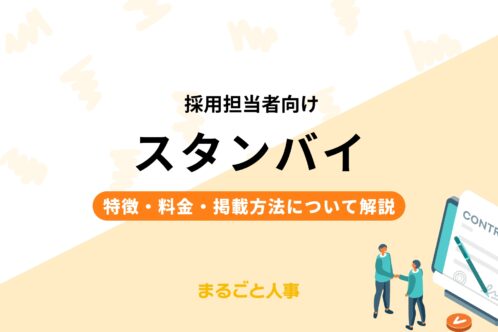
【採用担当者向け】スタンバイとは|特徴・料金・掲載方法について解説
- 採用媒体・チャネル
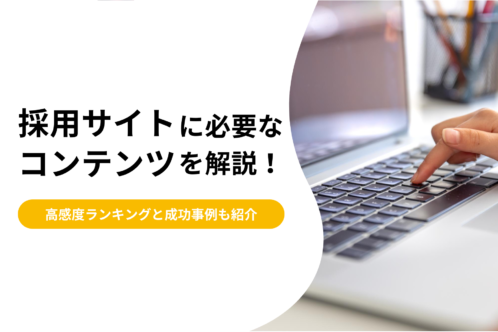
採用サイトに必要なコンテンツを解説!ホームページ高感度ランキングと成功事例も紹介
- 採用媒体・チャネル
- 採用広報










