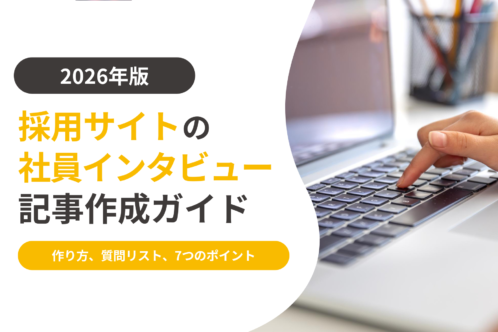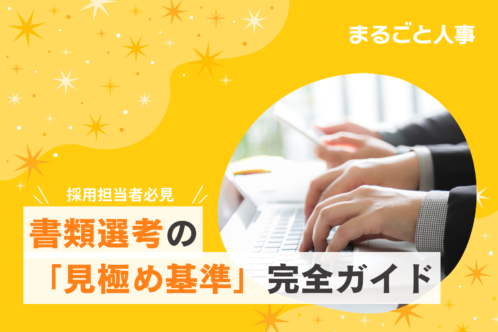採用・労務・経理に関するお役立ち情報
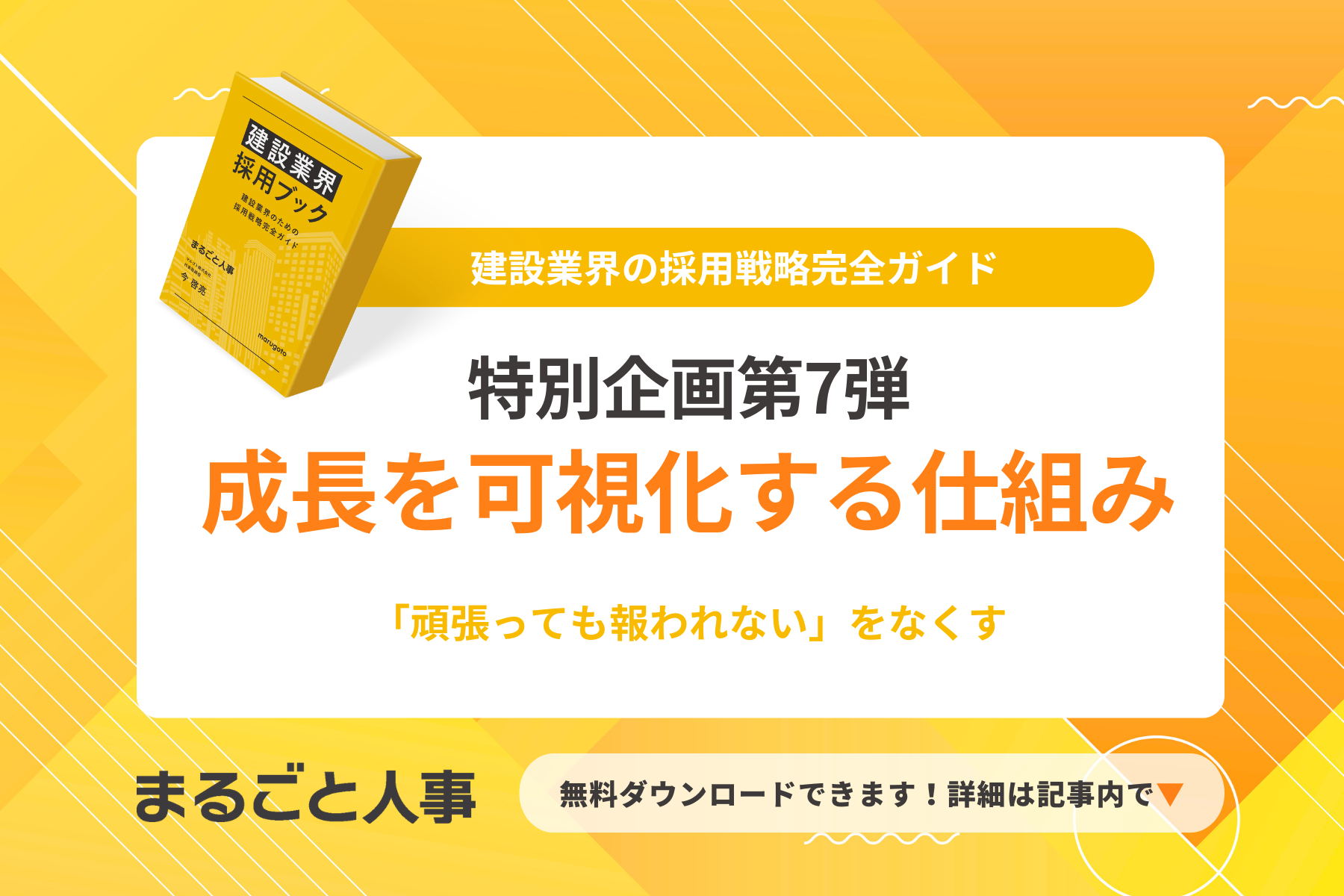
「頑張っても報われない」をなくす
多くの中小建設企業では、評価制度があっても、実際には年功序列や主観で判断されがちです。
- 評価基準が曖昧
- 何を頑張れば評価につながるか分からない
- 直属上司の印象だけで決まる
こうした状況では、「頑張っても意味がない」という空気が生まれ、モチベーション低下や離職につながります。
評価制度は、社員の成長と組織の成果を両立させる「道しるべ」であるべきです。
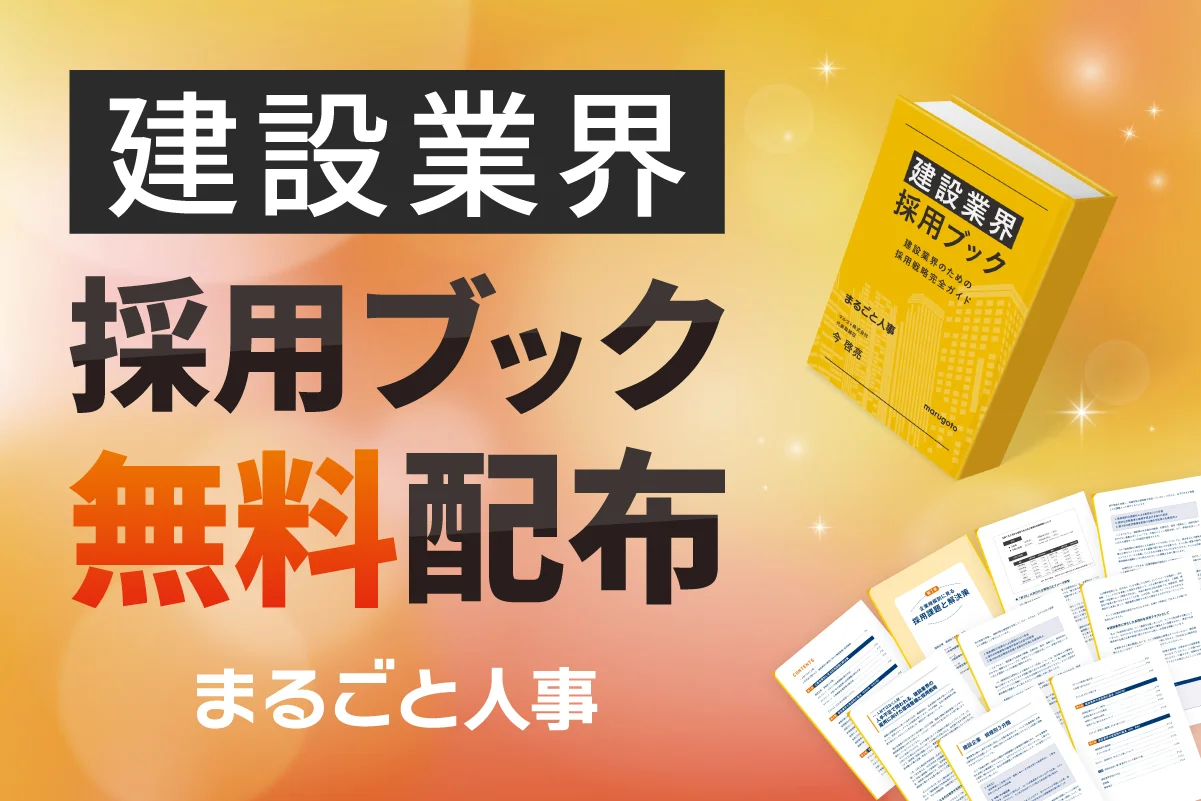
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
関連動画:建設業界採用ブックの解説動画
評価の目的は「成長支援」である
評価=査定というイメージが根強いですが、本来の目的は、「成長支援」です。
・いまどこにいて、
・何ができていて、
・次にどこを伸ばすべきか
を見える化することで、自分の現在地と進むべき方向を明確にできます。
そのためには、評価項目の明文化と、等級(グレード)による段階整理が有効です。
例)施工管理職のグレードイメージ:
- グレード1:材料管理、KY活動、図面理解
- グレード2:安全・工程管理、打合せ同席、帳票作成
- グレード3:現場リーダー、発注者対応、原価管理
このように「成長の階段」を可視化すると、現場で育つ・活躍するイメージが持てるようになります。
「主観ゼロ」は無理でも、納得感はつくれる
完全に主観を排除する評価は不可能です。しかし、「何を見ているか」を明確にすることで、納得感ある評価は可能です。
- 職能スキル(技術力、図面理解、安全意識)
- 業務成果(原価率、工期遵守、受注件数)
- 行動特性(報連相、後輩指導、当事者意識)
このように複数の軸でバランスよく評価し、「1on1面談」でフィードバックを行うことで、評価の透明性が高まります。
フィードバックは、褒める・課題を示す・期待を伝えるの3点を意識すると、相手の納得度が高まります。
キャリア面談は“短期志向”を防ぐ機会
若手社員ほど「とりあえず3年」「この現場が終わったら辞めよう」といった短期的なキャリア観にとらわれがちです。
そこで重要なのが、半年〜1年ごとのキャリア面談です。業務評価とは別軸で、
・今後やってみたいこと
・得意・不得意の実感
・将来像のイメージ
などを、本人の言葉で整理する時間を設けることで、「この会社で成長できそう」という感覚を育てます。
また、「本人の希望」と「会社の計画」のすり合わせを行う場としても機能します。
評価と処遇はどうつなげる?
「評価はするけど、給与は変わらない」という状態では、意味を持ちません。評価→等級→処遇(昇給・昇格)という流れを明示しましょう。
- 等級が上がれば手当が増える
- 役割が変われば職位が変わる
- スキルによって給与が上下する
といったルールを明確にしておくことで、社員の納得感や挑戦意欲につながります。
また、定期昇給と成果昇給を分ける設計をすると、公平性が高まります。
例:
- 定期昇給:年1回、在籍年数に応じて一律昇給
- 成果昇給:評価結果に基づいて個別加算
このように、評価が働き方・処遇・キャリアとつながることが、制度定着のカギとなります。
次回予告
次回は、「多様性時代の採用視点」というテーマで語ります。
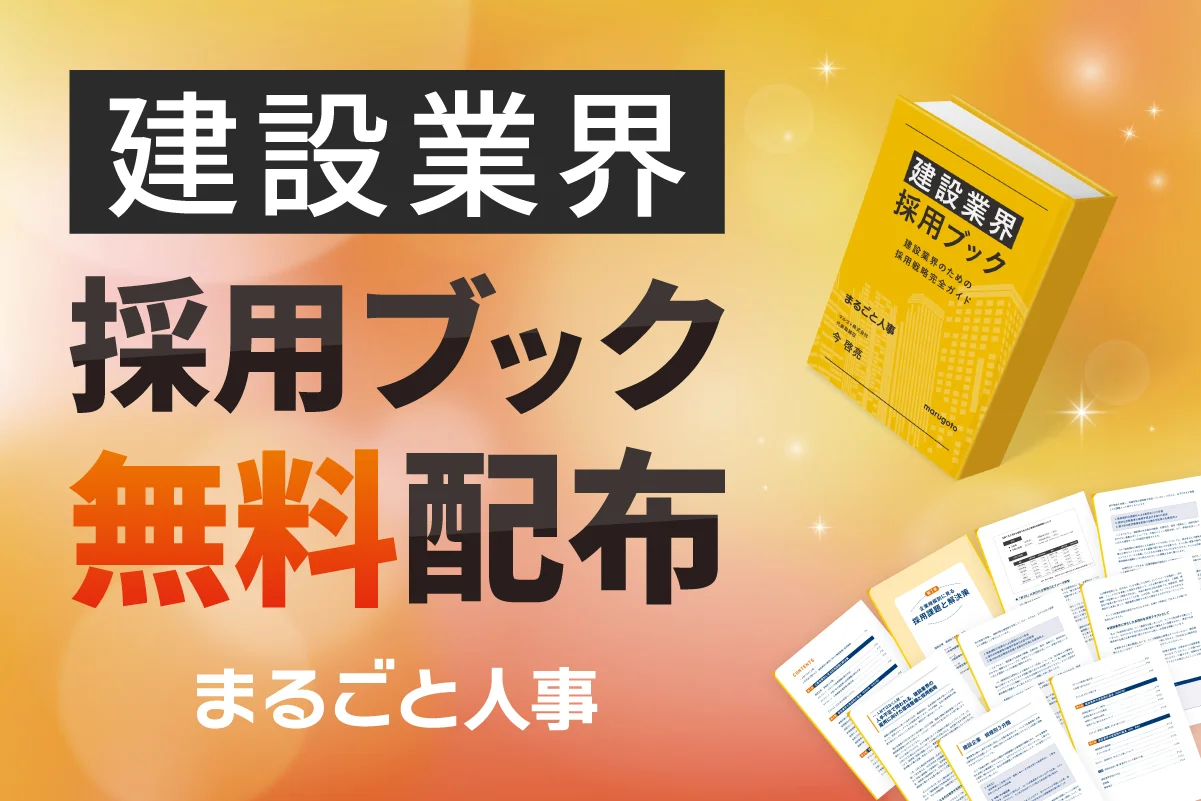
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
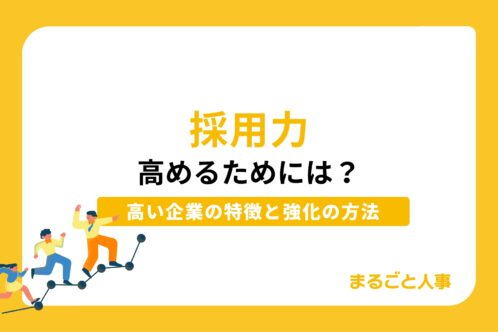
採用力とは?高い企業の特徴と強化するための7つの方法
- 採用企画
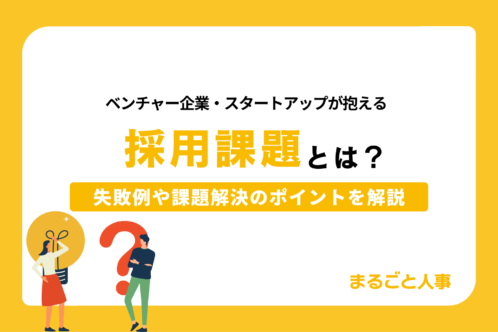
ベンチャー企業・スタートアップが抱える採用課題とは?失敗例や課題解決のポイントを解説
- 採用企画

現場監督の採用が難しい理由と成功の秘訣|転職動向から導く有効な採用戦略とは
- 採用企画
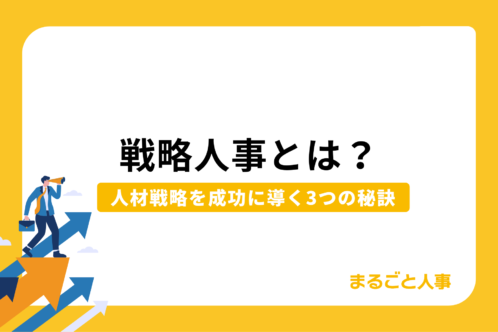
戦略人事とは?人材戦略を成功に導く3つの秘訣
- 採用企画
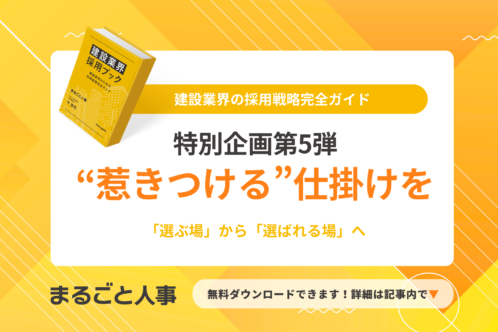
第5回 面接・選考で“惹きつける”仕掛けを【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】
- 採用企画
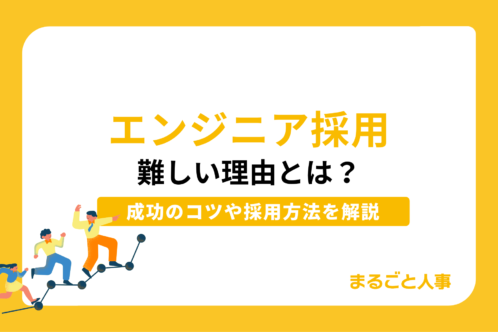
【2025年最新】エンジニア採用が難しい理由とは?成功のコツや採用方法を解説
- 採用企画