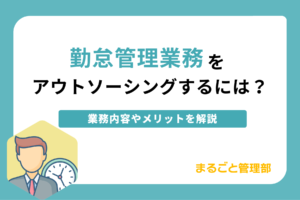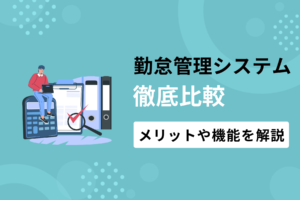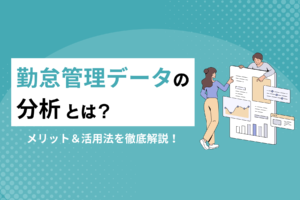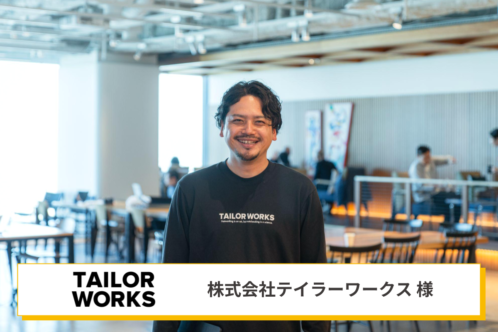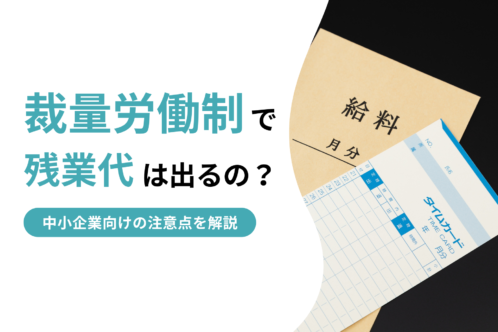採用・労務・経理に関するお役立ち情報
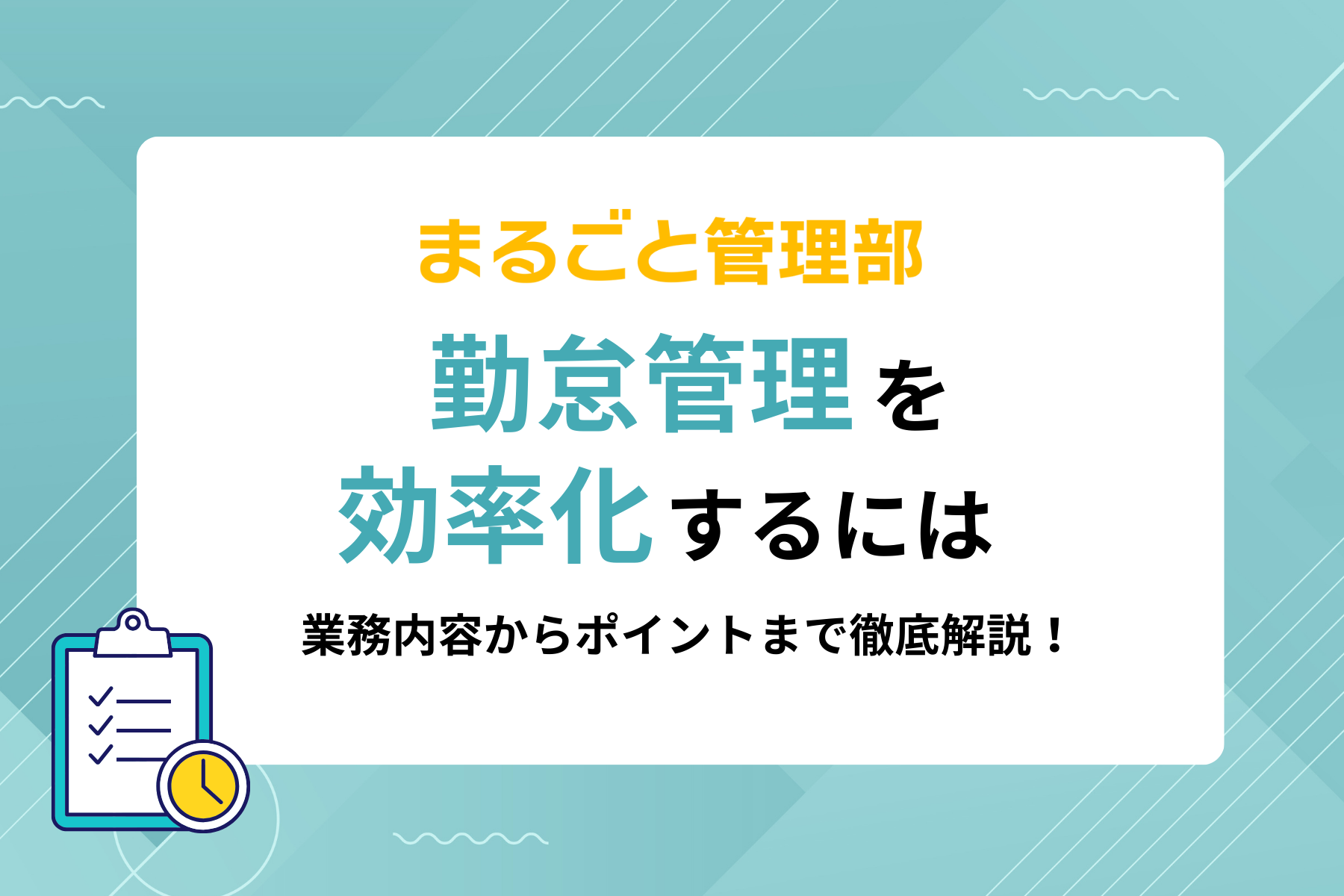
クラウド型勤怠管理システムやRPAの導入により、集計・申請フローの自動化、ミスアラートの即時通知など、業務負担を大幅に削減できます。
本記事では、勤怠管理を効率化するためのポイントと、おすすめのツールを紹介します。
日々の業務をより深く理解できるトピックスを扱っているので、勤怠管理業務の効率化や改善をしたいと考えている担当者様はぜひお役立てください。
「まるごと管理部 労務プラン」では、勤怠関連・給与業務をはじめとする業務を人事労務チームが代行します。1ヶ月単位の更新で低リスクで始めやすいのも特徴です。

労務の課題解決に役立つ
「HRテックツール カオスマップ2025」
労務業務の課題ごとに利用できるHRテックツールがわかる!全195種類のサービスを一挙紹介
目次
勤怠管理業務が煩雑になりやすい4つの要因

勤怠管理業務は企業経営に必要な業務でありながらも、働き方の多様化や法律の改正により年々複雑化しています。
ここでは、勤怠管理業務が煩雑になりやすい要因を3つ紹介します。
勤怠管理業務の改善方法を考えるためには、複雑化しやすい原因を把握しなければなりません。以下の要因はどの業界の企業にとっても共通のものを厳選しています。
勤怠管理業務に問題を抱えている方は下記を参考に、問題と感じている原因を明確にしてみてはいかがでしょうか。
1.勤務形態によって管理内容が異なる
勤務形態は労働者が働く際の勤務時間や労働条件を指します。
勤務形態によって労働時間の契約内容や、賃金の割増条件が異なるため、勤怠管理業務の管理内容も変わります。
誤った勤務形態や労働条件で勤怠を管理してしまうと、適切な給料を支払えなくなってしまうので注意が必要です。
代表的な勤務形態と管理方法は以下のとおりです。
| 勤務形態 | 所定労働時間 | 休憩の有無 | 時間外労働の割増有無 | 休日労働の割増有無 | 深夜労働の割増有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定時間制 (通常勤務) | 固定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 変形労働時間制 | 変動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フレックスタイム制 | 始業・終業を労働者に委ねる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 事業場外みなし 労働時間制 | 所定労働時間&みなし労働時間 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 裁量労働制 | みなし労働時間(時間は労働者にゆだねる) | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 高度プロフェッショナル制度 | なし | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| シフト制・ 交代勤務制 | 変動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宿直勤務制 | なし | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
| 管理監督者 | なし | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
2.扶養範囲内で勤務を希望する従業員への対応が必要
扶養控除は所得税や住民税の計算において、納税者が扶養している家族がいる場合に適用される控除です。
扶養控除の対象になるには年間の収入額を調整する必要があるため、扶養控除内での勤務を希望している従業員がいる場合、扶養控除の基準を考慮した勤怠管理が必要になります。
扶養控除の対象となる条件は法改正によって変わることがあるため、毎年確認する必要がある点も煩雑になりやすい要因の一つだといえるでしょう。
3.ミスにつながりやすい
従来の紙やエクセルでの勤怠管理は、集計に時間がかかるだけでなく、人為的ミスも多発しやすいという大きな課題があります。さらに、残業時間の把握が曖昧になりやすく、労基法や36協定に抵触するリスクも高まります。特に、従業員数が増える成長企業では「管理の手間」「正確性」「法令順守」のすべてが大きな負担となり、業務効率や従業員満足度に悪影響を及ぼします。
4.テレワークで働く従業員の対応が必要
テレワークは企業に出社せず働く性質上、タイムカードや紙の出勤表などの勤怠管理システムを活用している企業の場合、別の対応策を講じる必要があります。
なお、デジタルでの勤怠管理システムを使用しても、実態に即していない時間を打刻する可能性もあるため、定期的に実態調査を実行するなど、勤怠管理の適正化に努めなければなりません。

労務の課題解決に役立つ
「HRテックツール カオスマップ2025」
労務業務の課題ごとに利用できるHRテックツールがわかる!全195種類のサービスを一挙紹介
勤怠管理業務を効率化する3つのコツ

勤怠管理業務の効率化には、「勤怠管理システムの導入」、「労働時間の適正管理」、「アウトソーシングの導入」が有効です。それぞれの具体的な方法やメリットを解説します。
1. 勤怠管理システムの導入
✔ 勤怠管理システムとは?
勤怠データをデジタルで記録し、勤務時間の集計や給与計算に活用できるシステムです。手作業を削減し、勤怠管理をスムーズにします。
勤怠管理システムにはオンプレ型とクラウド型があるので注意が必要です。
✔ 勤怠管理システム導入のメリット
- 打刻ミスや入力ミスの削減
ICカードやスマホアプリで正確な打刻ができ、不正や記入ミスを防止。 - 集計作業の自動化
システムが出勤・退勤時間を自動集計し、手作業での確認や修正を削減。 - リアルタイムでのデータ管理
クラウド型なら、遠隔地の社員の勤怠状況もリアルタイムで把握可能。 - 給与計算や会計システムと連携
勤怠データを給与計算システムに自動連携し、転記ミスを防止。 - 法令遵守の強化
勤怠データを正確に自動集計できるため、残業時間の把握や有給休暇の管理が容易になる。 - 人材定着の強化
リアルタイムで勤務状況を確認できることで、マネジメント層は適切な労働時間管理が可能
2. 労働時間の適正管理
✔ 労働時間の適正管理とは?
従業員の労働時間を適正に管理し、長時間労働を防ぎながら業務の効率化を図ることです。勤怠管理システムが自動で記録を行う一方で、管理ルールの設定や従業員の意識向上が求められます。
✔ 労働時間の適正管理のメリット
- 長時間労働の抑制
事前に労働時間の上限を設定し、超過しそうな場合にアラートを発信。 - 休憩・休暇の取得促進
有給休暇の取得状況を可視化し、計画的な取得を促進。 - 業務負担の平準化
過重労働を防ぎ、適正な労働時間配分を行うことで、効率的な業務運営が可能。 - コンプライアンス対応の強化
労働基準法の遵守を徹底し、労務リスクを低減。
3. アウトソーシングの導入
✔ 勤怠管理のアウトソーシングとは?
勤怠データの集計、給与計算、法改正対応などを外部の専門業者に委託する方法です。業務負担を軽減し、正確な処理を実現できます。
✔ アウトソーシング導入のメリット
- 勤怠管理業務の負担軽減
管理者が行うデータ確認・修正作業を大幅に削減し、本来の業務に集中できる。 - 専門家による正確な処理
法令改正や最新の労務管理ルールに基づいた適切な対応が可能。 - コストの最適化
システム導入や社内教育のコストを抑えつつ、必要なサービスだけを利用できる。 - トラブル対応の迅速化
勤怠データの異常値や不正打刻のチェックを専門業者が行い、問題発生時の対応が迅速化。
まとめ
- 勤怠管理システムの導入により、記録・集計の自動化と転記ミスの削減が可能。
- 労働時間の適正管理を行うことで、長時間労働を抑制し、コンプライアンスを強化。
- アウトソーシングの活用により、業務負担を軽減し、専門的な知識による適正な管理が可能。
これらを組み合わせて活用することで、勤怠管理業務を効率的に運用できます。

労務の課題解決に役立つ
「HRテックツール カオスマップ2025」
労務業務の課題ごとに利用できるHRテックツールがわかる!全195種類のサービスを一挙紹介
勤怠管理の効率化を実現するアプローチ方法

社内で完結する方法(内製アプローチ)
勤怠管理をすべて社内で行う方法です。
クラウド型の勤怠管理システムを導入すれば、打刻・休暇申請・残業集計などを自動化でき、紙やExcelでの作業が減ります。
また、運用ルールを明確にし、従業員にも操作方法をしっかり周知することで、打刻漏れや申請ミスを防げます。
社内で仕組みを整えることで、自社に合わせた柔軟な運用が可能になります。
メリット:
- 外部委託費用がかからない
- 自社ルールに合わせて運用できる
- 社内にノウハウが蓄積される
注意点:
- ノウハウ不足があると初期設定や運用ルールづくりに手間がかかる
- 労務担当者の負担が残る
労務代行サービス・社労士事務所に委託
勤怠管理や給与計算などを、労務の専門家に任せる方法です。
勤怠データの集計、残業時間のチェック、法改正への対応などを代行してもらえるため、担当者の負担を大幅に減らせます。
特に、法令遵守が求められる勤怠管理では、社会保険労務士事務所などのサポートが安心です。
毎月の勤怠締めや給与計算を正確に行いたい企業におすすめです。
メリット:
- 専門家による正確な処理
- 法改正や就業規則変更にも対応してもらえる
- 担当者の負担が減る
注意点:
- 月額費用がかかる
- 急な変更対応には時間がかかる場合がある
勤怠管理システムのカスタマーサクセス・導入支援を活用
クラウド型勤怠管理システム(SaaS)を導入するときは、
ツール提供会社のカスタマーサクセス(導入支援担当者)に相談するのも効果的です。
初期設定や勤怠ルールの登録、打刻方法の設定などをサポートしてもらえるため、導入がスムーズになります。社内に詳しい人がいなくても、正しい設定で運用をスタートできる点が魅力です。
メリット:
- システム導入がスムーズになる
- 導入後の運用定着をサポートしてもらえる
- 費用が比較的安い
注意点:
- どのシステムを選ぶのかは自社で調べて決める必要がある
- 対応範囲はシステム設定や操作方法の支援など一部に限られるためリソースはかかる
- 労務や法令面の相談には対応していない
業務を効率化できる勤怠管理ツールの種類3選

勤怠管理業務を効率化するツールは複数あり、それぞれメリットとデメリットが異なります。
ここでは勤怠管理業務を効率化できるツールを3つ解説します。
従業員のITスキルや自社の予算を考慮して、ニーズにマッチしたツールを選択してみてはいかがでしょうか。
| 種類 | 特徴 | 費用の目安 |
| 勤怠管理システム(オンプレミス) | ・主に大企業で導入される ・自社のサーバーにソフトウェアをインストールして使用する ・運用コストが発生する ・独自のカスタマイズが可能 | ・初期費用:約30~200万円 ・運用・管理コスト:約1万円/月 |
| 勤怠管理ソフト(SaaS) | ・主に中小企業で導入される ・サーバーがクラウド上にある ・初期費用を抑えられる ・インターネット環境があればどこでも利用できる ・スマートフォンアプリに対応しているものもあり | ・初期費用:約3~50万円 ・月額利用料:従業員1人あたり約200円~500円 |
| スマートフォンアプリ型勤怠管理システム | ・主に中小企業で導入される ・スマホにアプリをインストールして使用する ・集計コストが発生する ・細かいカスタマイズはできないことが多い | ・運用・管理コスト:1人100~500円/月 |
勤怠管理システム(オンプレミス)
勤怠管理システム(オンプレミス)は自社でサーバーを構築し、管理するツールを指します。
オンプレミス型のメリットは以下のとおりです。
- 自社の働き方・特性にあったカスタマイズがしやすい
- 情報漏洩のリスクが少ない
オンプレミス型のデメリットは以下のとおりです。
- 初期費用が高い
- 自社にITスキルのノウハウがないと運用が難しい
- システムのサポートが終わると変更が必要になる
導入コストが高く、うまく運用を始めるにも労力と専門知識が必要になるので、ある程度規模の大きい企業でないと導入が難しい傾向が強いです。
勤怠管理ソフト(SaaS)
勤怠管理ソフト(SaaS)はインターネットを経由して、外部の勤怠管理サーバーを活用するツールを指します。
SaaS型のメリットは以下のとおりです。
- 導入が簡単にできる
- 初期費用が安い
SaaS型のデメリットは以下のとおりです。
- 外部のサーバーを活用するため、情報漏洩のリスクがともなう
- 自社の特性に合わせたカスタマイズが難しい
初期費用・管理コストが低いだけでなく、多種多様なソフトが展開されているため、自社にマッチしている仕様であれば中小企業でも導入しやすいツールであるといえるでしょう。
スマートフォンアプリ型勤怠管理システム
スマートフォンアプリ型勤怠管理システムは、スマートフォンに専用のアプリをインストールし管理するツールを指します。
スマートフォンアプリ型勤怠管理システムのメリットは以下のとおりです。
- リモートワークでも問題なく対応できる
- 打刻機など、専用のデバイスが必要ない
スマートフォンアプリ型勤怠管理システムのデメリットは以下のとおりです。
- 端末の機種やOSによって使用できない場合がある
- 不用意にOSをアップデートしてしまうと、動かなくなる恐れがある
どこでも簡単に打刻できる強みがあるため、フィールドワークの多い企業におすすめです。
勤怠管理を効率化した事例を紹介

労務代行サービス「まるごと管理部(労務プラン)」を導入し、勤怠管理業務を効率化した事例を紹介します。
まるごと管理部(労務プラン)では、効率化に関わるツールへの移行作業までサポートしておりますので、スムーズに業務効率化を進めることができます。
勤怠管理の工数を、約60%削減した事例
LOVEをはぐくむ家族型ロボット『LOVOT(らぼっと)』を展開しているGROOVE X株式会社。労務のリソース不足とノウハウ不足のため、まるごと管理部(労務プラン)を導入いただきました。
複数の店舗があるなか、システムは導入していたものの、勤怠情報を入力してもらうためのリマインドなどに時間がかかっていました。
まるごと管理部(労務プラン)では、システムの活用を進めると同時に、社員の方が運用しやすいようなフローも構築。
社内でかかっていた工数の60%ほどを削減することに成功しました。
月次業務の締め日を5日短縮した事例
AIを活用したBtoBマッチメイキングエンジン『TAILOR WORKS』を提供しているベンチャー企業 株式会社テイラーワークスでは、バックオフィスのリソース不足や属人化といった課題を抱えていました。バックオフィス担当者の退職を機にまるごと管理部(労務・経理プラン)を導入し、実務の代行はもちろん、業務フローの整備やシステムの導入なども依頼。
マルゴトでは勤怠チェックや給与計算などの業務フローを見直し、システム活用によって効率化を図れる業務はシステム活用も推進しました。
結果、月末の締めにかかる日数を5日短縮。ベンチャー企業でありながら、安定的なバックオフィス運営が実現できています。
勤怠管理の方法を解説

勤怠管理には、下記のような複数の手法があります。自社が今どの手法を導入しているかによって、効率化の方法も変わってきます。
1.タイムカード(打刻機)
- 概要: 出勤・退勤時に打刻機でタイムカードを記録する方法。
- メリット: シンプルで導入コストが低い。
- デメリット: 不正打刻のリスクがあり、手動集計が必要。
2.ICカード・指紋認証・顔認証
- 概要: ICカードや生体認証を用いて打刻する方法。
- メリット: なりすましを防止し、正確なデータを取得できる。
- デメリット: 初期導入コストが高い。
3.勤怠管理システム(クラウド型・オンプレミス型)
- 概要: 専用のシステムを使って、PCやスマートフォン、タブレットなどから打刻する方法。
- メリット: リアルタイムでデータを確認でき、給与計算とも連携可能。
- デメリット: 操作習得やシステム維持費がかかる。
4.ワークフローシステムの活用
- 概要: ワークフローを活用して、複数のシステムを連動
- メリット: 入力のミスや工数が減る。
- デメリット: システムの仕様変更があった場合にエラーになることも。
5.Excel・スプレッドシート
- 概要: 出勤・退勤時刻を手入力し、管理する方法。
- メリット: 無料で運用可能。
- デメリット: 手作業が多く、ミスや不正のリスクがある。
勤怠管理の効率化は企業成長に必要不可欠

本記事では業務効率化につながる、勤怠管理に関する情報を解説しました。
勤怠管理の効率化には多くの方法があるため、自社の特色に合った方法を選択することが重要です。
多様なツールをスムーズに確認するためにも、勤務形態や規模を元に煩雑になっている課題を特定し、自社に必要なツールの機能や特長を明確にすることを心がけましょう。
勤怠管理に手間がかかるなど、勤怠管理に関する悩みがある経営者・管理部門のご担当者様がいましたら、労務ノウハウが豊富な「まるごと管理部(労務プラン)」に相談してみてはいかがでしょうか。
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
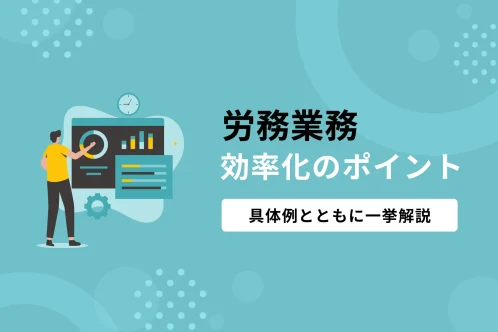
労務業務を効率化する5つのポイント|具体例とともに解説
- バックオフィス業務
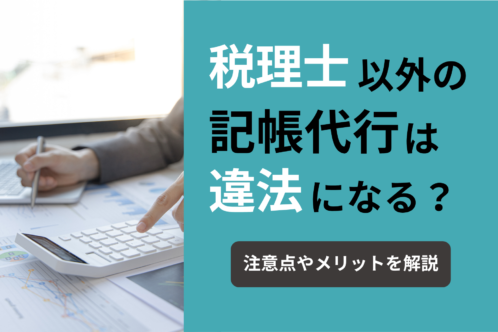
税理士以外が記帳代行すると違法になる?注意点や依頼のメリットを解説
- バックオフィス業務
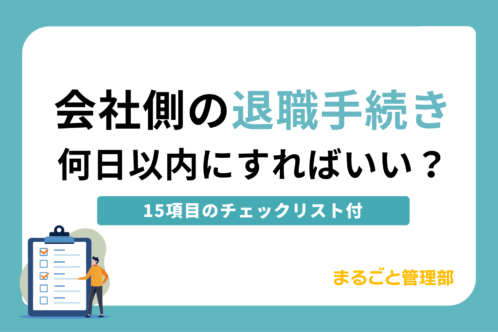
【会社側】退職手続きチェックリスト付き|15項目と実務ポイントを解説
- バックオフィス業務

介護事業所の労務管理はどんな業務?効率化に向けたポイントを解説
- バックオフィス業務
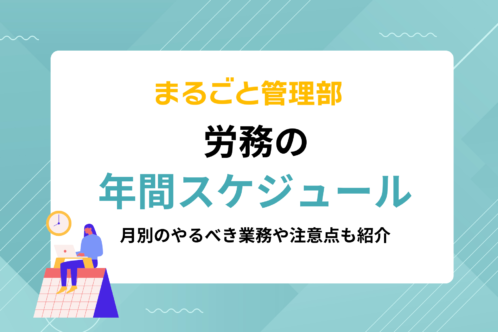
労務の年間スケジュール|月別のやるべき業務や注意点も紹介
- バックオフィス業務

勤怠管理システムの導入を成功させるには?基礎からポイントまで解説
- バックオフィス業務