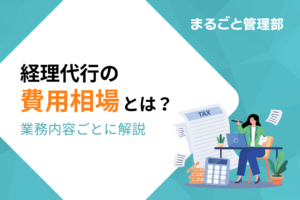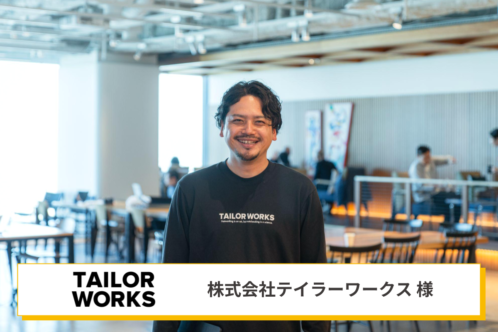採用・労務・経理に関するお役立ち情報
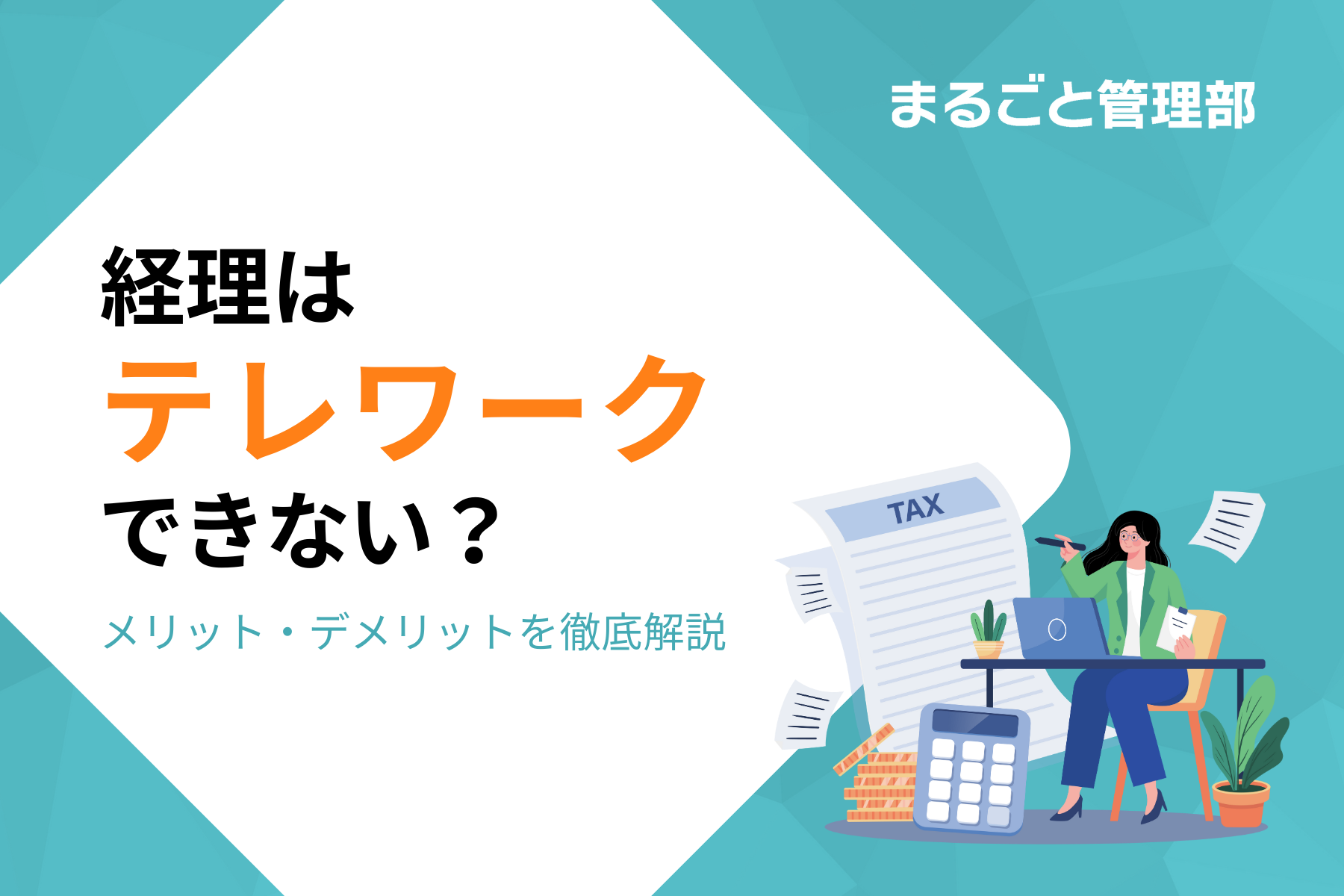
多様な働き方が推進される現代では、テレワークも新たな選択肢として定着しつつあります。一方で「経理業務はテレワークに向かない」と考える企業も少なくありません。脱ペーパー・ハンコ、セキュリティへの懸念など、経理のテレワークには課題も多いからです。
今回は経理業務のテレワーク化における課題と対応策、導入によるメリット・デメリットを見ていきましょう。
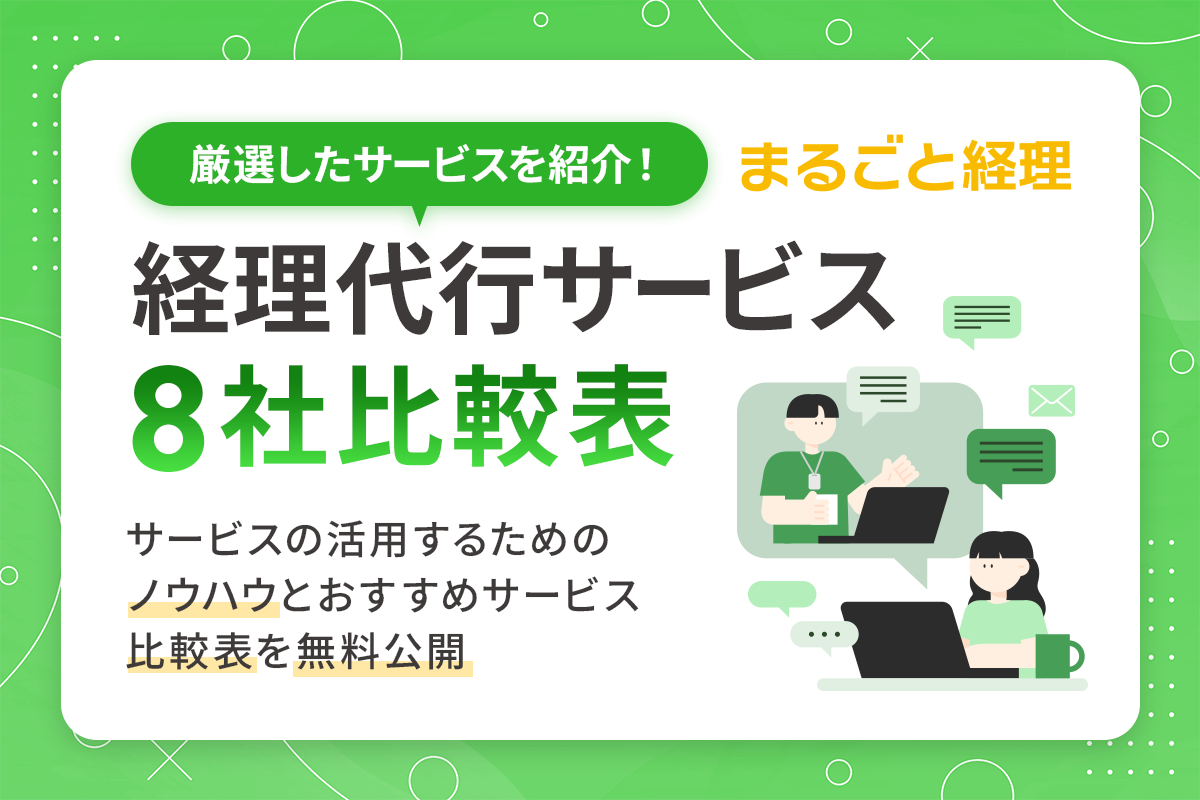
経理代行サービス比較表
経理代行サービスの活用の基本を解説。8社のサービスが一気に比較できます!
目次
経理はテレワークが難しい? リモート化における課題とは

経理業務のリモート化には、どんな課題があるのでしょうか。まずは経理業務のテレワーク化が進む背景と課題、対応のポイントをまとめました。
テレワークの需要は増している
新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに広がったテレワークは、今や一般的な働き方のひとつです。ワークライフバランスの改善や働き方改革の推進によって、場所や時間に縛られない柔軟な働き方への社会的な需要も高まっています。
多くの企業では営業部門や企画部門などでテレワークが浸透している一方、経理部門はオフィスに出勤して業務を行うケースが少なくありません。部門間の扱いの差は、社内の不公平感を生み出す要因にもなりえます。
無理なく業務に支障を来さない形で経理のテレワークを可能にするためには、どうすればよいのでしょうか。
テレワークで経理を行う際の課題
総務省の調査(参考:https://telework.mhlw.go.jp/telework/trs/)では、テレワークを導入している企業は、令和5年の時点で約50%に達しました。一方、令和2年の厚生労働省の調査(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000782363.pdf
)では、テレワークできない理由の1位は「テレワークでできる業務が限られているから」(68%)です。また同調査では、経理を含めた事務職は最もテレワーク率の高い職種となりました。
比較的テレワーク率の高い事務職の中で、どうして経理のテレワークは難しいのでしょうか。そこには、経理業務特有の課題が関係しています。
経理のリモート化は脱ペーパー化がカギ
総務省が2024年に公表した「テレワークの普及定着に向けた課題と対応策に関する調査研究結果報告書」(参考:https://www.soumu.go.jp/main_content/000951880.pdf)では、テレワークが定着しない理由は「コミュニケーション」に次いで「紙が多いから」が多くなりました。
経理部門は、請求書や領収書などの紙資料を多く扱う部署です。特に日本企業では、伝統的に紙の帳票や請求書が使われてきました。さらに経費の承認や支払い手続きにおいては、承認者の押印を必要とする「ハンコ文化」も根強く残っています。対面を前提とした業務が、要因が経理業務のテレワーク化を難しくしているのです。
電子帳簿保存法の改正によって領収書や請求書のデータ保存が義務となるなど、社会的にも脱ペーパー化の流れが進んでいます。経理のテレワークを進めるには紙ベースの業務フローを見直し、脱ペーパー化の推進が必要です。
とはいえ、すべての経理業務を脱ペーパー化することは、取引先の対応状況や社内のシステム環境によっては難しい場合もあります。経理では、リモートでできる業務とできない業務を適切に切り分け、効率的な業務分担を行わなくてはならないのです。
経理業務をリモート化するメリット・デメリット

経理業務のテレワーク化は、企業と従業員の双方にさまざまな影響をもたらします。導入を検討する際は、メリットとデメリットの両面を理解したうえで、自社に適した方法を選択しましょう。
メリット
経理業務のリモート化には、以下のようなメリットがあります。
①電子化によって業務が効率化する
書類の電子化が進むと経理のリモート化が可能になるだけでなく、業務プロセスそのものが効率化します。
経費申請や経理処理がオンラインで完結するようになれば、従業員の手続きの手間が大幅に削減されるからです。本来の業務に集中できるようになり、企業全体の生産性向上にもつながります。
さらに経理部門では、請求書や領収書などの紙の管理業務が減少します。文書の保管スペースも不要になり、検索性も向上するので、書類管理が容易になるのです。さらに経理データが電子化されることで、財務状況の把握や詳細な業績分析もしやすくなります。
②紙によるトラブルが減る
リモート化に伴う脱ペーパー化は、電子帳簿保存法への対応も容易にします。電子帳簿保存法は、ペーパーレス化による文書管理の手間削減やコストカットなどを目的とした法律です。
紙の書類を長期保存する場合、破れたり色あせたりして劣化するリスクがあります。また、火災や水害などの災害による損失、盗難や紛失のおそれもあるでしょう。請求書や領収書を電子化しておけば、こうしたリスクを大幅に軽減できます。
またクラウドシステムを活用すれば、バックアップも容易になり、データの安全性も向上します。
③多様な働き方が可能になる
経理業務がリモートで行えるようになれば、さまざまな事情を抱える従業員が働きやすくなります。育児や介護と仕事の両立が容易になり、離職率の低下にもつながるでしょう。
柔軟な働き方ができる環境は、新たな人材の獲得にも有利に働きます。特に2025年からは、改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。4月から事業主は、子育て中の従業員に対して、3歳になるまでの間、テレワークなどの柔軟な働き方を提供することが努力義務となりました。
経理部門でもテレワークが可能になれば、こうした社会要請にも対応が可能になります。
④通勤時間・コストの削減
テレワークを導入すると、経理担当者の通勤にかかる時間や交通費も削減されます。長時間に及ぶ通勤時間を有効活用できれば、ワークライフバランスの向上や業務効率の改善にもつながります。
企業側にとってもオフィススペースの縮小や通勤手当の削減など、コスト面でのメリットが大きい取組です。
デメリット
経理業務のリモート化で注意したい点は、以下のとおりです。
①情報セキュリティのリスク
経理部門は企業の財務情報や取引先情報、従業員の個人情報など、機密性の高い情報を扱います。これらの情報を自宅など社外で扱うことによる、セキュリティリスクは無視できません。
リモートワーク環境では、情報漏洩対策のためのセキュリティ対策が必須となります。対策には追加のコストや、運用ルールの整備が必要となるでしょう。
②コミュニケーションの希薄化
オフィスで顔を合わせて仕事をする場合と比べて、テレワークではコミュニケーションが希薄になりがちです。
特に経理業務では、領収書の確認や予算に関する相談など、細かなやり取りが必要なケースが多くあります。オンラインツールだけでは、こうしたコミュニケーションがスムーズに行かず、すれ違いや情報伝達ミスが生じる可能性もあります。情報のチェック体制や、相談窓口などを整えましょう。
③業務の切り分けの難しさ
経理業務では紙の原本確認や社内の承認印が必要な業務など、オフィスでの作業が不可欠なケースもあります。現実的には、すぐにすべての経理業務をテレワークで行うことは難しい場合が多いかもしれません。
まずはリモートで行える業務と出社が必要な業務を適切に切り分け、効率的な勤務体制を構築する必要があります。業務の切り分けや勤務管理が複雑になることも、デメリットのひとつと言えるでしょう。
経理業務のリモート化にはアウトソーシングもおすすめ
経理業務のテレワーク化を検討する際、煩雑な業務改革や環境整備に裂けるリソースがない企業では、アウトソーシングもおすすめです。リモート化が難しい業務を専門の業者に委託することで、自社の経理担当者はより専門的な業務に集中できます。
まるごと管理部(経理プラン)では、ツール導入・仕組みづくりから日々の業務まで、専門スタッフが代行。年末調整や決算サポートといった、年次業務も支援します。1か月単位で導入可能なうえ、マニュアルやフロー整備でノウハウの継承も可能です。
経理業務のアウトソーシングは、人手不足解消や社内研修の簡略化にもつながります。長期的には、コストパフォーマンスのよい選択肢なのです。
まとめ

経理業務のテレワーク化には、適切な準備と対策が必要です。紙の書類やハンコが必要な業務を見直し、脱ペーパー化を進めることで、社会的要請にも応えられます。
さらにテレワーク化が実現すれば、業務効率の向上やトラブルの減少のほか、従業員の働き方にもよい影響があります。一方で、情報セキュリティのリスクやコミュニケーションの希薄化、業務の切り分けには、慎重な対策が必要です。
すべての経理業務をテレワーク化することが難しい場合は、アウトソーシングの活用もおすすめです。専門業者に業務を委託することで、自社の経理担当者はより適した業務に集中できるようになります。
電子帳簿保存法の改正など法制度の整備も進み、テレワーク化に向けた環境は整いつつあります。企業の規模や業務内容に応じて最適な方法を選択し、段階的に導入を進めていきましょう。
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
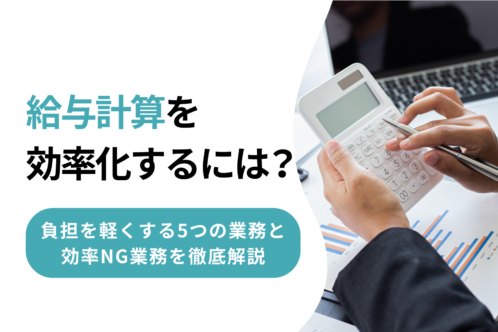
給与計算を効率化するには?自動化できる5つの業務とNG業務を徹底解説
- バックオフィス業務
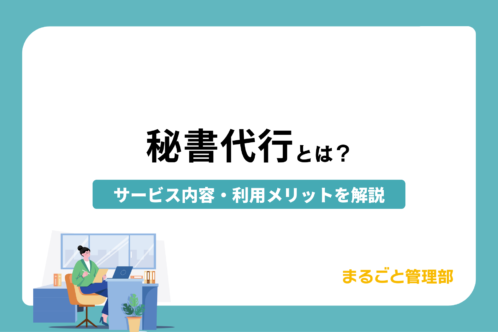
秘書代行とはどんなサービス?利用メリットを解説
- バックオフィス業務
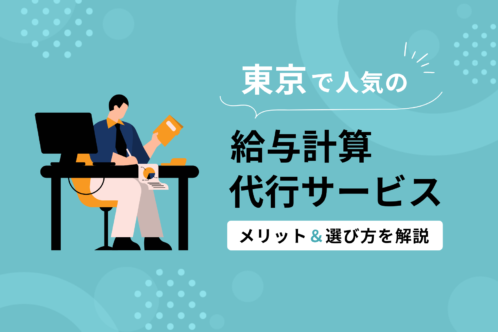
東京で人気の給与計算代行サービス4選!利用のメリットや選び方を解説
- バックオフィス業務

おすすめの経費精算システムとは?比較ポイントを解説
- バックオフィス業務

大阪のおすすめ経理代行業者4選!依頼できる業務も合わせて解説
- バックオフィス業務
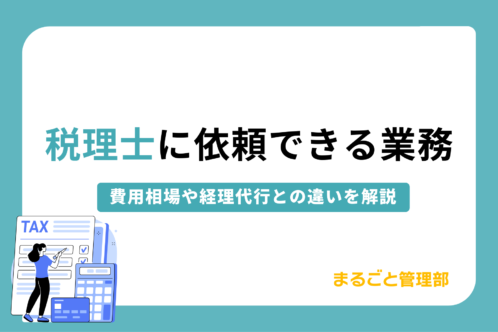
税理士に依頼できる業務とは?費用相場や経理代行との違いを徹底解説
- バックオフィス業務