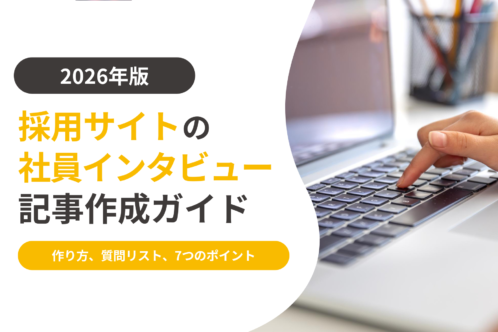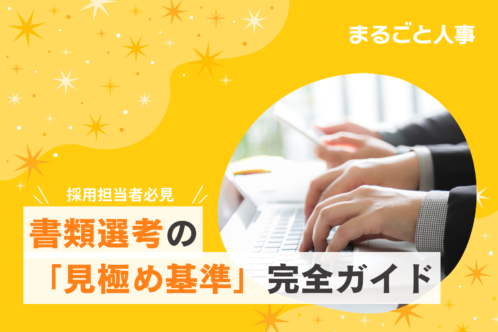採用・労務・経理に関するお役立ち情報
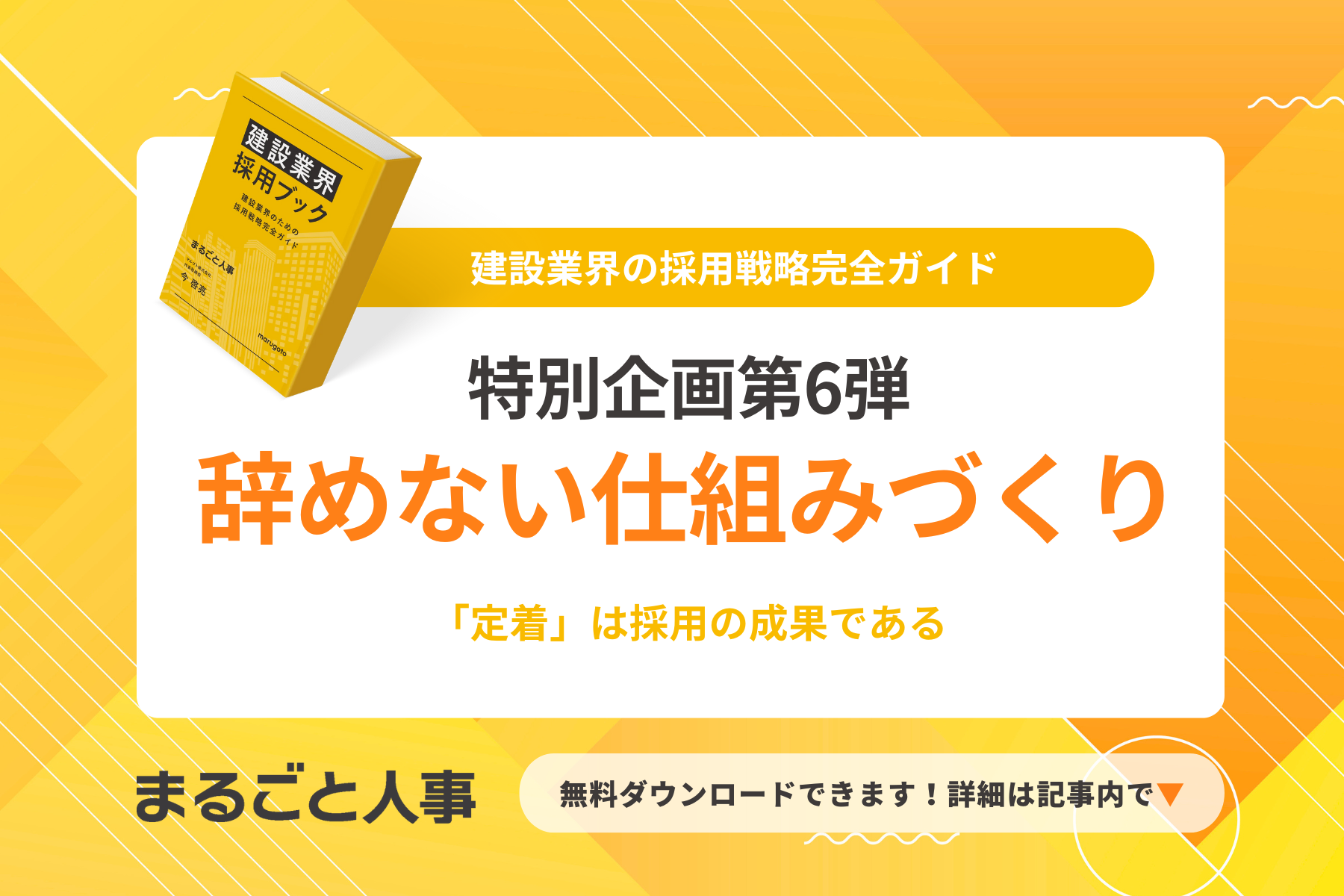
「定着」は採用の成果である
せっかく時間と費用をかけて採用しても、早期離職が続けばその努力は無駄になってしまいます。特に建設業界では、現場に慣れるまでに一定の時間がかかるため、「3ヶ月以内」「1年以内」の離職率を下げることが、企業の安定成長に直結します。
定着率が高い企業には、次のような共通点があります:
- 入社初日〜1週間の「迎え方」が丁寧
- OJTとOFF-JTのバランスが取れている
- 初期段階の業務が明確に定義されている
- 困ったときの相談先が明文化されている
定着とは、制度や施策ではなく「文化」として根付くべきものです。そのためには、現場の理解と協力が欠かせません。
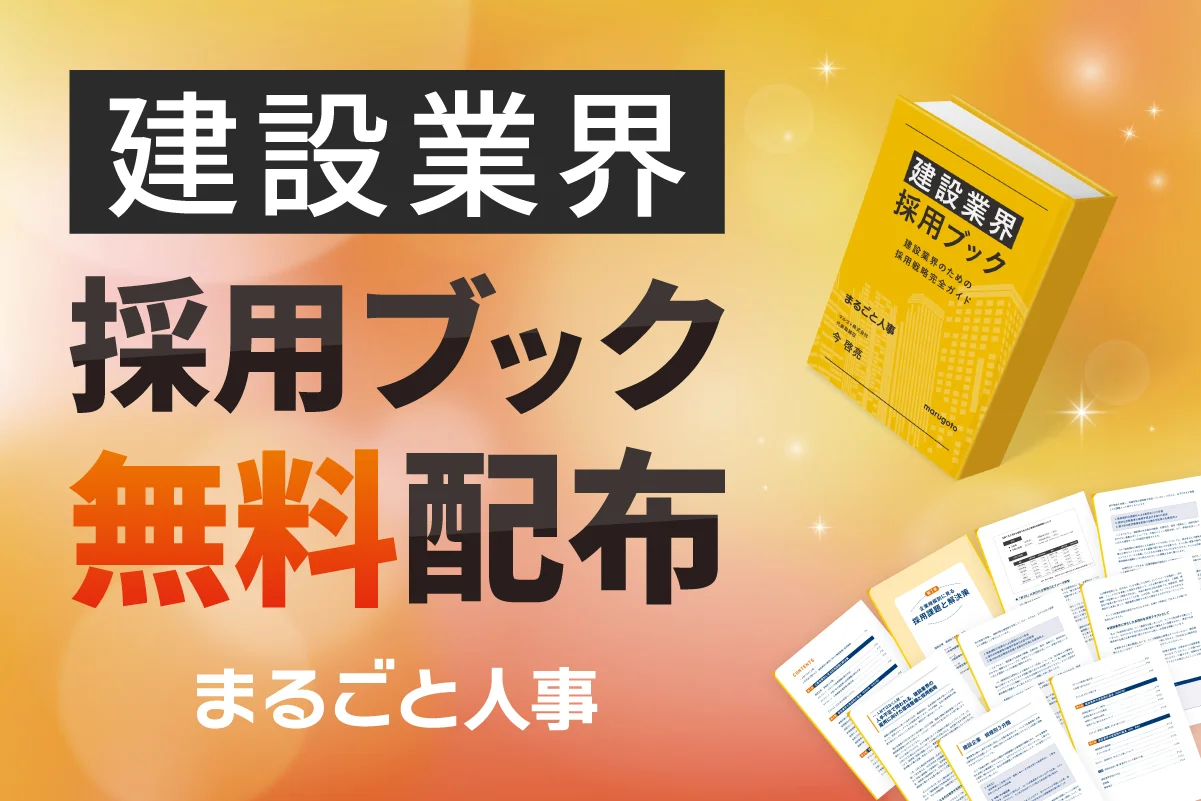
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
関連動画:建設業界採用ブックの解説動画
「放置しない」オンボーディング
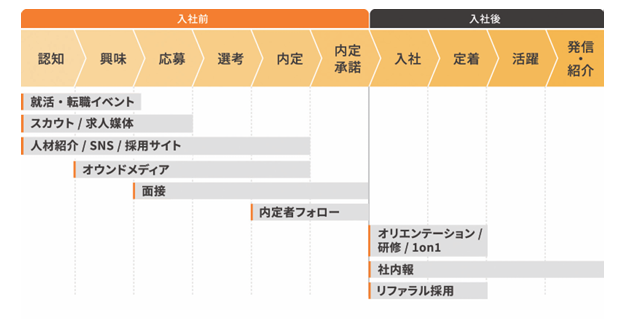
中途社員や若手社員が入社してまず直面するのは、「何をすればいいか分からない」という不安です。
このタイミングで放置されてしまうと、「歓迎されていない」「成長できなさそう」という印象を与えてしまい、離職リスクが一気に高まります。
そのために必要なのが、明文化されたオンボーディング(初期育成設計)です。たとえば:
- 1週間目:社内ルールと安全教育/現場見学
- 2〜3週間目:先輩同行による現場補助
- 1ヶ月後:一部業務の単独対応開始
- 3ヶ月後:現場責任者との振り返り面談
このような道筋があるだけで、新人は安心して業務に向き合えます。
また、オンボーディング責任者を決めて、進捗をチェックする仕組みを設けると、育成の属人化を防ぐことができます。
「育つ現場」にはルールと対話がある
定着と育成のカギを握るのは、現場の風土です。なんでも現場任せ、あとは本人のやる気次第という状況では、人は育ちません。
育つ現場には、以下のような仕組みがあります:
- 新人への声かけを習慣化(毎朝「困ってることある?」)
- ミスやトラブルがあったときの共有ルール(怒らない・責めない)
- 週1回の簡単な振り返りミーティング
- ベテラン社員への「育成役割」の明示
こうした文化を「当たり前」として根付かせるには、会社としての姿勢が問われます。
現場リーダーに対して「技術だけでなく、人を育てることも役割」だと伝えることが第一歩です。
離職予兆の早期発見と対応
どんなに丁寧に育成していても、離職はゼロにはなりません。だからこそ、辞める前のサインを察知し、先手を打つことが重要です。
たとえば:
- 以前よりも挨拶が少なくなる
- 報連相が減る/雑談がなくなる
- 無断欠勤や遅刻が出始める
こうした兆候が見えたら、上司や人事が早めに声をかけ、面談を行うことが大切です。その際、「辞めるな」と説得するのではなく、「不満や不安」を拾い上げるスタンスが信頼関係につながります。
また、第三者的な立場(例:外部の育成コンサル、信頼できる先輩社員など)を活用してヒアリングすることで、より率直な意見が聞けることもあります。
育成の文化は「評価制度」に表れる
最後に重要なのが、人を育てた人がきちんと報われる仕組みです。
- 若手の定着率が高いリーダーは高評価
- OJT担当には毎月の「育成振り返りシート」を提出してもらう
- 現場の新人教育状況を経営会議で共有
こうした取り組みを通じて、「人を育てることが大切だ」という価値観を組織全体で共有できます。
育成文化のある会社は、次第に「辞めない会社」「人が集まる会社」へと変化していきます。
次回予告
次回は、「人事評価とキャリア支援」をテーマに、成長を可視化し、個人と組織がともに伸びる仕組みづくりについて解説します。
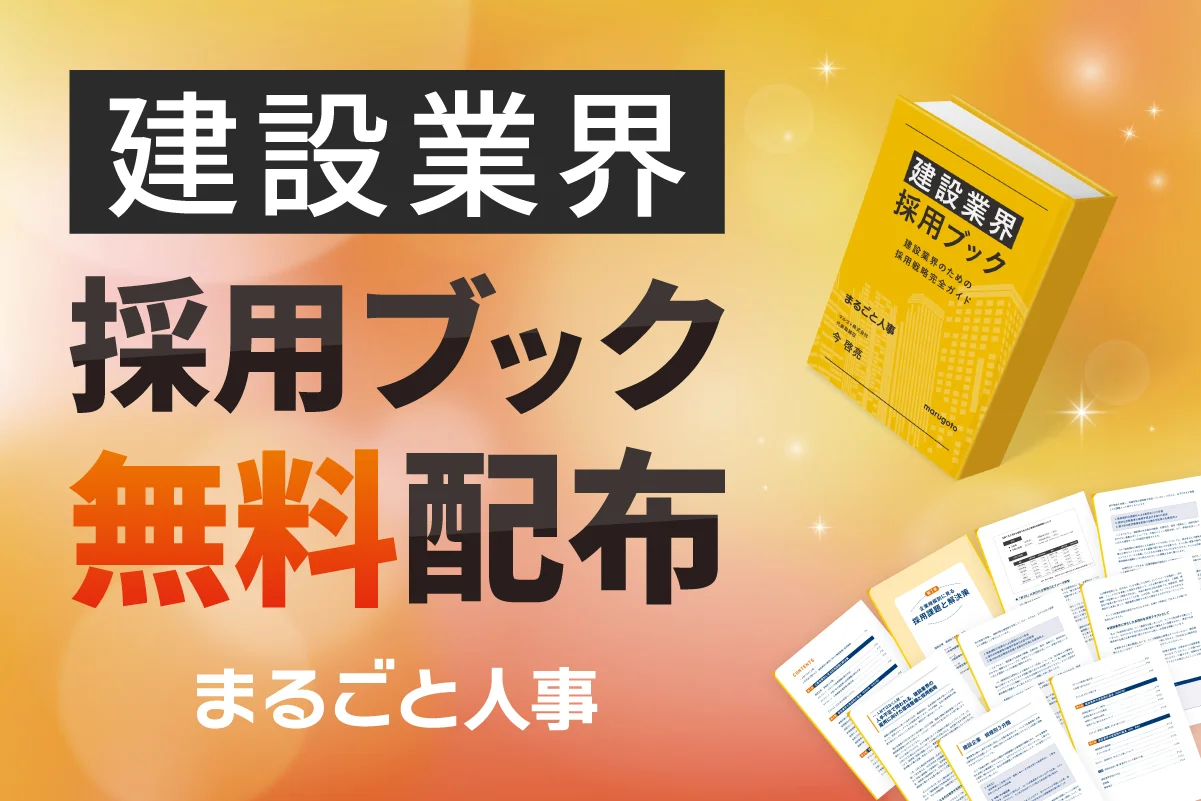
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
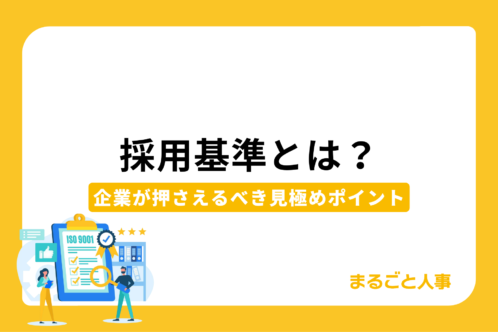
採用基準とは?企業が押さえるべき意義・手順・人材の見極めポイント
- 採用企画
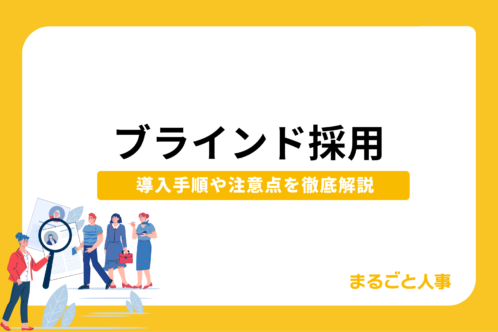
ブラインド採用とは?メリット・デメリット、導入手順や注意点を徹底解説
- 採用企画
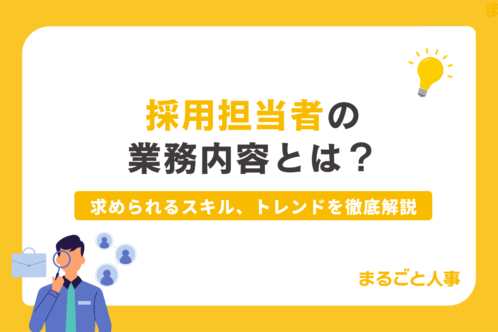
採用担当者の業務内容を徹底解説!人事担当との違いや必要なスキル、心構えまで
- 採用企画
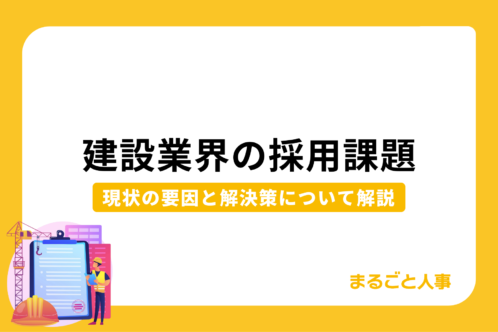
建設業界の採用課題とは|現状の要因と解決策について解説
- 採用企画
- 採用オペレーション
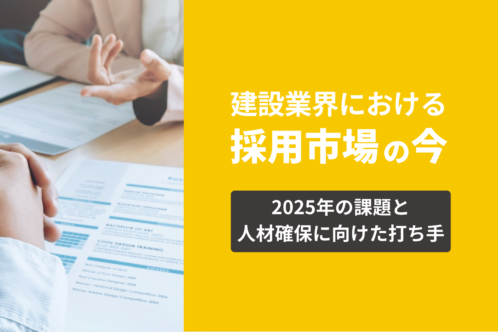
建設業界における採用市場の今|2025年の課題と人材確保に向けた打ち手
- 採用企画
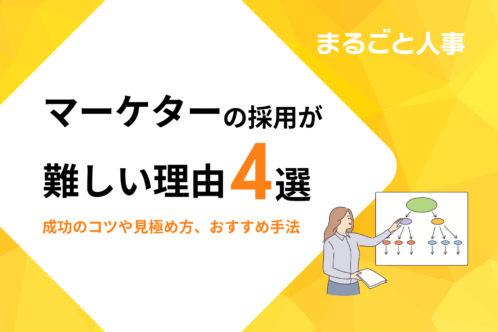
マーケターの採用が難しい理由4選|成功のコツや人材の見極め方、おすすめ手法
- 採用企画