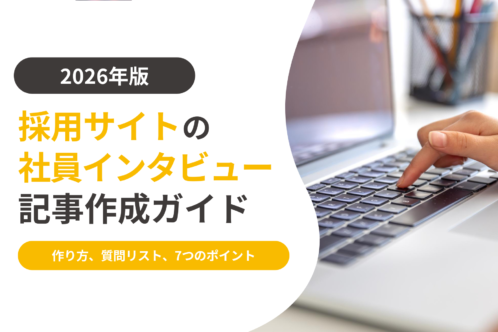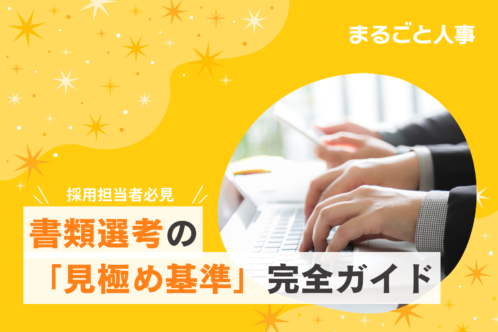採用・労務・経理に関するお役立ち情報
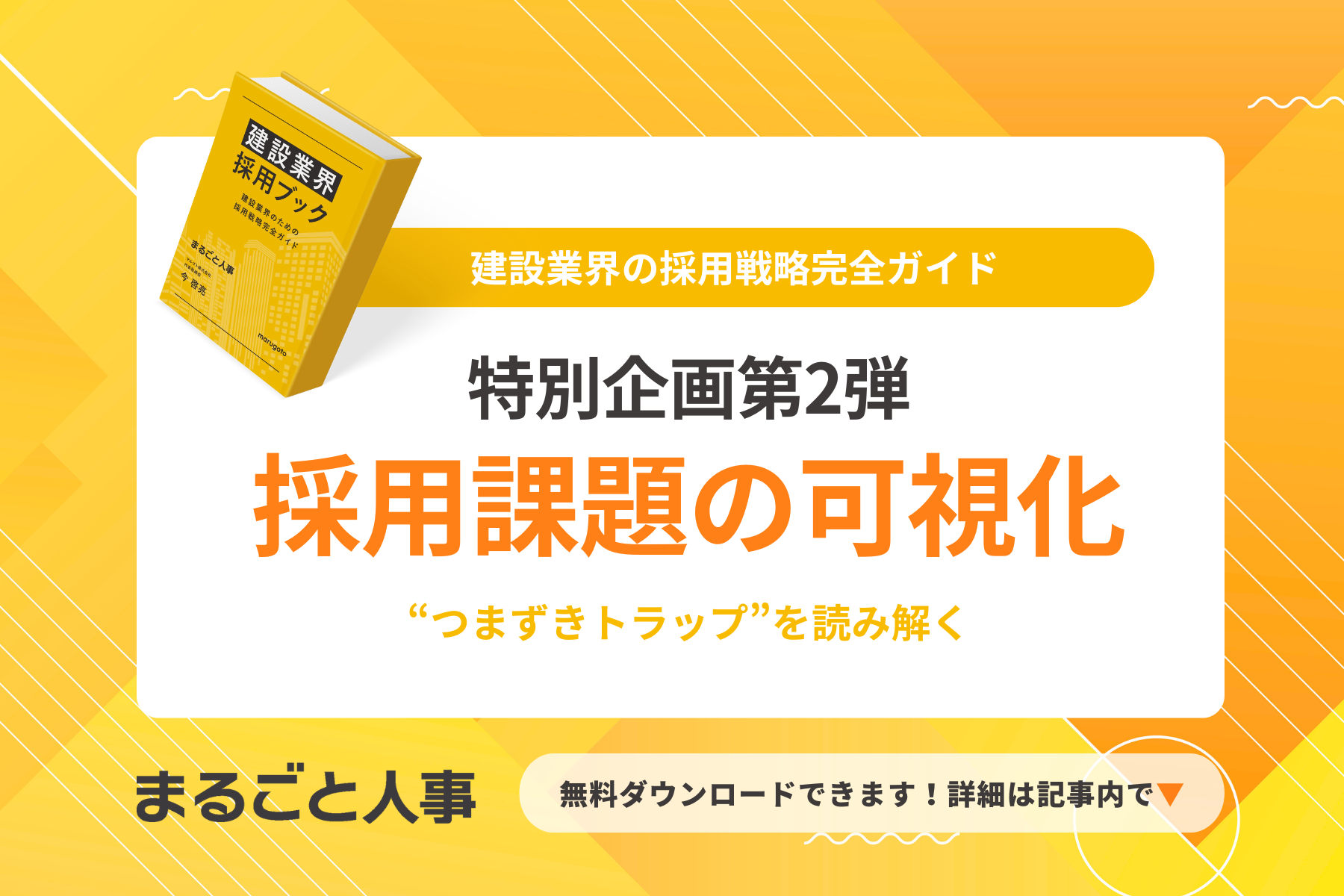
採用フローを正しく描けていますか?

企業の採用活動には、業種や職種を問わずおおむね共通するフローがあります。具体的には以下のようなステップが一般的です。
- 必要人材の定義と要件整理
- 募集要項の作成
- 求人媒体・チャネルの選定と発信
- 応募受付と書類選考
- 面接・評価プロセス
- 内定提示・入社手続き
- オンボーディング・初期育成
このように一連の流れがあるにもかかわらず、実際の現場では「目の前の人手不足を埋める」ことに追われ、個別の施策が場当たり的に行われているケースが少なくありません。
特に中小の建設企業では、採用担当者が他業務と兼任していることも多く、採用フロー全体を俯瞰して設計・改善する余力が限られているのが実情です。
しかし、採用活動は単なる補充作業ではなく、企業の未来を形づくる最重要戦略の一つです。だからこそ、まずはこのフローを構造的に理解することから始めなければなりません。
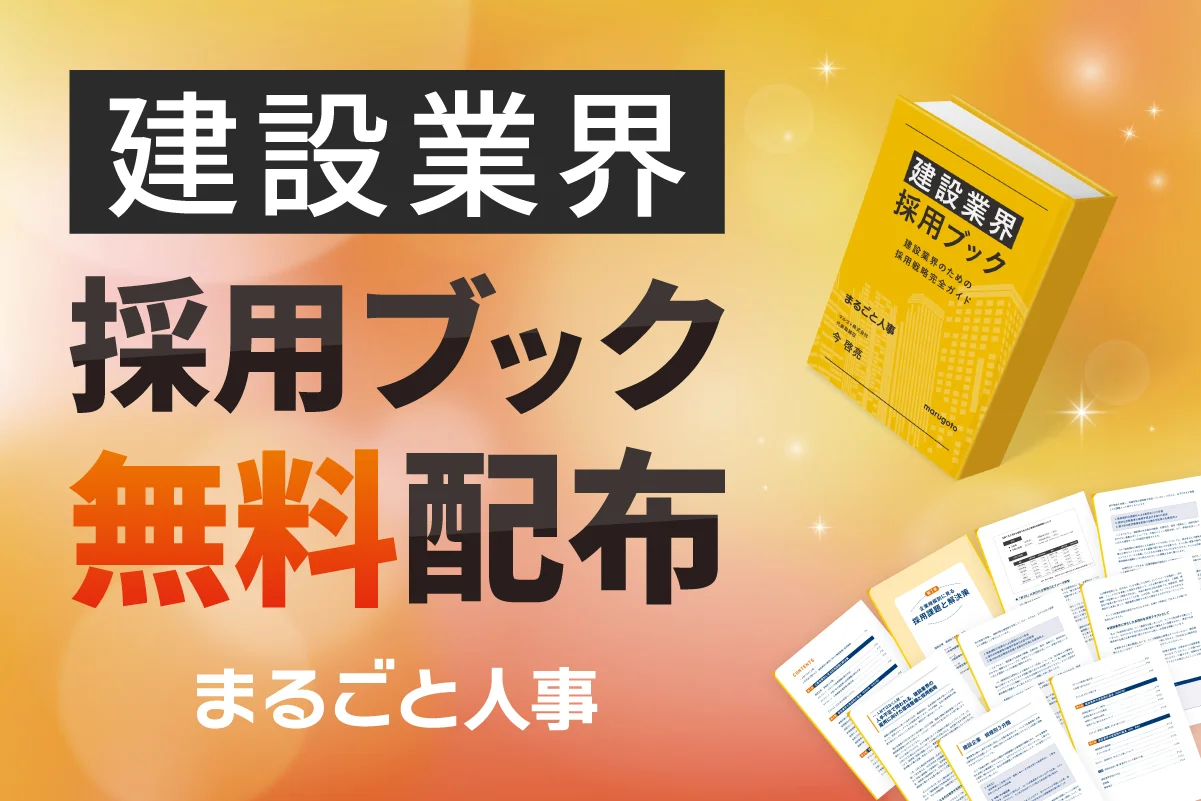
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
関連動画:建設業界採用ブックの解説動画
フェーズごとに潜む“つまずきトラップ”
採用活動における典型的な失敗は、特定のステップにおける構造的な“つまずき”です。以下は建設業において特に多く見られるトラップの例です。
| フェーズ | 主な課題 |
|---|---|
| 定義フェーズ | ターゲット像が曖昧:「施工管理経験3年以上」などの漠然とした要件だけで進めてしまい、応募者と現場ニーズのギャップが発生。 |
| 要件設計フェーズ | 求人内容が刺さらない:給与や休日日数といった最低限の情報しか載せられず、求職者が「この会社で働く理由」を感じられない。 |
| チャネル運用フェーズ | 媒体選定の最適化不足:ハローワークのみ、紹介会社任せなどに偏り、広がりのある母集団形成ができない。 |
| 選考フェーズ | 面接での見極め不足:現場任せで面接基準があいまいなまま、属人的な判断に頼ってしまう。 |
| 内定〜入社フェーズ | 辞退・バックレが発生:内定後の連絡が形式的、入社までにフォローがないなど、候補者が不安になり離脱してしまう。 |
| 入社後フェーズ | 初期対応が属人的:配属後の育成やメンター制度が曖昧で、数ヶ月での離職につながってしまう。 |
これらは個別に見ると些細なようですが、積み重なれば企業の採用競争力を著しく損なう要因となります。
可視化と振り返りが改善の鍵
こうしたトラップを回避するためには、採用活動のPDCAを“設計業務”と捉えなおすことが重要です。
まずは、自社の採用活動をプロセスマップとして可視化してみましょう。各ステップにおいて「誰が、何を、いつまでに、どのように対応しているか」を洗い出すことで、属人的になっている部分や判断基準が曖昧な箇所が明確になります。
たとえば、
- 書類選考の合否判断を何をもとに決めているのか
- 面接時に候補者へどんな情報提供をしているか
- 内定後〜入社前の連絡頻度と内容
などを丁寧に振り返ることで、改善すべきポイントが見えてくるはずです。
また、KPIの設定も重要です。応募数だけでなく、書類通過率、面接実施率、内定辞退率、初期定着率などを追いかけることで、ボトルネックとなるフェーズを定量的に特定できます。
“現場巻き込み型”体制へ進化させる
採用活動は人事部門や経営層だけのものではありません。現場の理解・協力なしには実効性ある採用体制はつくれません。
たとえば、
- 面接に現場の若手社員を同席させる
- 内定者懇親会や現場見学を実施する
- 入社後の配属先リーダーに事前情報を共有する
といった工夫により、候補者との信頼構築がスムーズになります。
また、現場が「採用は人事の仕事」と距離を置いていると、せっかくの採用活動が定着・活躍につながりにくくなります。
採用活動そのものを現場の組織づくりの一環としてとらえる視点が必要です。
次回予告
次回は、「応募が来ない」「採用できない」背景にある“母集団形成”の課題について詳しく掘り下げます。地方・中小企業が直面する構造的な制約と、その突破口を探っていきます。
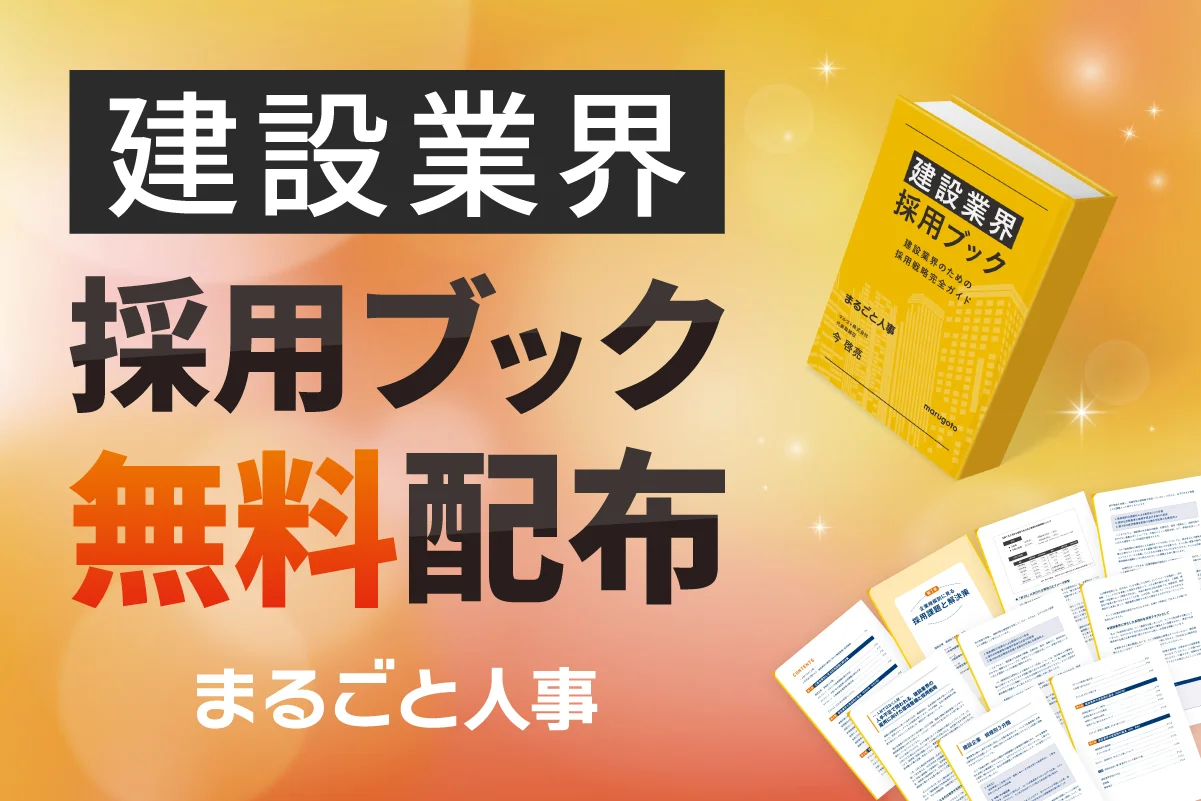
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
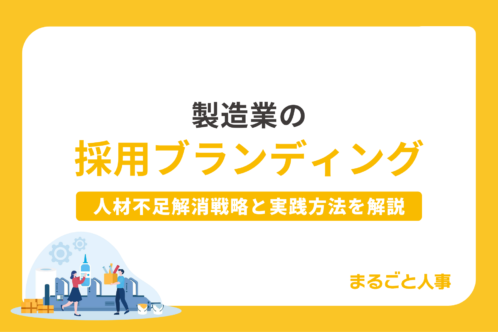
製造業の採用ブランディング|人材不足を解消する戦略と実践方法を解説
- 採用企画
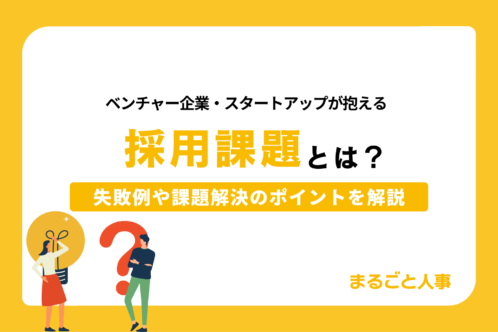
ベンチャー企業・スタートアップが抱える採用課題とは?失敗例や課題解決のポイントを解説
- 採用企画
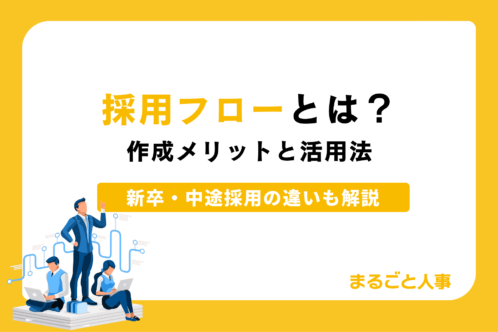
採用フローとは?作成のメリットと活用法、新卒・中途の違いをフロー図で解説
- 採用企画
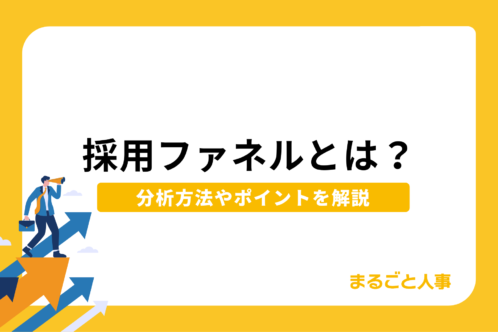
採用ファネルとは?分析方法やポイントを解説!
- 採用企画
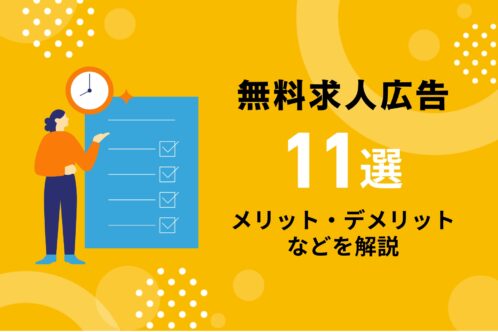
【2025年版】無料求人広告11選|効果を出すポイントやメリット・デメリットを解説
- 採用企画
- 採用媒体・チャネル
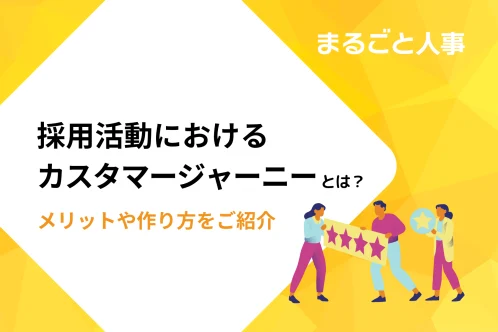
採用活動におけるカスタマージャーニーとはなにか?メリットや作り方を紹介
- 採用企画