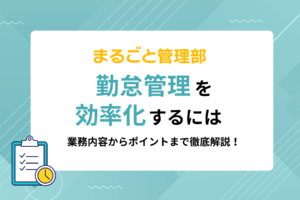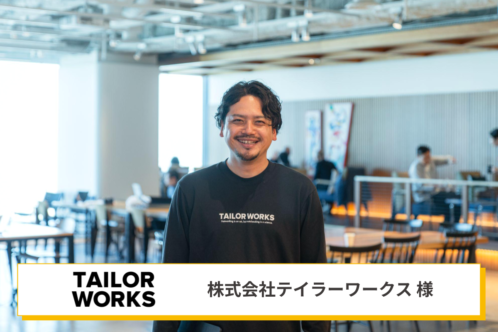採用・労務・経理に関するお役立ち情報

働き方改革や多彩なワークスタイルの普及を背景に、企業における勤怠管理の重要性が年々増加してきています。
働き方に関する時代の流れに応えるためにも、業界や事業規模など関係なく、多くの企業が勤怠管理システムを導入していることはご存知でしょうか。
本記事では、そんな勤怠管理システムを導入する際に知っておきたい、基本的な知識から導入のポイントまで解説します。
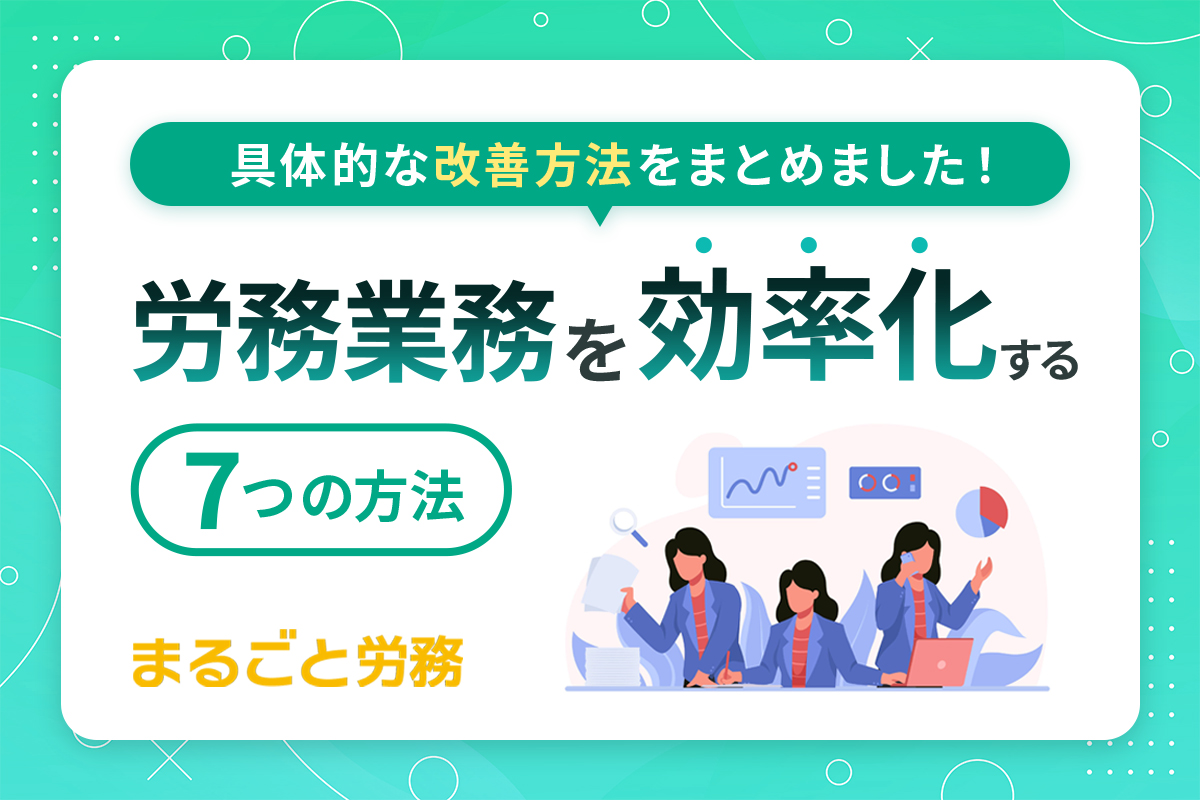
労務業務を効率化する7つの方法
人事・労務業務の効率化に悩む担当者様向けに、現状の課題と7つの効率化方法をご紹介!
目次
勤怠管理システムとは

勤怠管理システムとは、出退勤の打刻や有休申請など、勤怠管理業務を効率よくサポートしてくれるシステムです。
働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が強化されるなど、労働時間に関する法的なルールが見直されたことに加え、テレワークなど多彩なワークスタイルが一般的になってきたことから、導入する企業が増えつつあります。
ただし、うまく機能を活用するためには、導入目的を明確にし、システムごとの機能を比較することで、自社にマッチしているかどうかを判断する必要があります。
勤怠管理システム導入の目的
勤怠管理システムを導入するきっかけとしては、以下のようなものがあります。
- 業務効率化
- 多様化する働き方への対応
- 人的ミスの削減
- 労働基準法や労働安全衛生法などの法令遵守のため
目的によって最適な機能が異なってくるので、導入する際には自社の課題や現状を良く確認し、なぜ勤怠管理システムを導入するかを明確にするとよいでしょう。
勤怠管理システムの機能一覧
勤怠管理システムに備わっている機能は以下のとおりです。
- 打刻機能
- 有給・残業などの申請・承認
- シフト作成
- 労働状況把握
- 勤務時間や給与の自動集計
同じ機能でも、システムごとで使い勝手や対応範囲が異なるので、比較する際には実際の使用方法まで確認するとよいでしょう。
特に、打刻機能はスマートフォンでも対応できるものから、カードや指紋などの認証機能付きのものまで、システムによって機能の詳細が異なる傾向が強いです。
勤怠管理システム導入のメリット3選

勤怠管理システムの導入になかなか踏み切れない場合は、導入するとどんなメリットが得られるかを整理してみることをおすすめします。
ここでは、勤怠管理システムを導入すると期待できる、メリットを3つ解説します。
メリットを把握して、自社の課題を解決できるかどうか判断してみてはいかがでしょうか。
業務時間の短縮
勤怠管理システムは、労働時間の計算やシフトの管理が自動で対応してくれるので、管理業務にかかる時間を短縮できます。
特にテレワークで勤務している人やパートで勤務している人がいるなど、複数の働き方・雇用形態の従業員がいる職場は、どうしても業務が複雑になりがちです。
勤怠管理システムを活用すると、複数の働き方・雇用形態に合わせた管理ができるようになるため、労働時間や残業時間の管理も少ない工数で対応できます。
打刻漏れや打刻ミスを防げる
勤怠管理システムによっては、打刻ミスを防ぐためにアラームで通知してくれるものが多くあります。
打刻漏れや打刻ミスは適切な勤怠管理を妨げるうえ、修正に労力が発生してしまいます。
アラームによって打刻漏れや打刻ミスを減らせれば、より適切な勤怠管理が可能です。
法令を守りやすくなる
勤怠管理システムの自動計算機能を駆使すれば、残業時間の集計や有給取得状況の確認が短時間でできるようになります。
残業時間の総数や有給取得状況をこまめに確認することは、労働基準法・労働安全衛生法などの法令を守ることにつながるため、気づかずに法令を犯してしまうリスクを軽減可能です。
勤怠管理システムによっては、法令改正に合わせて機能を更新してくれるものもあるので、少ない労力で新しい法令に対応できます。システムを検討する際には、法改正に対応しているか、その場合設定変更などは必要かを確認しましょう。
関連記事:https://marugotoinc.jp/blog/kintaikouritu/
勤怠管理システム導入のデメリット3選

勤怠管理システムをうまく導入するには、運用する際に発生するデメリットを把握しなければなりません。
ここでは、勤怠管理システム導入で起こり得るデメリットを3つ解説します。
デメリットを把握することで事前に対策を講じることが可能なので、導入トラブルを防ぎたい人は参考にしてください。
業務改善につながらない場合がある
プラン内容を確認せずに契約してしまうと、期待していた機能が使えない恐れがあります。
給与計算など他システムとのデータ連携を希望する場合は、連携できるかどうか、どんな方法で連携するのかを明確にしておくとよいでしょう。
また、勤怠管理システムを導入しても、打刻や申請のルールが伴っていなければ労働時間の適正な確認ができず、業務の効率化に繋がらないケースもあります。システムを活用してどのような運用フローにするのかも併せて検討しておくことがおすすめです。
使い勝手が悪い場合がある
勤怠管理システムは担当者だけでなく従業員も使用するため、打刻機能など日常的に使用する機能には使いやすさが重要になります。
そのため、担当者に都合が良くても従業員にとって使い勝手が悪いと、かえって業務の質が落ちる可能性が高いです。
使い勝手を万全にするためにも、従業員の「働き方」に応じた打刻方法や管理方法かどうか、導入サポートがあるかなどをチェックしましょう。
ランニングコストが発生する
Excelやタイムカードで管理するケースに比べ、勤怠管理システムを使用した方がコストが増加しやすい傾向があります。
自社仕様にカスタマイズすればするほど、必要なランニングコストは大きくなるので、導入によって得られる効果と費用のバランスを考えてプランを調整しましょう。
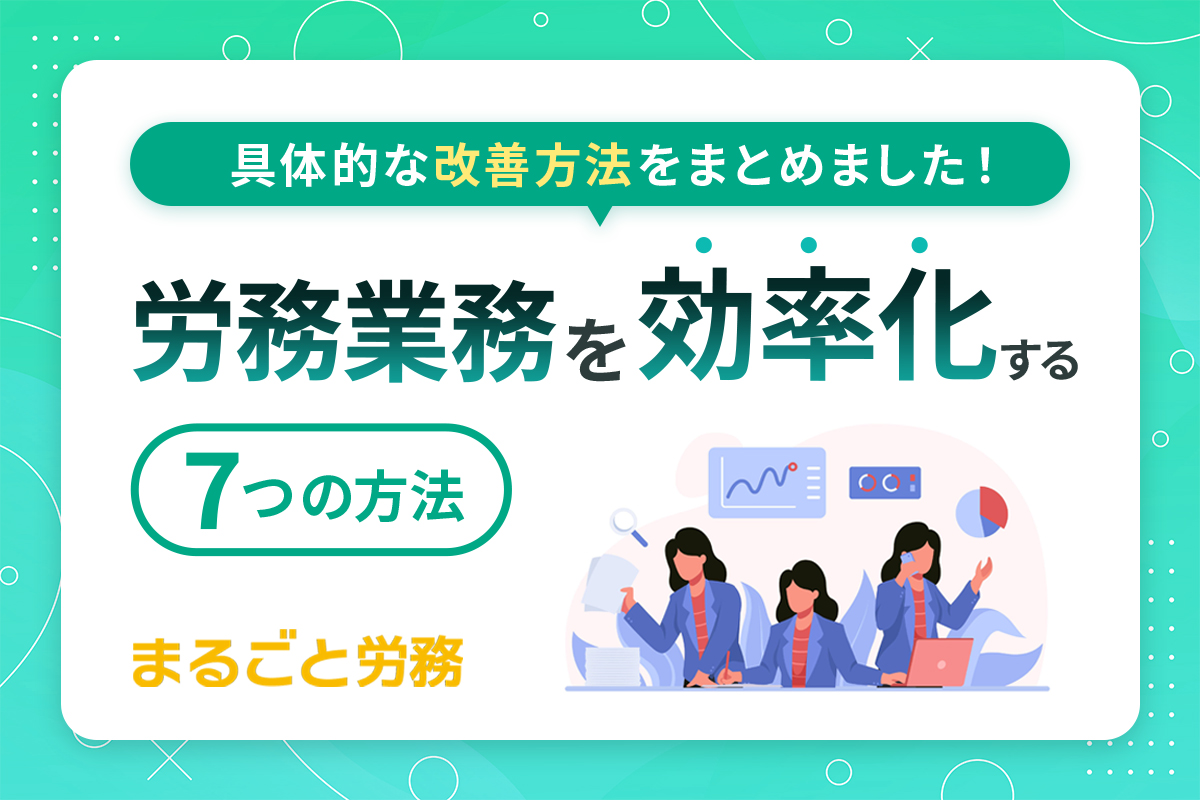
労務業務を効率化する7つの方法
人事・労務業務の効率化に悩む担当者様向けに、現状の課題と7つの効率化方法をご紹介!
勤怠管理システムの選び方

自社にあった勤怠管理システムを選ぶために意識したい要素は、以下のとおりです。
- 既存システムとの連携が可能か
給与計算ソフトや会計システムなど、API連携が可能なシステムを選ぶと、データの二重入力をせずに済むため、業務の手間をさらに削減できます。
- 自社の働き方に合っているか
テレワークや外出が多い環境の場合、外部からでも出退勤を打刻できるように、スマートフォンから出退勤打刻システムにログインできると、使い勝手が良くなります。
- 操作がしやすいか
直感的な操作ができるか、勤怠データの確認や修正が簡単にできるかなど、管理者だけでなく、現場の従業員も使いやすいシステムであることが重要です。
上記のポイントをスムーズに判断するためにも、事前に自社の課題や働き方を分析しておくことをおすすめします。
また操作のしやすさは第三者の目線が必要になるので、他の部署で働いている社員に協力してもらうと、より正確に判断しやすいです。
勤怠管理システム導入までの流れ

勤怠管理システムを導入する流れは、以下の4ステップに分けられます。
- 導入する目的を明確化する
現在の勤怠管理の問題点を整理し、テレワーク対応できる打刻システムやシフト管理など、どのような機能が必要かを明確にします。
- 勤怠管理システムを選定する
必要な機能が揃っているかだけでなく、予算内に運用できるか、既存システムとの連携が可能かなど、複数の観点から勤怠管理システムを選定する必要があります。
- 機能・操作方法を従業員に共有する
導入スケジュールや打刻方法、申請・承認フローなどの運用ルールを、説明会や動画で共有します。
- 試運用したのち、本格導入を決定する
2週間前を目安に、テスト運用を実施し、問題がないかを確認します。試運転時は会社全体で運用するのではなく、一部の部署や管理者だけで試験運用することをおすすめします。
もし、初めて勤怠管理システムを導入するため、スムーズに対応できるか不安に感じている場合は、導入サポートがついているプランを選ぶことをおすすめします。
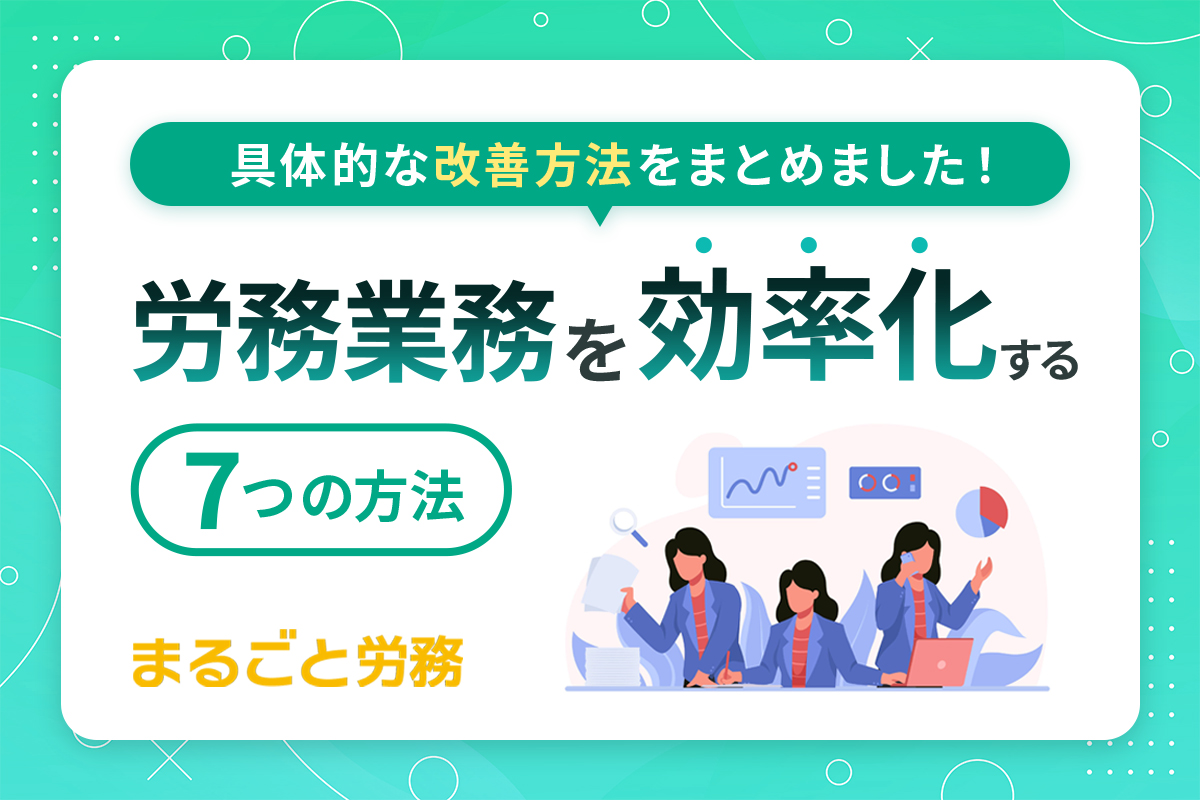
労務業務を効率化する7つの方法
人事・労務業務の効率化に悩む担当者様向けに、現状の課題と7つの効率化方法をご紹介!
勤怠管理システム導入3つのポイント

ここでは勤怠管理システムをスムーズに導入するために意識したいポイントを、3つ解説します。
導入するうえで見落としがちな要素も紹介しているので、初めてシステムを導入しようとしている人はチェックしてみてください。
導入時に用意しておくべき情報を整理する
勤怠管理システムを導入するためには、従業員や企業のさまざまな情報が必要です。
導入時に必要になることが多い情報は、以下のとおりです。
- 従業員の個人情報
- 就業規則
- 組織体系
- 従業員の雇用形態
初期の情報入力をミスしてしまうと、誤った方法で勤務管理することになってしまうので、間違いの内容に情報を整理しましょう。
勤怠管理システムの導入意図を従業員に共有しておく
勤怠管理システムをうまく社内のシステムに取り入れても、従業員が適切に操作できないと意味がありません。
従業員が適切に機能を使用し、業務効率と勤怠管理の質を上げるためにも、勤怠管理システムの導入意図を従業員に共有しておくことをおすすめします。
一方的な情報発信のみで共有作業を完了させてしまうと、従業員がシステムを適切に活用できない恐れがあります。
従業員からの疑問に対応するためにも、全従業員に向けて説明会を実施し、質疑応答の時間をつくるなどの工夫を凝らすとよいでしょう。
運用後のサポート範囲を確認しておく
勤怠管理システムのプランによっては、導入後に機能がカスタマイズできない可能性があります。
もし、今後新たな働き方を採用する動きがあるなら、新たな働き方に合わせた機能のアップグレードができるのかを、事前に明確にしておくとよいでしょう。
勤怠管理システム導入の成功には「自社に合ったプラン」を選ぶことが大事

本記事では、勤怠管理システムを導入する際に知っておきたい、基本的な知識から導入のポイントまで解説しました。
勤怠管理システムを導入すると、時代のニーズにあったさまざまなメリットを得ることが可能です。
うまく勤怠管理システムを導入するためにも、本記事の内容を確認し、導入の流れやうまく導入するポイントを把握しておくとよいでしょう。
もし、「システムの導入までサポートしてくれる勤怠管理システムを導入したい」と考えている労務・バックオフィス担当者がいましたら、「まるごと管理部(労務プラン)」に相談してみるとよいでしょう。

「まるごと管理部(労務・経理プラン)」の資料を無料でダウンロード
労務・経理を仕組みづくりから実務まで代行!
急な担当者の退職など社内のバックオフィス担当の代わりとして伴走支援します
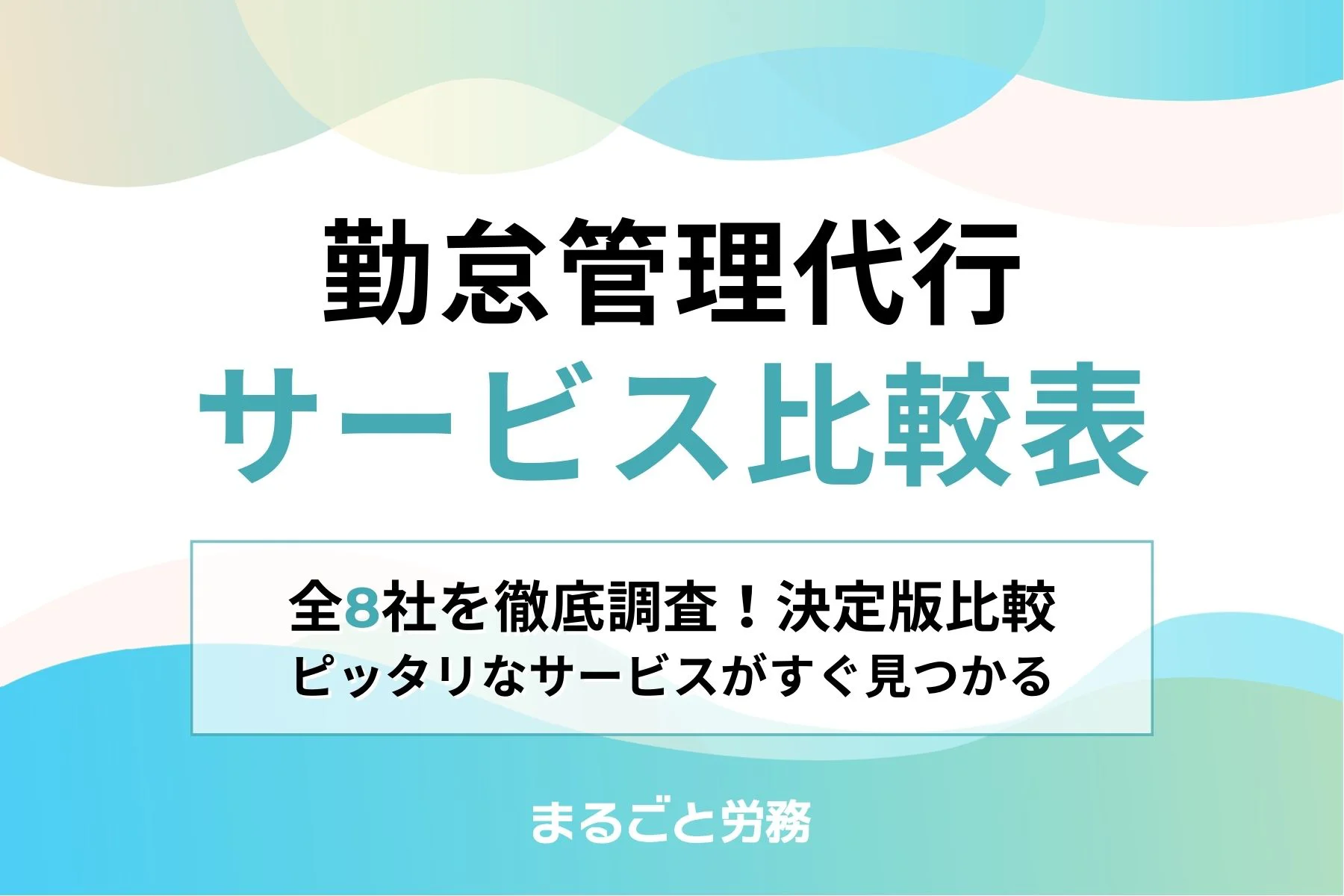
勤怠管理代行サービス比較表
ぴったりなサービスがすぐ見つかる!サービスの概要やポイントもバッチリ把握
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
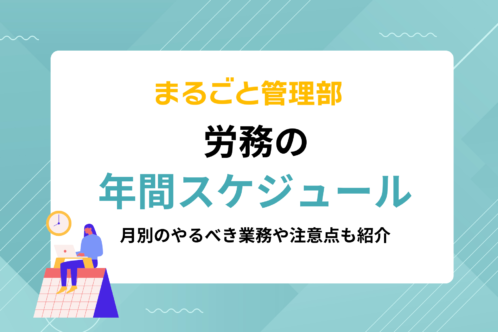
労務の年間スケジュール|月別のやるべき業務や注意点も紹介
- バックオフィス業務
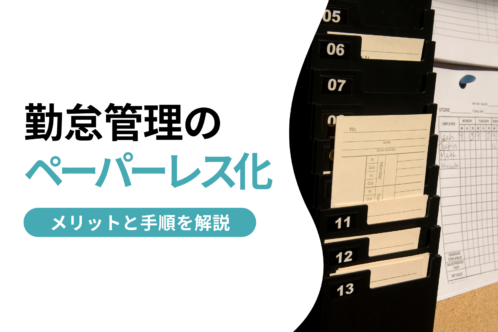
勤怠管理のペーパーレス化とは?導入のメリットと手順を解説
- バックオフィス業務
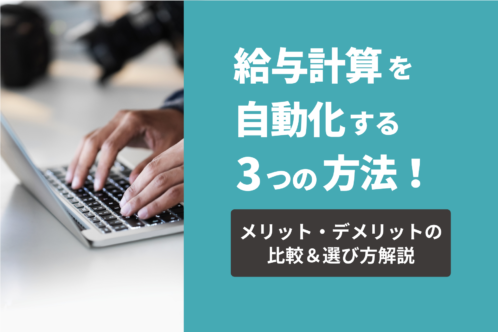
給与計算を自動化する3つの方法!メリット・デメリット比較&選び方解説
- バックオフィス業務
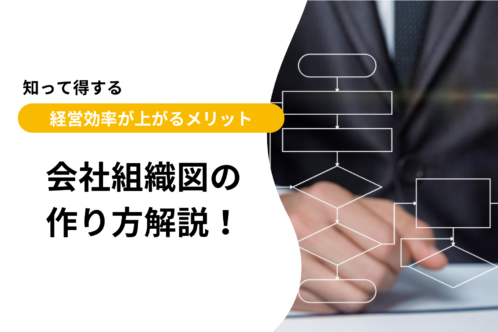
会社組織図の作り方解説!知って得する経営効率が上がるメリット
- バックオフィス業務
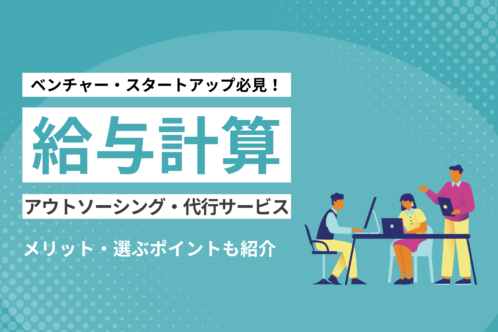
ベンチャー・スタートアップ必見! 給与計算のアウトソーシング・ 代行サービスを徹底解説
- バックオフィス業務
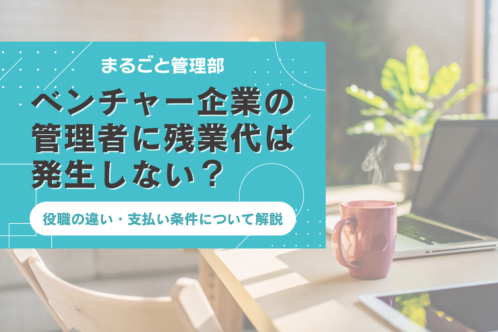
ベンチャー企業の管理者に残業代は発生しない?役職の違いや支払いの条件について解説
- バックオフィス業務