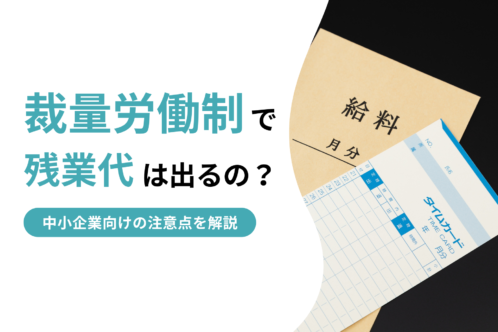採用・労務・経理に関するお役立ち情報
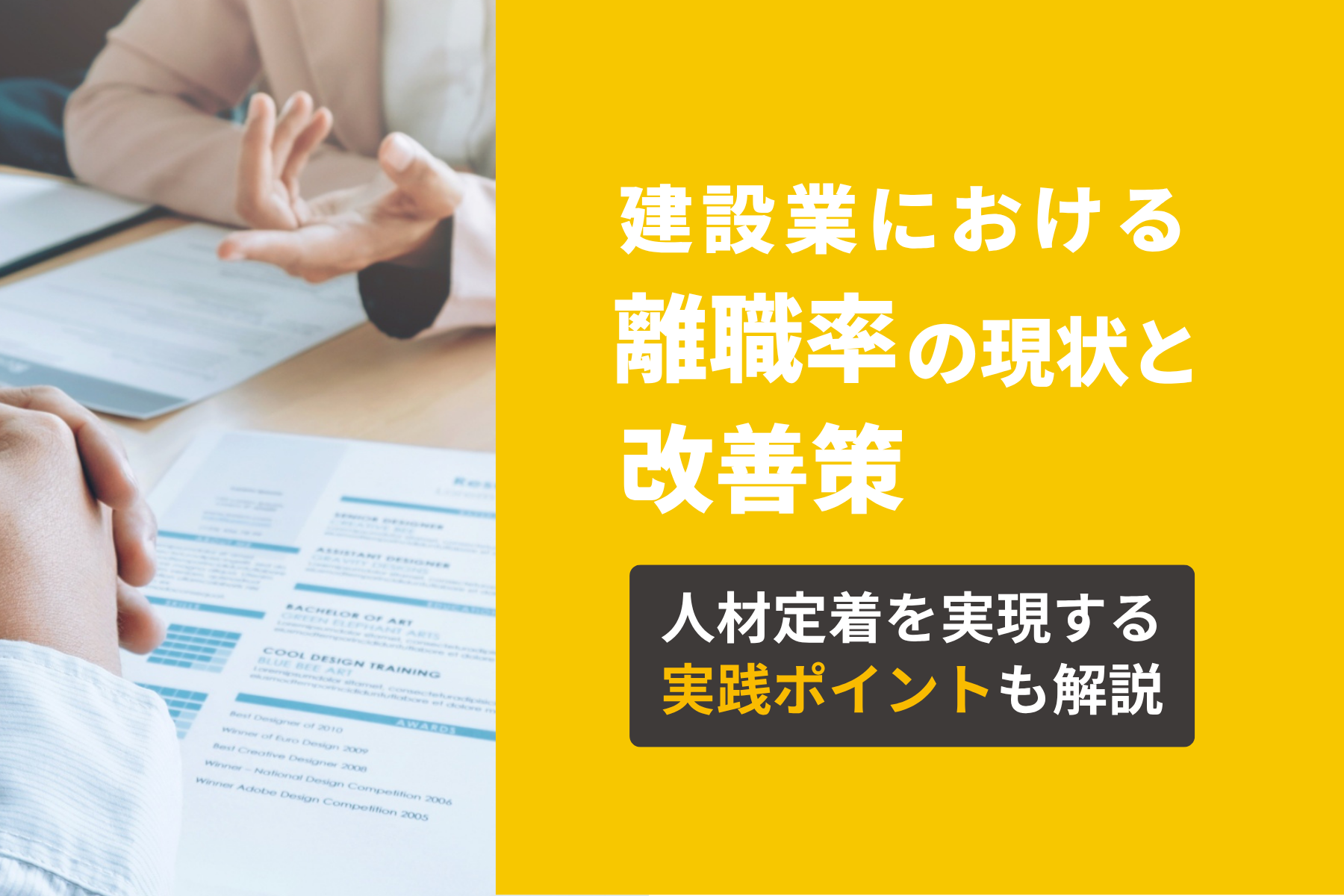
建設業界では、慢性的な人手不足に加え、離職率が現場運営や企業成長の大きな障壁となっています。とくに若年層の定着が難しく、育成コストの損失や現場力の低下を招く事例も少なくありません。労働環境の改善や制度設計の見直しに着手する企業も増えていますが、根本的な解決には現状の正確な把握と、業界特性に即した対策が不可欠です。
本記事では、建設業界における離職率の定義や数値的実態を解説したうえで、離職が発生する背景と対処法を明らかにしていきます。あわせて、人材定着を目指すうえで有効となる外部支援の活用法についても紹介します。
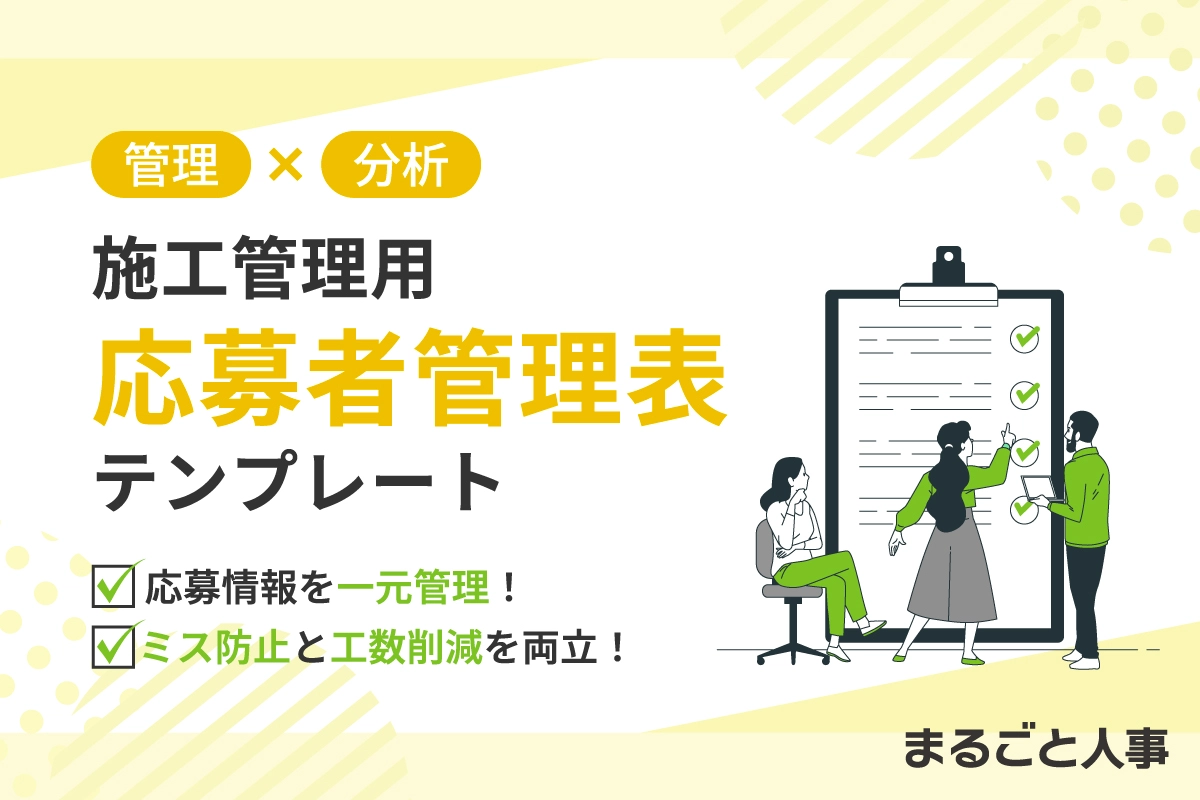
施工管理用
応募者管理表テンプレート
施工管理特化の管理テンプレートを無料で公開!応募者管理のミス防止&工数削減、データの分析に役立ちます
目次
離職率とは

従業員の定着状況を把握するうえで、離職率は欠かせない指標です。ここでは、離職率の意味と具体的な計算方法について整理します。建設業界における実態を理解する前提として、数値の捉え方を正しく認識しておくことが重要です。
離職率の定義と意味
離職率とは、一定期間内に企業を退職した従業員の割合を示す数値です。企業規模や業種にかかわらず、労働環境や職場の魅力度を測る上で使われます。
とくに若手人材の定着率や育成状況を判断する指標として注目されやすい傾向にあります。採用活動を活性化させても、短期間で人材が流出してしまえば、人手不足の解消にはつながりません。
離職率の数値には人材育成や業務設計の在り方が反映されるため、継続的に観察しながら改善していく必要があります。
離職率の計算方法
離職率は、以下の式で算出します。
計算対象期間は、1年間とするのが一般的です。たとえば年間で20人の社員が退職し、平均在籍者数が200人であれば、離職率は10%となります。
ただし、採用数や事業拡大によって在籍人数が増減する場合、月単位・四半期単位での補正が必要です。より精緻な数値を得たい場合は、部門別や職種別に分けた分析が有効です。
数値だけで判断せず、退職理由や人員構成との関連性も総合的に見ていきましょう。
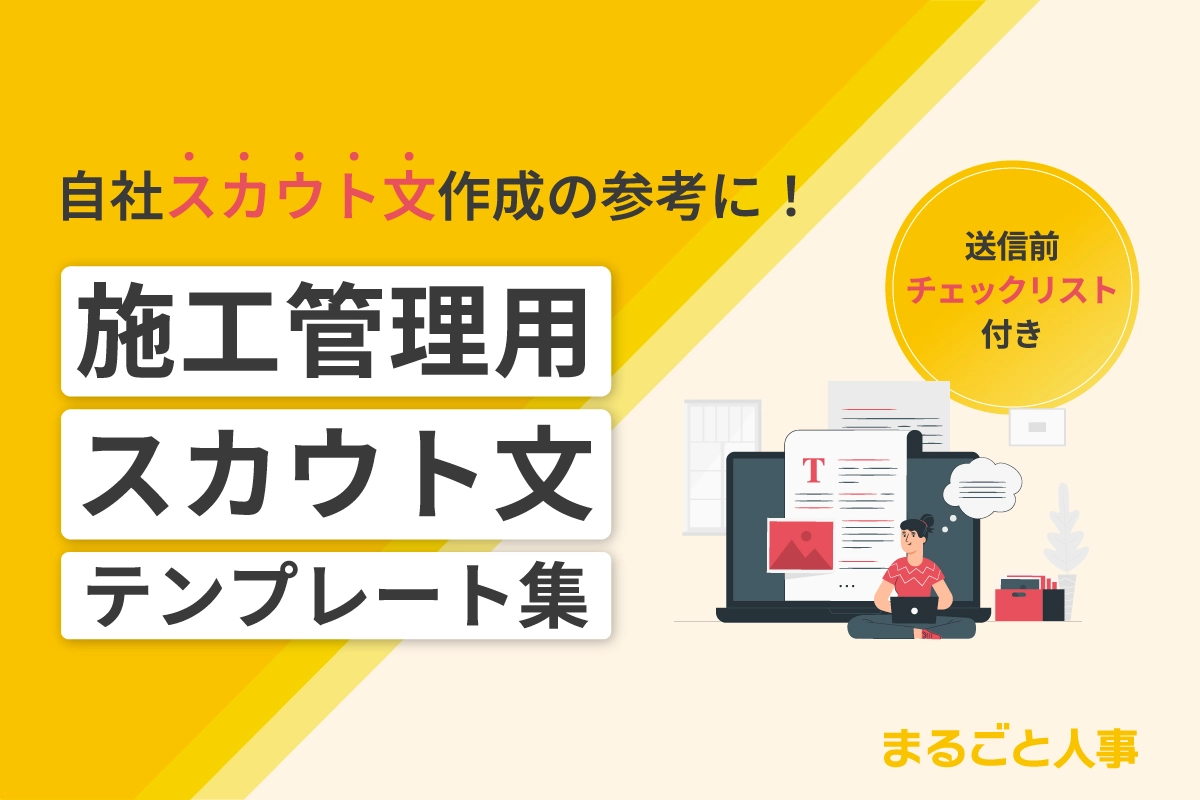
施工管理用スカウト文
テンプレート集
自社の魅力が伝わるスカウト文で応募数の向上を!送付前に確認すべきチェックリスト付き
建設業界の離職率の実態
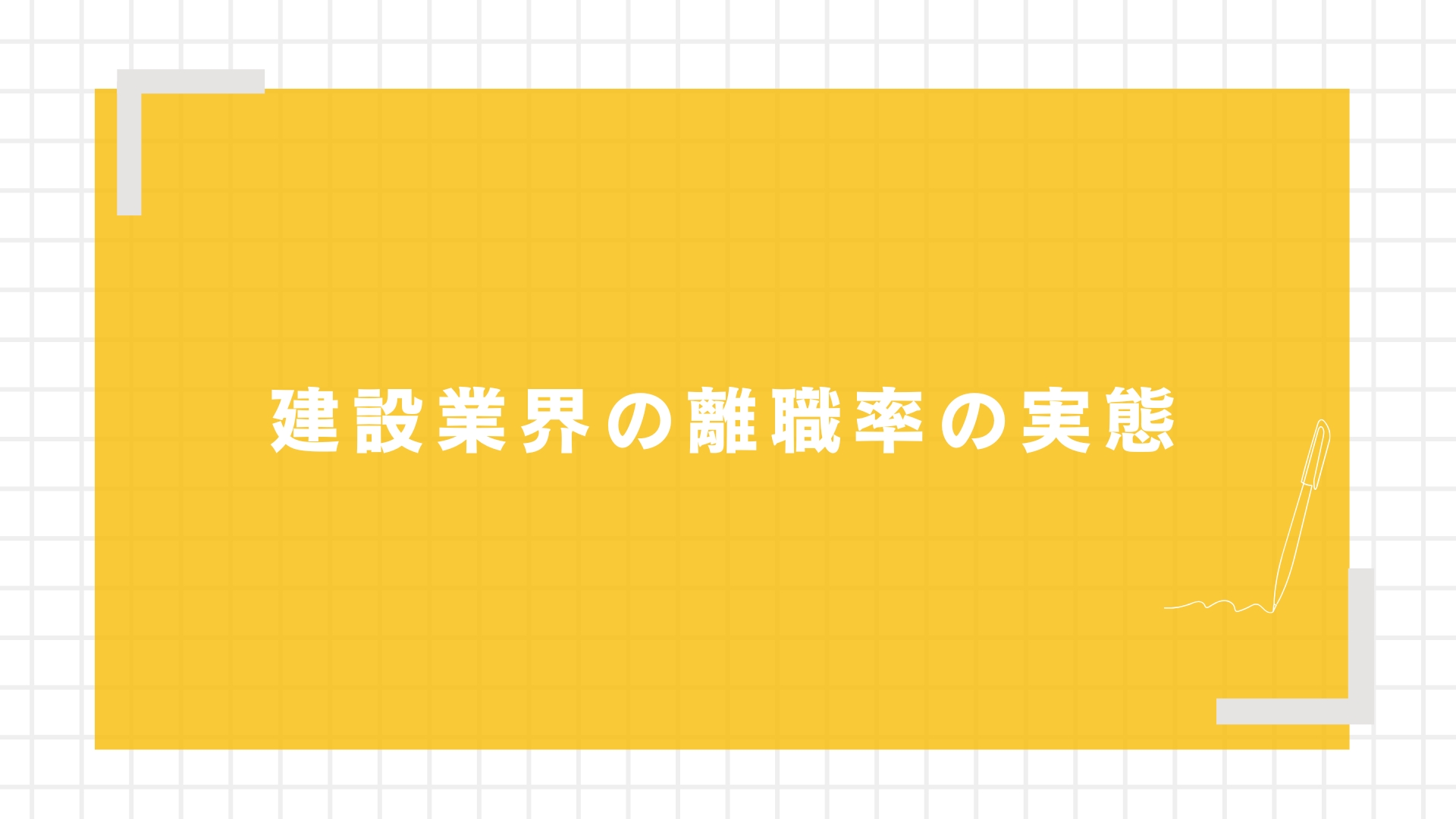
建設業の人材定着に課題を抱える企業が多い中で、まずは離職率の現状を正確に把握することが重要です。ここでは、公的データをもとに建設業界の離職率を確認し、他業界との比較や職種別の傾向を通じて実態を読み解いていきます。
出典:厚生労働省|令和5年雇用動向調査結果の概要「産業別の入職と離職」
厚生労働省のデータと他業界との比較
建設業の離職率は、他業種と比較して決して特別高いわけではありません。2023年の統計によると、建設業全体の離職率は10.1%で、産業全体の平均15.4%を大きく下回っています。
一般労働者においても離職率は10.3%と低めであり、安定した雇用環境が維持されている状況です。
採用戦略を考える際には、他産業との比較や業態別のデータに基づき、正確な理解をもとに取り組みを進める必要があります。
職種別の離職傾向
業種ごとの離職率に着目すると、生活関連サービス業や宿泊業、飲食サービス業が30%前後と際立って高い一方、建設業は全体の中で低水準に位置しています。とくに一般労働者における建設業の離職率は10.3%で、医療・福祉の13.3%などを下回る水準です。
他職種と比べた数値からも、建設業は労働環境の安定性という面で誤解されがちであることが読み取れます。
建設業界で離職率が高くなる要因
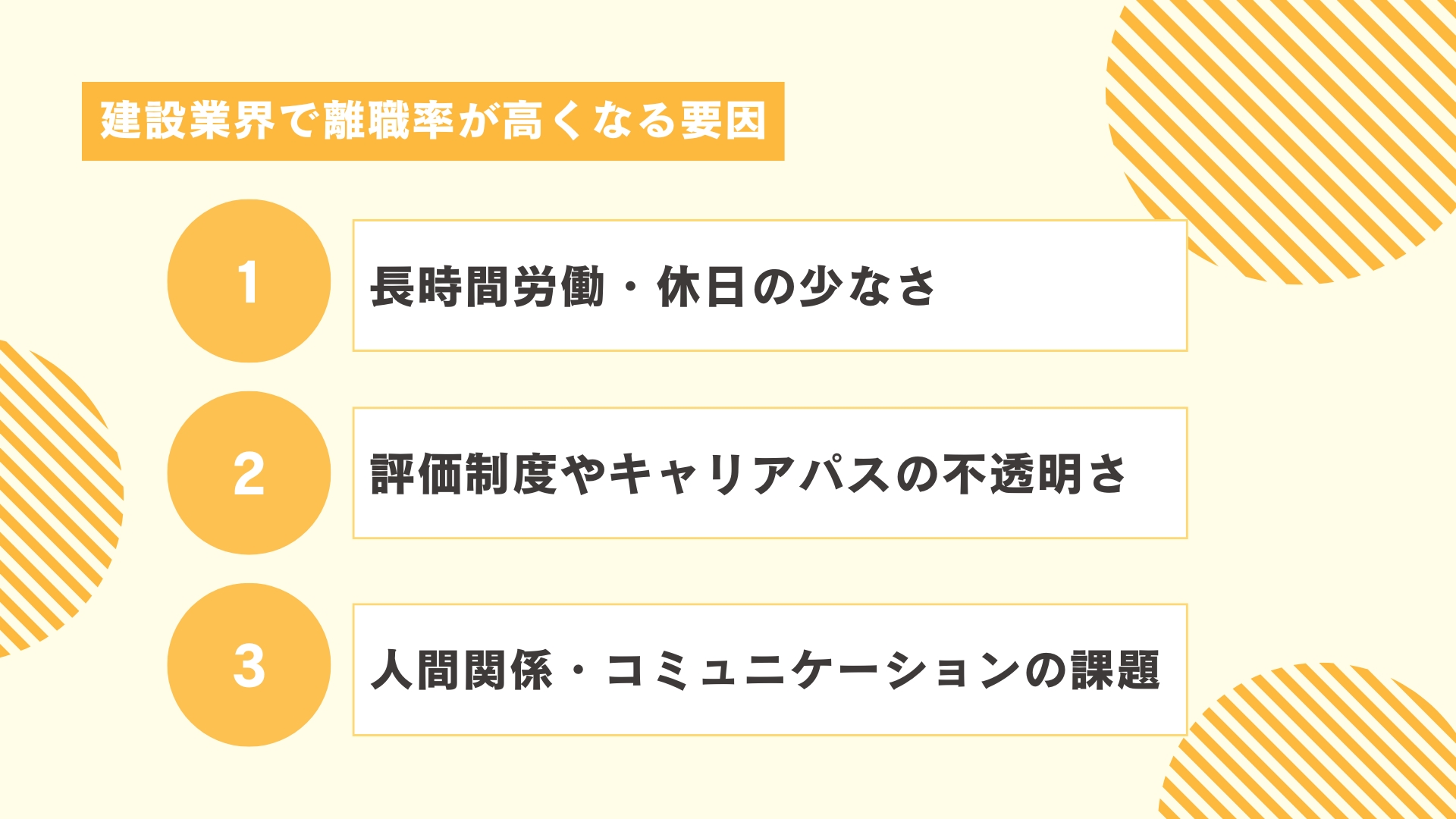
離職率が他産業より低い傾向にあるとはいえ、現場では人手不足が慢性化しています。ここでは、建設業界で働き続けることが困難となる背景について、実務の視点と業界特有の構造から検証します。
長時間労働・休日の少なさ
建設業において離職の大きな要因の一つとなるのが、長時間労働の常態化です。週60時間以上の超過勤務が続くことも珍しくなく、現場の負担が大きい状況が続いています。
さらに、繁忙期と閑散期の差が激しく、安定した働き方を描きにくい点も離職につながる要因です。休日日数に関しても、週休二日制を導入できていない企業が多く、他業種に比べて労働環境に大きな開きがあります。
評価制度やキャリアパスの不透明さ
成長の実感が得にくい評価制度も、離職につながる要因です。建設現場では年功序列や現場経験の長さが重視されがちであり、実力を正当に評価されないと感じる若手も多く見受けられます。
とくに施工管理や技能職では、職位の変化や昇進の基準が不明瞭なままに据え置かれているケースもあり、モチベーションの維持が困難になります。また、資格取得や次のキャリアへのステップを企業が支援しない場合、中堅層の流出にも拍車がかかるでしょう。
人間関係・コミュニケーションの課題
多重下請け構造や現場ごとのメンバー入れ替えの多さが、職場の人間関係を希薄にしやすくしています。とくに若年層は孤立感を抱きやすく、悩みを相談できる体制がないまま離職するケースが後を絶ちません。
現場ではベテラン層との価値観の違いや指導方法に対する不満が蓄積しやすく、精神的な負担を招きます。コミュニケーションの機会が十分でない職場ほど、早期退職のリスクが高まります。
建設業界の離職率を改善する具体策
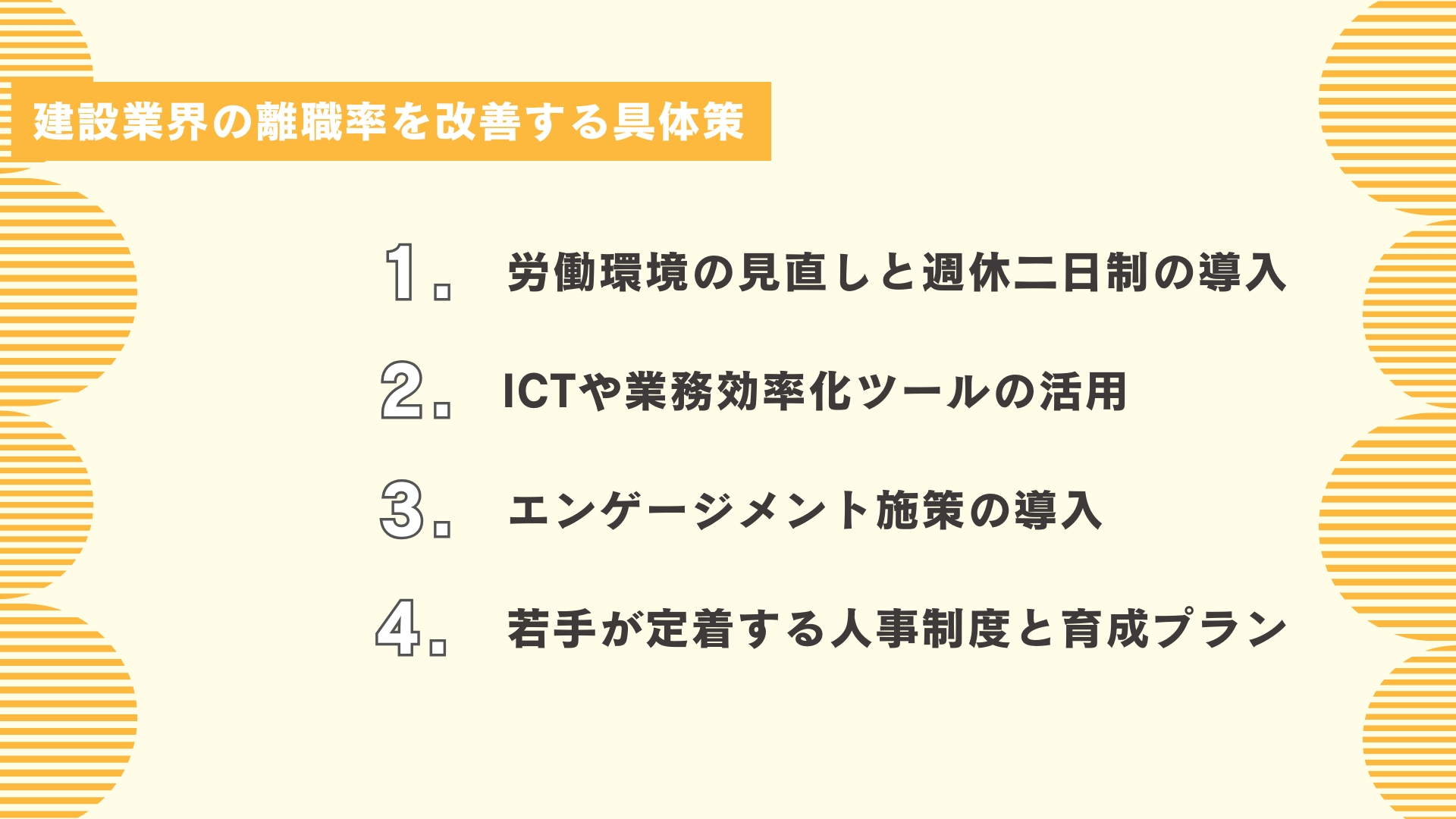
人手不足が深刻化する中で、離職を防ぐための取り組みが急務となっています。以下では、建設業に特化した具体的な改善策を紹介し、現場環境の見直しから人事制度の刷新まで、実効性のある施策を紹介します。
労働環境の見直しと週休二日制の導入
週休二日制の導入は、建設業の労働環境を大きく改善する手段です。国土交通省は「働き方改革加速化プログラム」を通じて週休二日制の実現を掲げており、発注者と企業が連携した取り組みが進められています。
また、現場の勤務間インターバル確保や長時間労働の是正も重要です。休日がしっかり確保されれば心身の健康が保たれ、定着率向上にも直結します。就業管理体制の整備は、若手の確保においても大きな意味を持ちます。
ICTや業務効率化ツールの活用
業務の煩雑さを軽減するためには、ICTツールの導入が効果的です。図面の共有や進捗管理、帳票の電子化など、施工管理を中心としたデジタル活用によって、現場負担を大幅に軽減できます。
結果として、残業削減や情報共有の円滑化が進み、働きやすさが向上します。とくに若手人材はデジタル機器への抵抗が少なく、ツールが整備された職場への定着率が高くなる傾向です。
エンゲージメント施策の導入
従業員との信頼関係を築くためには、エンゲージメント向上を意識した制度設計が求められます。定期的なフィードバック面談やサーベイの実施により、職場への満足度やモチベーションを把握できます。
とくに、個人の貢献を正当に評価し、働きがいを認識させる取り組みが有効です。業務外の交流機会を増やすことも、心理的な距離を縮める手段となります。数値化できる指標をもとに改善を繰り返す体制が、定着率の向上につながります。
若手が定着する人事制度と育成プラン
若手人材の流出を防ぐには、キャリア形成を支援する明確な育成計画が不可欠です。経験年数やスキルに応じた職務設計と目標設定を行い、成長を実感できる仕組みが重要となります。
また、資格取得にかかる費用の補助や講習支援などの制度が整えば、自己投資意欲が高まります。評価制度にも透明性が求められ、納得感のある昇給や昇格の仕組みがある企業ほど離職率が低下するでしょう。
建設業の離職率改善には外部支援の導入も有効
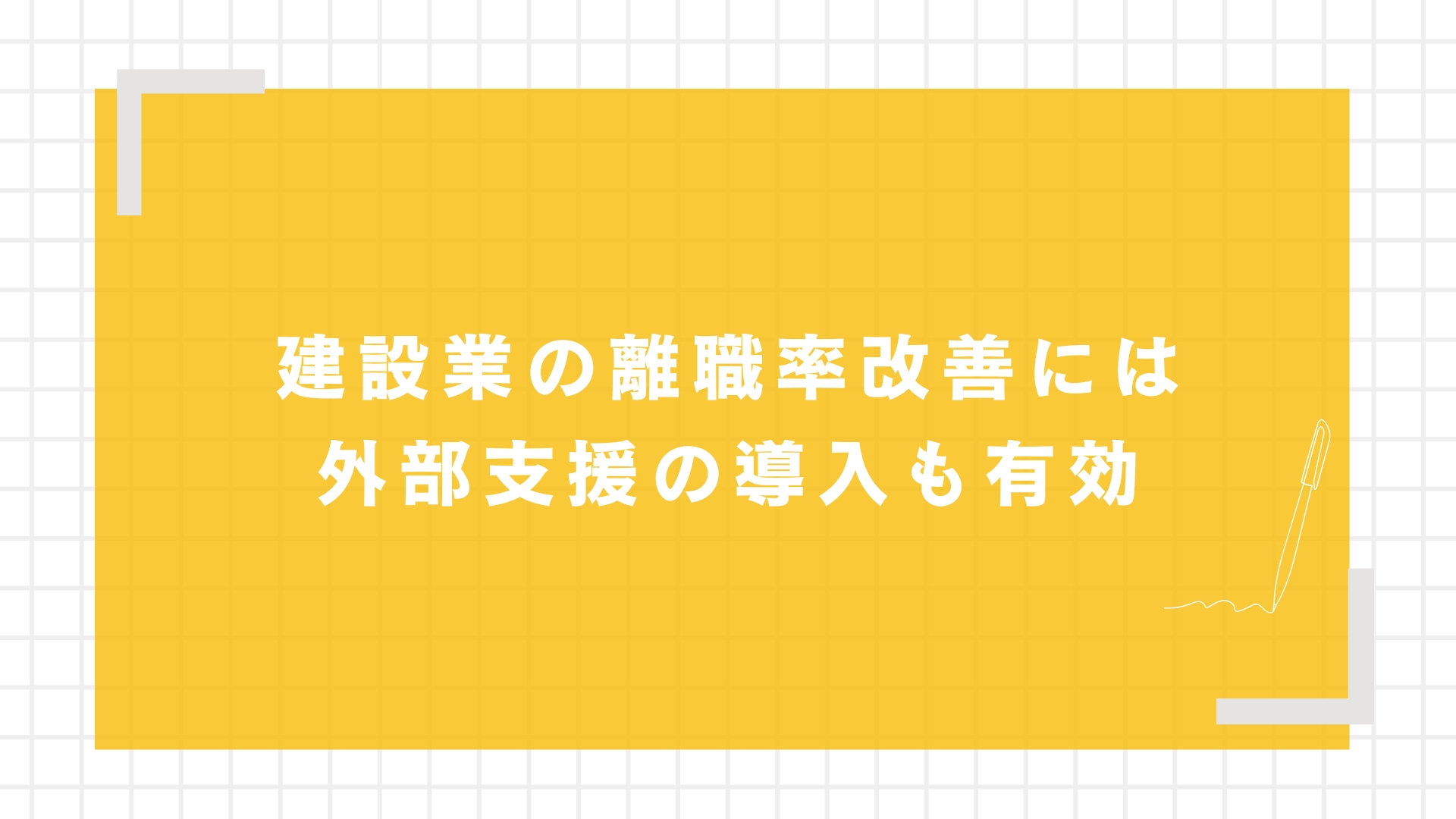
建設業界では人材確保と定着支援を同時に求められる一方で、採用活動や人事設計に割けるリソースが限られがちです。こうした背景から、採用領域を外部へ委託する動きが広がっています。
たとえば「まるごと人事」のような業界特化型の採用代行サービスであれば、求人設計から母集団形成、面接調整まで一貫して対応可能です。加えて、建設業ならではの就労環境やキャリア観を踏まえたサポート体制を備えており、採用精度と業務効率を同時に高められます。
まとめ
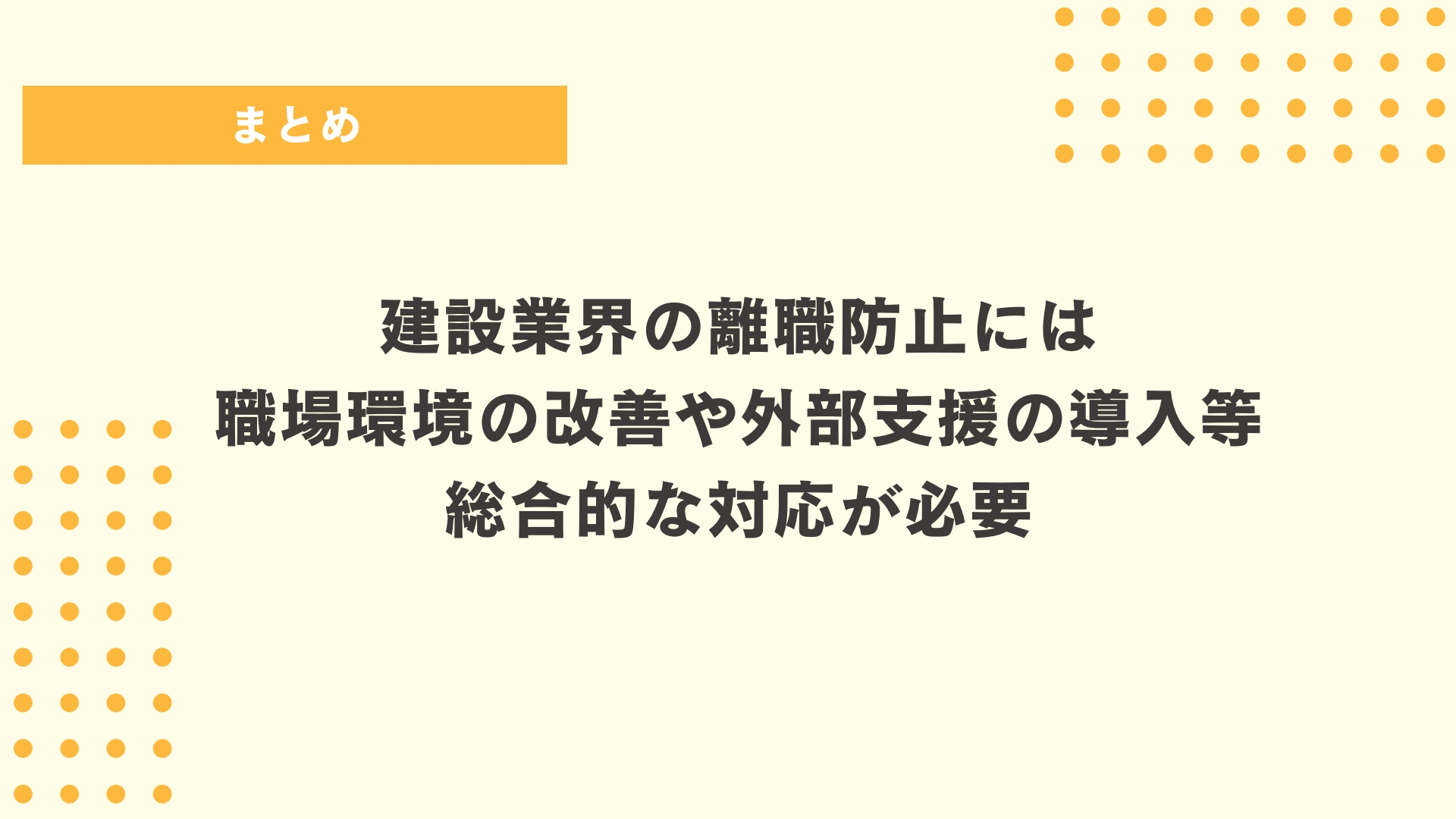
建設業界の離職率は他産業と比較して決して高くはないものの、若年層や技能系職種においての離職傾向が目立ちます。要因には長時間労働やキャリア不透明感、人間関係などが挙げられ、それぞれに対して明確な対策が必要です。
週休二日制の整備やICT導入、エンゲージメント施策を導入すれば、職場環境は改善されやすくなります。加えて、専門的な知見を持つ外部パートナーとの連携も、効率的かつ的確な採用・定着支援につながります。
離職防止を成功させるには、本記事で紹介した視点を重視した総合的な対応が必要です。
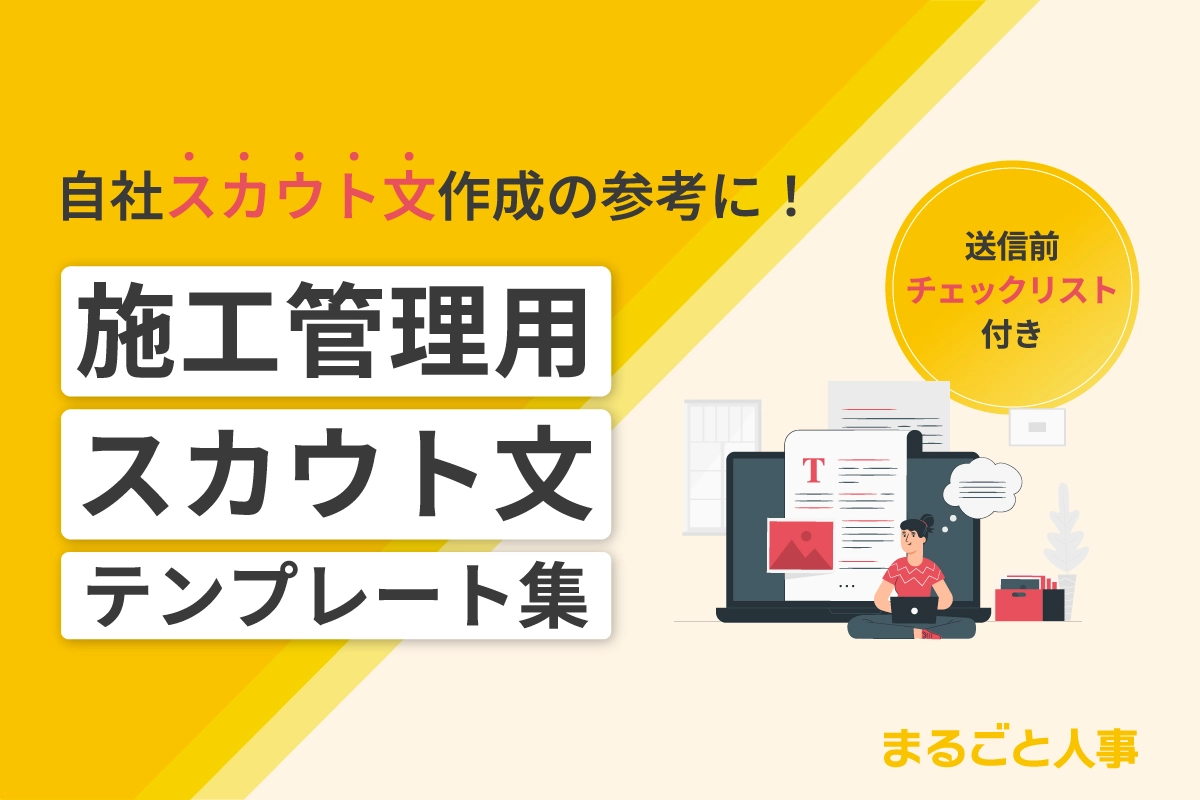
施工管理用スカウト文
テンプレート集
自社の魅力が伝わるスカウト文で応募数の向上を!送付前に確認すべきチェックリスト付き
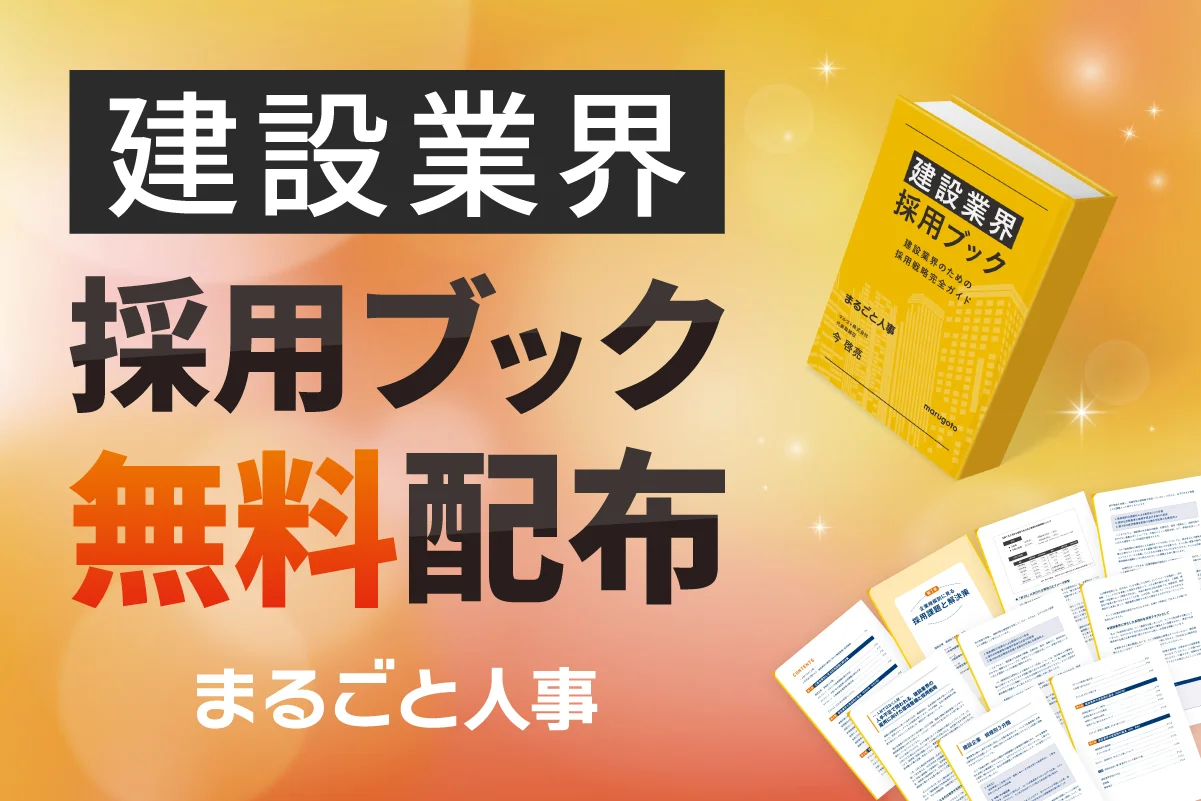
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事

採用ペルソナ設計5ステップを解説|採用活動に役立てる方法を紹介【シート付き】
- 採用企画
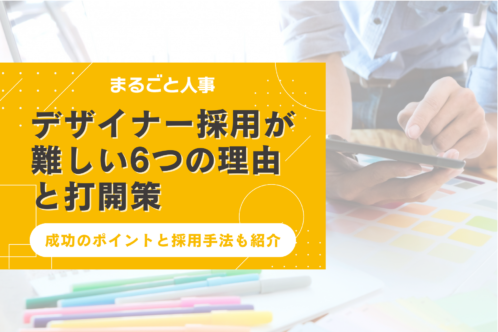
デザイナー採用が難しい6つの理由と打開策|成功のポイントと採用手法も紹介
- 採用企画
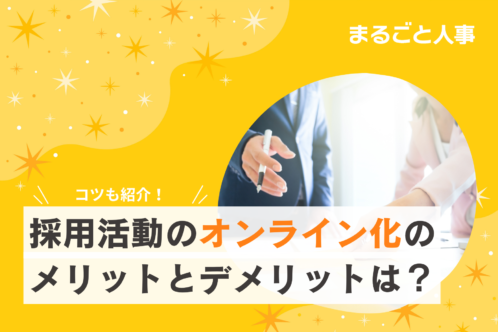
採用活動をオンライン化するメリット・デメリットとコツを紹介
- 採用企画
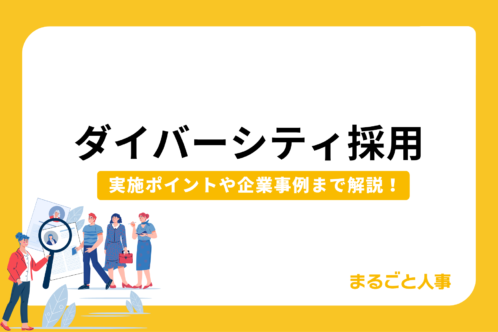
ダイバーシティ採用とは?メリット、課題、実施ポイントを解説
- 採用企画
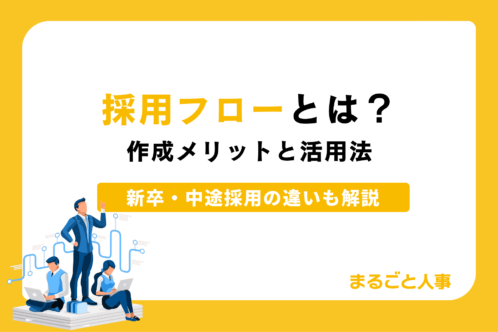
採用フローとは?作成のメリットと活用法、新卒・中途の違いをフロー図で解説
- 採用企画
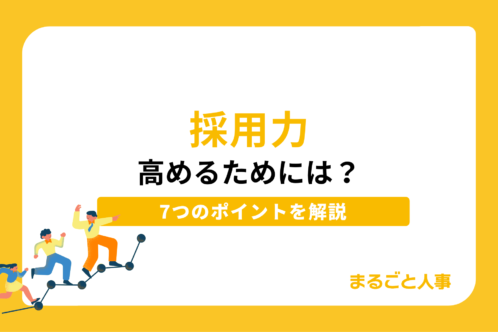
採用力とは?採用力を高める7つのポイントを解説
- 採用企画