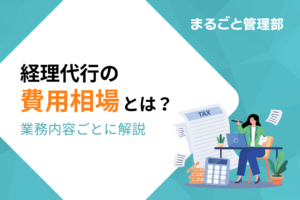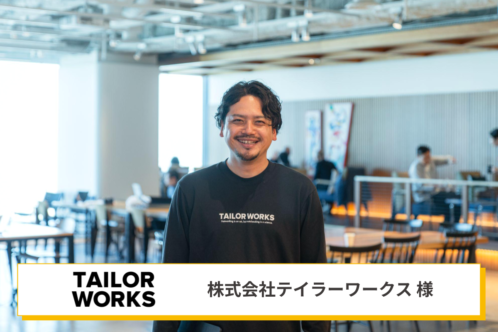採用・労務・経理に関するお役立ち情報

経費精算の効率化は、アナログ業務が残る現場においては強力な生産性の向上が期待できます。経費精算システムの導入は、従業員数の少ない中小企業やベンチャー企業にとっても魅力的な選択肢です。
この記事では、主に中小企業やベンチャー企業が導入を検討すべき経費精算システムとはどのようなものかについて、具体的な機能や主な比較ポイントに触れながら解説します。
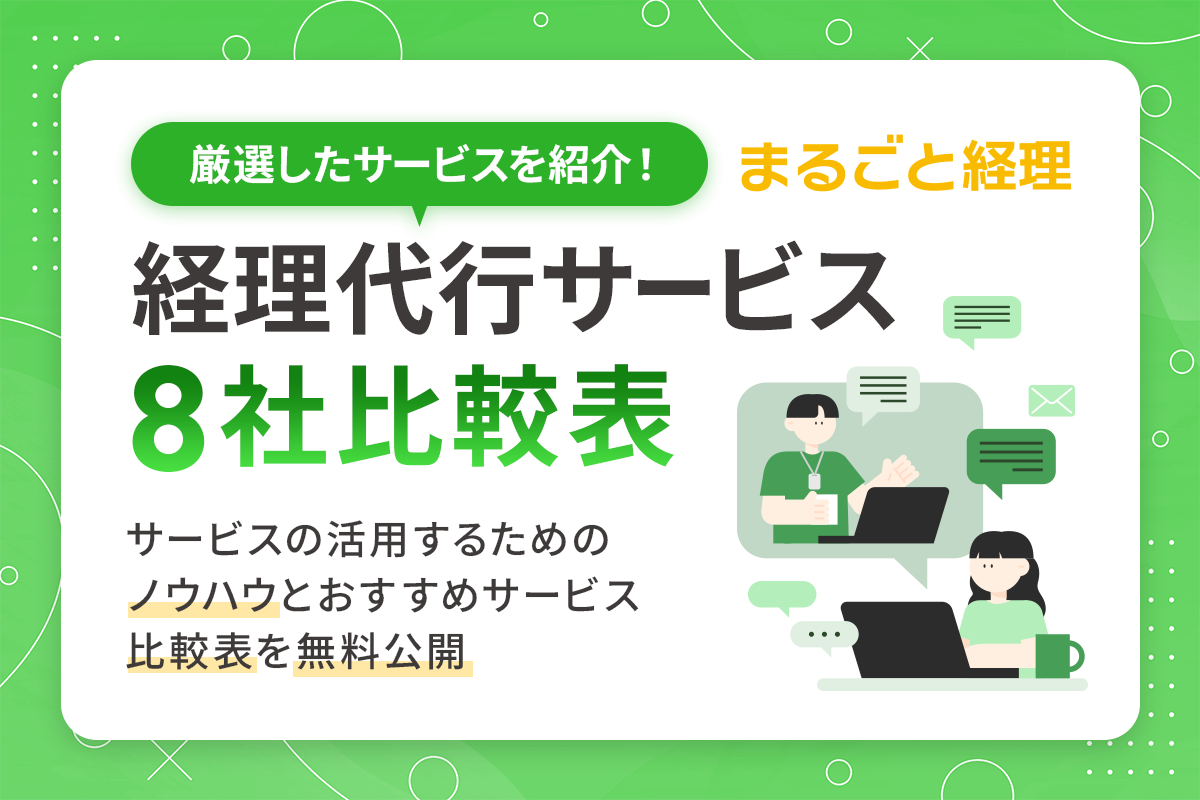
経理代行サービス比較表
経理代行サービスの活用の基本を解説。8社のサービスが一気に比較できます!
目次
経費精算システムの役割

経費精算システムは、その名の通り経費精算業務を効率化するためのサービスです。経費精算に伴う経費項目の入力を自動化・省力化し、申請や承認などもシステム上で実行できるようになります。
経費精算の業務は、企業の規模に関わらず必ず発生します。近年は多様な組織規模の企業に対応した様々な経費精算システムが提供されており、簡単に導入可能です。特にクラウド型のサービスは導入ハードルが低く、初期費用を抑えつつすぐにシステムを利用できるため、非常に便利です。
経費精算システムと会計システムとの違い

経費精算システムと似たようなサービスに、会計システムが挙げられます。会計システムは、主に帳簿の作成やそれに伴う計算・仕分けといった業務を効率化するためのシステムです。
一方で経費精算システムは、経費の申請から承認、そして会計処理に至るまでの、会計システムの領域も含めた業務の効率化に役立ちます。会計システム単体で導入するよりも、経費精算システム導入の方が申請者や経理担当者の業務効率化の面で高い効果を発揮するでしょう。
経費精算に関する周辺業務も含めた効率化を検討している場合、経費精算システムの導入がおすすめです。
経費精算システムを導入するメリット

経費精算システムの導入は、大企業が積極的に取り組んでいる印象も受けます。ただ近年はサービスの多様化に伴い、中小企業やベンチャー企業における導入事例も増えてきました。
中小企業やベンチャー企業が経費精算システムを導入するメリットには、以下の3つが挙げられます。
手動業務の削減に伴う生産性の向上
経費精算システムの導入は、手動でのデータ入力や書面作成の負担を削減し、生産性向上に貢献します。データのインプットや転記、そして出力に至るまでのほとんどの作業をシステム上で自動化できるので、従来発生していた業務負担を大幅に減らせるでしょう。
ヒューマンエラーの削減
ヒューマンエラーの削減においても、経費精算システムの導入は非常に有効です。入力の自動化を各プロセスの中で進められるため、入力ミスなどのリスクを極限まで減らせます。
ヒューマンエラーに起因する修正作業やダブルチェックなどの負担を削減し、迅速な業務遂行に貢献できるでしょう。
ペーパーレス化の促進
経費精算に伴うほぼ全ての業務がシステム上で完結できることにより、ペーパーレス化を実現できます。これまで書面で実施していた申請や承認といった手続きも、オンラインで実施することにより紙の利用を解消可能です。
印刷や確認のコストを最小限に抑え、生産性の高い業務環境を整備できます。
中小企業やベンチャー企業で導入されている主な経費精算システム

経費精算システムには複数の種類が存在しますが、中小企業やベンチャー企業においては主に以下のサービスが人気です。
楽楽精算
楽楽精算は、日本における導入数がトップクラスに多いサービスとして知られています。紙やエクセルを使った経費精算業務の脱却をコンセプトとしている製品で、申請から承認、保存に至るまでを自動化できます。
PCからのアクセスはもちろん、スマホからの利用にも対応しているため、働き方改革の推進にも役立ちます。
Concur Expense経費精算システム
Concur Expense経費精算システムは、中小企業向けの機能が充実していることで知られる経費精算システムです。QRコード決済サービスをはじめ、多様なサードパーティ製品との連携に対応し、業務のペーパーレス化に役立ちます。
初期費用はかからず、月額料金も3万円からで利用可能なコストパフォーマンスの高さも人気の理由の一つです。
ジョブカン経費精算
ジョブカン経費精算は、ベンチャー企業はもちろん、大企業まで幅広く導入されている人気の経費精算システムです。経費精算にかかる負担を1/10に抑えられる効率化機能を備え、意思決定の高速化に貢献します。
電子帳簿保存法に完全対応しているなど、最新の法改正にも迅速にキャッチアップできるのがポイントです。
ベンチャー企業が経費精算システムを選ぶ際の比較ポイント

経費精算システムは製品によって強みや実装機能が異なるため、正しい比較ポイントを押さえておくことが重要です。
経費精算システム選びにおいては、以下の3つを踏まえた選定を進めると良いでしょう。
自社課題の解決に適した機能があるか
経費精算システム選びでは、まず自社の課題の解決につながる機能が備わっているかどうかを確認しましょう。必要機能が十分でない製品を導入しても、期待しているような導入効果を得ることが難しくなるためです。
まずは自社の課題をあらかじめ洗い出しておき、それぞれの課題解決につながる機能を把握の上、製品のピックアップを実施すると良いでしょう。
適切な費用対効果が望めるか
費用対効果を考えることも、経費精算システム選びにおいては重要です。必要以上に規模の大きなシステムや料金が高額な製品を導入すると、経費精算システム導入の効果以上にコストが圧迫し、適切な成果が得られなくなります。
自社の予算を踏まえた上で、少人数での稼働でも適切なリターンとコストパフォーマンスが期待できるサービスを選ぶことが大切です。
導入負担を小さく抑えられるか
ベンチャー企業が経費精算システムを選ぶ際には、クラウド型のサービスがおすすめです。というのも、クラウド型製品の多くは初期費用が無料、あるいは最小限の設定となっていることが多く、導入負担を小さく押さえられるためです。
また、クラウド型の製品は継続課金となりますが、小規模での運用の場合は極端に高額になる心配もありません。導入時の負担を減らして気軽にはじめられ、それでいて将来のリスクも小さく、事業が軌道に乗ったら再度環境を検討するようなビジョンを設定しておくと良いでしょう。
重視すべき経費精算システムの機能とは?

経費精算システムを導入する上でどのような機能に着目すると良いのでしょうか。ポイントとしては、以下の3つの機能を重視した選び方ができるのが理想です。
各種入力自動化機能
経費精算システム導入に際しては、どれくらい入力作業を自動化して負担を減らせるのかが大切です。経費精算に伴う労力の大半はデータ入力や共有の中で発生するため、できる限り少なくできるものを選びましょう。
他社ソフトとの連携機能
入力の自動化と合わせて重要なのが、他社ソフトとの連携機能です。すでに導入している、あるいはこれから導入するソフトとの互換性が確保されていると、データの入力をさらに自動化したり、情報共有なども効率化できたりします。
交通系ICカードリーダーとの連携、Slackやチャットワークといったコミュニケーションツールとの連携機能については、特に導入の恩恵が大きいため注目したいところです。
電子ワークフロー機能
経費精算システムは、申請から承認までの手続きが完全にシステム上で実施できるものを選びましょう。申請プロセスが十分にカバーされていないシステムを導入してしまうと、中途半端に書面での作業が発生したり、出社負担が増えたりするからです。
まとめ

この記事では、経費精算システムとはどのようなツールなのか、導入に際してはどんなポイントに注目すべきなのかについて解説しました。
中小企業やベンチャー企業でも、今後事業が拡大していくにつれ、その負担も大きくなっていくことから、早期から経費精算システムの導入と現場での運用を進めておくことが大切です。
また、経費精算の負担を短期間で解消したい場合には、月額制の経理代行サービス「まるごと管理部(経理プラン)」の活用もおすすめします。業務を1ヶ月単位から任せることができ、長期的な利用はもちろん、経費精算システムの導入や運用体制が構築されるまでのつなぎとして活用するようなアプローチも可能です。
サービス利用にあたって、自社の業務プロセスの変更が強いられることはなく、すぐに経理業務の効率化を進められます。
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
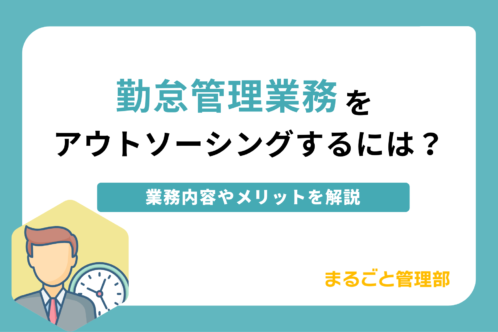
勤怠管理のアウトソーシング(代行)サービス10選!業務内容やメリットを徹底解説
- バックオフィス業務
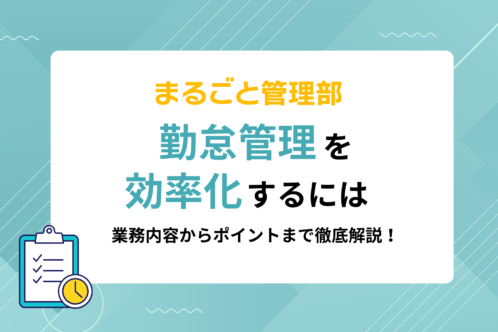
【勤怠管理を効率化するには】業務内容から効率化のポイントまで徹底解説!
- バックオフィス業務
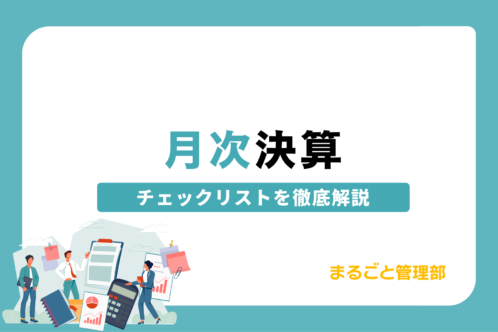
月次決算のチェックリストを徹底解説!年次決算の負担を減らすポイント
- バックオフィス業務
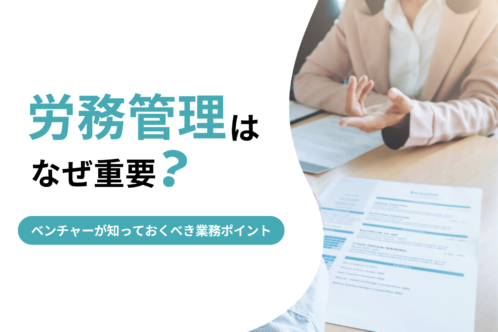
労務管理はなぜ重要?ベンチャー企業が知っておくべき業務のポイント
- バックオフィス業務

人事労務BPOとは?導入のメリットや依頼できる業務を徹底解説
- バックオフィス業務
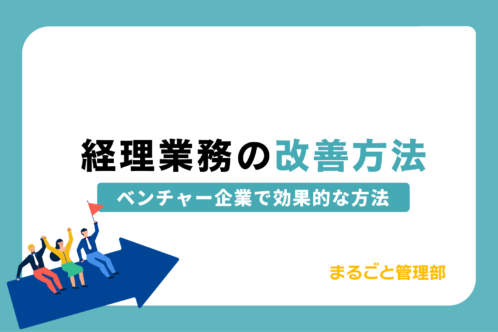
経理の業務改善方法とは?中小企業の働く実態から見る施策を解説
- バックオフィス業務