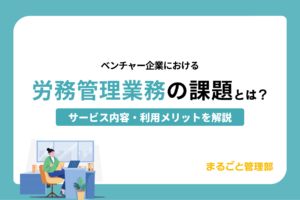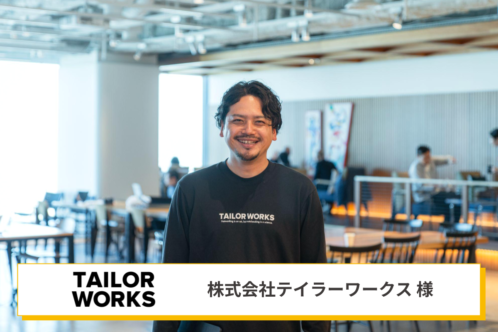採用・労務・経理に関するお役立ち情報

社内規定や経費精算システムや勤怠管理システムなどのツール導入にあたって、社内での質問が絶えず担当者が手動対応するコストが増えていませんか。
そこでおすすめなのが社内FAQの導入です。社内FAQを整備しておけば、疑問点があった時の問い合わせを減らしたり、新入社員への引き継ぎがスムーズに進みます。
ナレッジを一元管理すると、社員が必要な内容をすばやく取得でき、メールやチャットによる社内問い合わせ対応の工数が削減されます。
本記事では社内FAQの導入ステップの注意ポイントやナレッジマネジメントのコツを解説し、企業が抱える課題を比較検討しながら解決する方法を紹介します。
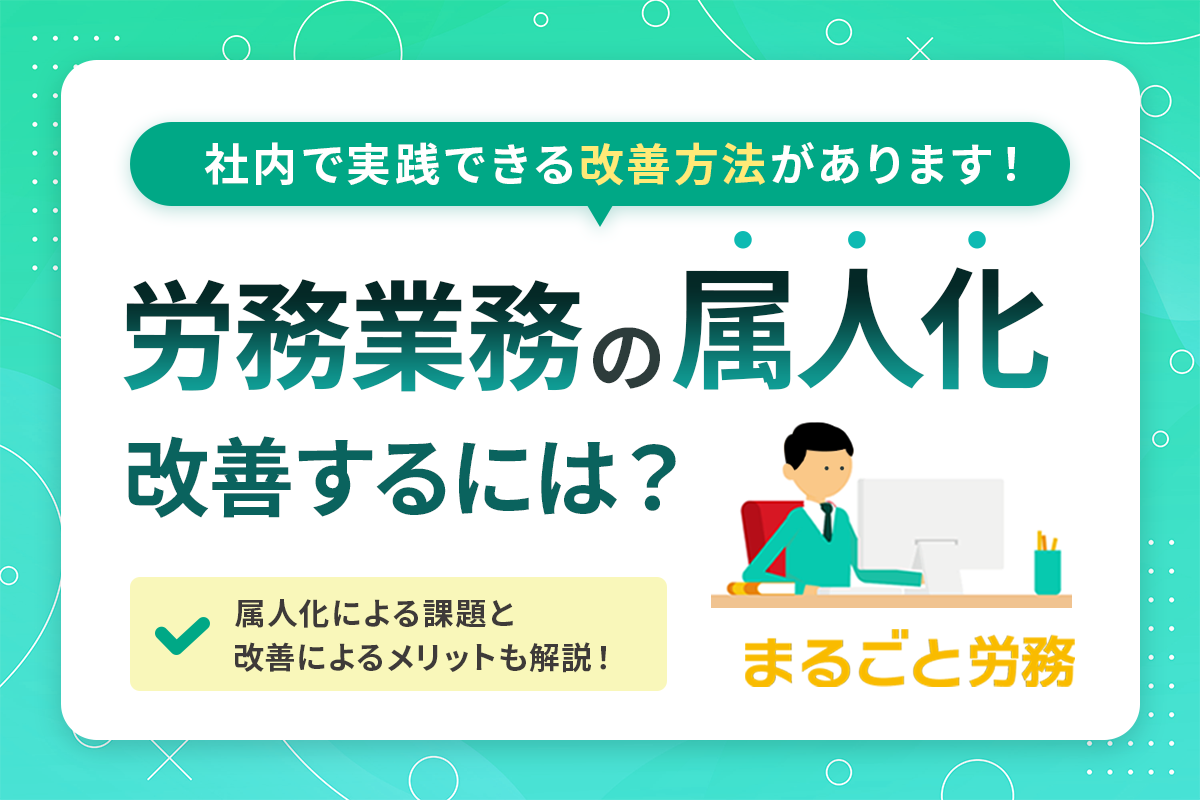
労務業務の『属人化』を改善する方法
労務業務の属人化を解消するための、具体的な方法を徹底解説します!
目次
社内FAQとは?導入が必要な理由と企業での活用方法を紹介

社内FAQは、企業が内部で共有する知識の蓄積や運用に役立つシステムです。問い合わせが多く寄せられる組織では、導入によって問題解決の効率が高まり、担当者の負担が軽減されます。特に新しいツール導入を進めている企業や独自の社内システムを持っている企業に効果を発揮します。また近年増えているリモートワークを導入している場合はコミュニケーションコストの削減にもつながります。
以下で具体的なメリットを解説します。
バックオフィスの工数削減
有給や忌引きなどの申請などの社内規定や社内で使用している経費精算システムや勤怠管理システム等のシステムの利用方法など、社内や部署ごとに決まったルールがある場合には、社員がいつでも見れるFAQのようなもので準備していくことがおすすめです。
問い合わせやミスが多い作業は限られていますので、そういった作業部分だけでも社内FAQを作成することで同じ内容で毎回対応する必要がなくなり、対応するバックオフィスメンバーの工数を削減することが可能です。
また内線電話やメール・チャットで問い合わせに対応する場合と比べても、社内FAQでツールなどの画面のスクリーンショットなどを用意しておくことで、誤解を防ぎながら効率的に対応することができます。
引き継ぎの効率化
新入社員が入った場合や、部署移動などで新規に社員が増えた場合にも社内FAQを作成しておくメリットが大きいです。細かい社内ルールやツールの使用方法などはすぐに覚えられるものではないので、困った時に見ておくものとして伝えておくことで、正確な情報を伝えることが可能となります。
また社内FAQなどがない場合、引き継ぎをする担当者によって伝えている情報の違うケースもあるため、そのような属人化したルールなどを防げるというメリットもあります。
使われない社内FAQの特徴と、改善のための注意ポイント
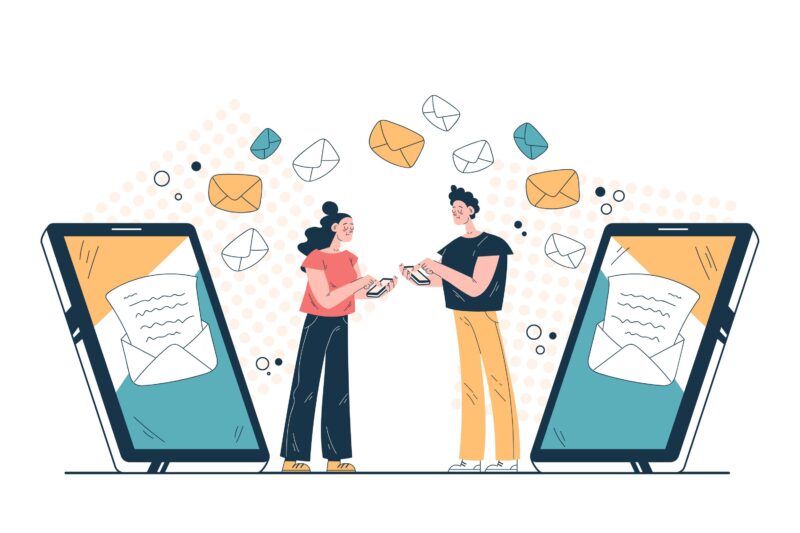
社内FAQが使われなくなる原因の一つは、情報が分散していて要点がわかりにくいことが多いです。また社内FAQへのアクセスがしにくい場合、作成したFAQや資料を閲覧できず、従業員がアクセスする意欲を失うことも多いです。さらに古い情報のまま更新されない社内FAQですと、最新情報かどうかの問い合わせも発生するため社内FAQの効果が大幅に減少することにも繋がります。
コストを削減しながら更新性や将来的な拡張性を考えるなら、社内FAQと既存の仕組みを連携させて運用する方法も検討することがおすすめです。
社員がFAQを使わない理由とは?よくある3つの問題を解説
- 設計や作成段階で社員の質問を十分に収集していないために、必要な回答が網羅されていない
- 検索性が低く、アクセスしづらい構造になっている
- 更新作業が滞り、最新情報が反映されていない
これらが積み重なると、社内FAQのメリットを活用できず、形だけの運用になりやすいです。
また担当者の熱意が伝わらないまま導入してしまうと、従業員間で情報を共有する意識が育たず、有用な活用に繋がらないケースが多いです。
しかし、社内FAQの導入ポイントを押さえて作成を行えば、中長期的に業務効率の向上やコスト削減など大きな効果が見込めます。
FAQを検索・活用しやすくするための具体的な作成方法とは
業務に役立つ社内FAQを作るには、まず質問と回答を整理し、社員が欲しい情報を網羅することが重要です。
以下のような点に注意して作成を行うことがおすすめです。
- 社内の就業規則や経費申請ツールのURLなど、関連する情報にもアクセスしやすくする
- スクリーンショットや図などを活用して、一目で分かりやすい内容にする
- 基本的なことばかりでなく、よくつまづくケースやイレギュラーにも対応する
- 最初の作成時や、見直しのタイミングで社内に広く課題となっていることを募集する
- 最新情報になっているか定期的に更新を行う
またPDFなどの更新がしづらい形式ではなく、GoogleスプレッドシートやGoogleドキュメント、notionや有料ツールなどを活用してFAQツールを導入することがおすすめです。もし、PDFなどで配布する場合は最新ファイルへのアクセスが簡単にできるようにすることや、更新日などで最新版が分かるようにする点などに注意する必要があります。
また有料となりますが、AIや検索機能を活用して素早く解決策にアクセス可能な構造にしたり、チャットボットを組み合わせると社員が自然な言葉で質問しても回答が返ってくるため、運用コストの削減や教育の効率化につながります。
社内FAQ運用を成功させるための導入のポイント

社内FAQの導入や運用を進めるには、社内FAQの利便性や情報の正確性、信頼性を高めることがおすすめです。
せっかく社内FAQを作成しても、活用されなかったり、社内FAQ自体の使い方の質問が来てしまうと本末転倒となりますので、導入の際には以下の流れに沿って導入することがおすすめです。
まずは特定のツールなど限定した範囲から作成する
広く浅く作成するよりも、まずは全社員が共通して使用している労務系や経理系のツールなどから作成することがおすすめです。バックオフィスへの問い合わせが多いものや社内で疑問の声が多いものを選び、定期的に発生することが判明しているイレギュラーへの対応も含めて、まずは深掘りしたFAQを作成して社内の共有することがおすすめです。
社内の声をフィードバックする
社内FAQを作成する際には、一方的に社内の利用を進めるのではなく、使用感やまとめ方など社内からのフィードバックを集め、改善していくことがおすすめです。職種や部署によって元々の理解度や課題も違うため、広く情報を集めて内容を改善していき、狭い範囲でも普段から使用してもらう習慣を作っておくことが重要となります。
社内からの問い合わせはすぐに社内FAQに反映する
社内からのフィードバックや記載されていないイレギュラーケースに関しても、なるべく早く社内FAQに盛り込むことがおすすめです。可能であれば、社内からの問い合わせに関しては社内FAQを更新した上で、社内FAQに盛り込んだ旨を添えて、返答できるようにしておくことがおすすめです。
また問い合わせが多い内容に関しては優先度を設定して、目立つ位置に記載するなど重要な内容にアクセスしやすい内容にすることもおすすめです。
社内FAQへのアクセシビリティを考える
作成した社内FAQへのアクセスがしやすい環境を作成しておくことも重要です。社員がたどり着きやすい設計を考えることで、検索や回遊性が高まり、短時間で問題を解決できる環境を生み出せます。
社員が分かりやすいアクセス経路を作成しておいたり、定期的に全社メールやチャットなどで周知を行うなど、社内FAQが存在することの周知やアクセスしやすい環境作成がおすすめです。
定期的に最新情報に更新する
社内FAQに載っている情報が古いと社内FAQに対する信頼性が下がるため、定期的に情報を確認して更新することがおすすめです。特に普段あまり使用していないツールなどでは、UI/UXなどの仕様が変わっていたり、社内フローが変わったにも関わらず社内FAQが対応していないケースもあるため注意が必要です。
そのため、社員側から細かなことでも変化を教えてもらえる窓口作りや、社内FAQを管理する部署やチームで予め定期的に最新情報に更新するタイミングを作っておくことがおすすめです。
まとめ:使われる社内FAQの導入が重要

人材不足やDXなどが多くの企業の課題となっている中、社内FAQの導入や整備の重要度はこれからますます上がっていく可能性が高いです。
まだ社内FAQを導入していない企業や、社内FAQを見直ししたい企業は、本記事の内容を参考にしながら活用される社内FAQを目指していきましょう。ポイントを押さえて運用や更新を行えば、バックオフィスの対応工数を始め、多くの社員が質問などの工数を減らし効率的に業務を進めることが可能となります。ぜひ自社に合う社内FAQの形式やシステムを比較しながら検討し、業務の効率化に繋げてください。
月額制バックオフィス代行の「まるごと管理部」労務プランや経理プランでは社内FAQの導入の際のサポート実績もありますので、社内FAQの導入や改善でリソースが足りない場合やノウハウが足りない場合はぜひお気軽にご相談ください。
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
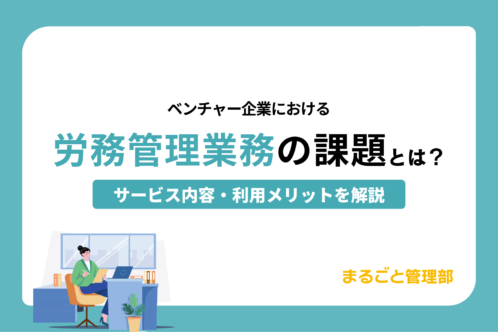
ベンチャー企業における労務管理業務の課題とは?改善ポイントを解説
- バックオフィス業務
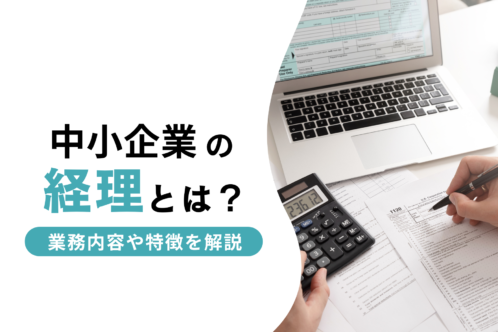
中小企業の経理とは?業務内容や特徴を解説します
- バックオフィス業務
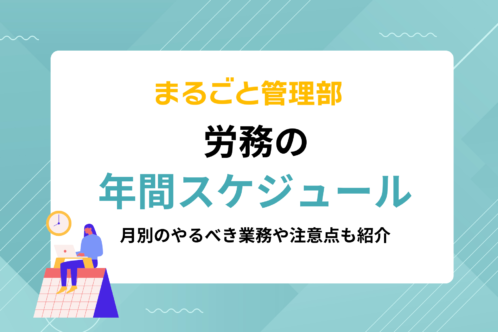
労務の年間スケジュール|月別のやるべき業務や注意点も紹介
- バックオフィス業務

シフト管理ができる勤怠管理システムとは?導入メリットや製品の選び方
- バックオフィス業務
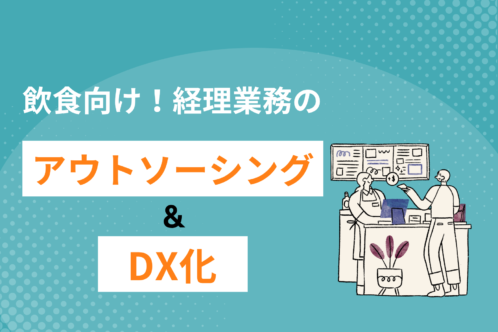
飲食店の経理アウトソーシングとDX化のポイント!
- バックオフィス業務
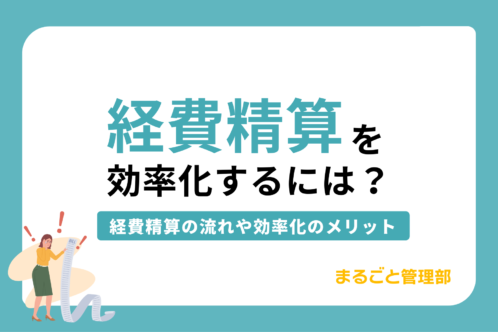
経費精算を効率化するには?経費精算の流れや効率化のメリットも紹介
- バックオフィス業務