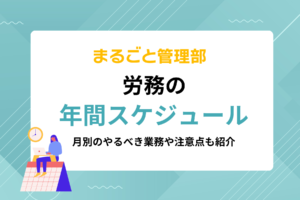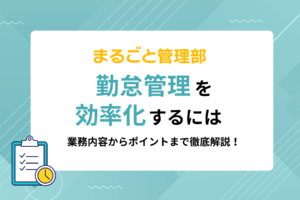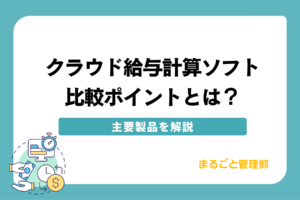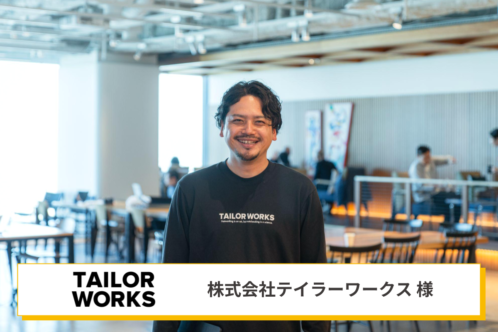採用・労務・経理に関するお役立ち情報
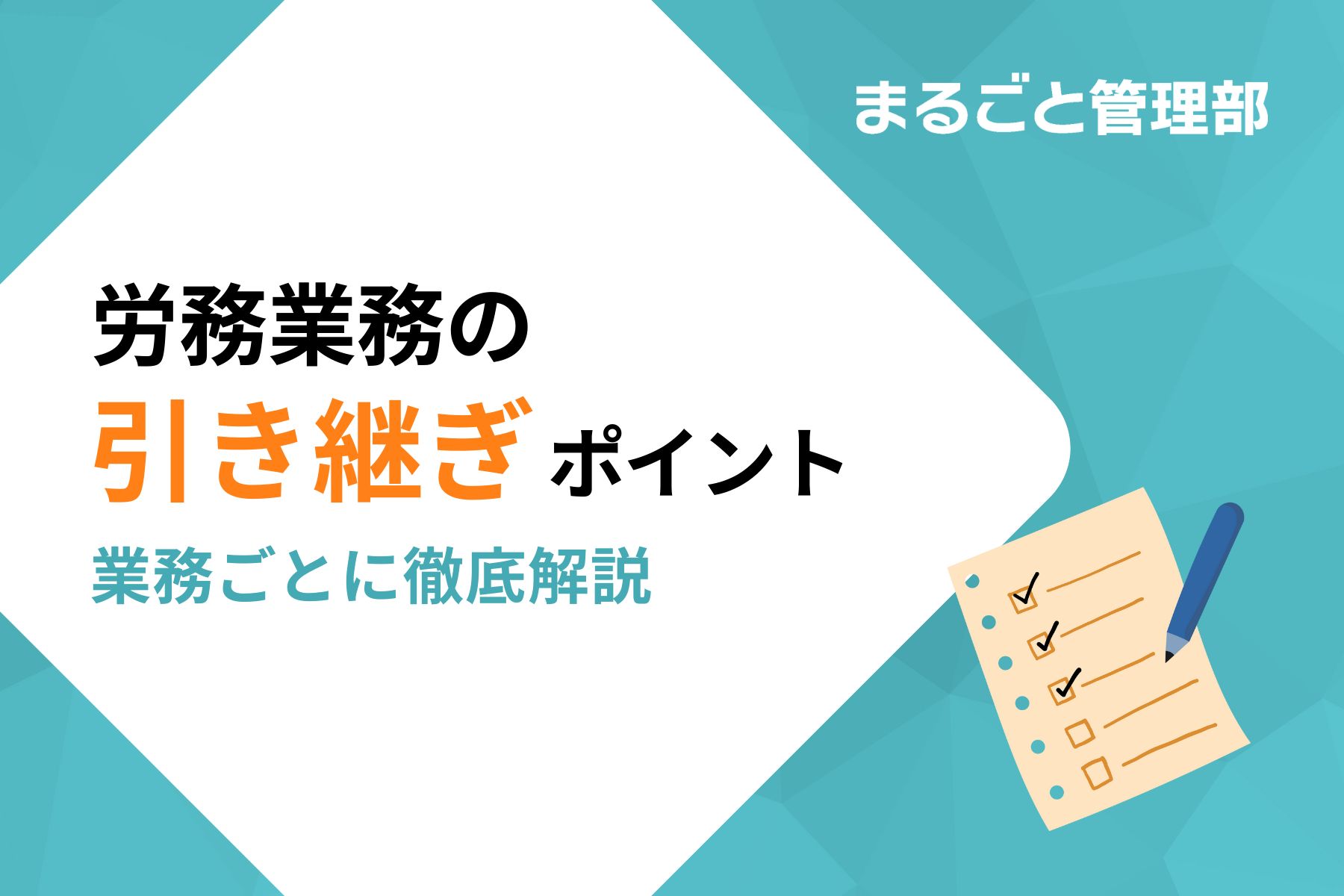
労務業務は経営の基盤として必要不可欠である一方、売り上げに直結しにくいことから経費削減の一環として少数精鋭で担当している場合が多いです。そのため、一人でも担当者が退職してしまうと業務に大きな支障が出てしまい、会社の経営に悪影響を及ぼす事態に陥ってしまいます。
本記事では担当者が退職するリスクのために備えておきたい、労務の引継ぎに関する情報を解説します。
労務業務の引き継ぎをきっかけに、業務効率化を図るとよいでしょう。以下の記事では、労務業務を効率化する方法やポイント、押さえるべき注意点も解説しています。

バックオフィス人材を補填する5つの方法
リソース不足や急な退職時に比較できるバックオフィス人材の補填する方法を解説します!
目次
労務業務の引き継ぎをしないリスクとは?
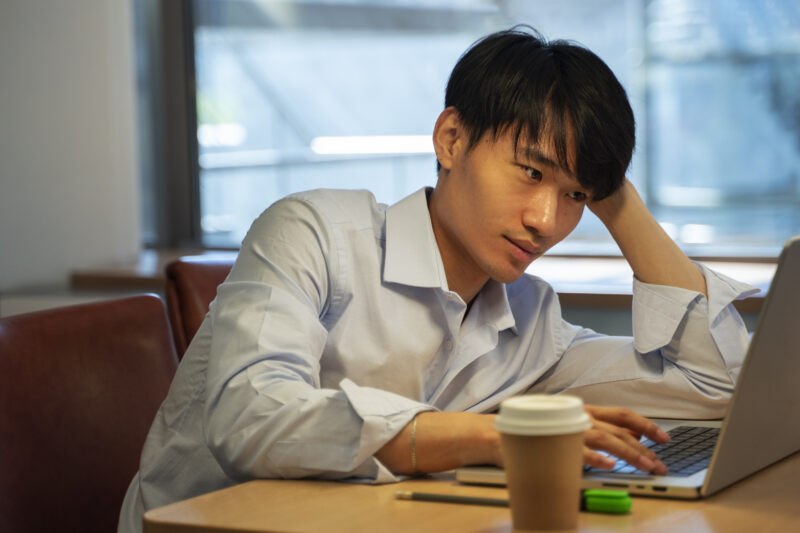
労務は専門性の高い業務であるため、引き継ぎがうまくできないと企業の経営に多くの不具合を引き起こしてしまいます。
ここでは、労務業務が引き継ぎ出来ていない場合に発生するリスクを3つ解説します。
効果的な対策を講じるために、以下のリスクを把握しておくと良いでしょう。
業務に対応できなくなる
引継ぎができていないと、現状の管理状態を把握するのが難しくなってしまうため、業務に対応できなくなる可能性が高くなります。
労務経験が豊富な人材を新たに補充しても、これまでの状態を調査しなければならないため、正常な業務体制に復旧するまでに時間を要します。
労務業務が滞っていると、社内のその他業務にも影響が出るので、労務だけでなく企業の他部門でも対応できない業務が発生する恐れがあります。
知識やノウハウの損失
引継ぎができていないと、業務の進め方や過去の対応履歴、社内特有のルールなどが引き継ぎ先に継承されないため、企業特有の知識やノウハウが損失してしまいます。
それにより作業効率が大幅に下がってしまう、過去にあったミスが再発してしまうなど、業務の品質低下につながります。
知識やノウハウの蓄積は時間がかかるものなので、一度失ったノウハウを再度取り戻すには多くの時間が必要になると理解しておくと良いでしょう。
法的トラブルが起きてしまう
給与計算業務や社会保険のトラブルは、法律違反や契約違反といった法的トラブルまで発展してしまうことも珍しくありません。
法的トラブルを引き起こしてしまうと、企業の社会的信用度が大きく落ちてしまい、売り上げや経営に悪影響を与えてしまいます。
企業に勤めている従業員にも大きな不安を与えることになるので、労務業務が原因で法的トラブルにつながる事態は、何としても避けたいケースだといえるでしょう。

バックオフィス人材を補填する5つの方法
リソース不足や急な退職時に比較できるバックオフィス人材の補填する方法を解説します!
引き継ぎのポイントを業務ごとに徹底解説

労務にはさまざまな業務があり、業務によって引き継ぎのポイントが異なります。
ここでは4つの労務業務を取り上げ、それぞれの業務概要と引き継ぎのポイントを解説します。 健全な経営体制を維持するために、経営者もポイントを把握し、担当者が引き継ぎしやすい環境を整えることを心がけましょう。
勤怠管理
勤怠管理は正しい給与計算や労働時間を把握するために、従業員の出勤状況や勤務時間を記録・管理する業務です。
労働基準法を守りつつ、効率的な働き方を実現するには必須の業務であり、正しい勤怠管理をすることで健全な労働環境を整えられます。
勤怠管理システムや勤怠管理ソフトを導入することで、業務の労力を大幅に削減できるため、企業がツールを使用しているかどうかで、引き継ぎの手間が大きく変わります。
勤怠管理の引き継ぎポイント
自社の就業規則や労働基準法の概要を確認するのはもちろん、ツールの使い方やサーバーの状態を共有しておくと、ツールの不具合にも対応できるようになります。
また、引き継ぎには有休管理簿や残業時間の管理資料など、従業員の勤怠に関する情報が必要になるので、従業員の勤怠情報を常にまとめておき、引き継ぎ時に現在の状態を簡単に共有できるようにしておくことをおすすめします。
給与計算
給与計算は従業員に支払う給与額を正確に算出する業務です。
契約条件や各種控除額に基づく計算が必要になるので、引き継ぎをする際には引き継ぐ社員がどの程度の専門知識を有しているかが重要になります。
また、勤怠管理情報から勤務時間・残業時間の集計をするため、勤怠管理業務と連携が取れているかどうかで、引き継ぎの手間が大きく変わります。
給与計算の引き継ぎポイント
給与計算業務の引き継ぎには就業規則・給与規程の確認と、給与計算の方法を共有する必要があります。
給与計算方法を共有する際には、以下の項目に関する情報を整理しておくと、スムーズに引き継ぎできます。
- 所得税や住民税などの法定控除の内容
- 会社独自のルールとして積立金・社宅家賃等の控除を締結しているかが書き示されている、賃金に関する労使協定の有無
- 従業員が加入している積立金や互助会費などの任意控除の内容
- 通勤手当や資格手当など、給与に関係する福利厚生制度
また、勤怠締めから給与計算までのスケジュールを一緒に確認しておくと、給与締めの忙しい時期にも問題なく対応しやすくなるでしょう。
保険手続き
保険手続きは従業員が加入する社会保険や労働保険の届出・手続きを管理し、従業員が事故や病気になった際などに、適切に加入した保険内容を受けられるようにサポートする業務です。
企業で手続きが必要な社会保険の大まかな種類は以下のとおりです。
- 健康保険
- 厚生年金保険(介護保険)
- 雇用保険
- 労災保険
社会保険は手続きが複雑なだけでなく、ミスしてしまうと従業員との大きなトラブルに発展することもあるので、引き継ぐ社員で対応が難しい場合は社労士等の専門業者に委託することも視野に入れておくと良いでしょう。
保険手続きの引き継ぎポイント
従業員が退職したときや従業員を採用したときなど、シチュエーションごとに業務内容が異なるので、それぞれの対応をまとめておくと、漏れなく業務を共有できます。
また、社会保険・労働保険の手続きを始める際に必要な資料のチェックリストを作成すると、引き継ぐ社員が資料を確認し忘れる事態を防げるのでおすすめです。
福利厚生業務
モチベーション向上や離職率低下に効果を発揮する福利厚生制度を充分に活かすためには、労務が福利厚生のサポートやサービスを計画・運営・管理する必要があります。
育児・介護休業や健康診断の実施、社員食堂など、企業が導入しているサポートや施設によって内容が大きく異なるため、引き継ぎ内容も企業によって変わりやすい傾向が強いです。
福利厚生業務の引き継ぎポイント
福利厚生は食事補助や住宅補助、学習手当などサービスごとに支援する金額や対象となる条件が企業ごとに異なるので、福利厚生制度の全体像がわかる資料等を確認すると良いでしょう。
各福利厚生制度によって対応頻度が変わってくることも考えられるので、どの時期に発生しやすい業務なのか整理して、スケジュールを共有しておくと、よりミスなく業務を引き継ぐことが可能です。
また、単に引き継ぐだけでなく、従業員や働き方のニーズに合わせて新しい福利厚生を追加するなど、こまめに内容を見直すように伝えておくと、費用対効果の高い福利厚生サービスを維持できます。
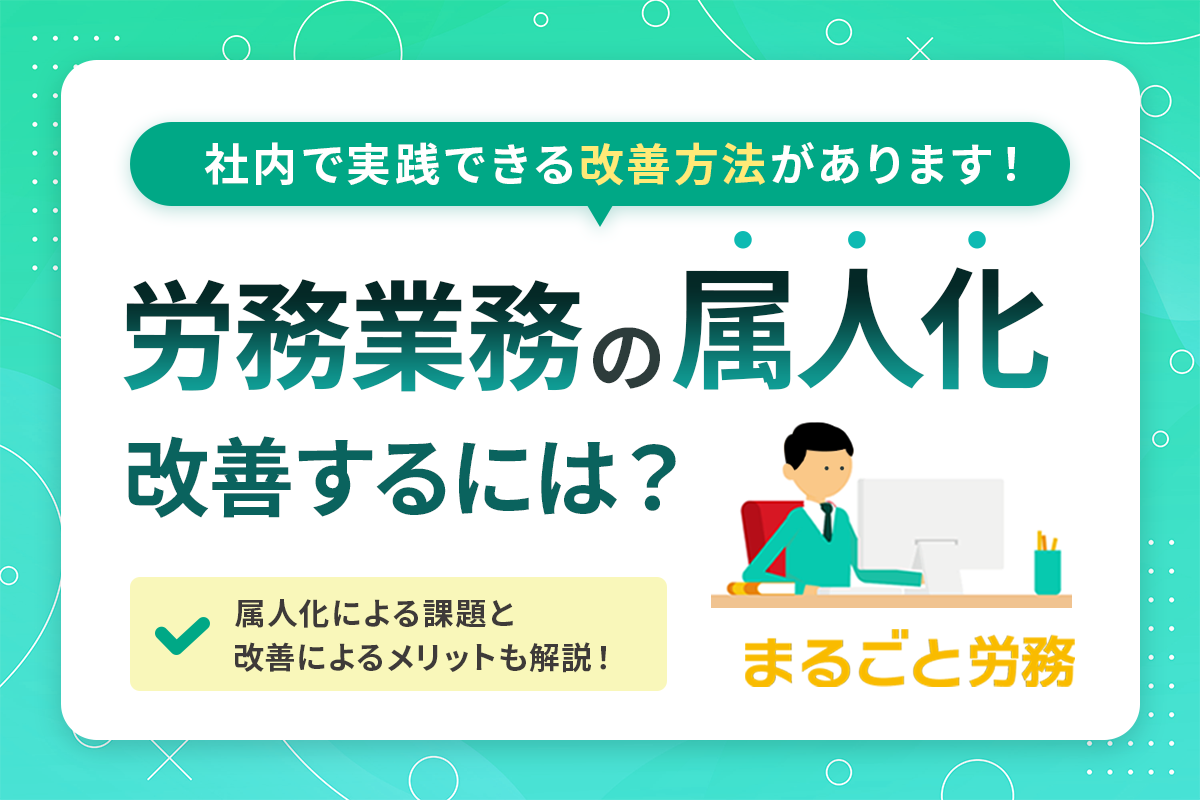
労務業務の『属人化』を改善する方法
労務業務の属人化を解消するための、具体的な方法を徹底解説します!
労務業務を引き継ぐ時に活用したい3つの方法

労務の引き継ぎは業務内容によって異なりますが、効率よく引き継ぐための方法は共通しています。
ここではどんな労務業務にも活用できる、効率的な引き継ぎ方法を3つ解説します。
以下の方法を事前にまとめておくと、引き継ぎだけでなく業務効率の改善にもつながるので、労務担当者は実践してみてはいかがでしょうか。
業務フローやチェックリストを作成する
業務ごとにフローやチェックリストを作成すると、作業の漏れがなく対応できるようになるため、引き継ぎ資料として活用してみると良いでしょう。
ただし、簡潔な文章や図を使うなど第三者視点の見やすさを意識しないと、引き継ぐ社員が活用できない場合があるので注意しましょう。
業務フローやチェックリストを作成するためには、業務を洗い出す必要があるため、業務のブラックボックス化を防げる、業務改善のヒントを見つけられるなど、引き継ぎ以外にもメリットが多くあります。
ミスした内容をまとめておく
自分がミスした内容は引き継いだ人もミスする可能性が高いため、ミスした内容をまとめておくことも、クオリティの高い引き継ぎ資料を作る際に必要です。
ミスした経緯や内容をまとめるだけでなく、解決策や改善内容を記載しておくと、引き継ぐ社員がトラブルに対応しやすくなるのでおすすめです。
年間/月間スケジュールを作成する
労務は毎年/毎月やるべき事項が決まっているため、各期間中に対応すべき業務を明確にしておき、年間/月間スケジュールを作成することをおすすめします。
スケジュールを作成する前に、社会保険や税金などの法定で決まっている業務の他、会社独自の福利厚生やイベントに関わる労務業務などを事前に洗い出しておくと、すべての内容を網羅しやすくなります。
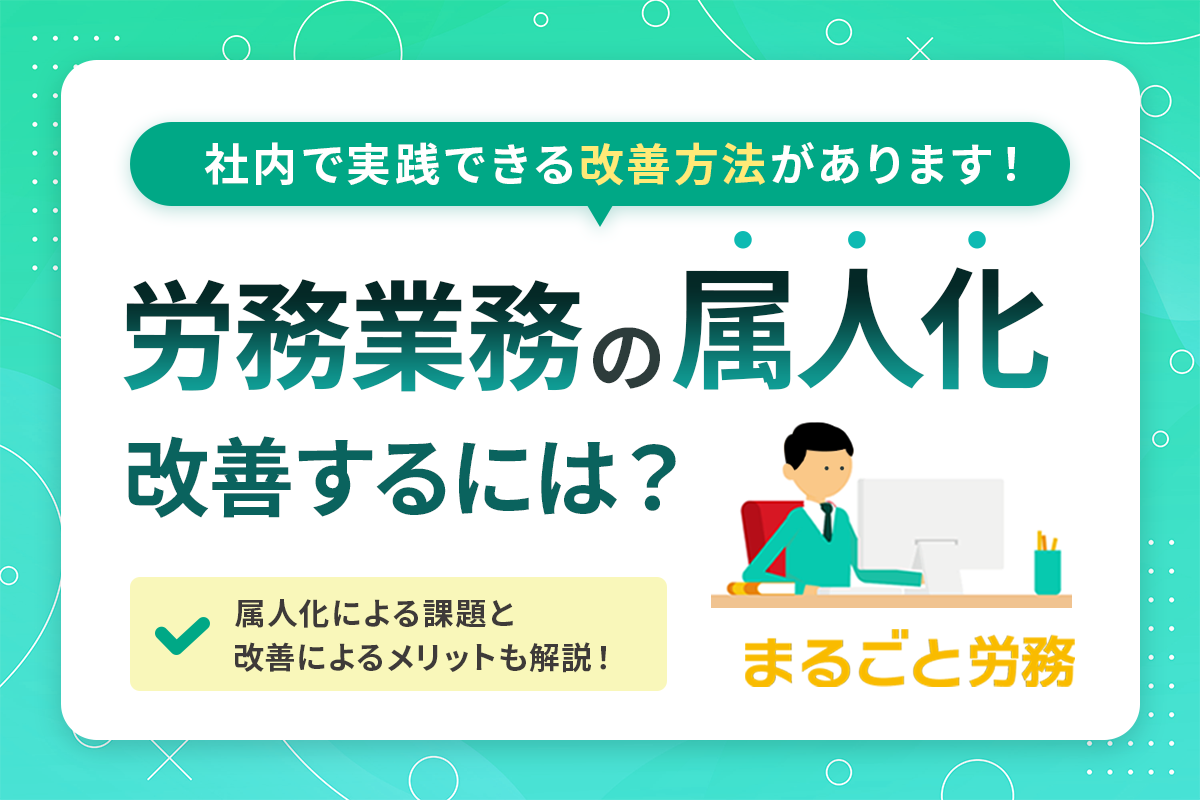
労務業務の『属人化』を改善する方法
労務業務の属人化を解消するための、具体的な方法を徹底解説します!
引き継ぎ期間が短い場合は上司と連携しよう

急な転職や部署配属で引継ぎの期間が短い際には、マニュアル作成を最優先に実施し、信頼できる上司に引き継ぎをサポートしてもらうよう、連携しておくと良いでしょう。
誰でも理解できるマニュアルを作成しておくと、たとえ自分でなくても引き継ぐ社員に業務を説明できます。
ただし、マニュアルを読ませるだけだと、引き継ぐ社員が誤った解釈をしてしまう可能性があるため、ある程度業務に精通している上司に引き継ぎ作業のサポートを依頼しておくことが大切です。
労務の引き継ぎを見直すと効率化のヒントを得られる

本記事では担当者が退職するリスクのために備えておきたい、労務の引継ぎに関する情報を解説しました。
引き継ぎの準備を事前にしておくことは、急な退職に対するリスクに備えられることはもちろん、業務の見直しによって効率化のヒントを得られることにもつながります。
労務の効率化は企業を成長させるうえで、必要不可欠な要素になるので、本記事の方法を参考に引き継ぎ資料を作成してみると良いでしょう。
もし引き継ぎが難しく、労務業務に不安を抱えている経営者がいましたら、多彩なバックオフィス代行サービスを提供している「まるごと管理部(労務プラン)」に相談してみてはいかがでしょうか。
関連記事
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
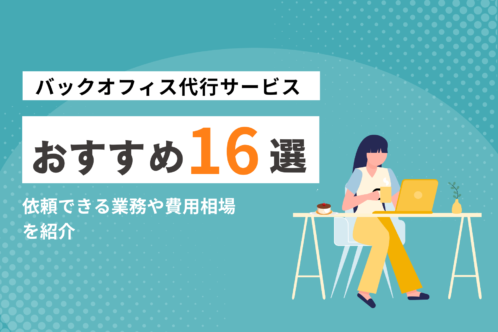
バックオフィス代行サービスのおすすめ16選!依頼できる業務や費用相場を紹介
- バックオフィス業務
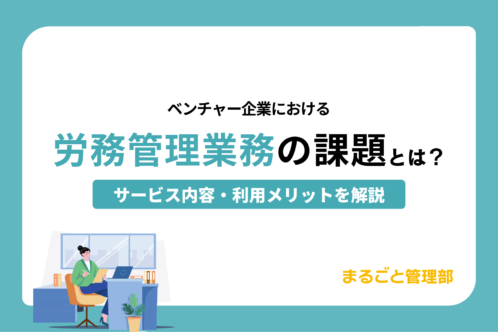
ベンチャー企業における労務管理業務の課題とは?改善ポイントを解説
- バックオフィス業務
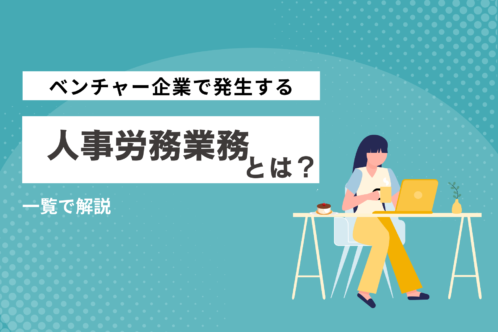
ベンチャー企業で発生する人事労務業務は?一覧で解説
- バックオフィス業務
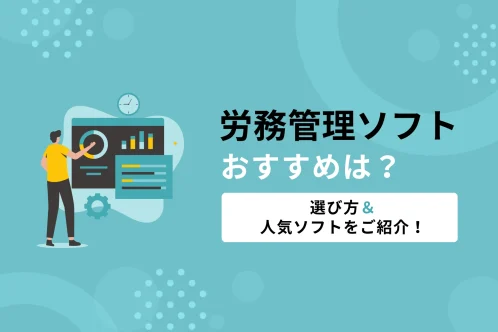
労務管理ソフトのおすすめは?選び方や人気のソフトを紹介
- バックオフィス業務

経理DXって何?注目すべき実現のステップとは
- バックオフィス業務

労務AIで業務効率UP!3つの活用メリットと導入リスク完全ガイド
- バックオフィス業務