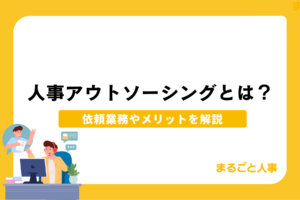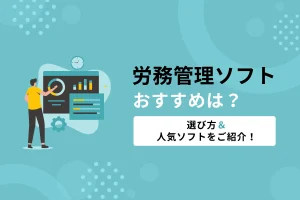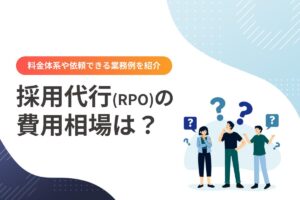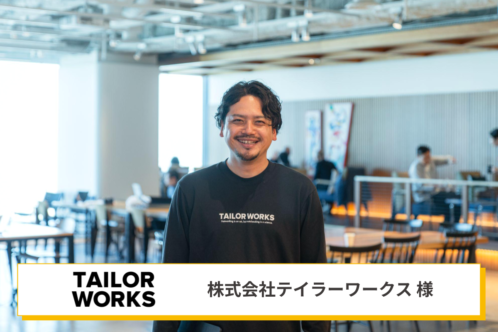採用・労務・経理に関するお役立ち情報
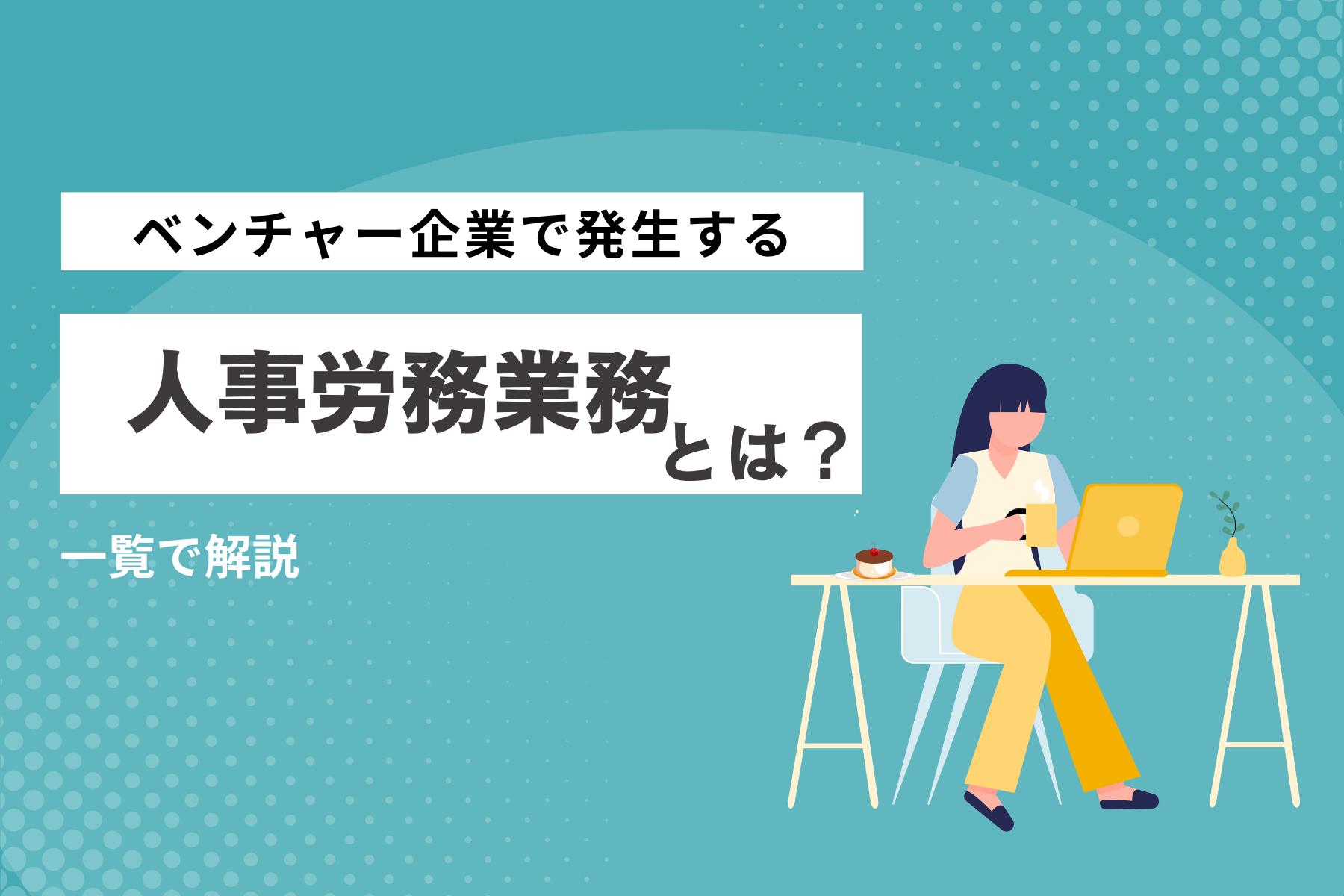
人事労務に関する業務は、企業規模に関わらず発生します。直接事業の収益に関係するものではありませんが、健全な組織運営を支え、優秀な人材の活躍を促すことで、成長をサポートすることが求められる分野です。
この記事では、人事労務とはどのような業務を指すのか、現場では年間を通してどのような業務が発生するのかについて、詳しく解説します。
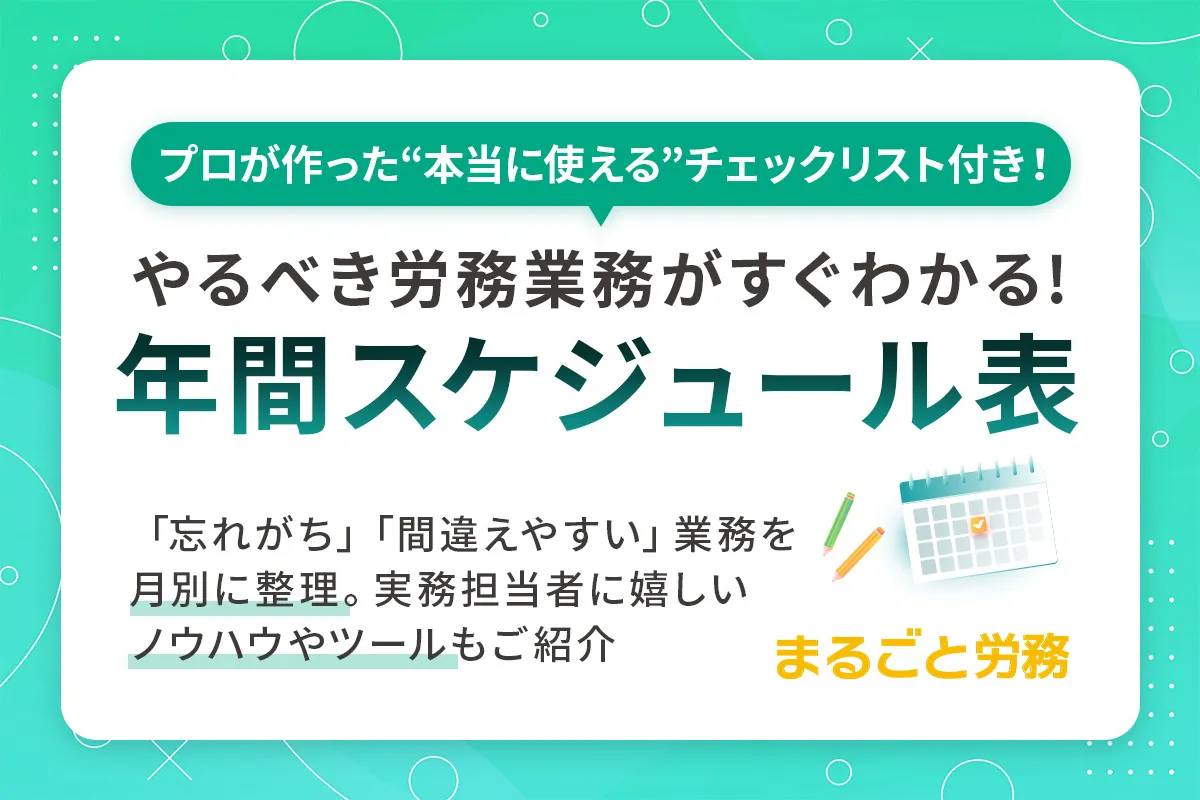
労務業務の年間スケジュール
「まるごと管理部(労務プラン)」が作った便利なスケジュール表を特別に無料公開!計画的に労務業務を進めるためのポイントをまとめています
目次
人事労務とは

人事労務は、人事業務と労務業務をひとまとめにして呼んでいるものです。いずれの業務も組織に所属している従業員のサポート、および彼らのマネジメントに関するものであり、円滑な業務の遂行を支える上で欠かせません。
人事労務が正しく行われることは、人材の育成や適材適所の配置において重要な意味を持ちます。
どれだけ優秀な人物を確保することができても、彼らの強みを伸ばすことができなかったり、強みが活きるポジションを与えられなかったりすると、期待しているようなパフォーマンスは得られません。正しく人事労務を実践できる環境は、従業員や組織のポテンシャルを引き出す上で、重要な意味を持ちます。
人事と労務の仕事の違いは?

人事労務は、人事と労務の仕事をまとめた表現です。ただ、両者の業務は微妙にその役割が異なるため、業務内容を丁寧に理解する上ではその違いを知っておかなければなりません。
まず人事の仕事は、組織の人材に関する業務全般を指します。どうすれば従業員が生き生きと働くことができるのか、どんな強みを持っているのか、そしてどのように評価すれば組織の成長に役立つのかといったことを考えるのが人事です。
一方の労務の仕事は、働く人の給料や休み・ルールの管理など、従業員が安心して働ける環境づくりを促すものです。どれだけ人材配置や育成に力を入れていても、従業員にとってストレスの大きい環境が現場であるようでは、肝心の強みを伸ばすことはできません。
それどころか、人材の価値を軽視していると従業員からみなされ、パフォーマンスの低下や離職率の増加につながることもあります。このような事態を回避する上で必要なのが労務です。
このように、組織を支える人に関与するということで人事の仕事と労務の仕事は密接に関与していることから、人事労務という形でひとまとめにされています。
人事労務担当者の主な役割

人事労務担当となった場合、どのような業務が発生するのでしょうか。ここでは人事労務のくくりから、労務の役割を確認しましょう。
人材確保
人事労務担当者の主な業務は、人材の確保です。近年はあらゆる業界で人手不足が懸念されており、その解消に向けた施策が求められます。優秀な人材を確保するためのリクルーティングはもちろん、少ない人手でも現場が回るような計画の検討が必要です。
人材確保に際しては多くの手続きが発生し、採用計画の策定から募集、そして選考活動を通じての内定、採用手続き、雇用契約の締結と、忙しなく動き続けることとなるでしょう。
評価
社内の従業員を評価することも、人事労務の仕事です。働きぶりや適性を踏まえた、正当評価基準を設定し、それに基づき評価することによって、従業員のモチベーション向上や生産性の改善に繋げることができます。
従業員一人一人の得意・不得意を客観的に評価し、成長や改善の指針を示すことが重要です。
人材育成
人材の育成を主に進めるのも、人事労務の仕事です。従業員に必要な研修機会の提供や、育成管理、そして教育担当者の配置や効果的なサポート体制の整備などを担います。
労働環境整備
安心・安全の労働環境の整備は、健やかな人材活用を支える重要な業務です。従業員の離職要因の特定と排除、労災の予防、その他法律違反につながる要因の特定や違反防止に務めます。
勤怠管理を正しく行い、勤務時間や有給消化の状況をリアルタイムで確認することも、人事労務部門には求められています。
労働者の手続き
雇用契約や社会保険の手続きといった、各種手続きを従業員に代わって行うのが人事労務部門の役目です。エンゲージメントの低下やコンプライアンス違反を防ぎ、組織力を高い水準で維持します。
労働者の継続就業を促す
従業員が少しでも長く働けるよう、各種サポートを提供します。健康管理の増進によって心身の不調による離職や休職を回避する取り組み、健康診断の実施、ハラスメント対策窓口の設置など、職場環境の悪化予防と従業員の健康管理が業務内容です。
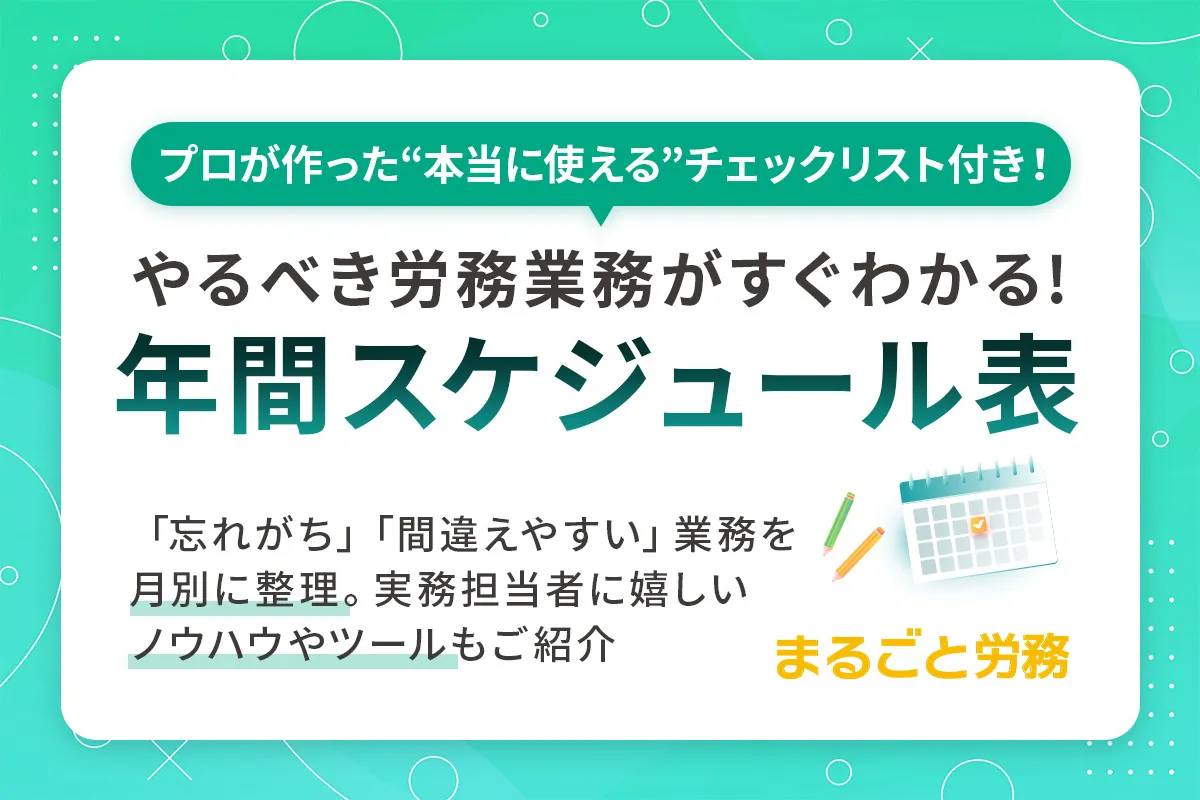
労務業務の年間スケジュール
「まるごと管理部(労務プラン)」が作った便利なスケジュール表を特別に無料公開!計画的に労務業務を進めるためのポイントをまとめています
主な人事労務の業務一覧

以下では、人事・労務それぞれの主な業務を紹介します。人事・労務の業務は明確に分かれているわけではありませんので、企業によっては双方を兼務していたり、異なる業務分担の場合もあります。
主な人事の業務一覧
人事の役割は単なる採用にとどまらず、戦略的な組織づくりの起点にもなります。ここでは、体制整備の基盤となる4つの主要業務について解説します。
人材採用
人材採用は、単に空いたポジションを埋める作業ではありません。中長期的な組織戦略に基づき、どの部署にどのような人材が必要かを見極め、将来の体制を見据えた採用計画を立てることが重要です。
新卒・中途いずれの採用でも、「即戦力か育成前提か」といった判断軸を明確にしておかなければ、入社後の定着や育成に悪影響を及ぼすおそれがあります。特に中小企業では、1人採用の成否が組織全体に影響を及ぼすため、経営陣との密な連携が欠かせません。
人材配置
せっかく採用した人材も、適切な配置がなければ能力を発揮しきれません。人材配置では個々のスキルや経験値だけでなく、本人の志向やキャリアビジョンを考慮することで、モチベーションを維持しやすい環境が整います。
特に小規模組織では、異動や昇進が部署の空気感や生産性に直結するため、配置判断の精度が問われます。加えて、既存メンバーとの相性や、将来的な組織構造の見直しを視野に入れておくことも欠かせません。
属人的な判断ではなく、明確な評価基準や人事データに基づく配置が、持続的な組織運営につながります。
研修・教育
人材育成は単発的な研修にとどまらず、成長の機会を段階的に設けることがポイントです。新人研修に始まり、キャリアの節目で必要なスキルを補う教育制度を整えることで、将来的な管理職候補や専門人材の土台を育むことが可能です。
加えて「誰に・どのタイミングで・何を学ばせるか」を仕組み化することで、教育が属人化せず、業務の引き継ぎや体制変更にも柔軟に対応できます。
評価制度の作成
組織としての一体感や公正性を保つうえで、評価制度の整備も避けて通れません。給与査定のためだけではなく、従業員の納得感やキャリア意識を高める手段としても機能させる必要があります。
評価項目や尺度が曖昧なままでは評価者の主観が入りやすく、不公平感を生む原因となります。そのため、役割や期待水準に応じた明確な基準を設け、面談やフィードバックを通じて本人とすり合わせる仕組みが求められるでしょう。
さらに、評価結果を人事異動や育成方針にどう反映させるかを設計しておくことで、人材戦略との一貫性も担保できます。制度としての完成度を高めるには、人事だけでなく現場の意見も反映させた設計と定期的な見直しが欠かせません。
労務が行う主な業務
労務管理は、従業員が安心して働ける環境づくりの要となる領域です。ここでは、体制整備や業務見直しの参考になる主要業務について解説します。
勤怠管理
勤務実態の正確な把握は、労務管理の出発点ともいえる重要な業務です。出退勤や休憩、残業、有給休暇の取得状況を適切に記録することで、法令順守と給与計算の正確性を確保できます。
特に、勤怠データにミスがあると未払い残業や過剰支払いのリスクが発生し、労使トラブルにつながるでしょう。近年はシステムを活用した打刻やデータ連携によって、業務の属人化を防ぎつつ集計の負荷を軽減する企業が増えています。
給与計算
給与計算は、労働時間・各種手当・控除のすべてが反映される繊細な業務です。
基本給に加え、残業代や通勤手当、住民税や社会保険料などの控除項目を正確に処理する必要があります。誤りがあれば従業員の信頼を損ねるだけでなく、行政への対応や再発行など余計な対応工数が発生します。
また、支給日までに計算を完了させるための締切管理も重要です。ミスを減らし、継続的に正確な処理を行うには、業務手順の標準化と定期的なチェック体制の構築が効果的です。
社内規定の整備
社内規定の整備は、ルールの明文化によってトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。就業規則や賃金規程、休暇制度のルールなどを整えておくことで、従業員との間に共通認識を生み出させることが可能です。
常時10人以上の従業員がいる事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務づけられており、未整備のままでは法的リスクが生じる可能性もあります。実際の運用に即した形で制度設計を行い、変更があれば速やかに更新・共有できる体制を用意しておくことが大切です。
社会保険の手続き
社会保険の手続きは、従業員の入退社やライフイベントに応じて発生する定型業務のひとつです。健康保険や厚生年金、雇用保険や労災保険に関する各種申請は、内容ごとに提出先や期限が異なるため、正確な理解と対応が求められます。
近年では電子申請の活用が推奨されており、手続きのミスや漏れを防ぐ意味でもデジタルツールの導入が有効です。社内での対応か外注を検討するか判断する際は、業務量の見通しや専門知識の有無を基準に考えるとよいでしょう。
健康・安全衛生の管理
従業員が安心して働くための環境づくりには、健康と安全の管理体制が欠かせません。労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場では安全委員会や衛生委員会の設置が義務化されており、健康診断やストレスチェックの実施も求められます。
これらの取り組みは義務であると同時に、従業員の定着率向上や離職防止にも寄与する側面があります。ハラスメント防止の窓口設置や長時間労働の是正など、実務対応を継続的に見直すことで、持続可能な職場環境の維持が可能になるでしょう。
人事労務担当者の年間スケジュールを確認
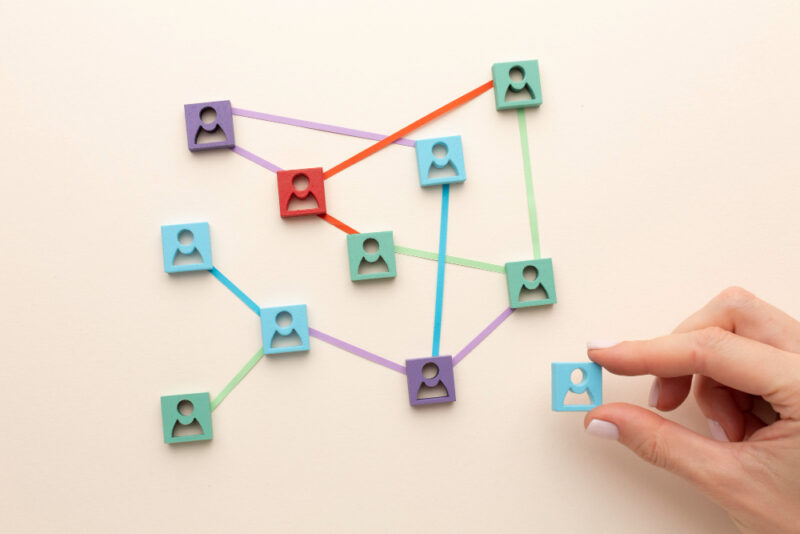
人事労務担当者は、シーズンによって主な業務が変わってきます。年間のスケジュールを確認の上、繁忙期と閑散期のタイミングを知っておくと、効果的な業務改善に役立ちます。
4~6月
4月から6月にかけては、多くの場合新入社員を迎え入れる手続きに追われることが一般的です。会社での働き方に慣れてもらうための就業サポートなどが主になります。
また、6月には賞与の支給を控えている企業も多く、給与計算や人事評価に関する業務がこの時期は増えるでしょう。
7~9月
7月から9月にかけては比較的季節業務の少ないタイミングとなります。社会保険の見直しに向けた算定基礎届の提出や、労働者死傷病の報告などが発生しますが、繁忙期ほどの忙しさはありません。
10~12月
10月から12月にかけては、社会保険料の改定に伴う給与システムの改訂対応などが発生します。
12月は年末調整が発生するため、最も忙しいタイミングの一つとなります。保険の控除などが発生する場合には対象の従業員に書類を提出してもらう必要も出てくるので、早めの確認が求められます。
1~3月
1月は、法定調書の提出や、給与支払報告書の提出が必要です。従業員との直接のやり取りは少なくなるものの、通常業務と合わせて遂行しなければならず、年度明けの準備もあるため、忙しくなるケースが多いです。
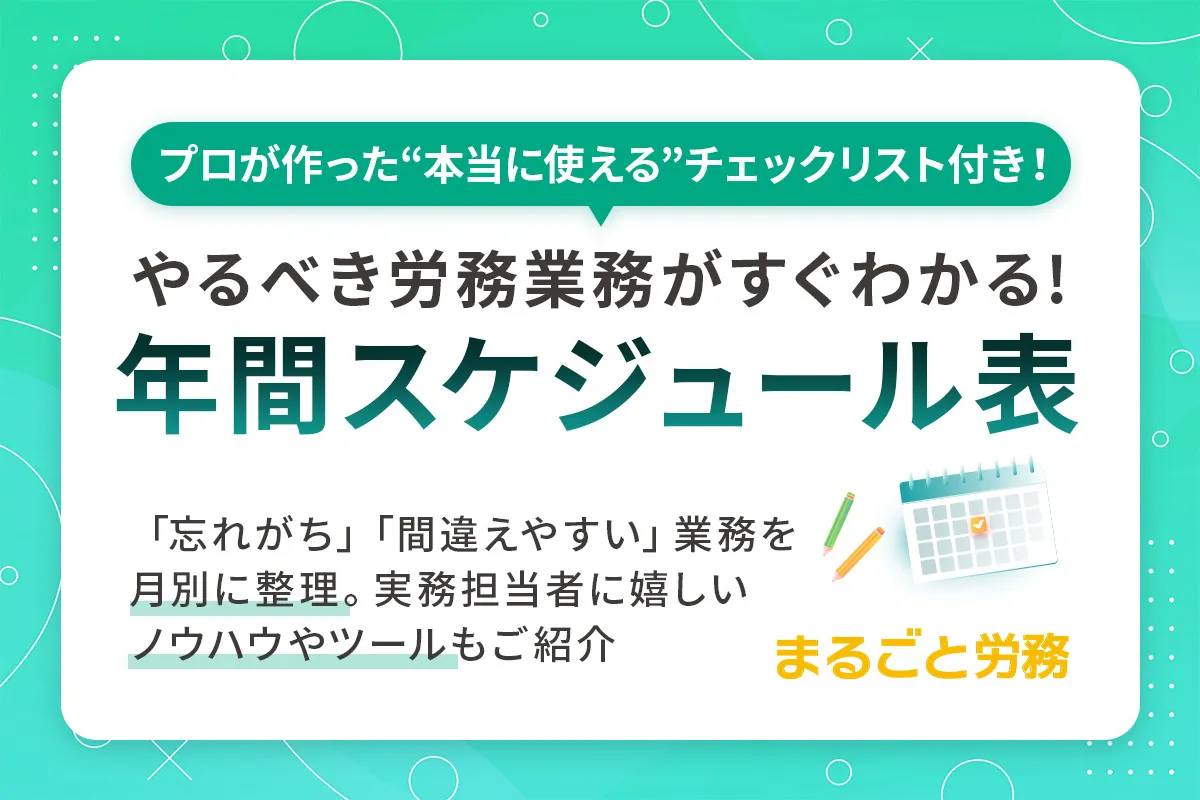
労務業務の年間スケジュール
「まるごと管理部(労務プラン)」が作った便利なスケジュール表を特別に無料公開!計画的に労務業務を進めるためのポイントをまとめています
人事労務の業務における課題

人事労務の業務においては、以下のような課題が存在します。
- 担当者の業務負荷が過多になりやすい
- 人事と労務の兼任により属人化する
- 情報共有の仕組みが不足しやすい
- 入退社や社会保険手続きでミスが発生しやすい
- 業務量の波により対応が不安定になりがち
人事労務の業務は多岐にわたり、法令対応や制度変更への対応も必要とされるため、担当者への負荷が集中しやすい領域です。特に中小企業では、限られた人員の中で人事と労務を兼務しているケースが多く、以下のような構造的な課題が生じやすくなります。
- 業務の属人化:特定の担当者にしか分からない業務が増えやすい
- 情報共有不足:マニュアルや引き継ぎ体制が整っていない
- オペレーションの不安定化:業務量の増減によって対応に差が出る
特に入退社時の各種手続きや社会保険の対応は、法的なミスが許されないため、正確性とタイミングが非常に重要です。また、月末や年度末など繁忙期には業務が一気に増加し、人的リソースの不足が表面化しやすくなります。
このような課題に対応するには、業務の可視化と適切な分担体制の整備が不可欠です。課題を定期的に棚卸しし、仕組みとして改善していくことで、業務効率化とリスク低減の両立が実現できます。
人事労務管理を効率化するには?

人事労務管理の業務は多岐にわたり、煩雑化しやすい領域です。効率化を図るには、業務全体を俯瞰して「どこにムダや属人性があるか」を洗い出し、ITツールや外部リソースを活用して標準化・自動化することが重要です。以下のステップで進めると効果的です。
① 業務フローの可視化と課題の洗い出し
- 現状の業務プロセスを図やリストで整理
- 紙・手書き・二重入力などのアナログ作業を特定
- 担当者による手順のばらつきや属人化の有無を確認
② クラウド型労務ソフトへの移行
- 勤怠管理、給与計算、社会保険手続きを一元管理
- 打刻データや申請情報をリアルタイムで自動反映
- 労務ミス・計算ミスを削減し、管理コストを圧縮
③ 他システムとの連携でデータ入力を最小化
- RPA(業務自動化ツール)を使ってルーティン作業を自動化
- API連携により、会計・勤怠・給与などのデータを統合
- 各システム間のデータ転記を不要にし、精度向上
④ ガイドライン整備と定期的な担当者教育
- 業務マニュアルやフロー図を作成し、誰でも対応可能な状態に
- 法改正や制度変更のたびに内容を更新
- 新任担当者向けの定期研修で知識差を解消
⑤ BPO(業務アウトソーシング)の活用
- 繁忙期や専門知識が必要な業務(社会保険手続き等)を外部委託
- 社内リソースを戦略業務へシフト可能に
- プロによる対応で法令遵守リスクも軽減
⑥ セルフサービス機能の導入
- 従業員自身が住所変更・扶養申請・休暇申請をオンラインで実施
- 人事への問い合わせ件数を削減
- 申請内容が即時反映されるため、事務処理の迅速化にも貢献
まとめ

この記事では、人事労務にはどのような業務が発生するのか、それぞれの仕事の内容を一覧形式で紹介しました。
人事労務はどの業務も社内の従業員を守り、育てる上で重要な意味を持っています。組織の規模に関わらず、どんな会社でも必要になることから、将来性を踏まえ効率化に向けて動いていくことが大切です。
月額制のオンライン代行サービス「まるごと管理部(労務プラン)」は、そのような人事労務に関する業務を外部に委託できるものです。月額制でサービスを利用できるため、コストパフォーマンスを最大限考慮した業務効率化を進めたい場合に活躍します。
人事労務業務について改善の必要性を感じている場合、お気軽にご相談ください。

「まるごと管理部」の
資料を無料でダウンロード
人事労務・経理を仕組みづくりから実務まで代行!
急な担当者の退職など社内のバックオフィス担当の代わりとして伴走支援します
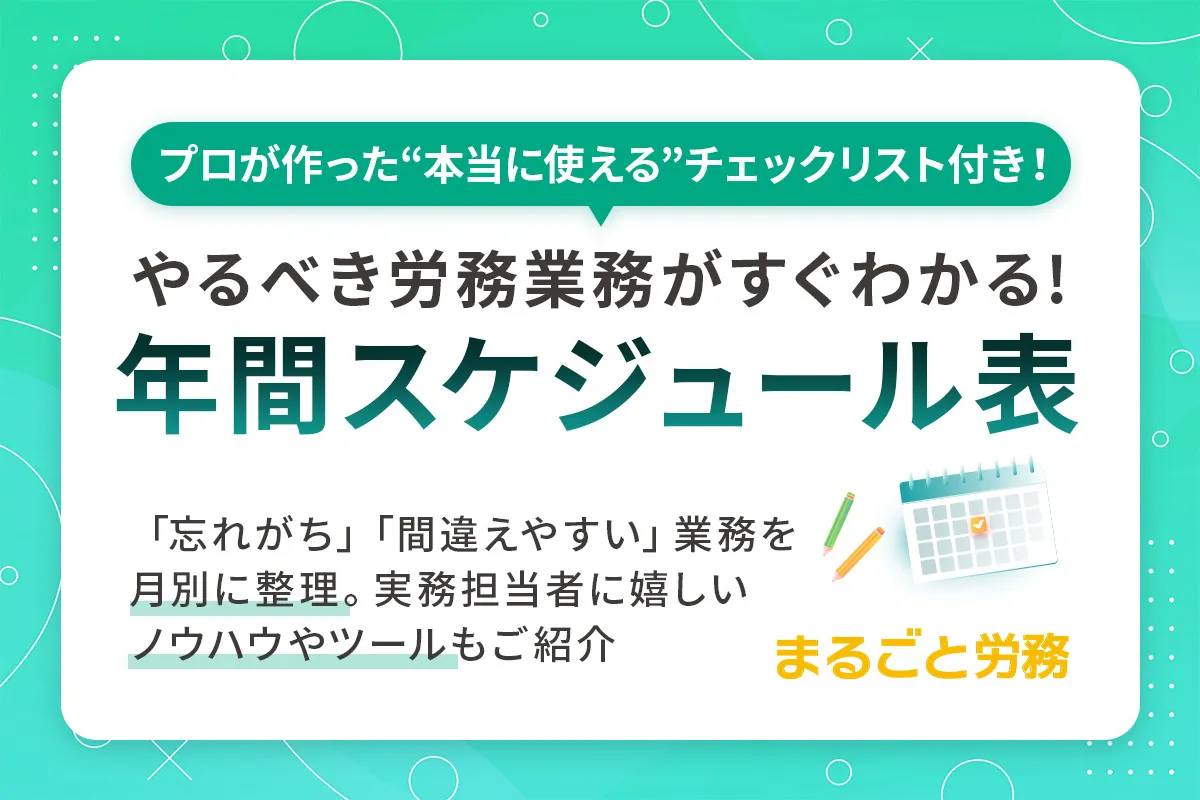
労務業務の年間スケジュール
「まるごと管理部(労務プラン)」が作った便利なスケジュール表を特別に無料公開!計画的に労務業務を進めるためのポイントをまとめています
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
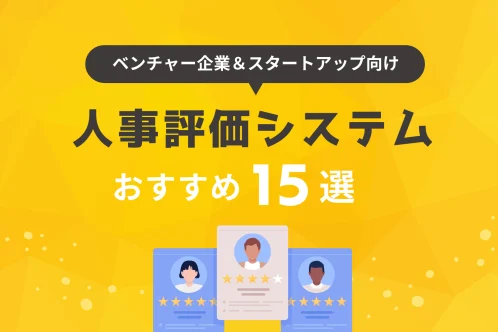
人事評価システムおすすめ15選!ベンチャー・スタートアップ向け
- バックオフィス業務

勤怠管理システムの導入を成功させるには?基礎からポイントまで解説
- バックオフィス業務
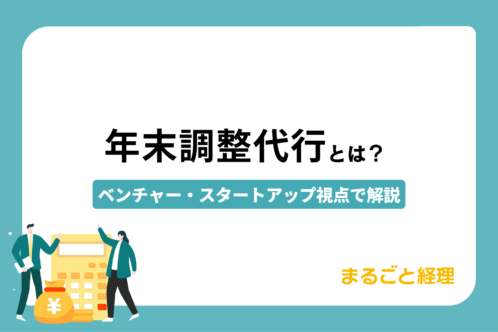
年末調整代行とは?中小企業・ベンチャーの活用ポイントを解説
- バックオフィス業務
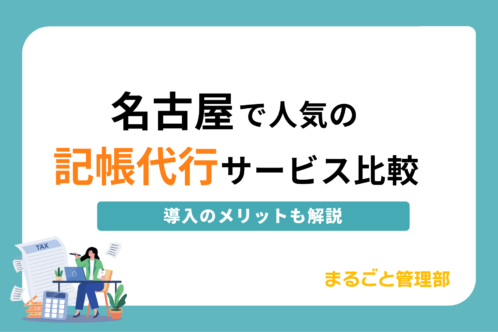
導入のメリットは?名古屋で人気の記帳代行サービス4選
- バックオフィス業務
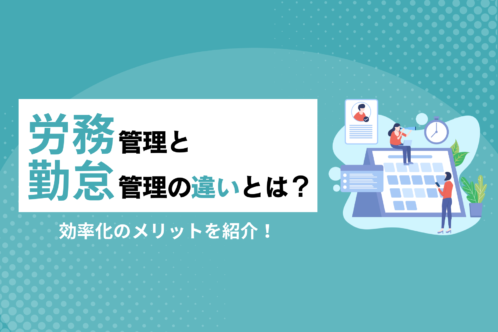
労務管理と勤怠管理の違いとは?効率化のメリットを紹介
- バックオフィス業務

【200ツールのカオスマップ付き】HRテックとは?導入メリット・事例・選び方を完全解説
- バックオフィス業務