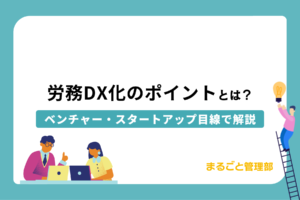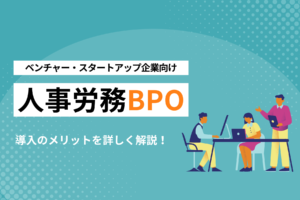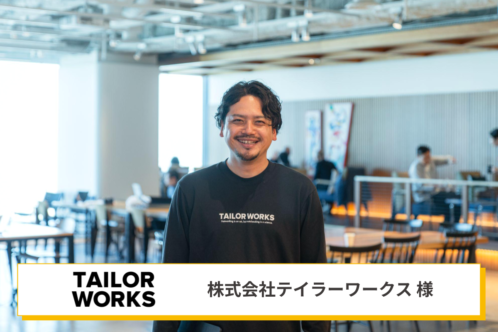採用・労務・経理に関するお役立ち情報
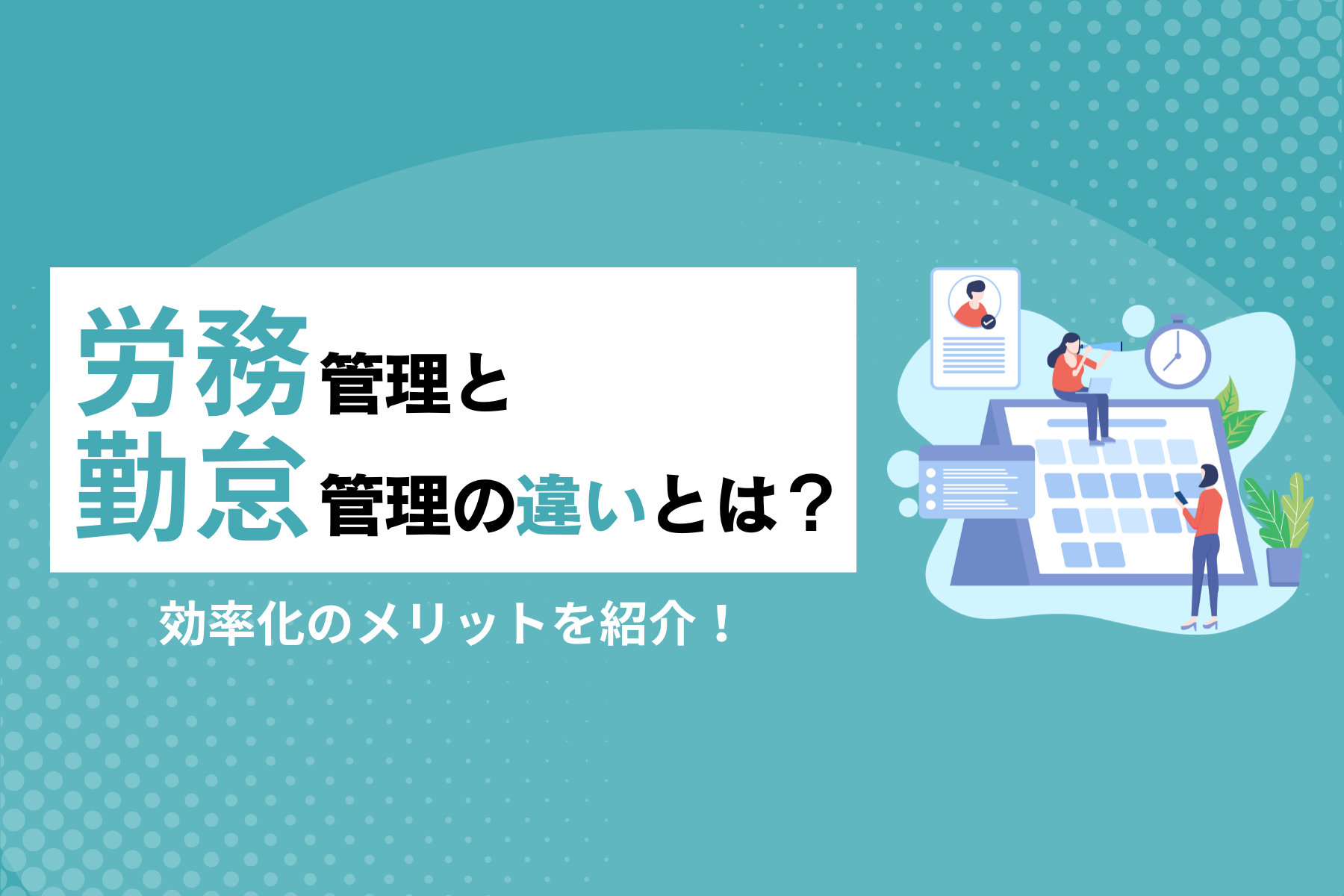
企業の成長を支える労務管理と勤怠管理。どちらも従業員の働き方を適切に管理するために不可欠な業務ですが、具体的な役割の違いを正しく理解できているでしょうか?
労務管理は、雇用契約や福利厚生、法令遵守など幅広い領域をカバーし、企業経営の基盤を支えるもの。一方、勤怠管理は、出退勤や残業、有給休暇の記録・管理を行い、給与計算の精度向上や労働時間の適正化を図ります。本記事では、それぞれの違いと、効率化のメリットを詳しく解説します。
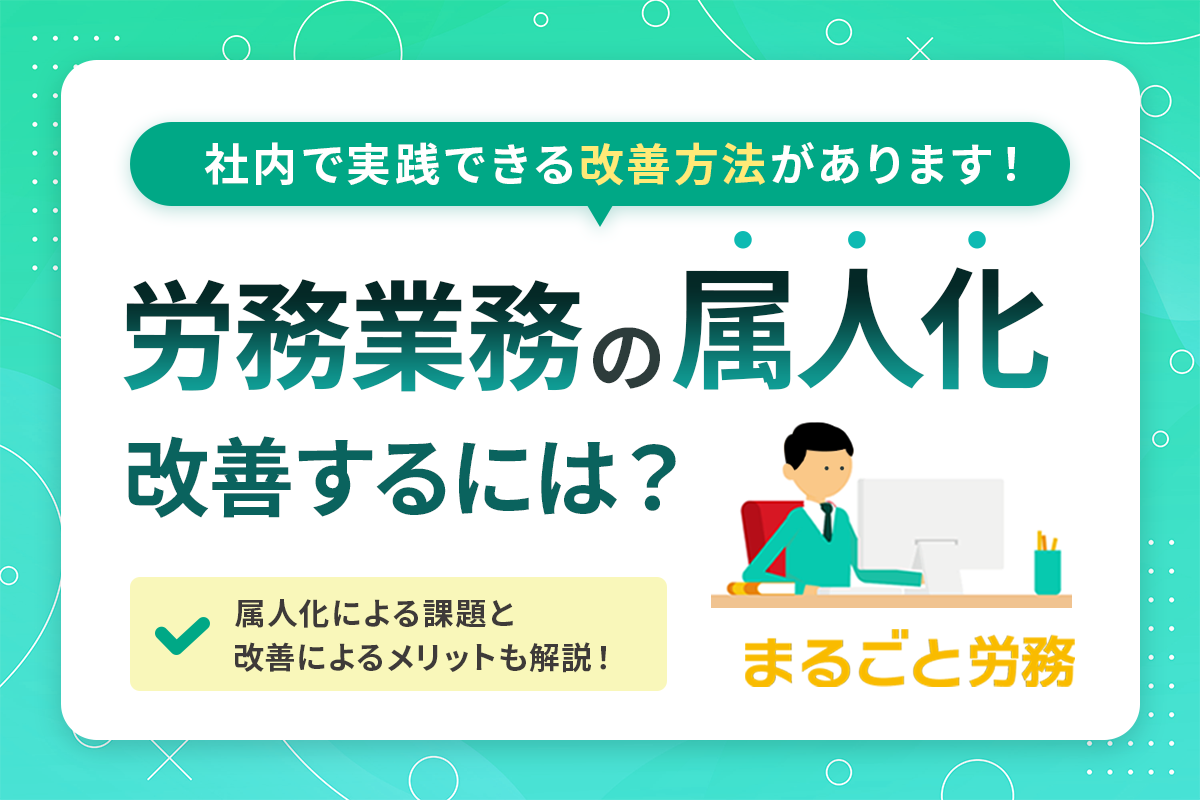
労務業務の『属人化』を改善する方法
労務業務の属人化を解消するための、具体的な方法を徹底解説します!
目次
労務管理とは

労務管理とは、従業員の雇用・給与・福利厚生・法令遵守を適切に管理し、企業の経営基盤を支える重要な業務です。
従業員が安心して働ける環境を整えることで、企業の生産性向上やコンプライアンス強化に貢献します。適正な労務管理を行うことは、組織の安定運営だけでなく、従業員満足度の向上にもつながり、長期的な企業の成長を支える要素となります。
労務管理の目的
労務管理の目的は、健全な労働環境の整備、従業員の権利保護、企業の法令遵守の徹底など多岐にわたります。
従業員が安心して働ける環境を提供することで、企業の生産性や組織の安定性を向上させることが可能です。
また、適切な労務管理を実施することで、労働トラブルの予防や企業のブランド価値向上にも寄与します。さらに、従業員の定着率を高め、優秀な人材の確保にもつながるため、企業の競争力を強化する重要な要素となります。
労務管理業務の具体的な内容
労務管理には、就業規則の整備、入退社手続き、安全衛生管理、労災対応、社会保険の管理など幅広い業務が含まれます。
これらは、企業の持続的な成長と従業員の安心・安全な労働環境を維持するために不可欠な業務です。
適切な労務管理を行わない場合、労働環境の悪化やコンプライアンス違反につながり、企業の評判や経営リスクに影響を及ぼす可能性があります。そのため、定期的な見直しと改善を行い、企業の状況や法改正に応じた柔軟な対応が求められます。
勤怠管理とは

勤怠管理とは、従業員の出勤・退勤時間、休暇、残業の管理を適正に行う業務です。労働時間の記録は、給与計算や法令遵守に直結するため、企業にとって不可欠な業務となるでしょう。
特に、長時間労働の抑制や未払い残業の防止、働き方改革への対応が求められる現代において、正確な勤怠管理の重要性が高まっています。適切な勤怠管理が行われることで、従業員の労働環境が整備され、企業のコンプライアンス強化にもつながります。
勤怠管理の目的
勤怠管理の目的は、適正な労働時間の記録、給与計算の正確化、法定労働時間の遵守です。労働時間を正確に管理することで、従業員の過重労働を防ぎ、適切な労働環境を維持できます。
また、正確な勤怠データが確保されることで、給与計算の誤差を最小限に抑えることができ、従業員とのトラブルを防ぐことにもつながります。
さらに、労働基準法の規定を遵守するためにも、正確な勤怠管理は企業のリスク管理において極めて重要な役割を果たします。
勤怠管理業務の具体的な内容
勤怠管理には、出退勤管理、残業時間管理、有給休暇の管理、シフト調整、深夜・休日勤務の管理など、多岐にわたる業務が含まれます。
従業員が適正な時間で働けるようにするだけでなく、企業側が労働時間の記録を正確に把握し、適切に対応することも重要です。
フレックスタイム制やリモートワークなど、従業員の働き方が多様化する中で、従来の固定的な勤怠管理では対応が難しくなっており、より柔軟な管理手法が求められています。そのため、企業の就業形態に合った勤怠管理体制の構築が不可欠となります。
就業管理とは

就業管理とは、従業員の勤務スケジュールやシフト管理を適正に行い、勤怠管理と連携しながら労働環境を最適化する業務です。
企業の業務形態や従業員の働き方に応じた柔軟な就業ルールの設計が求められます。特に、多様な働き方が推進される現代では、フレックスタイム制やシフト制、リモートワークなど、個々の労働条件に適した管理が企業の成長に直結します。
適切な就業管理を行うことで、従業員の負担軽減と企業の生産性向上が実現できます。
就業管理の目的
就業管理の目的は、企業の業務運営と従業員の勤務形態を適正に調整し、労働生産性を向上させることです。
従業員が安心して働ける環境を整えながら、企業の業務遂行に支障が出ないようにすることが求められます。例えば、シフト勤務が必要な業界では、適切な人員配置ができなければ、業務が回らず、生産性や顧客満足度の低下を招く可能性があります。
また、働き方改革に対応するためには、労働時間の柔軟な運用や、業務と生活のバランスを考慮したスケジュール設計が重要となります。
就業管理業務の具体的な内容
就業管理には、シフト管理、勤務体系の整備、休憩・休日の調整、変形労働時間制の運用など、業務を円滑に進めるための様々な業務が含まれます。
特に、小売業・医療機関・製造業などでは、適正な就業管理が業務の安定性や従業員の働きやすさに大きく影響します。繁忙期と閑散期で勤務時間を柔軟に調整する変形労働時間制の活用は、企業の労働コストを抑えながら従業員の負担を軽減する手法の一つです。
また、休憩や休日の適正な管理を行うことで、過労防止やワークライフバランスの向上にも寄与します。こうした就業管理の最適化が、企業の持続的な成長と従業員満足度の向上につながります。
労務管理と勤怠管理の違い

労務管理と勤怠管理は、どちらも企業の運営に不可欠な業務ですが、その役割には明確な違いがあります。労務管理は、従業員の雇用契約や人事、給与、福利厚生、労働環境の整備など、従業員の働き方全体を管理する業務です。
一方、勤怠管理は、出退勤や残業、有給休暇の取得状況を記録・運用する業務であり、労務管理の一部を担っています。適切な勤怠管理は、正確な給与計算や労働時間の適正化につながり、労務管理全体の質を向上させる重要な要素となります。
労務管理をするうえで勤怠管理が必要な理由
適正な労務管理を実現するためには、正確な労働時間の記録が不可欠です。勤怠管理が適切に行われていないと、労働時間の把握が不十分となり、未払い残業や長時間労働の見逃しにつながる可能性があります。
また、給与計算のミスや労働基準法違反のリスクが高まり、従業員との信頼関係や企業の信用にも影響を及ぼしかねません。さらに、法令遵守を徹底しなければ、行政からの指導や是正勧告を受けるリスクも高まります。
適切な勤怠管理を行うことは、労務管理の精度を高め、企業の持続的な成長を支える重要な要素となるのです。
労務管理・勤怠管理をシステム化するメリット

労務管理・勤怠管理のシステム化により、業務の効率化や人的ミスの削減が可能となり、企業全体の生産性が向上します。また、法令遵守の強化やデータの一元管理が容易になり、特に多拠点展開している企業やテレワークを導入している企業にとって、大きなメリットとなります。
クラウドを活用すれば、どこからでも勤怠データの管理・分析が可能となり、柔軟な働き方にも対応できるようになります。
労務管理業務の効率化
システム化により、従来の紙ベースやエクセル管理による手作業を大幅に削減でき、業務負担が軽減されます。
例えば、勤怠データの集計や給与計算の自動化により、確認作業や入力ミスを防ぐことが可能です。また、法改正への対応もシステムのアップデートによって即座に反映されるため、企業は最新の労働基準法を遵守した運用ができるようになります。
労務管理を効率化することで、担当者はより戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう。
勤務時間の正確な把握が可能
リアルタイムのデータ管理により、従業員の出退勤時間や労働時間を即座に把握できるようになります。これにより、未払い残業や過重労働の発生を防ぎ、法令遵守の強化につながります。
また、従業員自身が自身の労働時間を確認できるため、働き方の見直しやワークライフバランスの向上にも貢献します。さらに、アラート機能を活用することで、時間外労働の超過を未然に防ぐことができ、企業のリスク管理の強化にもつながるのが強みです。
遠隔地や複数拠点の管理が容易
クラウド型のシステムを活用することで、本社と支店、あるいは異なる拠点間の勤怠データをリアルタイムで一元管理できるようになります。これにより、離れた拠点の勤務状況や労働時間を一目で把握でき、管理者の負担が軽減可能です。
また、テレワークやフレックスタイム制を導入している企業にとっても、柔軟な労働時間の管理が可能となり、従業員の働き方の多様化にも対応しやすくなります。システム化により、組織全体の生産性向上と働きやすい環境づくりが同時に実現できるのです。
労務管理システムの必要性

企業の労務管理業務は、給与計算、社会保険手続き、勤怠管理、法令対応など、多岐にわたります。従来の手作業では対応しきれないほど業務が煩雑化しており、効率的な管理が求められています。
特に、労働基準法の改正やテレワークの普及など、働き方の変化に適応するためには、労務管理システムの導入が不可欠です。
勤怠管理システムと連携することで、データの一元管理が可能となり、よりスムーズな業務フローの構築が実現できます。
労務管理システムの活用ポイント

労務管理システムを導入すれば、業務の効率化が期待できますが、それだけでは十分ではありません。
効果的に活用するためには、自社の業務フローに適した機能の選定や、運用ルールの整備が不可欠です。
必要な機能を明確にする
システムを選定する前に、現在の労務管理業務の課題を整理し、必要な機能を明確化することが重要です。
例えば、紙ベースの申請業務が多く、承認フローが煩雑な場合は、電子申請機能を重視すべきです。一方、テレワーク社員が多い場合は、クラウド対応が必要不可欠となります。「自社の課題を解決するシステムとは何か」を基準に選ぶことで、業務効率を最大化し、無駄な機能を省いた最適な導入が可能になります。
自社に合った勤怠管理ができるシステムを基準に設計する
労務管理システムを導入する際は、勤怠管理システムとの連携を考慮することが不可欠です。出退勤記録や休暇管理が一元化されていなければ、データの整合性が取れず、業務の手間が増えてしまいます。
シフト制を採用している企業なら、柔軟なスケジュール管理機能が必要ですし、フレックスタイム制を導入している場合は、労働時間の計算が自動化されるシステムが適しています。
自社の勤務体系に合ったシステムを選定し、スムーズな運用につなげましょう。
セキュリティ対策を確認する
労務管理システムでは、従業員の個人情報や給与データなど、機密性の高い情報を扱うため、セキュリティ対策のチェックが不可欠です。
データの暗号化やアクセス権限の適切な設定はもちろん、多要素認証やIPアドレス制限といった高度なセキュリティ機能が備わっているか確認しましょう。また、クラウド型システムの場合は、サーバーの管理体制や災害時のデータバックアップ機能も重要です。
情報漏えいやデータ消失のリスクを最小限に抑え、安心して運用できる環境を整えましょう。
システムや操作画面がわかりやすいか確認する
労務管理システムは、労務担当者だけでなく、従業員が申請・確認するケースも多いため、直感的に操作できるUI/UXが設計されているかが重要です。
システムが複雑で使いにくいと、運用が定着せず、従業員の負担が増える可能性があります。また、スマートフォンやタブレットから利用できるか、マルチデバイス対応が整っているかもチェックポイントです。
誰でも簡単に使えるシステムを選定し、スムーズな運用と高い業務効率化を実現しましょう。
まとめ:労務管理と勤怠管理の違いを理解して業務を効率的に行おう

労務管理と勤怠管理は、それぞれ異なる役割を持ちながらも、企業の健全な運営において不可欠な要素です。
労務管理は、従業員の雇用契約や給与、福利厚生、法令遵守といった広範な業務を扱い、企業の持続的な成長を支える役割を担います。一方、勤怠管理は、労働時間や休暇の記録・運用を中心に、正確な給与計算や適正な労働環境の維持に直結する業務です。
これらの業務を効率化する方法には多様なアプローチがありますが、その一つとして活用したいのが「まるごと管理部(労務プラン)」です。
月額制で利用できるこの労務管理代行サービスは、1ヶ月単位で利用ができる、業務の効率化や人材不足の解消に貢献しています。フレキシブルに契約期間を変更できるので、システム改修の際の移行期間にも使用できるのが強みです。労務管理や勤怠管理の効率化を検討している場合は、ぜひご相談ください。

「まるごと管理部」の
資料を無料でダウンロード
人事労務・経理を仕組みづくりから実務まで代行!
急な担当者の退職など社内のバックオフィス担当の代わりとして伴走支援します
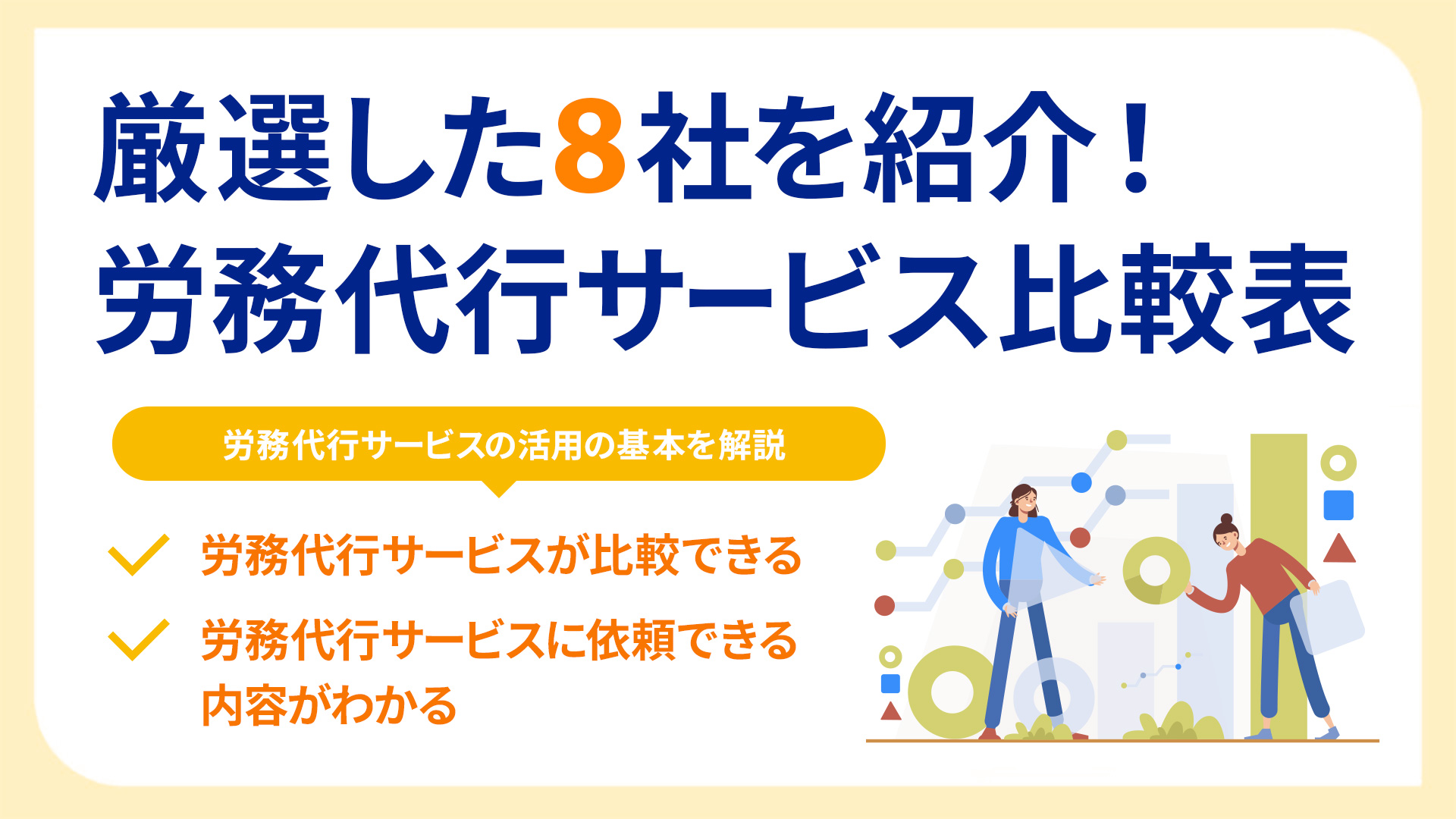
厳選した8社を紹介!
労務代行サービス比較表
労務代行サービスの活用の基本を解説。8社のサービスが一気に比較できます!
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事

【就業規則の作成・運用】でベンチャー・スタートアップが押さえるべきポイント
- バックオフィス業務
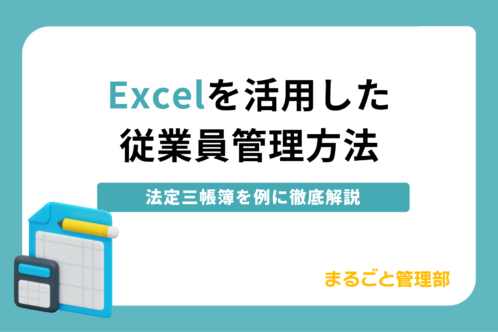
【エクセルで実施する従業員管理方法】法定三帳簿を例に徹底解説
- バックオフィス業務
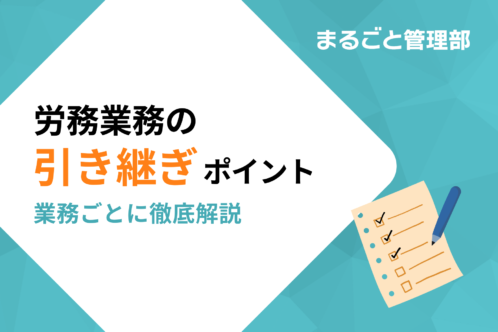
労務の引き継ぎポイントを業務ごとに徹底解説!
- バックオフィス業務
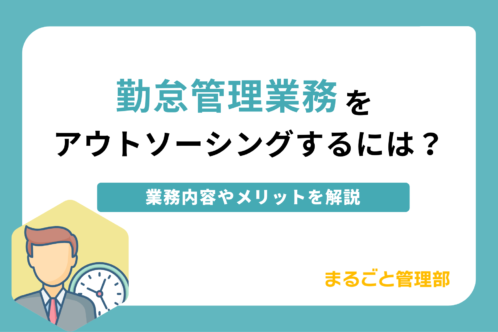
勤怠管理のアウトソーシング(代行)サービス10選!業務内容やメリットを徹底解説
- バックオフィス業務

経理DXって何?注目すべき実現のステップとは
- バックオフィス業務
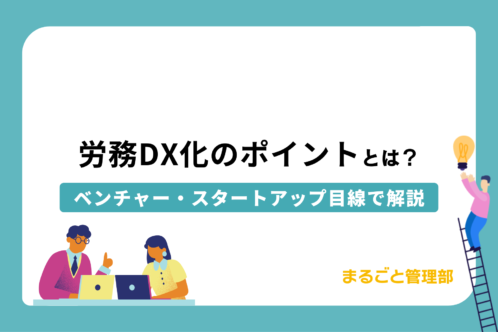
労務DX化のポイントをベンチャー・スタートアップ目線で解説!
- バックオフィス業務