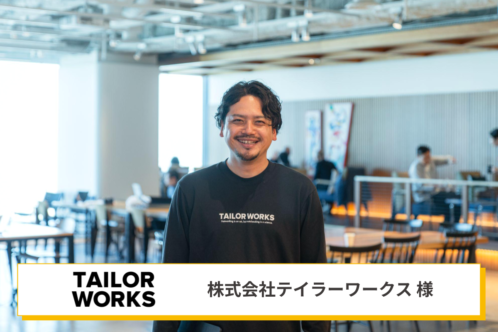採用・労務・経理に関するお役立ち情報

経理業務の効率化は、デジタルツールの積極活用によって大きく推進することができます。いわゆる経理DXは、すでに多くの国内企業で実践され、成果をあげてきました。
この記事では、経理DXとはどのような取り組みなのか、どのように仕組みを構築していくのか、詳しく解説します。
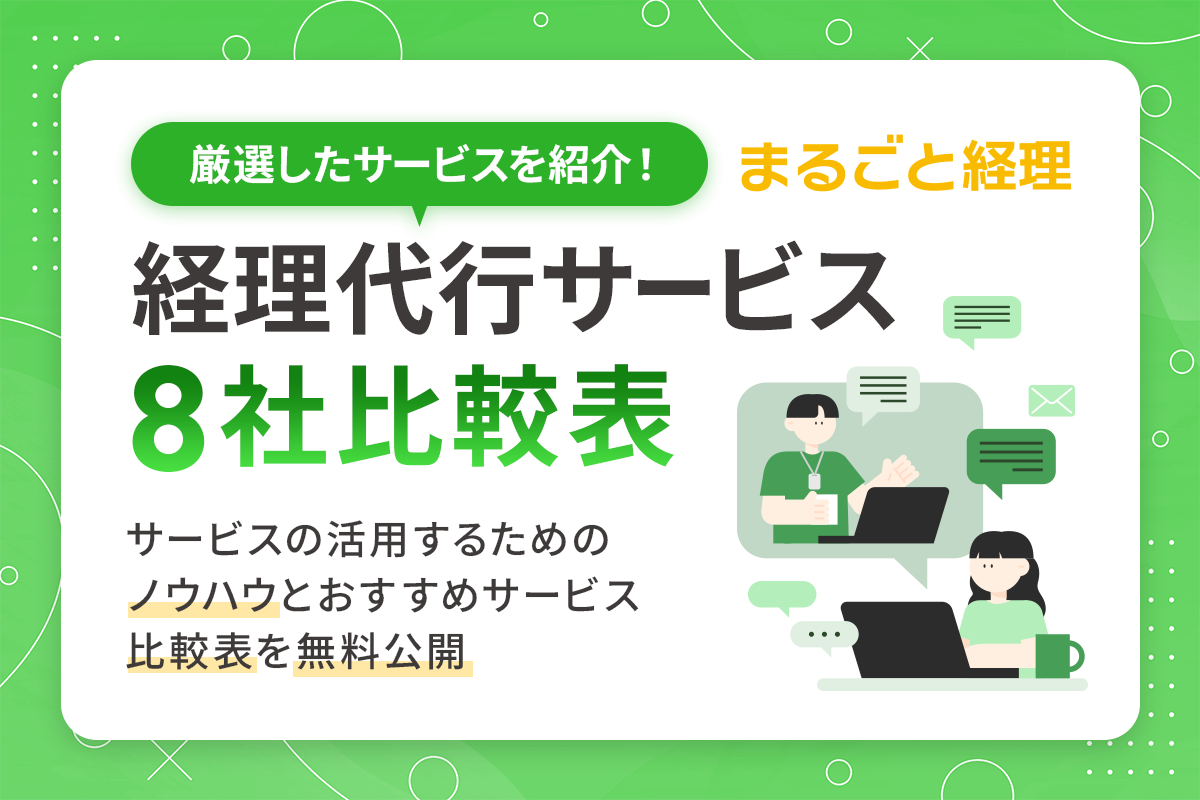
経理代行サービス比較表
経理代行サービスの活用の基本を解説。8社のサービスが一気に比較できます!
経理部門のDXとは?

経理DXとは業務プロセス全体を見直し、テクノロジーの力で企業の経営インフラを抜本的に進化させる取り組みです。
たとえば、AIによる自動仕訳やRPAによる定型業務の自動化、クラウド会計を活用したリアルタイム経営分析などが主な試作です。従来の手作業中心の経理から脱却することで、スピード・正確性・可視性を劇的に向上させることができます。
DXとデジタル化の違い
混同されがちな「デジタル化」と「DX」ですが、その本質には大きな違いがあります。
デジタル化とは、あくまで既存の業務プロセスを前提に、それをデジタルツールで効率化・省力化するアプローチです。紙の請求書をPDF化する、Excel作業をクラウド化する、会計ソフトに仕訳を入力するといった取り組みは、すべてこの範囲に入ります。
一方のDXは、そうしたデジタル化を基盤にしつつも、業務フローそのものや組織の役割、意思決定のスピードや精度までを見直し、「価値の出し方」を根本から変える変革です。
単なるデジタルツールの導入に留まらない、抜本的な変革を組織にもたらすのが、DXの最大の強みと言えるでしょう。
経理のDXが注目される背景

経理DXが強く求められる背景には、複数の要因が交錯しています。縁の下の力持ちとされてきた業務を生まれ変わらせることで、企業は多くの課題解決が可能です。
人材不足・担当者の属人化の限界
経理は専門性が求められる一方で、定型業務が多く、習熟にも時間がかかるポジションです。慢性的な人材不足が続き、ベテラン担当者に頼りきりの状態が少なくありません。
DXによって業務フローを可視化・自動化することで、「誰がやっても正しく処理できる仕組み」が生まれます。
人に依存しない体制づくりは、経理部門の継続性と信頼性を高め、経営全体の安定にもつながる取り組みです。
働き方改革・リモートワークの普及
近年の「働き方改革」やコロナ禍をきっかけに、リモートワークが一気に加速しました。経理部門も例外ではなく、紙書類や印鑑・出社前提の業務フローが大きな壁となっています。こうした旧来の体制を乗り越える手段こそが、経理DXです。
インボイス制度・電子帳簿保存法などの法改正への対応
2023年以降、インボイス制度や電子帳簿保存法の改正など、経理業務に直結する制度変更が相次いで施行されています。適格請求書の保存義務化、電子取引データの電子保存義務などにより、これまで以上に正確で透明性の高い管理体制が求められています。
これらに対応するには、DXツールの活用が不可欠です。電子請求書発行・クラウド型保存サービスなどを導入することで、法令対応と業務効率化を同時に実現できます。
クラウド会計や自動化ツールの普及
経理DXの実現を後押しする最大の要因の一つが、クラウド会計ソフトや自動化ツールの進化と普及です。
安価でありながら、使いやすさと機能性を両立し、中小企業にも導入しやすい設計の製品が広く登場しています。
銀行やカード明細の自動連携、AIによる仕訳の自動分類、ワークフローとの連携など、自動化の領域も拡大しています。導入のしやすさや費用対効果は、ますます高まっていくと考えられるでしょう。
DX化できる経理業務の具体例

経理のDXは「何から始めればよいかわからない」と感じる方も多いかもしれません。ここでは、DX化によって大きな効果が期待できる主な経理業務を紹介します。
会計ソフト・クラウド会計の導入による記帳の自動化
クラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携し、日々の取引データを自動で取り込みます。さらにAIが仕訳処理をサポートし、記帳の手作業を大幅に削減できるのが強みです。
入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの削減、記帳にかかる時間の短縮、そして迅速かつ的確な経営判断を実現できるでしょう。
請求書発行・受領処理の電子化
電子請求書システムを導入することで、請求書の作成・送付・受領といった一連の流れをデジタルで完結できます。紙の印刷や封入、郵送といったアナログ作業をなくし、請求書処理のスピードと効率が飛躍的に向上するでしょう。
さらには最新の法令にも対応できるなど、効率化にとどまらない、コンプライアンス強化が期待されます。
経費精算・承認ワークフローのクラウド管理
クラウド型経費精算システムを導入すれば、従業員がスマホやPCから経費を申請し、上司がオンラインで即時承認できます。領収書の電子保存や、AIによる不正検知機能も備えており、煩雑で時間のかかる経費処理が一気にスムーズなものになるでしょう。
申請〜承認までのリードタイム短縮に加え、内部統制強化、不正防止といったガバナンスの向上にもつながる、優れた施策です。
振込業務のオンライン化
インターネットバンキングを活用すれば、わざわざ銀行窓口に行くことなく、オフィスや在宅環境から振込が可能です。振込予約機能や複数承認ワークフローを設定できるため、不正や誤送金への備えも万全です。
業務の迅速化・省人化に加えて、セキュリティ水準の向上と承認体制の透明化にも期待できます。小規模な企業でも、少人数で確実な支払い体制を構築できるのが魅力です。
給与計算・年末調整のシステム化
勤怠管理システムと連携した給与計算ソフトを導入すれば、毎月の給与処理がボタン一つで完結できます。法改正に自動対応する仕組みもあるため、最新の税率や控除額にも正確に対応可能です。
年末調整業務も電子化すれば、従業員がオンラインで情報を入力し、書類提出や計算をすべてシステム内で収められます。
税務署への申告も電子で済ませ、正確性・効率性・法令遵守のすべてが実現するでしょう。
データ分析・レポート作成の自動化
各種ツールを組み合わせることで、KPIモニタリング、部門別の予算実績比較、キャッシュフロー予測などが視覚的に把握できるのは大きな強みです。
データに基づいた精度の高い意思決定が可能となり、経営のスピード感と戦略性を高められます。
従来では数時間かかっていたレポート作成も、わずか数クリックで完了するようになるケースも珍しくありません。
経理のDX推進の課題

経理業務におけるDXの必要性は広く認識されつつありますが、実際に導入・定着を進めようとすると、複数の課題が見えてくることもあるでしょう。
ここでは経理DXを阻む代表的な課題を、4つ解説します。
ツール導入に対する現場の抵抗・不安
新しいツールやシステムの導入において、最も大きな障壁となるのが現場の心理的な抵抗感です。
経理担当者の多くは、長年同じやり方で業務を遂行してきたため、操作方法の変更やフローの再構築に対して「混乱するのでは」「今のやり方でも問題ない」といった不安や懸念を抱くことがあります。
また、新システムの操作性や安定性への疑念も根強く、DX推進の足かせになります。こうした不安を払拭するには、段階的な導入や現場との対話を重ねる姿勢が不可欠です。
担当者のITスキル不足・教育の遅れ
経理部門では、ITツールやクラウドサービスへの理解が十分でないケースが珍しくありません。そのため、新システム導入時の操作ミスや設定不備が業務エラーや遅延を招くリスクがつきまといます。
加えて、教育が後回しになると、システムの持つ高機能を活かしきれず、「導入したけどあまり変わらなかった」という事態にもなりかねません。
導入後の運用体制が曖昧になる
DX化に成功する企業と、形骸化してしまう企業の違いは、導入後の運用体制の明確さです。せっかく新しいシステムを導入しても、誰が責任者なのか、どのように運用ルールを設けるのかが不明瞭なままでは、トラブルが起きた際の対応も後手に回ります。
また、システムの定期更新や活用状況のモニタリングが行われず、機能が陳腐化するリスクもあるでしょう。
投資対効果の不透明さ
経理DXの導入には、システムのライセンス料、初期設定費用、社員研修費など一定のコストが伴います。これに対して、「何年で回収できるのか」「具体的にどれだけ業務時間が削減されるのか」といった投資対効果の可視化が不十分だと、経営層は判断に二の足を踏みかねません。
過去のIT投資で期待した成果が出なかった企業ほど、新たな投資に慎重になる傾向があります。数字や成果事例をもとに、明確な導入効果を設計・提示することで、意思決定を後押しすることが大切です。
経理DXを進めるためのステップ

経理DXを成功に導くにはツール導入にとどまらない、一連のプロセスを戦略的に進めることが重要です。以下に、経理DXを推進するための5つのステップをご紹介します。
ステップ1:現状の業務フローを可視化・課題を洗い出す
DXを本格的に始める前に、まず行うべきは現状の把握です。経理業務の全体像をフローチャートなどで可視化し、各業務にかかる時間、関わる担当者、使用しているツールや手法を洗い出します。
業務一覧表の作成、現場担当者へのヒアリングなどを通じて、ボトルネックや改善余地を徹底的に掘り下げていくことが、DXの土台となる極めて重要な工程です。
ステップ2:目的に合ったツールを選定する
現状の課題が明確になったら、次はその課題を解決できる最適なツールの選定です。世の中には多種多様なクラウド会計ソフトや経費精算ツールがありますが、大切なのは「自社の業務内容・規模・予算にフィットしているか」という視点です。
必要な機能が揃っているか、操作性・UIのわかりやすさは十分か、既存の会計システムや業務フローと連携可能か、などを把握しておきましょう。
目的と手段を混同せず、課題解決に直結するツールを選び抜くことが成功のカギです。
ステップ3:スモールスタートで段階的に導入する
DXは一気に全社展開するのではなく、小さく始めて大きく育てる「スモールスタート」の考え方が鉄則です。
まずは優先度の高い業務やチームから試験導入を行い、実際の運用で得られたフィードバックを基に改善を繰り返します。段階的な導入により、現場の混乱を最小限に抑えつつ、実務に根差した調整が可能です。
ステップ4:現場教育と社内マニュアルの整備を実施する
どれほど優れたツールでも、使いこなせなければ真の効果は発揮されません。現場の理解とスキルの底上げが、DX定着のポイントです。
操作マニュアルやFAQ、動画教材などを整備し、誰でも安心して使える環境をつくることが求められます。
また、定期的な研修会やワークショップを通じて、実践的なノウハウを共有し、疑問や不安をその場で解消する機会を提供しましょう。サポート窓口の設置や、質問対応の即応体制の構築も、現場の安心感につながります。
ステップ5:定期的な効果検証と見直しを継続する
DXは導入して終わりではなく、「成果を検証し、常に進化させる」ことが不可欠です。業務時間の削減率などのKPIを設定し、ツールの導入前後で効果を定量的に評価します。
また、現場の声を積極的に収集・分析し、使いにくい部分や新たに発生した課題に対して柔軟に対応していく仕組みも、大切にすべきでしょう。
正しい手続きで課題解決型の経理DXを実現

経理DXは、単なる業務効率化にとどまらず、組織全体の生産性や経営判断の質を高める、戦略的な変革です。
現状の課題を丁寧に洗い出し、自社に合ったツールを段階的に導入しながら、現場との連携と継続的な見直しを行うことで、着実な成果につながります。
また、経理DXを推進する上では、成果が得られるまでに時間がかかる点も注意しなければなりません。経理代行サービスの「まるごと管理部(経理プラン)」では、DX推進に伴うリソースの不足や移行に伴うノウハウの不足を、必要な分だけ補えます。
月額制で利用できる、カジュアルな経理代行プランを提供しているため、長期での契約は不要です。導入に際しては既存のシステムをそのまま流用して代行を依頼できるので、代行のための準備をわざわざしてもらう負担からも解放されます。
経理DXを進めたいが、それに伴う負担の発生を懸念する場合や、すぐに効率化を実現したい場合には、以下のページよりさらなる詳細をご確認ください。
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事

東京のおすすめ経理代行業者4選!依頼するメリットも合わせて解説
- バックオフィス業務
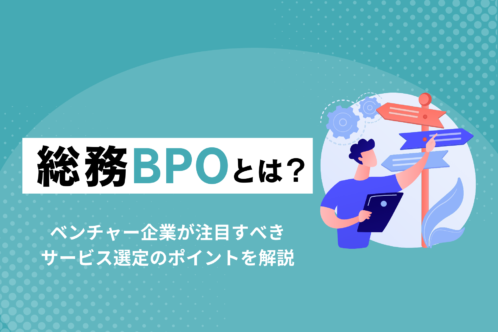
総務BPOとはどんなサービス?ベンチャー企業が注目すべきサービス選定のポイントを解説
- バックオフィス業務
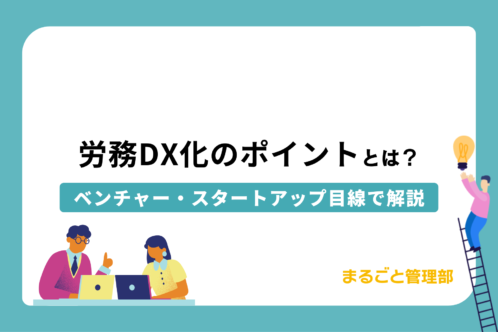
労務DX化のポイントをベンチャー・スタートアップ目線で解説!
- バックオフィス業務
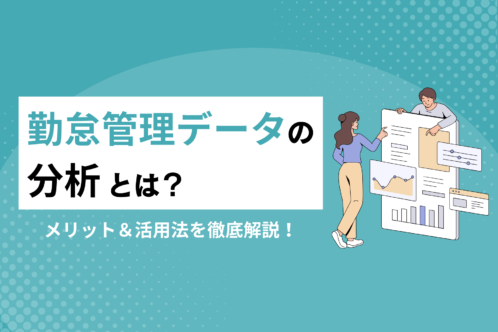
勤怠管理データの分析とは?3つのメリット&活用法を徹底解説
- バックオフィス業務
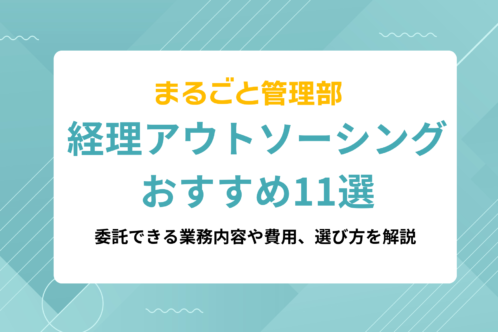
経理アウトソーシング会社おすすめ11選|委託できる業務内容や費用、選び方を解説
- バックオフィス業務
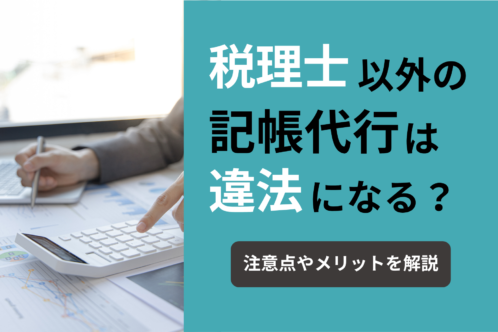
税理士以外が記帳代行すると違法になる?注意点や依頼のメリットを解説
- バックオフィス業務