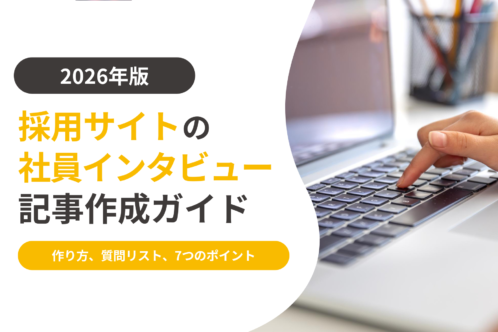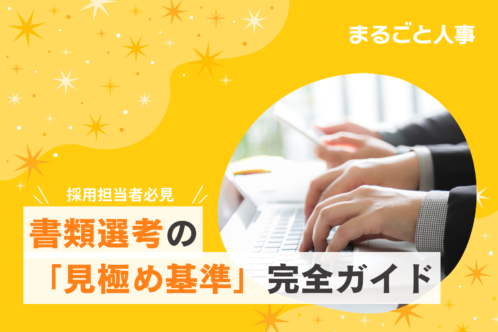採用・労務・経理に関するお役立ち情報
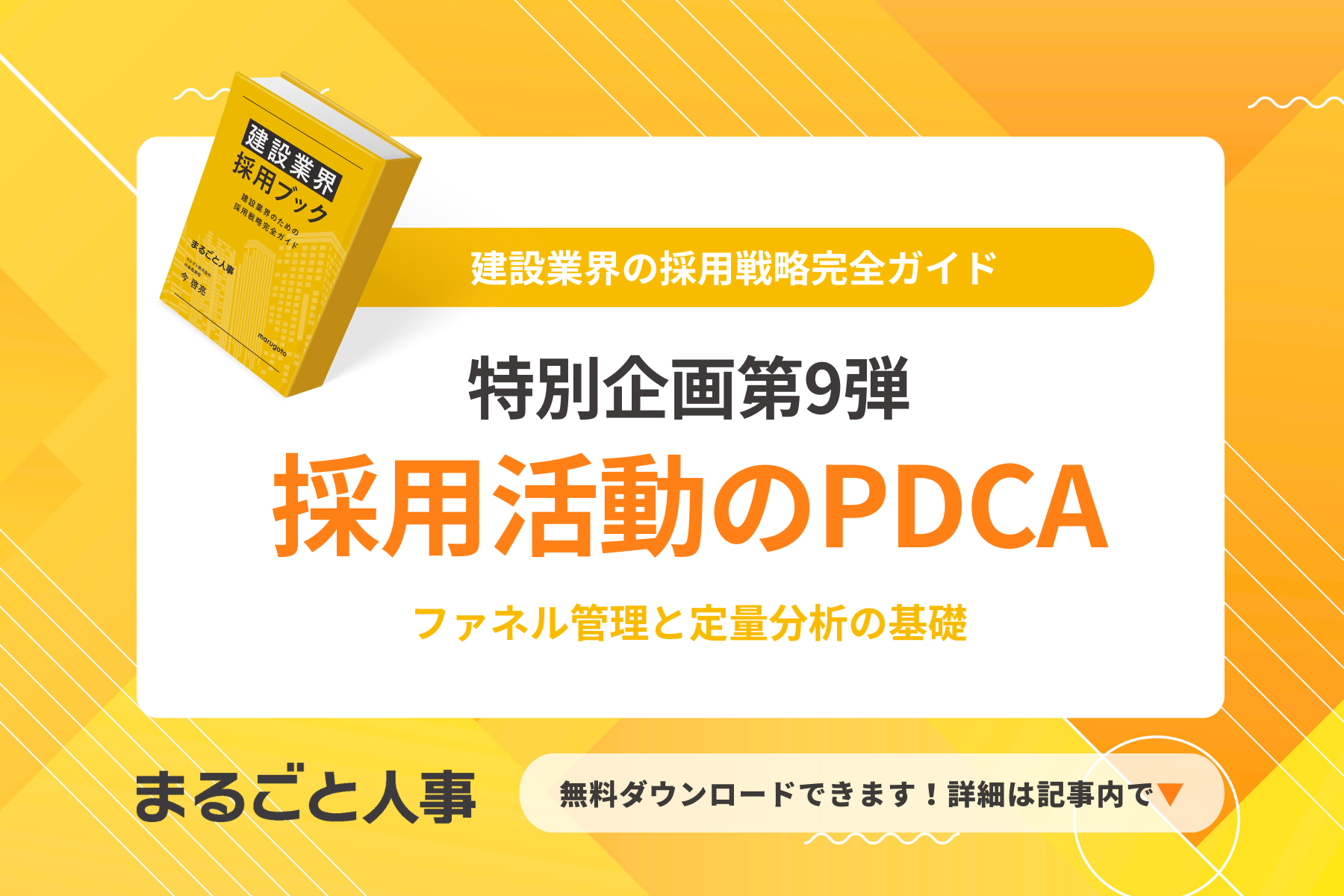
応募数だけで採用は語れない
「応募が来た=成功」という評価軸だけでは、採用活動の実態は見えてきません。なぜなら、
- 応募が多くても、面接に進まない
- 面接しても、内定辞退される
- 入社しても、すぐに辞めてしまう
といった“漏れ”が発生していることが多いからです。
特に中小建設企業では、「来てくれればありがたい」と思うあまり、応募数だけに目を奪われがちですが、採用はファネル(漏斗)構造で考える必要があります。
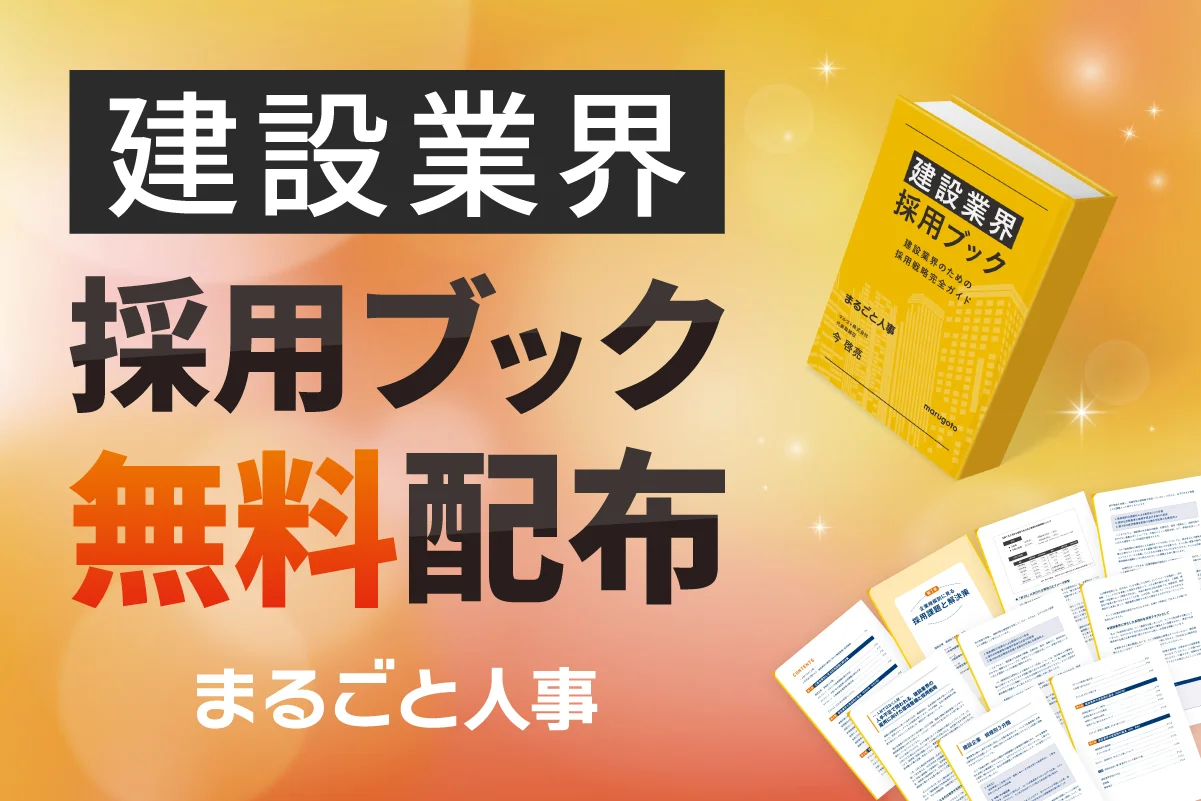
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
関連動画:建設業界採用ブックの解説動画
ファネル管理で「どこで詰まっているか」を把握する
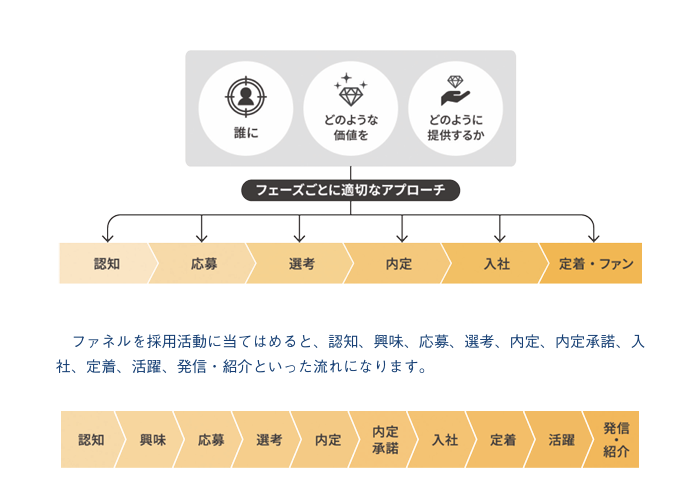
採用活動は、営業と同様に”ファネル”で可視化できます。代表的なステップは以下の通りです:
- 求人の閲覧数(求人媒体やSNSなど)
- 応募数
- 書類選考通過数
- 一次・最終面接通過数
- 内定承諾数
- 入社後定着数
このように各ステップを定量化しておくことで、「どこで歩留まりが悪くなっているのか」が明確になります。
たとえば:
- 書類通過率が低ければ、求人のターゲットや内容がミスマッチ
- 面接辞退率が高ければ、日程調整や印象形成の仕組みに課題
- 内定辞退が多ければ、条件提示やコミュニケーションに不足
といった仮説が立ち、次の一手を具体化しやすくなります。
データ分析のポイント:”率”で見る
採用の成果を語るうえで重要なのは、”数”ではなく”率”で見ることです。
- 応募数→面接数(面接率)
- 面接数→内定数(内定率)
- 内定数→承諾数(承諾率)
- 入社数→3ヶ月定着数(定着率)
これらの「コンバージョン率」を追うことで、
「何件応募があれば1名入社するか」
というコスト感や施策評価が見えてきます。媒体別・職種別・時期別などで比べてみると、より深い示唆が得られます。
採用レポートは経営資料である
中小企業では、採用は人事任せ、または現場任せになりがちです。しかし、
「誰をどのくらい、いつまでに採用できるか」
は、事業計画に直結する重要情報です。だからこそ、採用レポートは現場だけでなく、経営層に共有されるべきです。
採用の進捗や歩留まりを、月次や四半期単位で報告・可視化することで、
- 採用への理解とコミットが社内に浸透
- 予算や体制の根拠が明確になる
- 採用戦略が事業と連動する
といった効果が生まれます。
特に、定量データとセットで「なぜそうなったか」の要因分析や改善施策を記載すると、採用が“なんとなく”ではなく、戦略的な取り組みとして認識されます。
採用もPDCAで改善する
「求人出したけど、来なかった」で終わってしまっては、同じ失敗を繰り返します。
- Plan:どんな人を、どんなチャネルで、どう口説くかを計画
- Do:実行(媒体出稿、面接対応など)
- Check:数値で検証(応募数・歩留まり・定着)
- Act:改善(ターゲット・内容・対応プロセスの見直し)
というサイクルを回すことが、再現性のある採用成功につながります。
特に、感覚や経験値ではなく「データに基づいた改善」ができると、採用活動の精度が格段に上がります。
次回予告
次回(最終回)は、「採用から始まる会社のブランド戦略」と題し、採用活動を“広報・PR”として捉える発想の転換と、自社らしさを伝えるブランディング戦略についてご紹介します。
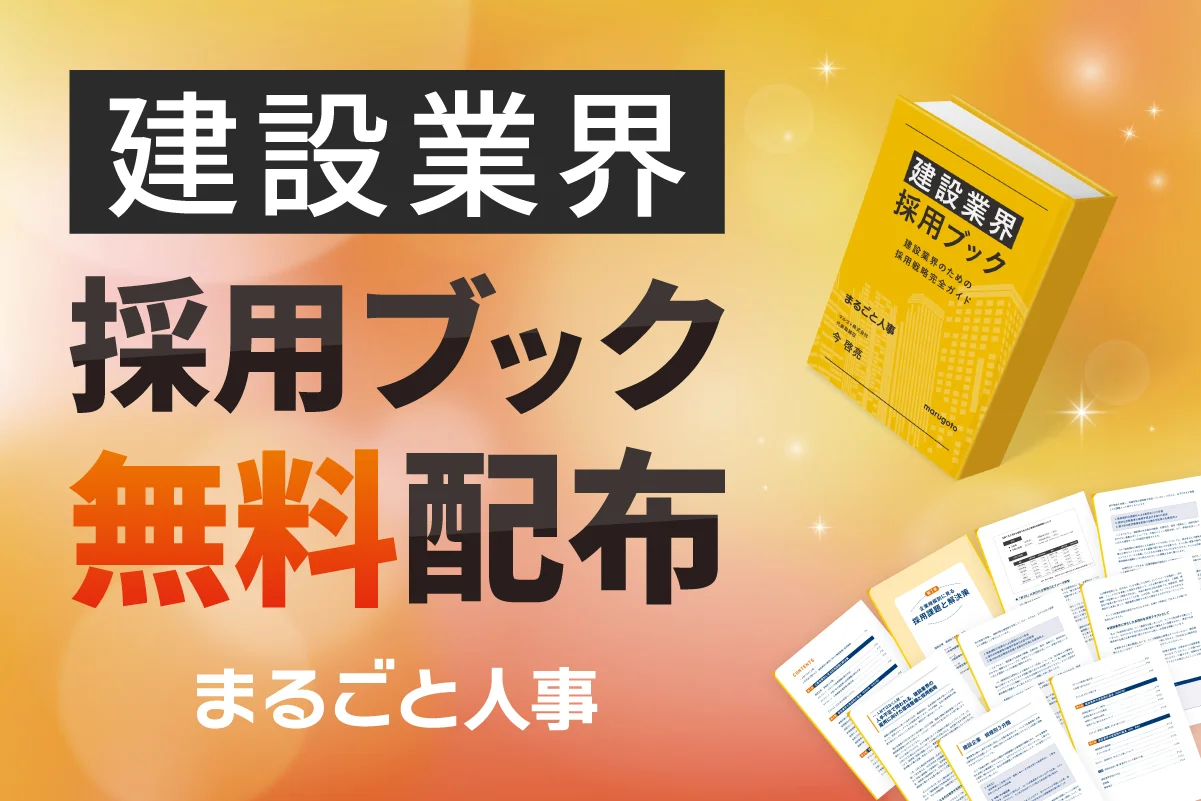
無料で公開!!
建設業界採用ブック
建設業界の“良い人材が採用できない悩み”を解決!応募から内定まで導く、現場目線の採用ノウハウ本を完全無料で公開中です!!
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
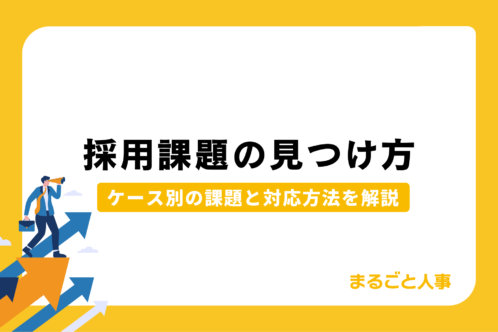
採用課題とは|見つけ方や課題別の解決方法と事例を紹介
- 採用企画
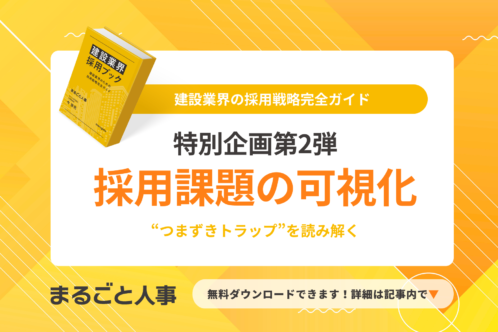
第2回「採用の全体像と“つまずきトラップ”を読み解く」【特別企画:建設業界採用ガイドブック解説】
- 採用企画
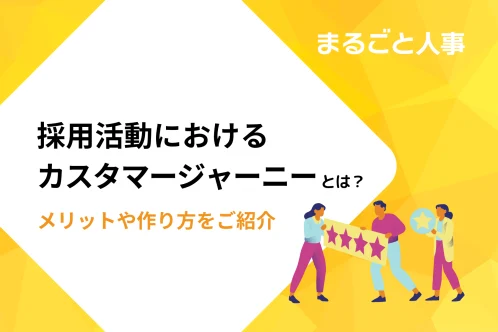
採用活動におけるカスタマージャーニーとはなにか?メリットや作り方を紹介
- 採用企画
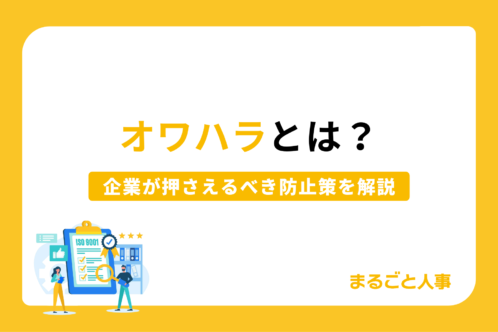
オワハラとは?企業が知っておくべきリスクと防止策6つを徹底解説
- 採用企画

建設業の新3K採用戦略|従来の3Kとの違いと実現に向けた具体策
- 採用企画
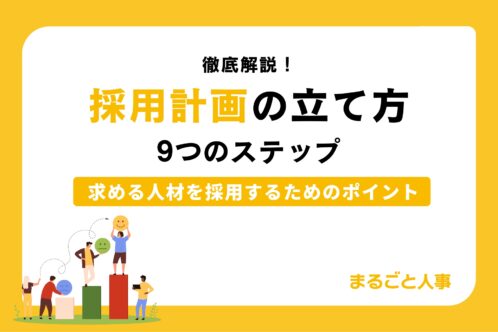
採用計画の立て方を徹底解説!9つのステップと求める人材を採用するためのポイント
- 採用企画