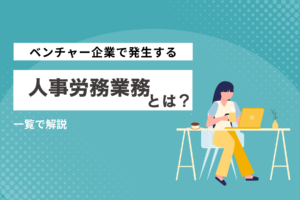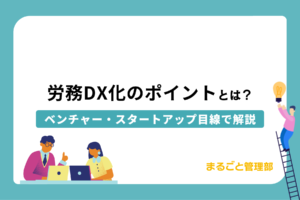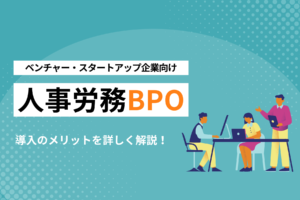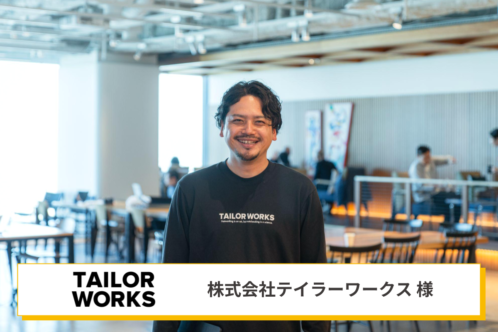採用・労務・経理に関するお役立ち情報
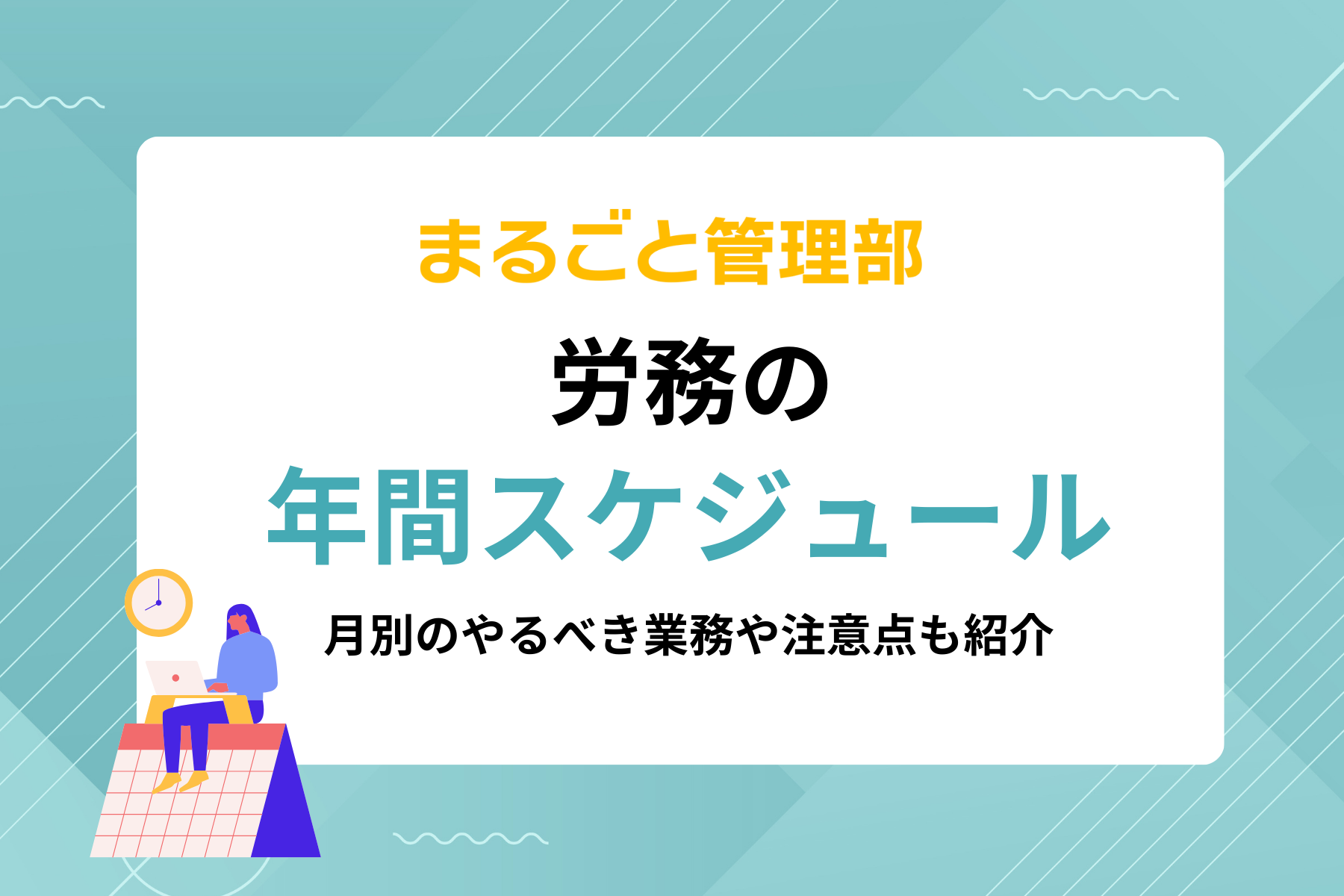
労務の業務内容は多岐にわたるため、なかなか業務を円滑に対応できずに悩んでいる担当者も少なくありません。業務を円滑に進めるには全体的なスケジュールを大まかに把握し、繫忙期の事前準備を計画的に実施することが大切です。
この記事では労務の年間スケジュールを解説します。
2025年度に注意すべきポイントも解説しているので、2025年度の業務スケジュールを計画しようとしている労務担当者は活用してみてください。
就業規則の作成ポイントについてはこちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
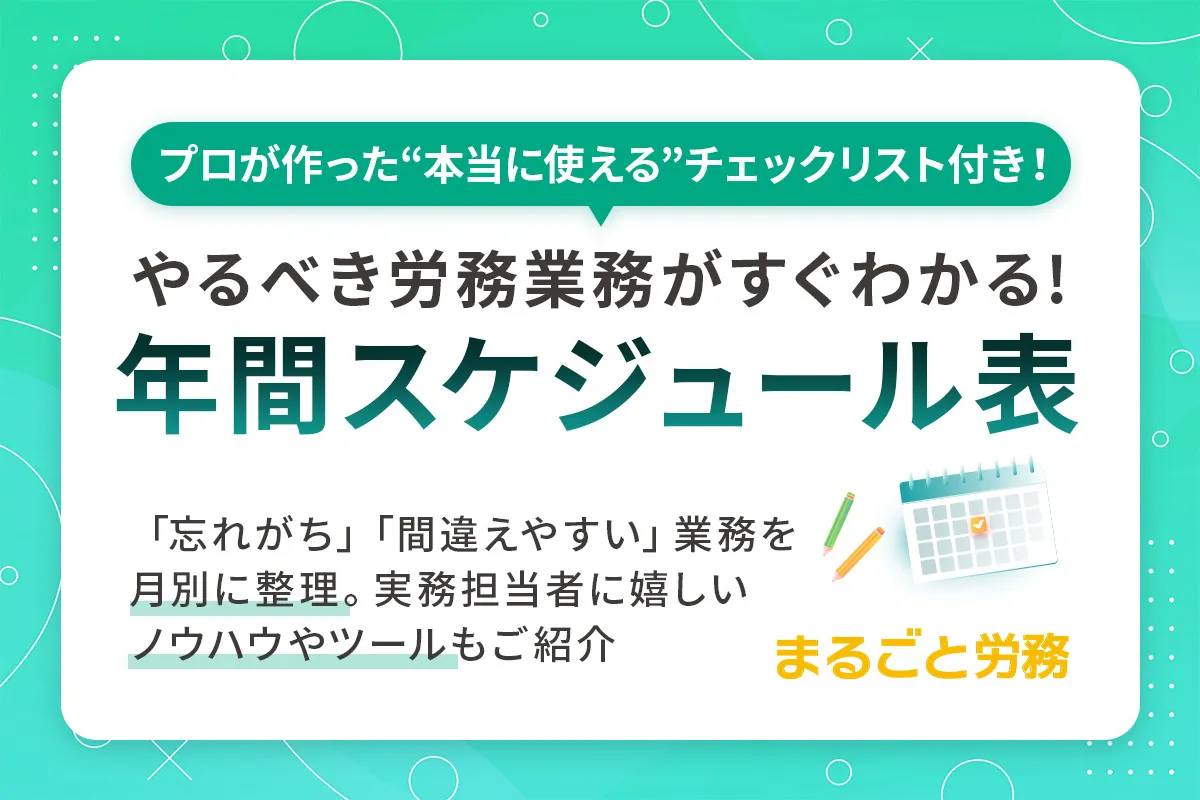
労務業務の年間スケジュール
記事といっしょに活用するとより効果的!「まるごと管理部」が作った便利なスケジュール表を無料配布中。チェックリストとノウハウを活用して、明日から労務業務をラクに進めましょう。
目次
企業における労務管理業務とは

企業における労務管理業務とは、従業員の勤怠・給与・社会保険手続き・就業規則の整備など、働く環境を整えるための管理業務全般を指します。労務トラブルの防止や法令遵守にも関わる、重要な分野です。
労務管理に関する詳細は、別記事もあわせてご覧ください。
関連記事:ベンチャー企業で発生する人事労務業務は?一覧で解説
労務における定例業務
| 頻度 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 毎月 | 給与計算、勤怠集計、前月分の社会保険料の納付 |
| 随時 | 入退社手続き、労災申請、傷病手当金の申請、36協定の締結・変更、育休・産休関連手続き など |
| 年間行事 | 年末調整、労働保険の年度更新、必要に応じた就業規則見直し |
労務分野では、月ごと・年間・随時で発生する多様なタスクが存在します。たとえば毎月の給与計算や勤怠管理は、基本的な業務として欠かせません。
加えて、入退社時の対応や法改正に伴う規程の更新も重要です。特に年度末には、年末調整や保険関係の更新など負荷が高まるため、事前のスケジュール管理が求められます。
特に時間がかかる労務業務に注意
定例業務の中でも、勤怠管理や給与計算はシステム化されていない場合、特に時間が取られる業務となるので注意が必要です。
また2020年に「パワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)」が施行され、2022年4月からは中小企業にも義務化されたことで、ハラスメントの対応やそもそもハラスメントが起きないようにするための仕組み作りが必要となっています。「組織文化形成」「メンタルケア」「人事評価」など、多岐にわたる領域に影響するため、労務担当者の負担が年々増しています。
労務年間スケジュールの作成手順

労務年間スケジュールの作成は、まず自社の法定手続きと社内行事を洗い出し、一覧にします。次に厚生労働省や社労士法人が公開するカレンダーを参照し、期限と提出先を記載しましょう。
期日順に並べ替え、その後担当者とチェック期限を割り当てます。月次業務と年次イベントを色分けすれば優先度が一目でわかるでしょう。
手順の最終段階としてExcelやクラウドツールに登録し、リマインダーを設定します。計画が固まったら経営層と共有し、変更点が生じた場合は即時反映すると修正漏れを防げます。
人事担当が不在でも進行状況が追跡できるようガントチャート形式で可視化し、年度終了後には達成率を検証して次年度の計画へフィードバックしましょう。
改正法公布時には速やかにタスク追加し、研修日程も同時に登録すれば教育漏れを防げます。完成したスケジュールはクラウドストレージに保管し、更新履歴を残す運用体制を整備すると監査対応も円滑です。
労務年間スケジュール作成におけるコツ
労務年間スケジュール作成のコツは、まず法改正や補助金情報を毎月チェックする仕組みを設け、半年ごとに計画を見直す習慣を作ることです。繁忙期直前に業務が集中しがちな月次処理は前倒しできる手続きと外部委託候補を分類し、平準化を図りましょう。
次にIT活用の観点では勤怠・給与・社会保険のデータをAPI連携することで入力ミスが大幅に減ります。担当者ごとに権限を設定し、変更履歴を自動保存すれば内部統制も強化できます。
さらにKPIとして期限遵守率・残業削減時間・法定調書修正件数を掲げ、数値評価で改善点を可視化しましょう。最後に経営陣へ月次報告を行い、追加リソースやシステム投資の判断材料に結びつけると継続的な効率化が進みます。
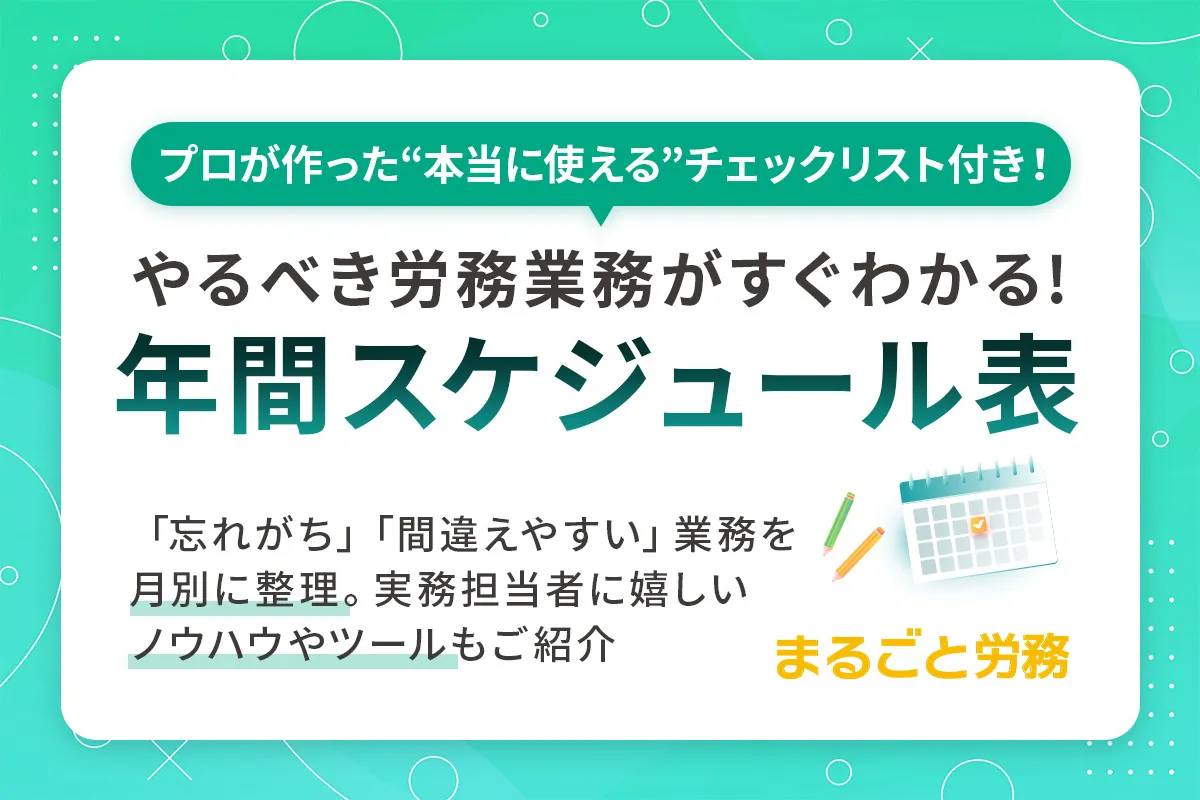
労務業務の年間スケジュール
「まるごと管理部」が作った便利なスケジュール表を無料配布中!チェックリストとノウハウを活用して、明日から労務業務をラクに進めましょう。
労務業務の年間スケジュールを一挙解説

労務の業務内容はどの企業も共通しているものが多いため、参考にしているスケジュールをそのまま自社の業務として適用させやすい特性があります。
そのため、年間スケジュールを参考にするメリットが他の部署よりも大きいといえるでしょう。
ここでは労務業務の年間スケジュールを月ごとに解説します。
繁忙期についても解説するので、繁忙期にキャパオーバーしないように注意したい担当者は参考にしてみると良いでしょう。
| 月 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 4月 | 新入社員の入社手続き、人事異動、給与改定、36協定更新の手続き |
| 5月 | 住民税年度更新準備 |
| 6月 | 労働保険年度更新・納付、高年齢者・障がい者雇用状況報告、住民税年度更新 |
| 7月 | 算定基礎届の提出、賞与支給・賞与支払届の提出、夏季休暇の案内 |
| 8月 | 給与改定決定後の処理、ストレスチェック実施 |
| 9月 | 地域別最低賃金の確認 |
| 10月 | 社会保険料の定時改定、厚生年金保険料率の改定、地域別最低賃金の反映 |
| 11月 | 被扶養者状況リストの確認、勤怠システムの確認 |
| 12月 | 年末調整、源泉徴収票作成・発行、賞与支給 |
| 1月 | 法定調書の提出、給与支払報告書の提出 |
| 2月 | 新卒社員入社準備 |
| 3月 | 36協定の締結・届出、新卒社員入社準備、4月の法改正に対する就業規則等の改訂準備 |
4月主な労務業務
- 新入社員の入社手続き
- 人事異動
- 給与改定
- 36協定更新の手続き
新入社員が入社するなど社内の人事業務が忙しくなるうえ、法改正の対応が必要な場合も珍しくありません。
他の月に比べて対応しなければならない業務が多い繁忙期であるため、労働条件通知書作成や雇用保険関連の手続きなど専門知識が必要な業務は、アウトソーシング業者に依頼して対応することも検討すると良いでしょう。
5月の主な労務業務
- 住民税年度更新準備
住民税は都道府県民税と市町村民税を合わせた地方税であり、前年の所得をもとに計算されます。
住民税の納付期間は原則毎年6月から翌年の5月までなので、毎年6月から納付する金額が変更になります。
給与の税額設定も変更しなければならないため、6月の業務が立て込まないようにするためにも、5月の内から住民税年度更新業務を進めておくと良いでしょう。
6月の主な労務業務
- 労働保険年度更新・納付
- 高年齢者・障がい者雇用状況報告
- 住民税年度更新
労働保険は労災保険と雇用保険のことを指します。
労働保険料は4月から翌3月に支払った賃金総額を基に計算するため、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を計算して、納付金額を支払わなければなりません。
納付期限は6月1日から7月10日までに設定されているので、6月中に労働保険関連の処理を終わらせておくと良いでしょう。
7月の主な労務業務
- 算定基礎届の提出
- 賞与支給・賞与支払届の提出
- 夏季休暇の付与、案内
算定基礎届は社会保険料を決定するために、事業主が毎年提出する書類です。
4月から6月に支給した給与・手当を基準に標準報酬月額を決定し、日本年金機構に提出することで適切な保険料が適用できます。
算定基礎届の提出期限は7月1日から7月10日までに設定されているので、7月前半に処理を終えなければなりません。
また、夏の賞与支給を6月下旬~7月上旬としている企業も多いことから、賞与支給があった場合は賞与支払届の提出も忘れずに行いましょう。
8月の主な労務業務
- 給与改定決定後の処理
- ストレスチェック実施
4月に給与改定を実施した場合には、給与改定決定後の処理も忘れずに対応しましょう。
社会保険関連の手続きや税金関連の処理など、複数の項目に対応しなければならないので、チェックリストを作り漏れがないように対応することをおすすめします。
9月の主な労務業務
- 地域別最低賃金の確認
9月に最低賃金の改定情報が公開されます。
10月から改定内容を反映しなければならないため、9月に確認して給与計算などに反映する準備を進めておくと良いでしょう。
10月の主な労務業務
- 社会保険料の定時改定
- 厚生年金保険料率の改定
- 地域別最低賃金の反映
社会保険料の定時改定は、7月に行った算定結果に基づいて社会保険料の改定することを指します。
似たような処理に社会保険料の随時改定があるため、実施時期や基準とする月などの違いをしっかりと把握してから、処理を実施することをおすすめします。
11月の主な労務業務
- 被扶養者状況リストの確認
- 勤怠システムの確認
被扶養者状況リストは健康保険における従業員の扶養家族の状況を一覧にまとめた書類です。
事業主が従業員の扶養家族の状況を確認・管理するために提出するもので、扶養から外れる人物がいる場合は被扶養者異動届を提出しなければなりません。
また、年末年始は労務業務が立て込んでしまうため、翌年の休日や祝日を確認して勤怠システムに不備がないか確認しておくと良いでしょう。
12月の主な労務業務
- 年末調整
- 源泉徴収票作成、発行
- 賞与支給
年末調整は従業員の1年間の給与所得に対して過不足なく所得税を計算し、税額を調整する重要な業務です。
従業員の給与総額の確定や所得税額の計算するなど、業務内容が多くあるうえ専門的な知識が必要になるため、外部の専門業者に委託する企業が多いです。
年末調整が完了したら、結果が反映された源泉徴収票を作成して、従業員に向けて発行します。
年末調整を中心とした業務が立て込むため、労務の繁忙期シーズンになるといえるでしょう。
1月の主な労務業務
- 法定調書の提出
- 給与支払報告書の提出
法定調書と給与支払報告書の提出期限は1月31日までに設定されているので、必ず対応するようにしましょう。
また、12月に実施していた年末調整や源泉徴収票関連の締め切りも1月31日までのため、何かしら不備があった際には、1月中に対応を終わらせておくことが大切です。
2月の主な労務業務
- 新卒社員入社準備
12月、1月の期間にくらべ余裕を持って業務に取り組みやすいので、4月の繁忙期に向けて4月入社予定の新卒社員関連の業務の準備や、雇入時健康診断の案内などのアナウンスを実施しておくことをおすすめします。
また、4月からの動きや去年の業務状況を見て、アウトソースの導入を検討しておくと、信頼できる業者を選ぶ時間を確保しやすくなります。
3月の主な労務業務
- 36協定の締結、届出
- 新卒社員入社準備
- 4月の法改正に対する就業規則等の改訂準備
4月から業務が過密になっていくので、事前に業務フローを整備して、キャパオーバーしないように準備しておくことをおすすめします。
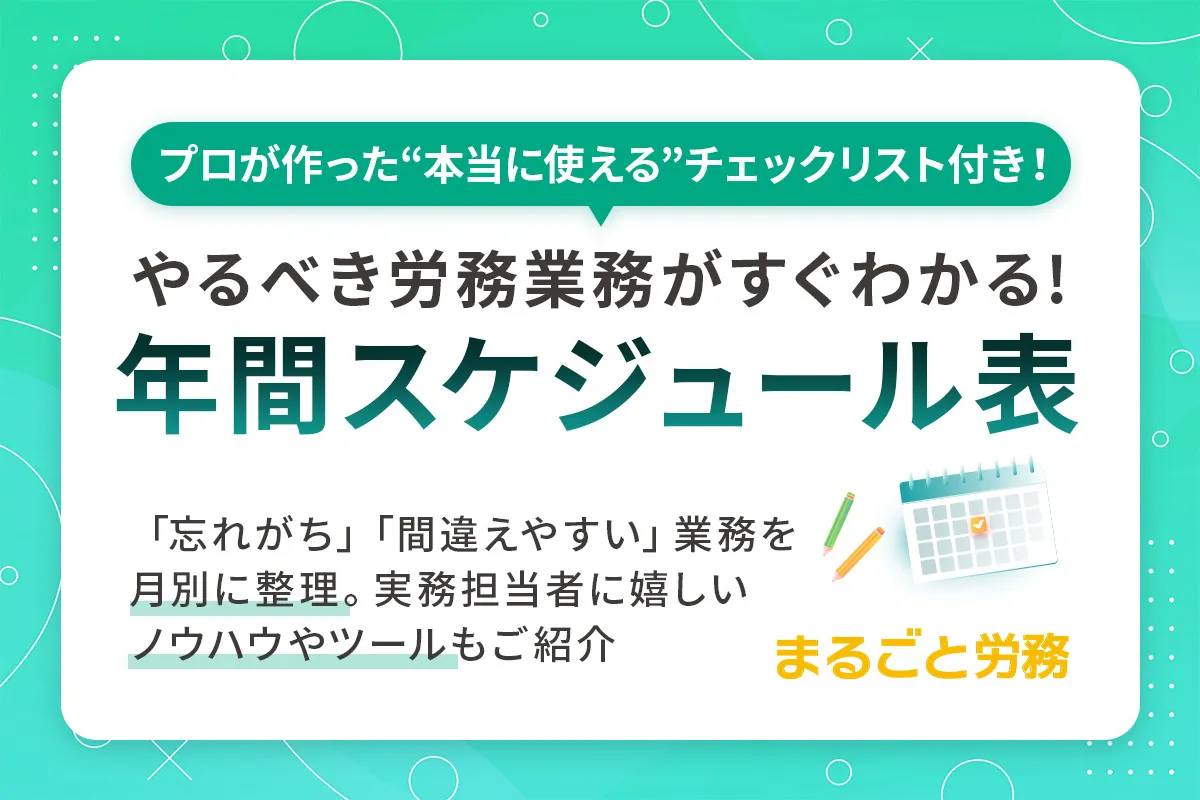
労務業務の年間スケジュール
「まるごと管理部」が作った便利なスケジュール表を無料配布中!チェックリストとノウハウを活用して、明日から労務業務をラクに進めましょう。
2025年度に注意すべき労務のポイント3選

労務の業務は法律にも大きく関係するため、年度ごとに注意するポイントの変化がある傾向が強いです。
ここでは、2025年度に注意すべき労務のポイントを3つ解説します。
年間スケジュールを計画する際に、労務に関係する法律の改正内容を反映させることで、不測のトラブルを回避することにもつながります。
万全な状態で労務業務を準備したい担当者は、ぜひ確認してみてはいかがでしょうか。
1.雇用保険法施行規則の改正
雇用保険法施行規則では以下の2項目が改正対象となります。
- 高年齢雇用継続給付(逓減給付率)
- 教育訓練給付関係
高年齢雇用継続給付に関する改正については、60歳以後の給与額が75%未満になる場合、65歳になるまでは各月の給与額の15%を支給することになっていましたが、改正後は10%に変更になります。
そのため、高齢者を雇っている企業は給与システムを更新する必要があります。
2.雇用保険法の改正
雇用保険法では以下の2項目が改正されます。
- 教育訓練支援給付金関係
- 就業促進手当
- 教育訓練休暇給付金の創設
教育訓練休暇給付金は仕事から離れて教育訓練を受ける場合に、生活費を支援する制度を指します。
教育訓練周りの給付金の制限や仕組みに変更があるので、教育訓練を活用する予定のある企業はチェックしておくと良いでしょう。
3.育児・介護休業法の改正
育児・介護休業法では以下の2項目が改正されます。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 子の看護休暇の拡大
働き方の柔軟化措置や働き方の多様性を取り入れる法律の整備が進んでいるため、リモートワークや短時間勤務など複数の働き方を実施しやすくなってきています。
しかし、働き方の多様化に伴って労務業務も複雑化しているので、キャパオーバーを防ぐために今後も労務業務を外部に委託する動きが加速していくでしょう。
2019年~2025年:労働基準法の主な改正一覧
以下に労務担当者が知っておくべき、2019年〜2025年の労働基準法の主な改正をまとめました。
こちらも参考にして、労務業務を進める必要があります。
| 年 | 改正項目 | 政府の参考リンク | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フレックスタイム制の拡充(清算期間の上限延長 等) | 厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説」 | 清算期間の柔軟化 など |
| 時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」 | 大企業:2019/4〜、中小:2020/4〜 段階適用 | |
| 年5日の年次有給休暇の確実な取得 | 厚労省リーフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得」 | 使用者による時季指定の義務 | |
| 高度プロフェッショナル制度 | 厚労省「高度プロフェッショナル制度の概要」 | 対象業務・年収要件 など | |
| 月60時間超の時間外労働の割増賃金率引上げ(制度設計) | 厚労省リーフレット(割増率・代替休暇 等) | 中小企業は猶予→2023年適用(下記参照) | |
| 過半数代表者の選出手続等・労働条件等の明示等の方法の見直し | 厚労省通知「過半数代表者の選出手続等及び労働条件等の明示等の方法の見直しについて」 | 明示方法の整理、代表者の選任要件 明確化 | |
| 2020 | 賃金請求権の消滅時効期間の延長(2年→原則5年・当面3年) | 厚労省リーフレット「未払賃金が請求できる期間などが延長」 | 2020/4/1以降支払期日の賃金から |
| 時間外労働の上限規制(中小へ適用開始) | 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」 | 中小企業 2020/4〜 | |
| 派遣労働者への待遇改善措置 | 厚労省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」 | 均等・均衡待遇、労使協定方式 等 | |
| 同一労働同一賃金(大企業へ適用) | 働き方改革特設サイト「同一労働同一賃金」 | 不合理な待遇差の禁止 | |
| パワハラ防止法(大企業へ適用) | 厚労省リーフレット「ハラスメント防止対策が強化」 | 中小は2022/4〜義務化 | |
| 2021 | 同一労働同一賃金(中小企業へ適用) | 厚労省「同一労働同一賃金 特集ページ」 | 中小企業に全面適用 |
| 正社員と非正規の不合理な待遇差の禁止 | 働き方改革特設サイト「同一労働同一賃金」 | 均等・均衡待遇の徹底 | |
| 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得 | 厚労省リーフレット(時間単位取得の導入) | 2021/1/1 施行 | |
| 高年齢者(70歳まで)の就業機会確保(努力義務化) | 厚労省「高年齢者雇用安定法の改正」 | 2021/4/1 施行 | |
| 2022 | 改正育児・介護休業法の施行 | 厚労省「育児・介護休業法について」 | 産後パパ育休 等 段階施行 |
| パワハラ防止法(中小企業へ適用) | 厚労省 特設ページ(パワハラ防止) | 2022/4/1 義務化 | |
| 改正個人情報保護法(労務関連の実務影響) | 個人情報保護委員会 特集ページ | 漏えい報告義務化 等 | |
| 2023 | 月60時間超の時間外労働の割増率引上げ(中小企業にも適用) | 厚労省リーフレット(割増率・計算例) | 60時間超は50%(中小も2023/4〜) |
| 賃金のデジタルマネーでの支払い解禁 | 厚労省「賃金のデジタル払い」 | 労基則改正(2023/4〜運用開始) | |
| 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超) | 厚労省「男性の育児休業取得率等の公表について」 | 2025/4〜は従業員数300〜1,000人にも拡大 | |
| 2024 | 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制(適用開始) | 厚労省 特設「特定業種の上限規制」 | 猶予終了・一部特例あり |
| 明示すべき労働条件事項の追加 | 厚労省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 | 就業場所/業務の変更範囲 等の明示 | |
| 2025 | 厚生年金「養育特例」の添付書類省略(電子申請様式 変更) | 日本年金機構「令和7年1月以降の電子申請様式の変更等」 | 事業主確認で添付省略可 など |
| 障がい者雇用関連の拡充(法定雇用率引上げ等の周知) | 厚労省「障害者雇用対策」 | 最新リーフレット/告示等は随時更新 | |
| 「柔軟な働き方を実現するための措置」義務化 | 厚労省 特設「柔軟な働き方を実現するための措置」/ 同「法改正のポイント」 | 2025/10/1 適用開始(5つの措置から2つ以上) |
年間スケジュールを把握して労務の効率化につなげよう!

この記事では労務の年間スケジュールを解説しました。
年間スケジュールを把握することは、労務業務を効率化することにつながります。
また、労務業務を適切に実施するためには、法律の改正内容も把握しておく必要があるので、労務に関係する法律はこまめにチェックするように心がけましょう。
年間スケジュールを確認して対応が難しい業務がある場合は、多彩なバックオフィス代行サービスを提供している「まるごと管理部(労務プラン)」に相談してみてはいかがでしょうか。

「まるごと管理部」の
資料を無料でダウンロード
人事労務・経理を仕組みづくりから実務まで代行!
急な担当者の退職など社内のバックオフィス担当の代わりとして伴走支援します
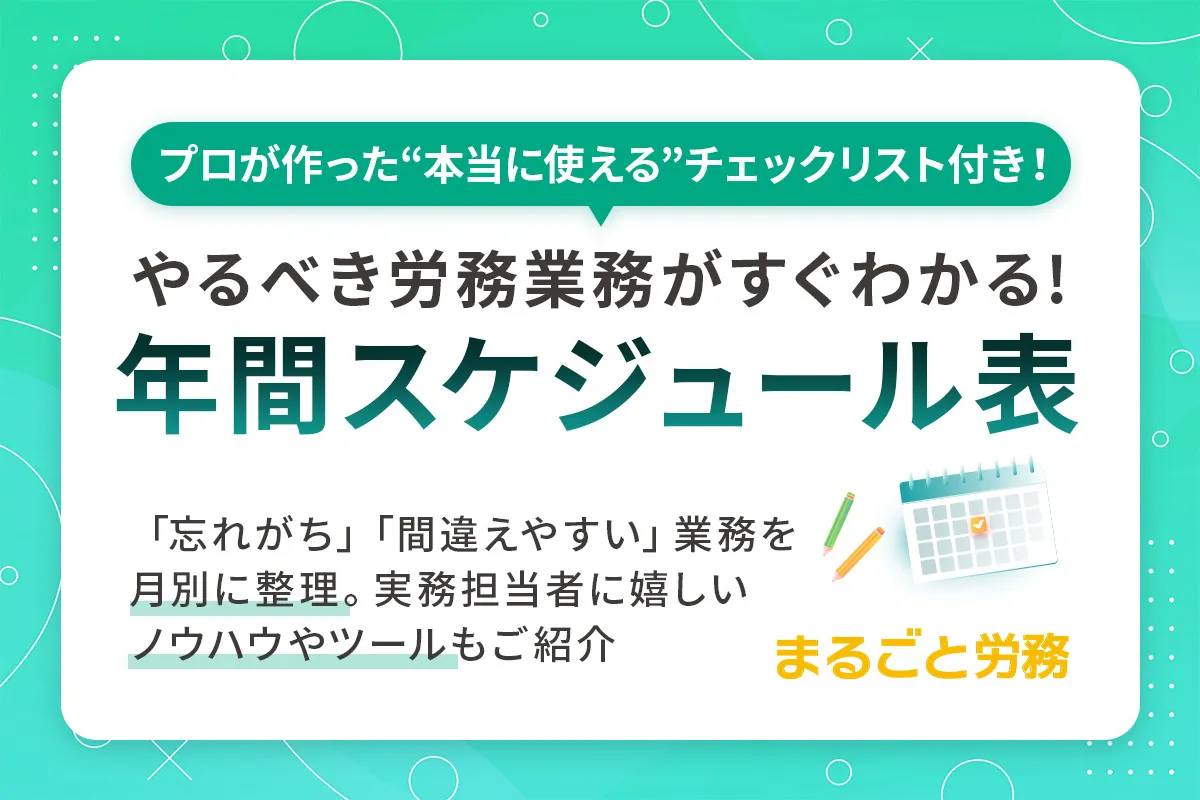
労務業務の年間スケジュール
記事といっしょに活用するとより効果的!「まるごと管理部」が作った便利なスケジュール表を無料配布中。チェックリストとノウハウを活用して、明日から労務業務をラクに進めましょう。
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
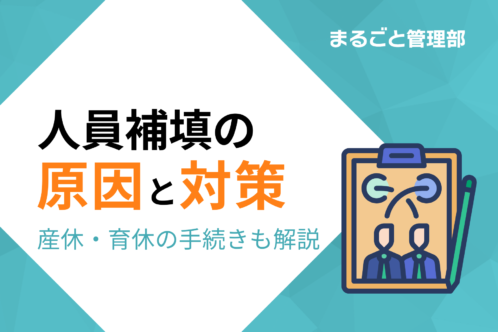
人員補填(補充)の原因と対策を解説|人事担当者が押さえるべき産休育休手続きも紹介
- バックオフィス業務
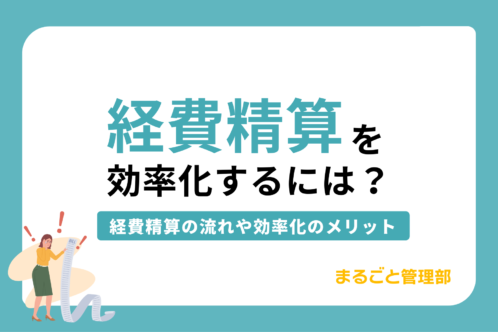
経費精算を効率化するには?経費精算の流れや効率化のメリットも紹介
- バックオフィス業務
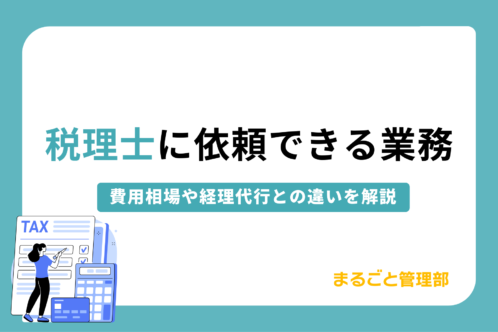
税理士に依頼できる業務とは?費用相場や経理代行との違いを徹底解説
- バックオフィス業務
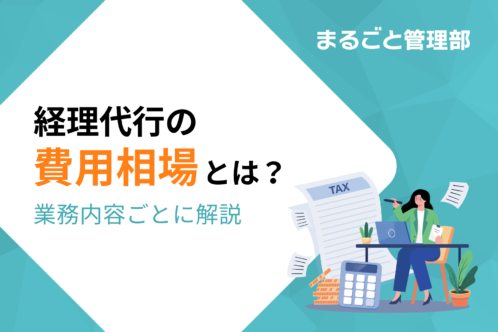
経理代行の相場とは?業務内容ごとに費用相場を徹底解説!
- バックオフィス業務
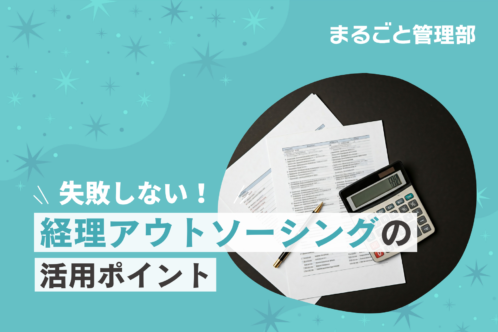
失敗しない経理アウトソーシングのポイントは?おすすめのサービスも紹介
- バックオフィス業務
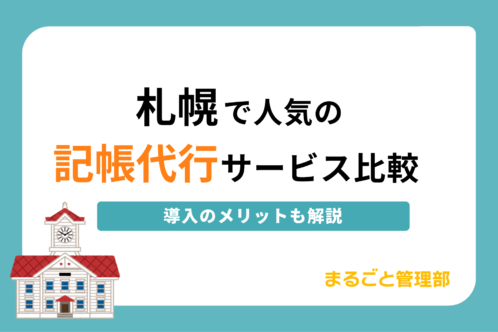
札幌で依頼したい記帳代行サービス4選。選び方のポイントを解説
- バックオフィス業務