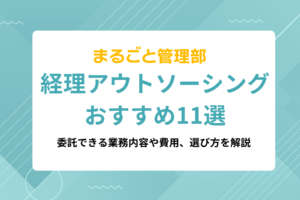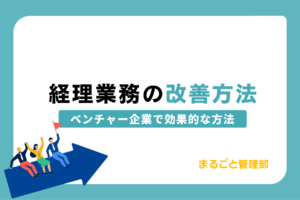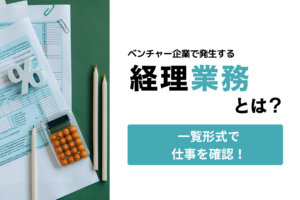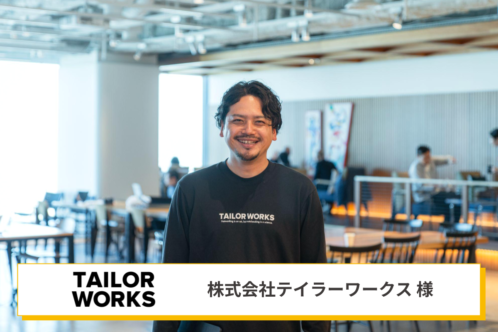採用・労務・経理に関するお役立ち情報
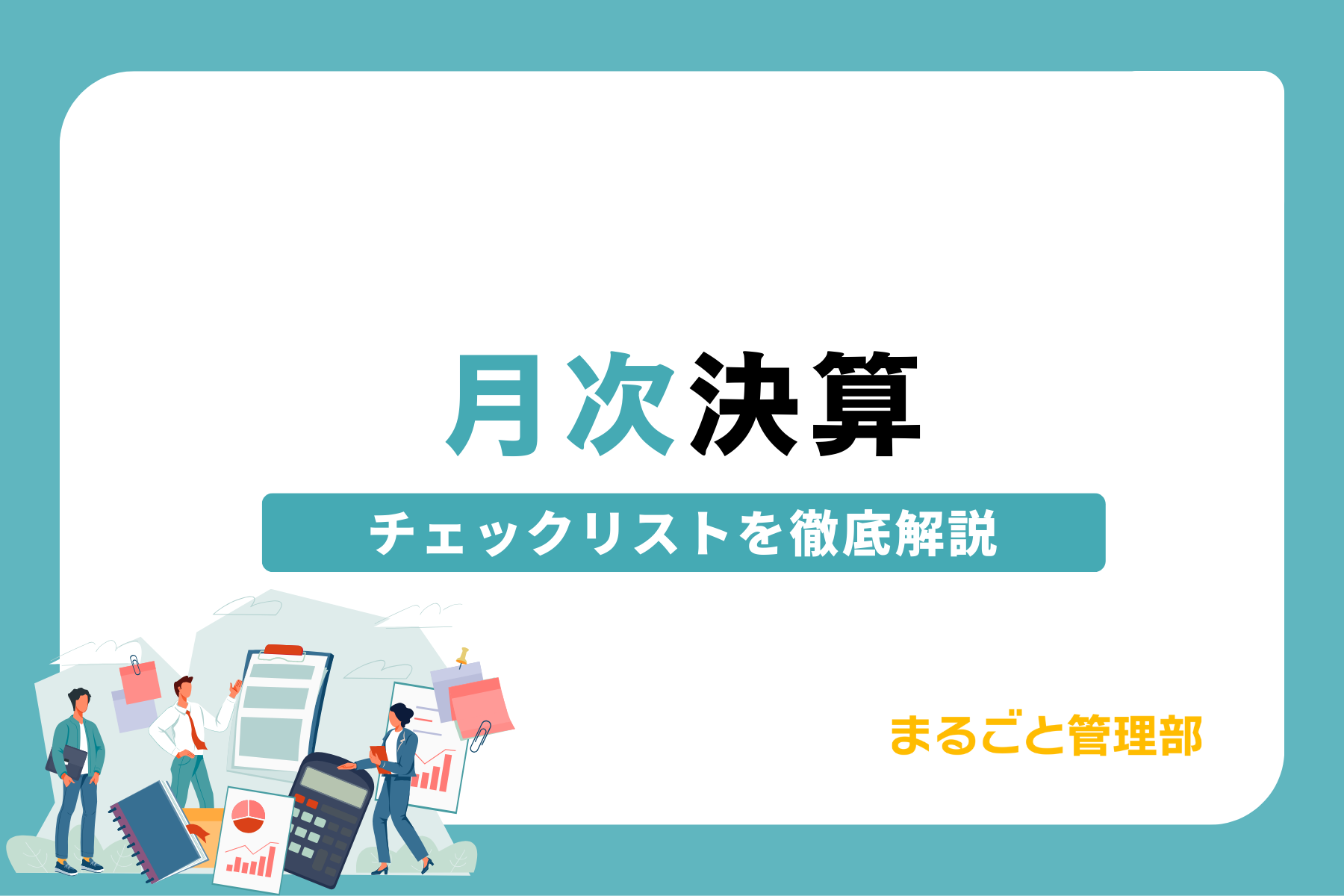
企業を経営する上で、年次決算は避けられない業務であり、手間がかかることから課題に感じている経理担当者も少なくありません。
上記のお悩みを持っている方には、毎月の月次決算をまとめ、年次決算にかかる負担を軽くすることをおすすめします。
この記事では、毎月の月次決算を効率良く行える「チェックリスト」の概要を徹底的に解説します。
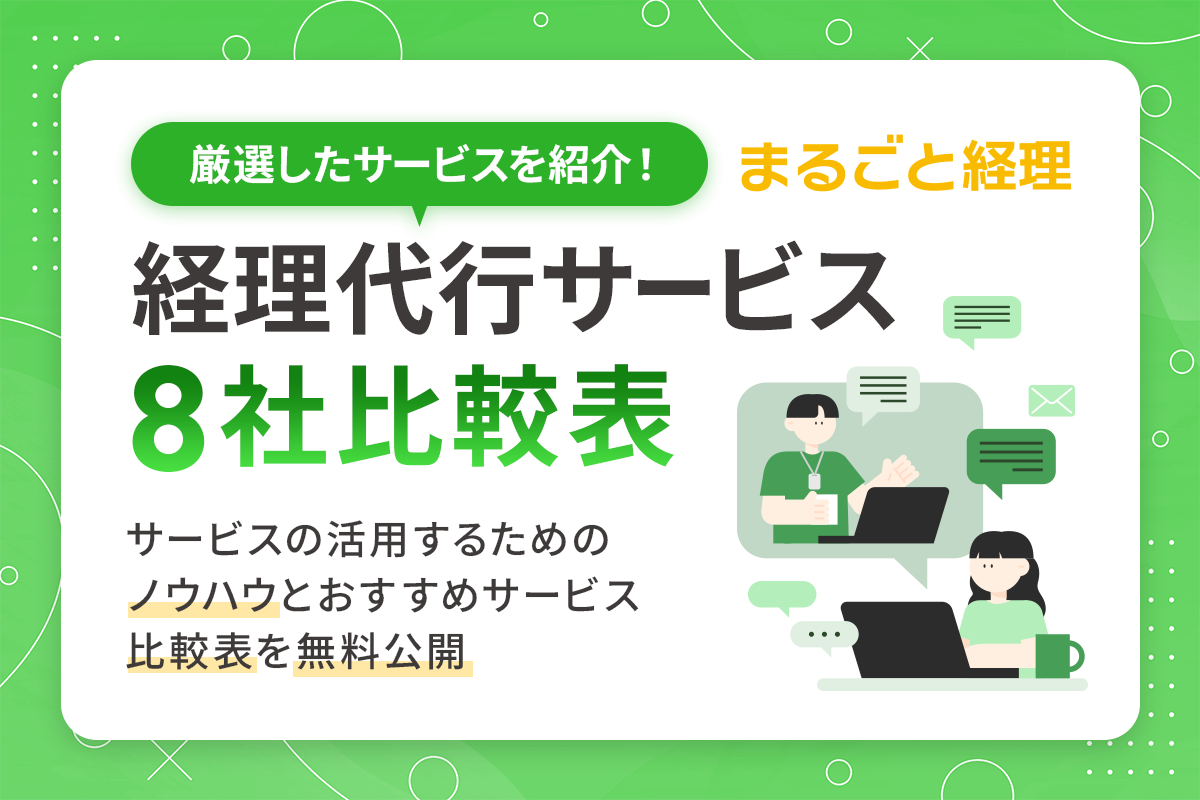
経理代行サービス比較表
経理代行サービスの活用の基本を解説。8社のサービスが一気に比較できます!
目次
月時次決算チェックリスト
以下のチェックリストを用いて、属人化も防止しましょう。
現金取引が日々遅れずに入力されているか
当座預金勘定の月末帳簿残高と銀行発行の当座預金照合表などが一致しているか
未決済手形の一覧表とその残高が勘定科目残高と一致しているか
売掛金明細表と、補助簿の各残高とが一致しているか
役員・社員等が消費した、たな卸資産について適正な販売価額で売上計上が行われているか
貸付金明細表と、補助簿の各残高とが一致するか
資産を賃借するための権利金などが、税務上の繰延資産に区分されているか
期中に売却、除却、交換、取替等により減少した資産について確認する
有価証券・出資金の取得、または減少があるか
支払手形明細表
買掛金取引先別残高一覧表と請求明細書
口座別残高と返済予定表・残高証明書の借入金残高
請求書、納品書等を参考にして、収益または他勘定へ振替えるべきものはないか
適正見積額が毎月計上されているか
貸借対照表がマイナス残高になっていないか
月次決算とは?

「月次決算」とは、企業や団体が毎月行う会計業務の一環で、月の財務状況や経営成績を把握するための決算処理を指します。
年度決算や四半期決算とは異なり、月ごとに定期的に実施され、主に資金繰り管理や経営成績のモニタリングに使用されることが多いです。
事業が拡大し、変化が大きいベンチャー・スタートアップにとっても例外ではなく、正確な月次決算を作ることは変化の大きい事業の経過を確認するのに役立ちます。
事業の状態を適時確認することで、課題解決の糸口を見つけることにも繋がりますので、月次決算を実施するメリットは大きいと言えるでしょう。
年次決算との違い
「年次決算」とは、1年に1度行う決算業務で、会社法によってすべての株式会社に義務付けられている特徴があります。
月次決算は年次決算の準備や経営の効率化などの目的で、あくまでも任意で行われるため、対象とする期間が異なることや義務付けられていないことが、年次決算の違いとして挙げられます。
関連記事:https://marugotoinc.jp/blog/keiri_os/
月次決算チェックリストを作る3つのメリット
月次決算チェックリストを作成すると、一定のクオリティとミスの防止に役立ちます。大きく3つのメリットがあるので解説します。
1、項目の標準化
判断基準を統一化すると、担当者の経験値に左右されずに一定のクオリティで決算を完了できます。
さらに、各タスクに「完了条件」と「エビデンス(どの資料を確認したか)」を紐付けることで、確認漏れを物理的に防ぎます。「完了印を押す」というアクションをフローに組み込むと、責任の所在が明確になり、ケアレスミスを最小限に抑えられるでしょう。
2、作業の重複や漏れ防止
決算業務の遅れは、多くの場合「次に何をすべきか」という迷いや、不必要な手戻りから発生します。チェックリストがあれば、業務全体を構造化が可能です。
余計な進捗確認メールやMTGが減り、チーム全体のリードタイム短縮に直結します。
3、属人化防止と効率的な引き継ぎ
チェックリストがあれば、ノウハウを組織の資産にできるでしょう。
特定の社員にしかわからない「ブラックボックス化した業務」は、組織にとって最大の経営リスクです。
ベテランの視点をチェック項目に反映させることで、組織全体のスキルレベルが標準化されます。
月次決算を作成する3ステップ

ここでは、月次決算を作成する手順を3ステップで紹介します。
計算する項目が同じである性質上、月次決算の作成方法はどの業界・規模の企業でも共通のものであると言えるでしょう。
月次決算に対するイメージがつかめていない方は、以下のステップを参考にしてみてはいかがでしょうか。
1、決算整理
「決算整理」とは、現金と預金残高の確認や未払費用や前払費用などを経過勘定に計上する業務を指します。
チェック項目が多いため、以下の項目を参考にして、見落としがないようにすることが重要です。
決算整理をミスしてしまうと、後の業務にも影響が出てしまうため、ミスがないかどうかきちんと見直すことをおすすめします。
2、月次報告資料の作成
「月次報告資料の作成」とは、損益計算書や貸借対照表など、決算整理した情報を資料にまとめる業務を指します。
月次決算で必要となる書類は企業によって異なるため、事業の性質や上司に報告する上で必要な情報を、明確にしておくことが重要です。
3、事業報告
損益計算書や貸借対照表など、決算整理した情報を資料にまとめたら、上司や経営陣に報告します。
なお、年次決算のように義務化された業務ではないため、株主への報告は必要ないことがほとんどです。
株主に報告する場合は、正式なフォーマットに資料をまとめ直す必要があります。
月次決算の効率化はチェックリストを活用しよう

ここでは、月次決算の決算整理で活用できるチェックリスト内容を、項目ごとに解説します。
チェックリストを活用することで、項目の抜け漏れや重複を避けられるため、月次決算の効率化が期待できます。
加えて、チェックリストを作成することで属人化を防止できるため、少ない人員で経理作業しているベンチャー・スタートアップの方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
現金
「現金」とは、企業がすぐに使える資産のことで、紙幣や硬貨などの手元にある現金や、即時に引き出し可能な銀行預金も含みます。
この項目では、現金取引が日々遅れずに入力され、日々の現金残高に係る金種別残高表が適時に作成保存されているか確認しましょう。
また、小口現金制度を採用している場合は、資金補充以外の入金がないかもチェックすることが重要です。
預金
「預金」とは、企業が銀行や金融機関に預けている資金のことです。企業の運転資金や支払いに使用されることが多く、現金と同じく流動性の高い資産として扱われることがほとんどです。
この項目では、当座預金勘定の月末帳簿残高と銀行発行の当座預金照合表などが一致しているか確認しましょう。
確認時には、両落ちによる仕訳入力の脱漏等がないか注意する必要があります。
受取手形
「受取手形」とは、取引先が企業に対して商品やサービスの支払いを約束した手形(手形による約束書)のことを指します。
手形は、一定の支払期日が設定されており、その期日になれば現金化できます。
この項目では、未決済手形の一覧表と、その残高が勘定科目残高と一致しているか確認しましょう。
確認時には、受取手形明細表と受取手形記入帳もチェックする必要があります
売掛金
「売掛金」とは、企業が商品やサービスを販売したが、取引先からまだ現金を受け取っていない債権(未収金)のことを指します。
この項目では、売掛金明細表と、補助簿の各残高とが一致しているか確認しましょう。
売上割戻し等が発生している場合は、税法上交際費等に該当しないか注意する必要があります。
たな卸資産
「たな卸資産」(棚卸資産)とは、企業が販売目的で保有している在庫のことを指します。
この項目では、役員・社員等が消費した、たな卸資産について適正な販売価額で売上計上が行われているか確認しましょう。
受払帳残高との差異があったときは、必ず原因を判明するように心がけましょう。
貸付金・仮払金等
「貸付金」は、企業が他者(取引先、関連会社、従業員など)に対して一定の期間貸し付けた資金のことを指します。
一方「仮払金」は、後日発生する正式な取引や経費に対する前払いのことを指します。
この項目では、貸付金明細表と、補助簿の各残高とが一致するか確認しましょう。
費用または他勘定へ振替えるべきものは処理を施す必要があります。
税務上の繰延資産
「繰延資産」とは、すでに支出が行われたにもかかわらず、その支出による経済的効果が将来にわたって得られると判断されるものを指します。
繰延資産は、支出を一度に費用として処理せず、将来の会計期間にわたって段階的に費用化(償却)するため、資産として一時的に計上します。
この項目では、資産を賃借するための権利金などが、税務上の繰延資産に区分されていることを確認しましょう。
固定資産・繰延資産
「固定資産」とは、企業が長期間使用することを目的として保有する資産で、通常は1年以上にわたり企業の業務や事業活動に利用されるものを指します。
この項目では、期中に売却、除却、交換、取替等により減少した資産について確認しましょう。
また、権利保有の事実を確認する際には、営業権等や契約書などの資料を照らし合わせる必要があります。
有価証券
「有価証券」とは、財産的な価値を持つ権利や義務を証券化したもので、法律上または市場において売買が可能な資産のことを指します。
この項目をまとめる際には、有価証券・出資金の取得、または減少があるか確認しましょう。
また、固定資産・繰延資産と同じように、事実を確認する際には、営業権等や契約書などの資料を照らし合わせる必要があります。
支払手形
「支払手形」とは、企業が商品やサービスの代金を支払うために、特定の期日に代金を支払うことを約束した手形のことを指します。
この項目では、支払手形明細表を確認する必要があります。
また、休祭日が決済日となっている手形の処理が一貫しているかにも注意が必要です。
買掛金
「買掛金」とは、企業が商品やサービスを購入した際に、後払いとして取引先に対して支払う義務がある未払いの代金を指します。
この項目では、買掛金取引先別残高一覧表と請求明細書を確認する必要があります。
また、長期にわたり動きのない取引先や買掛金残高が滞留している場合は、取引先に問い合わせるなど、問題を残さないように対処しましょう。
借入金
「借入金」とは、企業や個人が金融機関や他の企業、個人などから資金を借り入れた際に発生する返済義務のある負債のことを指します。
この項目では、口座別残高と返済予定表・残高証明書の借入金残高を確認する必要があります。
また、借入債務の実在性を担保するために、証拠書類で確認も徹底しましょう。
未払金・預り金等
「未払金」とは、企業が商品やサービスを購入した際、その代金をまだ支払っていない状態の金額を指します。
また、「預り金」とは、企業が一時的に他人の資金を預かっている状態を指します。
この項目では、請求書、納品書等を参考にして、収益または他勘定へ振替えるべきものはないか確認しましょう。
引当金・減価償却累計額
「引当金」とは、将来の特定の支出や損失に備えて、あらかじめ一定額を負債として計上しておく金額を指します。
「減価償却累計額」とは、企業が所有する固定資産の取得原価から、これまでに計上された減価償却費の累積額を指します。
この項目では、適正見積額が毎月計上されているか確認しましょう。
新規の従業員の採用や退職等により支給対象者が変化した場合は、金額の見直しをする必要があります。
貸借対照表
「貸借対照表」は、企業や組織のある時点における財政状況を示す財務諸表の一つであり、企業が保有する資産、負債、および純資産(資本)の状態を明確に記載したものを指します。
この項目では、貸借対照表がマイナス残高になっていないか確認しましょう。
マイナス残高があった場合、原因の特定と修正が必要です。
【まとめ】月次決算の効率化はチェックリストから、ベンチャー・スタートアップも活用しよう

この記事では、月次決算の効率化に活用できるチェックリストについて解説しました。
年次決算でミスを防止する策として、月次決算を毎月まとめることが有効です。
ただ、業務過程で項目を見落としがちなため、この記事で紹介した、チェックリストを活用することをおすすめします。
月次決算の業務を負担に感じている経営者・経理担当者は、多彩な経理のサブスクリプションサービスを提供している「まるごと管理部(経理プラン)」に相談してみてはいかがでしょうか。

「まるごと管理部」(労務・経理プラン)の資料を無料でダウンロード
労務・経理を仕組みづくりから実務まで代行!
急な担当者の退職など社内のバックオフィス担当の代わりとして伴走支援します
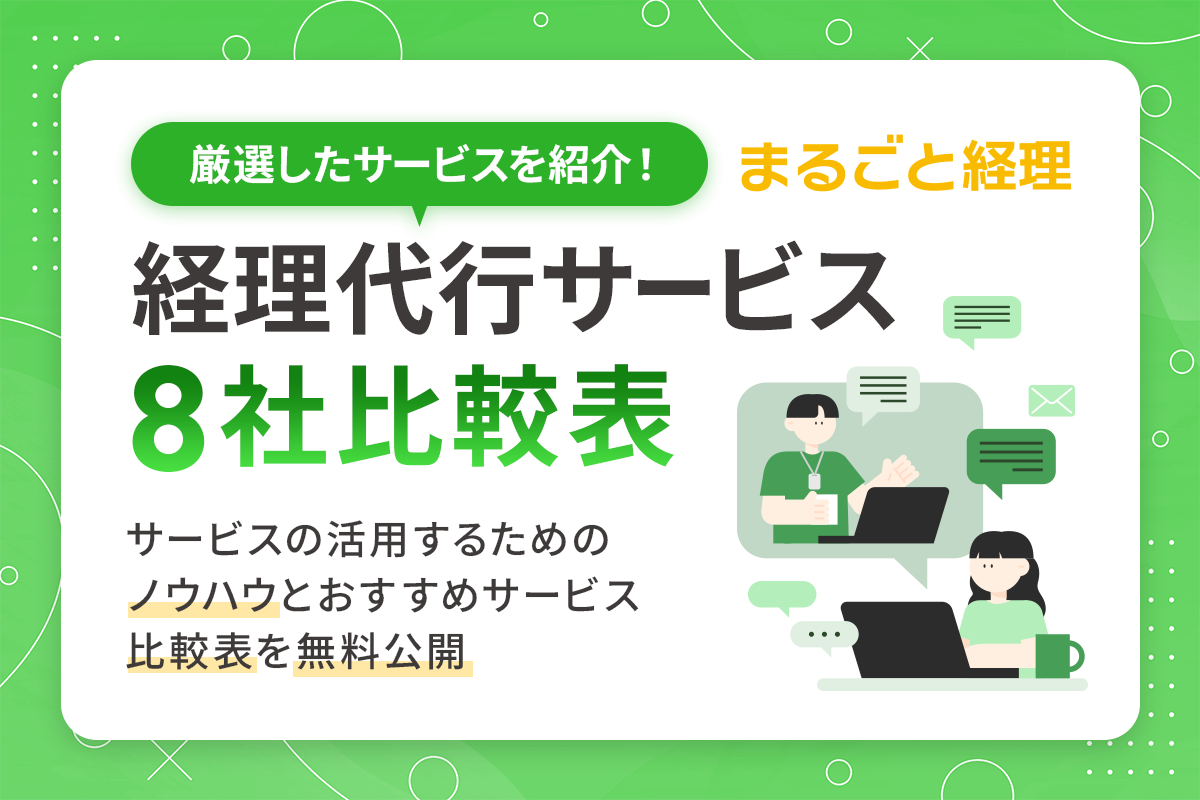
経理代行サービス比較表
経理代行サービスの活用の基本を解説。8社のサービスが一気に比較できます!
CATEGORYカテゴリ
TAGタグ
関連記事
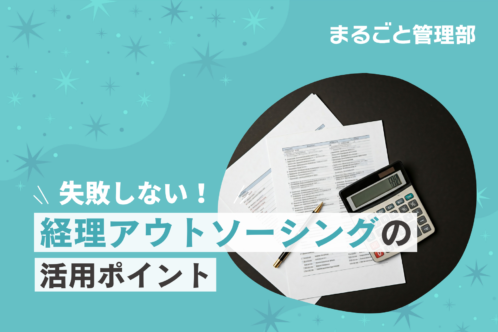
失敗しない経理アウトソーシングのポイントは?おすすめのサービスも紹介
- バックオフィス業務
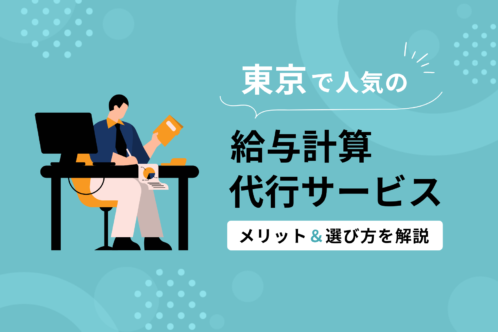
東京で人気の給与計算代行サービス4選!利用のメリットや選び方を解説
- バックオフィス業務

社員管理システムとは?導入のメリットや活用に向けたポイントを解説
- バックオフィス業務

人事労務系アウトソーシングをベンチャー・スタートアップ向けに解説
- バックオフィス業務

シフト管理ができる勤怠管理システムとは?導入メリットや製品の選び方
- バックオフィス業務
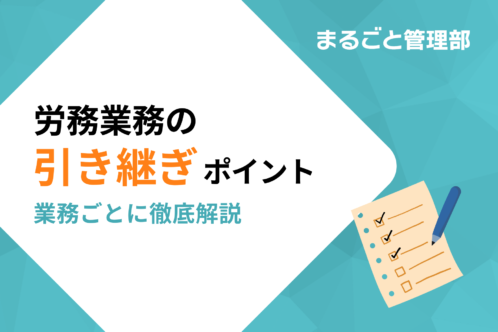
労務の引き継ぎポイントを業務ごとに徹底解説!
- バックオフィス業務